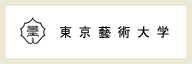イベント
Ⅱ.シンポジウム
シンポジウム『演奏・創作と芸術研究』
吉川 文
音楽研究科リサーチセンターでは、設置2年目にあたる2009年に公開シンポジウム『演奏・創作と芸術研究─芸術系大学院博士課程における学位授与プロセス─』を開催した。この催しは、ここまでの国内外の調査内容を整理し、その後の活動の方向性を考えていくにあたり、センターにとって重要な里程標のひとつとして位置づけられよう。当日のシンポジウム全容は、2010年3月に発行したシンポジウム報告書に詳しく掲載されている。ここでは基調講演、パネル・ディスカッションの内容をかいつまんでまとめ、さらにパネル・ディスカッション司会を務めたリサーチセンター運営委員の大角欣矢教授による総括文を前述の報告書より再録する。なお、当日のプログラム、参加者等は以下の通りである。
§1.シンポジウム概要
- 開催日時:
- 2009年12月19日(土)13:30?17:00
- 開催場所:
- 東京藝術大学音楽学部5号館5-109室
- プログラム:
- ◇開会挨拶
宮田亮平(東京藝術大学長)
西岡龍彦(東京藝術大学音楽学部副学部長) - ◇音楽研究科リサーチセンター活動報告
檜山哲彦(東京藝術大学音楽学部教授・音楽研究科リサーチセンター主任) - ◇基調講演
山縣 熙(大阪芸術大学大学院芸術研究科科長) - ◇パネル・ディスカッション
柿沼敏江(京都市立芸術大学音楽学部教授)
藤本一子(国立音楽大学音楽学部教授)
越川倫明(東京藝術大学美術学部教授・美術研究科リサーチセンター主任)
永井和子(東京藝術大学音楽学部教授・音楽研究科リサーチセンター運営委員)
大角欣矢[司会](東京藝術大学音楽学部教授・音楽研究科リサーチセンター運営委員) - ◇閉会挨拶
渡邊健二(東京藝術大学副学長)
- ◇開会挨拶
- 参加者数:
- 約100名
§2.基調講演
大阪芸術大学の山縣教授による基調講演では、演奏や創作といった芸術実践を専攻する博士課程を考えていくにあたって、「博士」とは何かという根本的な問いが立てられた。山縣教授は現代フランス思想を中心とする美学・芸術学を専門とする立場から、自身の博士課程での 経験、夏目漱石による博士号辞退のいきさつを下敷きに「博士」とは何かをあぶりだし、芸術系、特に実践に軸足を置く博士課程に何が求められていくのかという方向へと論を進めた。講演全体の流れを追ってみよう。
まず、本シンポジウムの重要なテーマとなる演奏・創作、いわゆる広い意味での創造= exécution する行為を考えたとき、それを専門とする博士課程における指導や教育、さらにその結果の評価はどうあるべきか、もとよりそれは可能なのかという問いから、そもそも実践ではなく理論を専門とするような人文科学の博士号の存在も、それほど簡明なものとは言えないことが指摘される。また、自らがフランスで体験した言語体験に即して、人が考えを言語化する、すなわち茫洋とした形で思考されたものを言葉にすることを翻訳= traduction という枠組みの中で捉え、同様に絵を描く、作曲・演奏をするといった表現活動も翻訳の一種と見なすことにより、芸術実践と論文との関係を考える手がかりが示された。
山縣教授自身は、1960年代に東京大学文学部美学美術史学科から大学院へ進み、文学修士取得後さらに後期博士課程へと進学したが、主任教授の考え、及び当時の風潮として3年で論文を書いて得られる課程博士などは博士に値しないと捉えられていたこともあり、博士論文を書き上げることなくフランスへ留学、帰国後に神戸大学に赴任したとのこと。ここで今度は後期課程を立ち上げる側になり、さらに大阪芸術大学へ移職後には芸術実践の制作系後期課程設置にも携わった経験が紹介された。自ら様々な場で博士課程と関わりを持ちながらも博士とは一定の距離を持ち続けてきたのは、「博士」に対して何某かの問題意識があったからであり、これは夏目漱石による博士号辞退の一件に沿って説明されることになる。
明治44年2月、夏目漱石は東京帝大の文学博士会で決まった博士学位授与に対し、文部省事務局長に宛てて博士辞退の書簡を送った。山縣教授は、その経緯について漱石自身の語っている講演記事や書簡、そして『我が輩は猫である』の中に透けて見える彼の博士観を資料に即して明らかにしている。漱石は「学問奨励の具としての博士制度」によって学問が少数の博士の専有物となる危険を感じとるとともに、そもそも「博士」が非常に細かく分化した「針の先で井戸を掘るような」研究をしているとして、世間一般の博士への評価、諸事万端に通じた者との見方を強く否定している。その一方で、博士号辞退の6年ほど前に書かれた『我が輩は猫である』では、漱石自身をモデルとしたと思われる主人が、博士や大学教授に対する尊崇の念を示している。文部省からの一方的な博士授与を辞退した背景には、博士になるなど馬鹿馬鹿しいと言いつつもその超俗的な部分にある種の思いを漱石が抱いていたことが窺われる。
山縣教授は、肩書きとしての博士や学者・教授といったもの対する漱石の距離の取り方に共感しながら、博士号辞退の経緯にもふれた漱石の講演『道楽と職業』での言及に照らして職業人としての研究者である自身の立場を振り返る。自分のやりたいことをやりたいようにできる道楽に対し、漱石は職業とは他人本位のものであり「取捨興廃の権威共に自己の手中にはない」としつつ、他人本位では成り立たない職業として科学者哲学者さらには芸術家を挙げている。山縣教授も、論文執筆においては自らの思いの「翻訳」に妥協を許さない気持ちを持ちながらも、多くの場合は自分自身の職業人としての研究者の立ち位置を意識し、さらにここから博士や博士課程の問題に向き合って論を進めていく。
博士課程の意義を具体的に考えていくにあたりまず示されたのは、1977年に最初の芸術系後期博士課程を設けた東京藝術大学の課程設置趣旨書である。ここでは芸術の専門技能や技術研究を深め、芸術の本質を極めようとする高度な研究者・教育者を育成していくため、後期博士課程を設置する必要性が謳われている。さらに博士課程に進んだ多くの者は、各地の大学で芸術に関わる教員職につくことが想定されていたことも窺われる。また、設置趣旨の関連資料としてあげられた大学設置審議会による東京芸術大学実地視察概要メモにおいては、「実技教官と理論担当教官との協力した形での指導」や「学位論文の重視、厳正な対処」に関する記載が見られ、芸術実践と理論的研究との関係が30年以上前から問題となっていた点を明らかにしている。
その後2000年前後には音楽実技系の博士後期課程を有する大学は7校を数えるようになる。大学教員等の研究教育職に就ける可能性がかなり低い段階において、博士課程に在籍するだけではなく、実際に学位を取得する者も非常に高い割合を占めるようになってきている現状は、文科省のまとめた大学院活動調査結果からも明白であり、学位取得にあたってどのような形でそれぞれの研究成果を学位論文に仕上げていくのかという点は非常に大きな問題となる。
それでは具体的に芸術実技系の論文とはどのような形であるべきなのか。まず山縣教授は職業としての大学教授という漱石の考えに沿った見方から、論文指導にあたって学生の望む論文に寄り添うような形を前提と考える。また、芸術実践を専攻する学生たちは、自身の実技実践と結びつく形で論文をまとめることにより、独創的な論文を仕上げることが可能になるとする。論文執筆もまた自らの考えを言語化する「翻訳」であり、ある種の「創造」であるとの見方がその背景にある。
さらに、フランスの思想家ドゥルーズの『感覚の理論』を引き合いに出しながら、儚い感覚作用に理論を与える必要性、すなわち芸術実践の現場での様々な問題を言葉によってフィードバックすることが、さらに次の段階に進む上で重要になること、実践と理論との相互性を土台に演奏や創作が論文を通じてさらに深められることにこそ、芸術実技系の論文の大きな意義のあることを提示し、続くパネル・ディスカッションで多様な議論が展開するためのひとつの場を整える形で、講演は締めくくられた。
§3.パネル・ディスカッション
休憩を挟んで行われたパネル・ディスカッションは、音楽研究科リサーチセンター運営委員である大角教授が司会を務め、4人のパネリストに基調講演を行った山縣教授が加わる形で進められた。まず、パネリストそれぞれの立場から後期博士課程との関わり、問題点が提起され、その後パネリスト間の意見交換、さらに会場からの質疑を受ける形となった。
最初に報告に立った京都市立芸術大学の柿沼教授からは、同大の後期博士課程の現状、およびアメリカの後期博士課程についての報告があった。京都市立芸術大学では、2003年の博士課程設置以来これまでに作曲専攻の学位取得者が出ており、演奏専攻では今年度末に最初の取得予定者がいるとのこと、学位論文執筆に向けて年度毎に研究発表や紀要論文の執筆が課され、その後最終論文の執筆にかかる。論文指導は音楽学の教員があたるが、最近では演奏と直結する内容の論文も増えてきており、演奏実技の教員も論文指導に加わる必要性が感じられる状況にあるとのことだった。一方、柿沼教授自身が博士号学位を取得したカリフォルニア大学サンディエゴ校の場合は早い段階から研究論文執筆のための授業が準備され、博士論文執筆に向けて体制、基礎が整えられている状況にある。さらに、アメリカの場合は博士に幅広い知識と専門性が求められており、博士の位置づけを確認していく上で様々に考慮すべき部分があることが指摘された。
続いて国立音楽大学の藤本教授から、フランスの事例紹介と国立音楽大学の状況が示された。EU発足後、ヨーロッパ全体での新たな教育政策の進展があり、フランスでもかなり状況が変化している。従来存在していなかった演奏専攻の博士課程も2009年の秋からパリ高等音楽院とパリ第4大学とが共同する形で設置され、今後どのような形で博士を輩出していくのか注目される。また、2007年に博士課程が設置された国立音楽大学の状況として、音楽学の教員による論文執筆指導の様子、演奏実践者ならではの論文の方向性が示された。さらに、今後学位取得者に対してどのような活動の場を想定し、社会に送り出していくことができるのかが重要な問題となるとの指摘があった。
東京藝術大学美術研究科リサーチセンター主任の越川教授からは、美術研究科リサーチセンターについての簡単な紹介後、美術研究科後期博士課程の現状・課題が提示された。実技系の学生は論文執筆経験が平均的に乏しいのに加え、ここにきて学位取得者の急増する現状は指導上大きな問題となる。さらに、研究領域により論文へのアプローチが多様であることに加え、それに対する教員の認識も様々であることは、創作と論文との関係づけをさらに難しいものとしている。これから、いかに興味深い創作や論文を生み出し、社会に問うていくことができるかが大きな課題ではないかとの指摘もあった。
最後に、東京藝術大学音楽研究科リサーチセンター運営委員の永井教授からは、パネリストとして唯一演奏家の立場から東京藝術大学の博士課程との関わり、教員の抱える問題について報告があった。当初、演奏家にとって博士課程や論文執筆の意義に疑問を持っていたとのこと、しかし現在は、学生が演奏に関してのみならず語学や研究等さまざまな面でサポートを受けながら自分の極めたい音楽に取り組むことのできる環境を非常に重要なものと考えている。また、論文についても日々の演奏実践の中から得られるものを、読み手を納得させられるような形でまとめるべきではないかとの指摘があった。その他、外部審査の問題なども言及された。
各パネリストの報告を受け、山縣教授も加わって、実技専攻にとっての博士課程、論文の内容や位置づけ、論文と実技とのバランス等に関わる問題が議論の俎上に載せられた。
まず取り上げられたのは、博士課程の論文に求められる独創性をどのように検証し、担保していくのかという問題である。たとえば美術の場合には現状では審査所見の公表という形以外に明確なものがないが、審査の評価基準、適切な審査委員構成などが重要視される。また、芸術実践における表現の独創性と、ある程度は既知の内容を語るのでなければ理解されない言語表現としての論文との関係にも話が及んだ。演奏実践を土台とした論文の難しさに関連して、理論を専攻する者による指導の限界、演奏専攻の教員の論文指導への関与の必要性も改めて指摘された。
演奏実践と論文との一体的評価、そのバランスの問題については、演奏と論文との評価のバランスにおいて、やはり専門とする演奏に比重を置いた評価が望ましいという意見や、個々人の取り組みについて一様な決め方はそぐわないとの見方が出された。いずれにしても、学位取得者に対する社会の評価は論文ではなく演奏を通してなされるという点には留意する必要がある。
会場からの質疑として、博士論文は修士論文とは異なり、単に独創性のあるものとしてだけではなく、新たな知的財産と認められるようなものである必要はないかといった見方、さらに基調講演の内容なども踏まえながら芸術実践と論文との関係を身体知と言語知との関わりから問う指摘などが出された。シンポジウム全体を通してのまとめとそこから見えてくる問題について、シンポジウム報告書からパネル・ディスカッション司会を担当した大角教授の総括を以下に再掲する。
§4.シンポジウムを振り返って(音楽研究科リサーチセンター運営委員 大角欣矢教授)
芸術分野における博士の学位とはどのようなものであるべきか──この非常に難しい問題を巡って、複数の大学の関係者が集まり、公開の場で討論を行った今回のシンポジウムは、恐らくこの種のものとしては日本で最初の試み、ということになるのではないだろうか。その意味で、何か特定の明確な結論を導き出すということではなく、そもそも議論すべき根本的な問題は何なのかという、今後の探究に向けた出発点を確認できたという点こそが、この催しの最大の成果と言ってよいだろう。
議論は多岐にわたり、その内容を簡単にまとめるわけにはいかないが、いくつか共通認識として確認できたこともある。例えば、博士の学位は、極めて優秀な実技の水準に達している者にのみ与えられるべきである、という点に関し、異論はなかった。しかし、人類の知的財産に何らかの新たなものを加える、という博士の学位に関する社会通念に照らして見た時、芸術の研鑽の成果がいかなる意味で「知的」であるのか、またその「新しさ(独創性)」がどのように検証されうるのか、という点に関しては、今後立ち入った理論的考察が必要であることがはっきりした。
この点に関し、今回繰り返し話題になった重要な認識は、音楽を行うことそのものが非常に知的なプロジェクトである、ということであろう。もしそうであるならば、音楽の実践において働く知性は、適切な指導の下で、例えば音楽解釈の言語化という局面においても能動的な作用を及ぼすはずであり、逆にそこで明確に意識化された知見が、今度は音楽実践へとフィードバックされて芸術表現をより豊かにする、というクリエイティヴな循環が可能になるはずなのである。
私がシンポジウムの最後に述べたように、学術的な営みがあまりにも自然科学的実証主義のモデルにあてはめて考えられてきたことに対し、20世紀の思想界は批判を強めてきた。それは、このモデルが絶対の信頼を置く「言語」が、実際には一般に信じられているほど正確でも合理的でも普遍的でもなく、むしろ無意識的なメカニズムや、とりわけ言語(=精神)の対極にあると思われてきた「身体」の強い影響下にあることが強調されるようになったからである。このような思想の影響は、人文系諸分野、とりわけ文学批評・文化研究など、事物の客観的な叙述よりもむしろその「解釈」を重要視する学問領域でいち早く現れてきた。
このような状況に鑑みるに、我々の置かれている立場は、ある意味では周回遅れのランナーのようなものと言えるかもしれない。つまり、自他共に「学術研究」から最も遠いところにいると思っていたのに、気がつくとトップを走っているのである。この言い方は決して誇張ではない。我々の経験と現実(リアリティ)を構築しているものが、簡単に言ってしまえば身体と言語との間の絶えざる相互流動的なプロセスである以上、音楽に対し知的にアプローチする試みは、最高度に刺激的で、実り多い成果をもたらす学術的企てであり得る。言い換えれば、演奏・創作と結びついた芸術研究は、学問世界一般の営みに対して、新たな生産的モデルを提示して行くことができる可能性すら秘めているのである。
私がここで述べたようなヴィジョンをどのように実現して行ったらよいのか、現時点ではまだ明確な道筋は見えない。ただ一つ確かなことは、それは誰か一人の努力やアイディアによって実現されるものではない、ということである。今回、含蓄の深い基調講演をしてくださった山縣先生を始め、パネリストとして有益な発表と中身の濃い議論をしてくださった諸先生方、会場で熱心に耳を傾け、また意見をくださったお一人お一人、そしてこのシンポジウムが可能となるためにご尽力頂いたすべての方々に心から厚く感謝申し上げる。また、この報告書を手にされた皆さんには、我々の探究に対して今後とも種々の仕方でご支援を賜るようお願い申し上げたい。このように、多くの人々の力を合わせた地道な努力の積み重ねだけが、我々を望ましい方向へと導いて行ってくれることだろう。