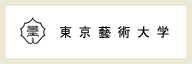リサーチ活動
Ⅰ.全体の潮流
1.ヨーロッパにおける高等教育改革と「研究」の新たな位置づけ
―ボローニャ・プロセスとヨーロッパ音楽院協会の取り組み
向井 大策
2000年代、ヨーロッパでは、ボローニャ・プロセス Bologna Processと呼ばれる高等教育改革が進められてきた。それに呼応するかたちで、ヨーロッパにおける音楽系大学でも、さまざまなとりくみが行われている。本稿では、ヨーロッパにおけるこうした高等教育改革の動向を紹介するとともに、そうした改革の流れが音楽系大学の博士課程プログラムにどのような影響を及ぼしているのかを考察したい。
とりわけ、注目したいのは、ボローニャ・プロセスを受け、ヨーロッパ各国の音楽系大学に「第3サイクル」(=博士課程)が設置されるようになった結果、従来の音楽学的な研究とは異なる、新たな音楽研究のあり方 ―Artistic Research― が、演奏、作曲など音楽における芸術系博士課程の方向性のひとつとして、明示されるようになったことである。その中心的な役割を果たした機関が、ヨーロッパ音楽院協会The European Association of Conservatoires= AECである。本稿では、同協会が進める「ポリフォニア・プロジェクト」について紹介すると同時に、そこで目指された新たな「研究」の位置づけについても考察していきたい。
ボローニャ・プロセスとは、ヨーロッパ高等教育圏 European Higher Education Area = EHEA 発足を目指して進められてきた、高等教育改革プロセスのことである。1999年にヨーロッパの29の国(および地域)によって締結された「ボローニャ宣言」にもとづき、10年間にわたる行程を経て、2010年、ヨーロッパ高等教育圏は発足し、当初は47カ国が参加した。
「ボローニャ宣言」以前のヨーロッパ諸国では、伝統的にそれぞれの国の教育風土に根づいた独自の高等教育のシステムが発展してきた。しかし、政治・経済のみならず学術分野においても世界規模での競争や協力関係が拡大するなかで、高等教育の分野においても、ヨーロッパ全体を統合するような高等教育圏を確立しようという機運が高まる。そうした機運のなかで、ボローニャ・プロセスに参加した各国の間では、10年間の行程で、大学の制度や学位のあり方、修業年限や単位システム、学位の質保証など、さまざまな点に関して、高等教育におけるヨーロッパ全体の共通の枠組みづくりについて話し合いが進められた。
ボローニャ・プロセスにおいて進められた改革としては、大きく以下の4つの項目を挙げることができる。
①「各国共通の学位のシステムの確立」、②「質保証 quality assuranceの共通の基準作り」、③「ECTS(ヨーロッパ単位互換システム)の採用」、④「学生や教師、研究者の流動性 mobility の促進」。特に①、②に関して言えば、「各国共通の学位のシステムの確立」については、それぞれ学士・修士・博士に相当する「第1サイクル」、「第2サイクル」、「第3サイクル」の3段階システムの採用が目指された。博士課程に関しては、2003年のベルリン会議において、第3サイクルの組み入れが提唱され、音楽院や音楽大学においても、それまで博士課程プログラムをもたなかった国や大学に、これに対応する動きが見られるようになっていく。また、「質保証の共通の基準作り」に関しては、どういった基準で学位を授与するかについて、ヨーロッパ全体の資格枠組みづくりと、それに合致する各国の「国レベルの資格枠組み」の整備が進められていった。その結果、2004年に、ヨーロッパ共通の「質保証の基準」として、学士・修士・博士のそれぞれの学位資格のあり方の基準を明確に記述した「ダブリン・ディスクリプター Dublin Descriptors」が公表されることとなる1。
さて、こうしたボローニャ・プロセスの進展のなかで、それまで各国で独自の制度をもっていたヨーロッパの音楽院、音楽大学においても、3段階システムや単位互換システムの採用、また質保証の基準づくりなど、ボローニャ・プロセスに対応するための改革が急務となった。その中で大きな役割を果たしたのが、ヨーロッパ各国の音楽院、音楽大学の関係促進のために設立されたヨーロッパ音楽院協会である。ヨーロッパ音楽院協会では、2004年から「ポリフォニア・プロジェクト Polifonia Project」という音楽高等教育に関する大規模なプロジェクトを発足させ、「ボローニャ・ワーキング・グループ」、さらに博士課程に関しては「第3サイクル・ワーキング・グループ」を設置して、さまざまな提言を行っている。
「ポリフォニア」におけるさまざまな提言のなかでも重要なものが、高等音楽教育における学位資格の基準のモデルを示した「ポリフォニア/ダブリン・ディスクリプターThe Polifonia/Dublin Descriptors」だろう2。そこでは博士課程に関して、音楽院における博士課程修了者にどのような能力や資質、専門性が求められるのかが、「ダブリン・ディスクリプター」に即して、次のように定義されている。
- 音楽研究の領域の深く体系的な理解とともに、その領域と関連したスキルと、研究や調査方法の習熟を証明した者
- 芸術的および学術的な統合性をもって中身のある研究プロセスを構想、計画、実行し、適用する能力を証明した者
- 研究や調査を通して、そのなかのいくつかは国内や国際的に評価され、適切なチャンネルを通じて広められるような、それなりの量の仕事を展開することで知識や芸術的理解の最前線を押し広げるような独自の貢献をした者
- 批判的な分析、評価、新しく複雑なアイディア、芸術的コンセプトとプロセスを統合することができる者
- 同分野の研究者や、より大きな芸術的、学術的コミュニティ、専門領域に関係する社会全般とコミュニケートできる者
- 知的共同体における芸術的理解の前進において創造的で先進的な役割を果たすことができることが期待される者
それでは、こうした音楽における芸術系博士課程の学位資格基準の前提となる「研究」とは、一体、どういったものなのだろうか。「ポリフォニア」では、「リサーチ・ワーキング・グループ」を立ち上げ、そのあり方についても議論を行っている。ここで強調したい点は、そこで模索されている「研究」というものが、従来の科学的、実証主義的な意味での「研究」とは違い、音楽院、音楽大学という実践的な場ならではの新たな「研究」のあり方であるということだ。
そこには、ボローニャ・プロセスの進展した2000年代において、「研究」をめぐる学術的、また社会的な背景や位置づけが、大きく転換したということがある。「研究」の意味づけが、従来の伝統的な、科学的、実証主義的「研究」に留まらず、より「包括的な」ものへと変化していったのである。例えば、先の「ダブリン・ディスクリプター」においても、「研究」は以下のように定義されている。
この語は、学術的、職業的、技術的な全ての領域における独創的で革新的な研究を支える幅広い活動を説明するために、包括的inclusiveなかたちで用いられる。それらの領域の中には、人文科学、伝統芸術、パフォーミング・アーツ、その他の創造的なアートもふくまれる。いかなる限定的な、あるいは制限された意味においても、また伝統的な「科学的方法」にのみ合致するようなかたちで用いられるものでもない3。
音楽の分野においても、こうした「研究」の新たな意味づけは、積極的に取り入れられている。「ポリフォニア・プロジェクト」の「第3サイクル・ワーキング・グループ」が、2007年に公表したGuide to Third Cycle Studies in Higher Music Educationでは、「ダブリン・ディスクリプター」の「研究」の定義をふまえた上で、芸術家による実践的な研究をArtistic Research と名づけ、次のように定義づけている。
- 創造的な芸術家Artists for the Artsによって、また創造的な芸術家とともに行われる研究。
- 4つの領域:音楽創造・音楽演奏・音楽教育・社会における音楽。
- 芸術体験や芸術的知識、技術だけでなく、実践者の目指す芸術的な目標も研究にふくむ。
- これまで暗黙のものであった音楽家の高度な専門知識や技術を研究対象としてオープンで、共有可能なものにする。
- 研究主体:「客観的」な観察者ではない。自分自身の認識のレベルや方法を、音楽現象を記述したり評価したりする基準だけでなく、調査の究極的な対象にもすることができる。
- 研究成果の公表:公のパフォーマンス、録音、マルチメディアによるプレゼンテーションもふくむ。
- umbrella conceptであり、既存のさまざまな研究分野から研究ツールや方法論、知識の基盤を活用することが出来る4。
ここにはいくつもの興味深い視点が見られるが、大きくまとめると、次のように言えるだろう。まず研究が芸術家自身の音楽実践にむすびついたものであるということ、芸術家の実践者としての主体性というものが重視されているということ、研究成果の公表が従来の論文や口頭発表にとどまらず、さまざまな形態のものを許容しているということ、研究のアプローチが学際的であることである。
このような新たなスタンスからのアプローチは、ヨーロッパにおいても、まだ始まったばかりと言っていい。音楽における新しい「研究」のあり方が、芸術系博士課程においてどのように実を結ぶのか。今後も、こうしたヨーロッパの動向に注目すると同時に、われわれも日本の芸術系博士課程における音楽研究の方向性について、さまざまな試行錯誤をしつつ、われわれ自身の学術的、芸術的風土に根ざした新たなあり方を模索していく必要があると思われる。
- 注
- 1:Shared ‘Dublin’descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards (2004)
[ http://www.jointquality.nl/content/descriptors/CompletesetDublinDescriptors.doc ] - 2:Polifonia/Dublin descriptors (2006)
[ http://www.jointquality.nl/content/descriptors/Polifonia-Dublin%20Descriptors%20020806%20external.pdf ]
さらにより詳細な規定については、以下を参照のこと。
Guide to Third Cycle Studies in Higher Music Education (2007)
[ aecsite.cramgo.nl/DownloadView.aspx?ses=16464 ] - 3:Shared ‘Dublin’descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards (2004)
- 4:Guide to Third Cycle Studies in Higher Music Education, pp. 16-17. (2007)