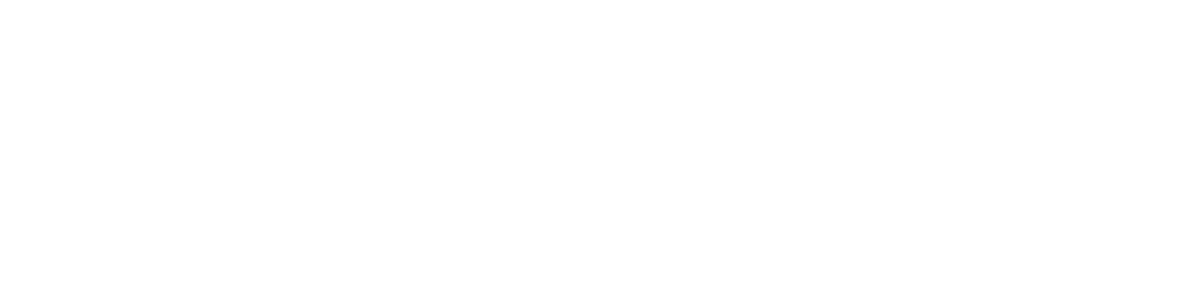

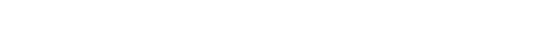
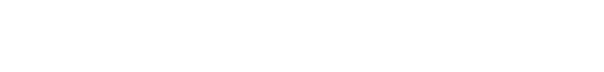
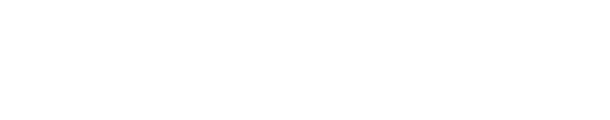
シンポジウム「藝大コレクションと美術教育」
→終了しました
→終了しました
日時:7月11日(火)18:00~19:30(開場17:30)
会場:東京藝術大学美術学部中央棟1階、第1講義室
参加方法:直接会場へお越しください。(事前申込不要、先着180名)
パネリスト:保科豊巳(本学理事)、日比野克彦(本学美術学部長)、秋元雄史(本学大学美術館館長)、千住博(日本画家)、古田亮(本学大学美術館准教授)
会場:東京藝術大学美術学部中央棟1階、第1講義室
参加方法:直接会場へお越しください。(事前申込不要、先着180名)
パネリスト:保科豊巳(本学理事)、日比野克彦(本学美術学部長)、秋元雄史(本学大学美術館館長)、千住博(日本画家)、古田亮(本学大学美術館准教授)
パンドラトーク
本学教員を中心とした多彩なゲストが、作品を解説・紹介します。
1)7月14日(金)北郷悟(本学美術学部彫刻科教授)「ラグーザの彫刻作品について」
→終了しました
2)7月22日(土)O JUN(本学美術学部絵画科教授)「私の自画像」
→終了しました
3)8月26日(土)木島隆康(本学大学院美術研究科教授)「油絵の修復」
→終了しました
4)9月 2日(土)小山登美夫(ギャラリスト・明治大学国際日本学部特任准教授)「ギャラリストからみた藝大生」
→終了しました
5)9月 9日(土)佐藤道信(本学美術学部芸術学科教授)「藝大の130年」
→終了しました
6)9月10日(日)桂英史(本学大学院映像研究科教授)「映像作品の現在」
→終了しました
集合場所:東京藝術大学大学美術館地下2階 展示室2
開始時間:各回とも14:00(開場13:30)
所要時間:1)~3)は約45分 4)~6)は約90分
参加方法:直接地下2階展示室2へお越しください。(事前申込不要、先着100名)※ただし当日の観覧券が必要です。
★各テーマ、所要時間は変更になる可能性がございます。
1)7月14日(金)北郷悟(本学美術学部彫刻科教授)「ラグーザの彫刻作品について」
→終了しました
2)7月22日(土)O JUN(本学美術学部絵画科教授)「私の自画像」
→終了しました
3)8月26日(土)木島隆康(本学大学院美術研究科教授)「油絵の修復」
→終了しました
4)9月 2日(土)小山登美夫(ギャラリスト・明治大学国際日本学部特任准教授)「ギャラリストからみた藝大生」
→終了しました
5)9月 9日(土)佐藤道信(本学美術学部芸術学科教授)「藝大の130年」
→終了しました
6)9月10日(日)桂英史(本学大学院映像研究科教授)「映像作品の現在」
→終了しました
集合場所:東京藝術大学大学美術館地下2階 展示室2
開始時間:各回とも14:00(開場13:30)
所要時間:1)~3)は約45分 4)~6)は約90分
参加方法:直接地下2階展示室2へお越しください。(事前申込不要、先着100名)※ただし当日の観覧券が必要です。
★各テーマ、所要時間は変更になる可能性がございます。
スペシャル・トーク
山口晃×古田亮 「ヘンな東京藝大」
→終了しました山口晃×古田亮 「ヘンな東京藝大」
日時:8月19日(土)14:00~16:00(開場13:30)
会場:東京藝術大学美術学部中央棟1階、第1講義室
参加方法:当日13:00より、第1講義室前の受付にて整理券を配付します。先着170名
※ただし、本展の観覧券(半券可)が必要です。
※整理券は1人につき1枚お渡ししますので、お連れ様がいらっしゃる場合は必ずグループ全員がお揃いになりましてから 整理券配布の列にお並び下さい。
会場:東京藝術大学美術学部中央棟1階、第1講義室
参加方法:当日13:00より、第1講義室前の受付にて整理券を配付します。先着170名
※ただし、本展の観覧券(半券可)が必要です。
※整理券は1人につき1枚お渡ししますので、お連れ様がいらっしゃる場合は必ずグループ全員がお揃いになりましてから 整理券配布の列にお並び下さい。
▼終了したイベント
2017年9月2日(土)14:00~15:00 会場:東京藝術大学大学美術館地下2階 展示室2(司会:古田亮[本学大学美術館准教授])

 第4回目は、本学卒業生であり、現代美術を扱うギャラリスト、コレクターとして広く知られる小山登美夫さんにご担当いただきました。小山さんは芸術学科で美術史を専攻しながらも、主に油画の学生と過ごしていたと言います。在学中から西村画廊で働き、同時代を生きる作家たちの制作現場を肌で感じながら、ギャラリストとしての経験を積んでいかれたそうです。白石コンテンポラリーアートに移ると、銭湯の建物をギャラリーに作り替えたスカイザバスハウスで、村上隆らの展示を開催。1996年にご自身のギャラリーを設立すると、バブル崩壊後ということもあり、海外に日本の現代作家を紹介していくことに力を注ぎます。小山さんのお話は、日本の現代美術のギャラリーの歴史として、非常に貴重で刺激に満ちたものでした。藝大生を含む今の若い作家にたいして、売れることを優先せず、自分が良いと思うものを大切にしてほしいと語りかける姿も印象的でした。
第4回目は、本学卒業生であり、現代美術を扱うギャラリスト、コレクターとして広く知られる小山登美夫さんにご担当いただきました。小山さんは芸術学科で美術史を専攻しながらも、主に油画の学生と過ごしていたと言います。在学中から西村画廊で働き、同時代を生きる作家たちの制作現場を肌で感じながら、ギャラリストとしての経験を積んでいかれたそうです。白石コンテンポラリーアートに移ると、銭湯の建物をギャラリーに作り替えたスカイザバスハウスで、村上隆らの展示を開催。1996年にご自身のギャラリーを設立すると、バブル崩壊後ということもあり、海外に日本の現代作家を紹介していくことに力を注ぎます。小山さんのお話は、日本の現代美術のギャラリーの歴史として、非常に貴重で刺激に満ちたものでした。藝大生を含む今の若い作家にたいして、売れることを優先せず、自分が良いと思うものを大切にしてほしいと語りかける姿も印象的でした。

 第4回目は、本学卒業生であり、現代美術を扱うギャラリスト、コレクターとして広く知られる小山登美夫さんにご担当いただきました。小山さんは芸術学科で美術史を専攻しながらも、主に油画の学生と過ごしていたと言います。在学中から西村画廊で働き、同時代を生きる作家たちの制作現場を肌で感じながら、ギャラリストとしての経験を積んでいかれたそうです。白石コンテンポラリーアートに移ると、銭湯の建物をギャラリーに作り替えたスカイザバスハウスで、村上隆らの展示を開催。1996年にご自身のギャラリーを設立すると、バブル崩壊後ということもあり、海外に日本の現代作家を紹介していくことに力を注ぎます。小山さんのお話は、日本の現代美術のギャラリーの歴史として、非常に貴重で刺激に満ちたものでした。藝大生を含む今の若い作家にたいして、売れることを優先せず、自分が良いと思うものを大切にしてほしいと語りかける姿も印象的でした。
第4回目は、本学卒業生であり、現代美術を扱うギャラリスト、コレクターとして広く知られる小山登美夫さんにご担当いただきました。小山さんは芸術学科で美術史を専攻しながらも、主に油画の学生と過ごしていたと言います。在学中から西村画廊で働き、同時代を生きる作家たちの制作現場を肌で感じながら、ギャラリストとしての経験を積んでいかれたそうです。白石コンテンポラリーアートに移ると、銭湯の建物をギャラリーに作り替えたスカイザバスハウスで、村上隆らの展示を開催。1996年にご自身のギャラリーを設立すると、バブル崩壊後ということもあり、海外に日本の現代作家を紹介していくことに力を注ぎます。小山さんのお話は、日本の現代美術のギャラリーの歴史として、非常に貴重で刺激に満ちたものでした。藝大生を含む今の若い作家にたいして、売れることを優先せず、自分が良いと思うものを大切にしてほしいと語りかける姿も印象的でした。
2017年8月26日(土)14:00~15:00 会場:東京藝術大学大学美術館地下2階 展示室2(司会:熊澤弘[本学大学美術館准教授])

 第3回目のパンドラトークは、本学で油彩画を中心とする保存修復研究に携わってこられた木島先生が担当くださいました。「古くて傷んだ油絵はパンドラの箱!――修復でよみがえる油絵――」と題された木島先生のトークでは、油絵の劣化・損傷が生じる原因に注目し、経年変化による劣化、そして人為的な破壊行為による損傷が生じてきた歴史が、明治期の油彩画や17世紀オランダのレンブラントの絵画などの多くの実例とともに紹介されました。そして、油彩画を保護する画材としての「ワニス」(Varnish)が果たしてきた役割を論じながら、芸大美術館所蔵作品の修復が実際にどのようになされてきたのかもご紹介くださいました。現在展示されている小磯良平《彼の休息》、原撫松《裸婦》、そして多くの油彩画作品が木島先生の保存修復油画研究室で修復されており、今回のトークは、保存修復の重要性を改めて認識させてくれるものでした。
第3回目のパンドラトークは、本学で油彩画を中心とする保存修復研究に携わってこられた木島先生が担当くださいました。「古くて傷んだ油絵はパンドラの箱!――修復でよみがえる油絵――」と題された木島先生のトークでは、油絵の劣化・損傷が生じる原因に注目し、経年変化による劣化、そして人為的な破壊行為による損傷が生じてきた歴史が、明治期の油彩画や17世紀オランダのレンブラントの絵画などの多くの実例とともに紹介されました。そして、油彩画を保護する画材としての「ワニス」(Varnish)が果たしてきた役割を論じながら、芸大美術館所蔵作品の修復が実際にどのようになされてきたのかもご紹介くださいました。現在展示されている小磯良平《彼の休息》、原撫松《裸婦》、そして多くの油彩画作品が木島先生の保存修復油画研究室で修復されており、今回のトークは、保存修復の重要性を改めて認識させてくれるものでした。

 第3回目のパンドラトークは、本学で油彩画を中心とする保存修復研究に携わってこられた木島先生が担当くださいました。「古くて傷んだ油絵はパンドラの箱!――修復でよみがえる油絵――」と題された木島先生のトークでは、油絵の劣化・損傷が生じる原因に注目し、経年変化による劣化、そして人為的な破壊行為による損傷が生じてきた歴史が、明治期の油彩画や17世紀オランダのレンブラントの絵画などの多くの実例とともに紹介されました。そして、油彩画を保護する画材としての「ワニス」(Varnish)が果たしてきた役割を論じながら、芸大美術館所蔵作品の修復が実際にどのようになされてきたのかもご紹介くださいました。現在展示されている小磯良平《彼の休息》、原撫松《裸婦》、そして多くの油彩画作品が木島先生の保存修復油画研究室で修復されており、今回のトークは、保存修復の重要性を改めて認識させてくれるものでした。
第3回目のパンドラトークは、本学で油彩画を中心とする保存修復研究に携わってこられた木島先生が担当くださいました。「古くて傷んだ油絵はパンドラの箱!――修復でよみがえる油絵――」と題された木島先生のトークでは、油絵の劣化・損傷が生じる原因に注目し、経年変化による劣化、そして人為的な破壊行為による損傷が生じてきた歴史が、明治期の油彩画や17世紀オランダのレンブラントの絵画などの多くの実例とともに紹介されました。そして、油彩画を保護する画材としての「ワニス」(Varnish)が果たしてきた役割を論じながら、芸大美術館所蔵作品の修復が実際にどのようになされてきたのかもご紹介くださいました。現在展示されている小磯良平《彼の休息》、原撫松《裸婦》、そして多くの油彩画作品が木島先生の保存修復油画研究室で修復されており、今回のトークは、保存修復の重要性を改めて認識させてくれるものでした。
2017年8月19日(土)14:00~16:00 会場:東京藝術大学美術学部中央棟1階 第一講義室
登壇者:山口晃(美術家)、古田亮(本学大学美術館准教授)

 今回のイベントでは、本学卒業生で、各所での個展の開催等、多方面でご活躍の美術家・山口晃さんをお招きしました。
今回のイベントでは、本学卒業生で、各所での個展の開催等、多方面でご活躍の美術家・山口晃さんをお招きしました。
藝大コレクションにおける卒業制作と自画像の歴史に触れながら、藝大で学んだことや、母校に対する率直な意見などを含め、様々な話題に話が膨らみました。特に、山口さんご自身の大学時代の制作品や、その頃のお話は、当時の藝大の様子を知る上でも大変興味深いものでした。当時教壇に立っていた先生方とのやりとりも話題になり、それぞれの先生の考え方や、当時の山口さんご本人の作品に対する姿勢がそこから明らかになりました。壇上のホワイトボードには、話が盛り上がるにつれて、山口さんが素早く絵を描く場面もあり、その度に場内の注目を集めていました。
ざっくばらんな語り口で進んだ今回のトーク。軽快な調子に場内から笑いがたえず、また時折本質を衝いた一言に一同頷く場面もあり、あっという間の2時間となりました。
登壇者:山口晃(美術家)、古田亮(本学大学美術館准教授)

 今回のイベントでは、本学卒業生で、各所での個展の開催等、多方面でご活躍の美術家・山口晃さんをお招きしました。
今回のイベントでは、本学卒業生で、各所での個展の開催等、多方面でご活躍の美術家・山口晃さんをお招きしました。藝大コレクションにおける卒業制作と自画像の歴史に触れながら、藝大で学んだことや、母校に対する率直な意見などを含め、様々な話題に話が膨らみました。特に、山口さんご自身の大学時代の制作品や、その頃のお話は、当時の藝大の様子を知る上でも大変興味深いものでした。当時教壇に立っていた先生方とのやりとりも話題になり、それぞれの先生の考え方や、当時の山口さんご本人の作品に対する姿勢がそこから明らかになりました。壇上のホワイトボードには、話が盛り上がるにつれて、山口さんが素早く絵を描く場面もあり、その度に場内の注目を集めていました。
ざっくばらんな語り口で進んだ今回のトーク。軽快な調子に場内から笑いがたえず、また時折本質を衝いた一言に一同頷く場面もあり、あっという間の2時間となりました。
2017年7月22日(土)14:00~15:00 会場:東京藝術大学大学美術館地下2階 展示室2(司会:古田亮[本学大学美術館准教授])

 第2回目のパンドラトークは、本展でも自画像が展示されている本学絵画科教授のOJUN先生がご担当されました。OJUN先生のトークは、ご自身の自画像が卒業制作提出直前の15分で描いた(!)エピソードから始まりました。そして、ほかの作家方の自画像のなかで、特に福田美蘭さんの自画像の、自らの姿をフレームから外れそうな位置に配した表現に関心を持たれたこと、ご自身の自画像制作は、18、19歳以降になるとあまり描かなくなり、それ以降は、他者の姿に関心を持っていたが、現在開催中の棚田康司さんとの二人展のなかで、再び自らの姿をモティーフに描いていることなど、OJUN先生が自画像にどのように対峙しているのかをご紹介いただきました。
第2回目のパンドラトークは、本展でも自画像が展示されている本学絵画科教授のOJUN先生がご担当されました。OJUN先生のトークは、ご自身の自画像が卒業制作提出直前の15分で描いた(!)エピソードから始まりました。そして、ほかの作家方の自画像のなかで、特に福田美蘭さんの自画像の、自らの姿をフレームから外れそうな位置に配した表現に関心を持たれたこと、ご自身の自画像制作は、18、19歳以降になるとあまり描かなくなり、それ以降は、他者の姿に関心を持っていたが、現在開催中の棚田康司さんとの二人展のなかで、再び自らの姿をモティーフに描いていることなど、OJUN先生が自画像にどのように対峙しているのかをご紹介いただきました。

 第2回目のパンドラトークは、本展でも自画像が展示されている本学絵画科教授のOJUN先生がご担当されました。OJUN先生のトークは、ご自身の自画像が卒業制作提出直前の15分で描いた(!)エピソードから始まりました。そして、ほかの作家方の自画像のなかで、特に福田美蘭さんの自画像の、自らの姿をフレームから外れそうな位置に配した表現に関心を持たれたこと、ご自身の自画像制作は、18、19歳以降になるとあまり描かなくなり、それ以降は、他者の姿に関心を持っていたが、現在開催中の棚田康司さんとの二人展のなかで、再び自らの姿をモティーフに描いていることなど、OJUN先生が自画像にどのように対峙しているのかをご紹介いただきました。
第2回目のパンドラトークは、本展でも自画像が展示されている本学絵画科教授のOJUN先生がご担当されました。OJUN先生のトークは、ご自身の自画像が卒業制作提出直前の15分で描いた(!)エピソードから始まりました。そして、ほかの作家方の自画像のなかで、特に福田美蘭さんの自画像の、自らの姿をフレームから外れそうな位置に配した表現に関心を持たれたこと、ご自身の自画像制作は、18、19歳以降になるとあまり描かなくなり、それ以降は、他者の姿に関心を持っていたが、現在開催中の棚田康司さんとの二人展のなかで、再び自らの姿をモティーフに描いていることなど、OJUN先生が自画像にどのように対峙しているのかをご紹介いただきました。
2017年7月14日(金)14:00~15:00 会場:東京藝術大学大学美術館地下2階 展示室2

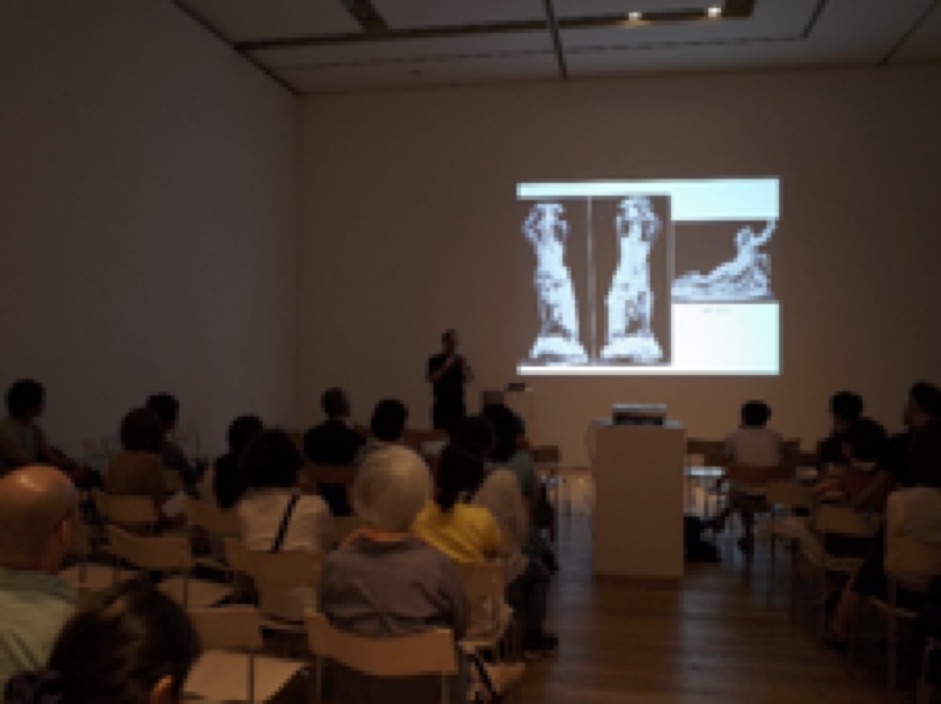 第1回目のパンドラトークは、本学彫刻科教授の北郷先生にお願いしました。北郷先生は本学のラグーザをはじめとする石膏コレクションを長年にわたり調査されており、その成果は、2010年の当館での展覧会「明治の彫塑 ラグーザと荻原碌山」でも紹介されています。このトークで北郷先生は、ラグーザの生地であるパレルモでの調査をふくめた長年にわたる研究の概要を、様々なスライドとともにご説明くださいました。パレルモの現地調査で発見されたラグーザの来歴にかかわる情報や、展示されている石膏像とブロンズとの比較、そして、彫刻をより正確に研究するための3Dデータ計測など、これまでの先生の研究が多面的に紹介されました。
第1回目のパンドラトークは、本学彫刻科教授の北郷先生にお願いしました。北郷先生は本学のラグーザをはじめとする石膏コレクションを長年にわたり調査されており、その成果は、2010年の当館での展覧会「明治の彫塑 ラグーザと荻原碌山」でも紹介されています。このトークで北郷先生は、ラグーザの生地であるパレルモでの調査をふくめた長年にわたる研究の概要を、様々なスライドとともにご説明くださいました。パレルモの現地調査で発見されたラグーザの来歴にかかわる情報や、展示されている石膏像とブロンズとの比較、そして、彫刻をより正確に研究するための3Dデータ計測など、これまでの先生の研究が多面的に紹介されました。

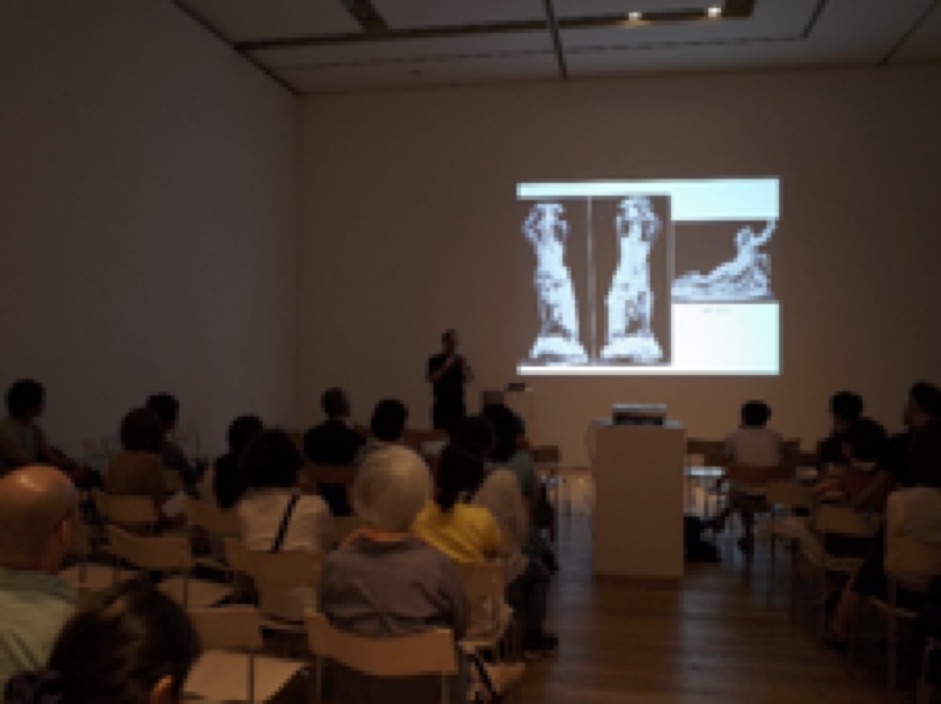 第1回目のパンドラトークは、本学彫刻科教授の北郷先生にお願いしました。北郷先生は本学のラグーザをはじめとする石膏コレクションを長年にわたり調査されており、その成果は、2010年の当館での展覧会「明治の彫塑 ラグーザと荻原碌山」でも紹介されています。このトークで北郷先生は、ラグーザの生地であるパレルモでの調査をふくめた長年にわたる研究の概要を、様々なスライドとともにご説明くださいました。パレルモの現地調査で発見されたラグーザの来歴にかかわる情報や、展示されている石膏像とブロンズとの比較、そして、彫刻をより正確に研究するための3Dデータ計測など、これまでの先生の研究が多面的に紹介されました。
第1回目のパンドラトークは、本学彫刻科教授の北郷先生にお願いしました。北郷先生は本学のラグーザをはじめとする石膏コレクションを長年にわたり調査されており、その成果は、2010年の当館での展覧会「明治の彫塑 ラグーザと荻原碌山」でも紹介されています。このトークで北郷先生は、ラグーザの生地であるパレルモでの調査をふくめた長年にわたる研究の概要を、様々なスライドとともにご説明くださいました。パレルモの現地調査で発見されたラグーザの来歴にかかわる情報や、展示されている石膏像とブロンズとの比較、そして、彫刻をより正確に研究するための3Dデータ計測など、これまでの先生の研究が多面的に紹介されました。
2017年7月11日 18:00~19:30 会場:東京藝術大学美術学部中央棟1階 第一講義室
登壇者:保科豊巳(本学理事)、日比野克彦(本学美術学部長)、千住博(日本画家)、古田亮(本学大学美術館准教授)、司会:秋元雄史(本学大学美術館館長)
 「藝大コレクションと美術教育」と題されたこのシンポジウムは、藝大コレクションのこれまでの歴史をたどりながら、藝大美術館のコレクションの役割と、制作者のための発表の場所としての美術館展示室の可能性を討議する機会となりました。
「藝大コレクションと美術教育」と題されたこのシンポジウムは、藝大コレクションのこれまでの歴史をたどりながら、藝大美術館のコレクションの役割と、制作者のための発表の場所としての美術館展示室の可能性を討議する機会となりました。
最初に、展覧会担当の古田先生による展覧会概要の説明のあと、古美術から多種多様な卒業制作など多岐にわたる藝大コレクションがこれまで展示・活用されてきた歴史と、それらを収蔵・展示する藝大美術館の独自性が紹介されました。
続いて、登壇者である千住先生、保科先生、日比野先生からは、学生時代からはじまる「藝大時代」の活動に焦点をあて、各々の先生方がどのようなスタンスで制作活動を進めていたのか、そしてそのとき、藝大は自らにとってどのような場所であったのかを振り返っていただきました。
そして、各々の先生が卒業制作を振り返りながら、藝大美術館のコレクション展示の場、 そして学生にとっての展示スペースとしての将来像に話題が広がりました。
藝大コレクションについて:
・学生時代、芸術資料館(当時)に展示されていた作品から学ぶことが本当に大きかった。絵因果経を模写する経験も大きかった。 ・古い作品に触れる経験を重ねることから、新しいものを生み出す刺激を得てほしい。
・次の世代を育てるときに、藝大コレクションに触れられる機会はとても良いはず。しかし、文化財の破壊につながることも避けねばならず、どう折り合いをつけるか。
展示スペースとして:
・学生にとって、ホワイトキューブの中で展示する経験値を重ねさせたい。制作の現場と展示の現場をクロスする経験があるとよい。
・学生に展示スペースとして無制限に開放するということは不可能だ。そのなかでどのように折り合いをつけてゆくかが考えどころになる。
・展示空間によって作品は変わるが、大学美術館の展示室スペースは、ある意味で因習的な美術館空間であり自由度は低い。この制限を受け入れたうえで展示を考えるしかない。
最後に、このシンポジウムが、学生にとっての制作発表の場としての美術館と、コレクションを継承し教育に資する活動を行う美術館という二つの側面を持つ藝大美術館の可能性をさらに考える契機となった、という秋元館長の総括とともにシンポジウムは終了しました。
ご来場の皆様、登壇くださった先生方に感謝申し上げます。
登壇者:保科豊巳(本学理事)、日比野克彦(本学美術学部長)、千住博(日本画家)、古田亮(本学大学美術館准教授)、司会:秋元雄史(本学大学美術館館長)
 「藝大コレクションと美術教育」と題されたこのシンポジウムは、藝大コレクションのこれまでの歴史をたどりながら、藝大美術館のコレクションの役割と、制作者のための発表の場所としての美術館展示室の可能性を討議する機会となりました。
「藝大コレクションと美術教育」と題されたこのシンポジウムは、藝大コレクションのこれまでの歴史をたどりながら、藝大美術館のコレクションの役割と、制作者のための発表の場所としての美術館展示室の可能性を討議する機会となりました。最初に、展覧会担当の古田先生による展覧会概要の説明のあと、古美術から多種多様な卒業制作など多岐にわたる藝大コレクションがこれまで展示・活用されてきた歴史と、それらを収蔵・展示する藝大美術館の独自性が紹介されました。
続いて、登壇者である千住先生、保科先生、日比野先生からは、学生時代からはじまる「藝大時代」の活動に焦点をあて、各々の先生方がどのようなスタンスで制作活動を進めていたのか、そしてそのとき、藝大は自らにとってどのような場所であったのかを振り返っていただきました。
そして、各々の先生が卒業制作を振り返りながら、藝大美術館のコレクション展示の場、 そして学生にとっての展示スペースとしての将来像に話題が広がりました。
藝大コレクションについて:
・学生時代、芸術資料館(当時)に展示されていた作品から学ぶことが本当に大きかった。絵因果経を模写する経験も大きかった。 ・古い作品に触れる経験を重ねることから、新しいものを生み出す刺激を得てほしい。
・次の世代を育てるときに、藝大コレクションに触れられる機会はとても良いはず。しかし、文化財の破壊につながることも避けねばならず、どう折り合いをつけるか。
展示スペースとして:
・学生にとって、ホワイトキューブの中で展示する経験値を重ねさせたい。制作の現場と展示の現場をクロスする経験があるとよい。
・学生に展示スペースとして無制限に開放するということは不可能だ。そのなかでどのように折り合いをつけてゆくかが考えどころになる。
・展示空間によって作品は変わるが、大学美術館の展示室スペースは、ある意味で因習的な美術館空間であり自由度は低い。この制限を受け入れたうえで展示を考えるしかない。
最後に、このシンポジウムが、学生にとっての制作発表の場としての美術館と、コレクションを継承し教育に資する活動を行う美術館という二つの側面を持つ藝大美術館の可能性をさらに考える契機となった、という秋元館長の総括とともにシンポジウムは終了しました。
ご来場の皆様、登壇くださった先生方に感謝申し上げます。
2017年9月9日 14:00~15:00 会場:東京藝術大学大学美術館地下2階 展示室2(司会:熊澤弘[本学大学美術館准教授])
 展覧会最終日前日に開催されたパンドラトークは、日本近代美術史を専門とされる芸術学科教授の佐藤道信先生にお願いしました。このレクチャーで佐藤先生は、東京美術学校創立から現在に到るまでの130年を、様々な資料とともに紹介されました。東京美術学校の様々な活動が「西洋系/日本東洋系の並置」「クラシック・現代系」「作家養成・教員養成」に明確に特徴付けられることを挙げつつ、後半の東京藝術大学美術学部の活動については、社会的要請に対応しつつ「新たな芸術表現に対応した組織改革」「国際化からグローバル化へ」「地域連携・産学連携」というキーワードから検証できることを紹介されました。日本近代美術史の枠組みを再定義するご研究で知られる佐藤先生ならではの興味深いレクチャーとなりました。
展覧会最終日前日に開催されたパンドラトークは、日本近代美術史を専門とされる芸術学科教授の佐藤道信先生にお願いしました。このレクチャーで佐藤先生は、東京美術学校創立から現在に到るまでの130年を、様々な資料とともに紹介されました。東京美術学校の様々な活動が「西洋系/日本東洋系の並置」「クラシック・現代系」「作家養成・教員養成」に明確に特徴付けられることを挙げつつ、後半の東京藝術大学美術学部の活動については、社会的要請に対応しつつ「新たな芸術表現に対応した組織改革」「国際化からグローバル化へ」「地域連携・産学連携」というキーワードから検証できることを紹介されました。日本近代美術史の枠組みを再定義するご研究で知られる佐藤先生ならではの興味深いレクチャーとなりました。
 展覧会最終日前日に開催されたパンドラトークは、日本近代美術史を専門とされる芸術学科教授の佐藤道信先生にお願いしました。このレクチャーで佐藤先生は、東京美術学校創立から現在に到るまでの130年を、様々な資料とともに紹介されました。東京美術学校の様々な活動が「西洋系/日本東洋系の並置」「クラシック・現代系」「作家養成・教員養成」に明確に特徴付けられることを挙げつつ、後半の東京藝術大学美術学部の活動については、社会的要請に対応しつつ「新たな芸術表現に対応した組織改革」「国際化からグローバル化へ」「地域連携・産学連携」というキーワードから検証できることを紹介されました。日本近代美術史の枠組みを再定義するご研究で知られる佐藤先生ならではの興味深いレクチャーとなりました。
展覧会最終日前日に開催されたパンドラトークは、日本近代美術史を専門とされる芸術学科教授の佐藤道信先生にお願いしました。このレクチャーで佐藤先生は、東京美術学校創立から現在に到るまでの130年を、様々な資料とともに紹介されました。東京美術学校の様々な活動が「西洋系/日本東洋系の並置」「クラシック・現代系」「作家養成・教員養成」に明確に特徴付けられることを挙げつつ、後半の東京藝術大学美術学部の活動については、社会的要請に対応しつつ「新たな芸術表現に対応した組織改革」「国際化からグローバル化へ」「地域連携・産学連携」というキーワードから検証できることを紹介されました。日本近代美術史の枠組みを再定義するご研究で知られる佐藤先生ならではの興味深いレクチャーとなりました。
2017年9月10日(日)14:00~15:30 会場:東京藝術大学大学美術館地下2階 展示室2(司会:熊澤弘[本学大学美術館准教授])
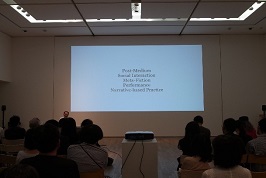 展覧会最終日に開催されたパンドラトークは、本学大学院映像研究科教授の桂英史先生にお願いしました。2005年に学部をもたない独立研究科として本学に設置された映像研究科は、従来の芸術諸分野を横断・統合し、映像に関する創造の現場という観点から新しいテーマに取り組んでいます。今回のパンドラ展では映像研究科修了制作は出展されませんでしたが、2007年度以降藝大コレクションとして収蔵されていることから、藝大コレクションの将来像を考える機会として、映像作品の状況をお話しいただきました。桂先生はまず、映像研究科の活動と研究・教育指針にふれたあと、映像研究科出身者の作品をご紹介されました。彼らの作品の意義をレクチャーされました。当館ではレクチャー会場となった展示室全体をつかって映像作品をプロジェクションする機会はほとんどなかったことから、今回のレクチャーは、今後の展示室の活用方法を再考する機会にもなりました。
展覧会最終日に開催されたパンドラトークは、本学大学院映像研究科教授の桂英史先生にお願いしました。2005年に学部をもたない独立研究科として本学に設置された映像研究科は、従来の芸術諸分野を横断・統合し、映像に関する創造の現場という観点から新しいテーマに取り組んでいます。今回のパンドラ展では映像研究科修了制作は出展されませんでしたが、2007年度以降藝大コレクションとして収蔵されていることから、藝大コレクションの将来像を考える機会として、映像作品の状況をお話しいただきました。桂先生はまず、映像研究科の活動と研究・教育指針にふれたあと、映像研究科出身者の作品をご紹介されました。彼らの作品の意義をレクチャーされました。当館ではレクチャー会場となった展示室全体をつかって映像作品をプロジェクションする機会はほとんどなかったことから、今回のレクチャーは、今後の展示室の活用方法を再考する機会にもなりました。
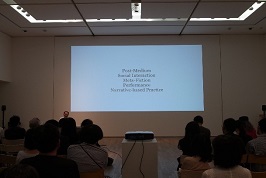 展覧会最終日に開催されたパンドラトークは、本学大学院映像研究科教授の桂英史先生にお願いしました。2005年に学部をもたない独立研究科として本学に設置された映像研究科は、従来の芸術諸分野を横断・統合し、映像に関する創造の現場という観点から新しいテーマに取り組んでいます。今回のパンドラ展では映像研究科修了制作は出展されませんでしたが、2007年度以降藝大コレクションとして収蔵されていることから、藝大コレクションの将来像を考える機会として、映像作品の状況をお話しいただきました。桂先生はまず、映像研究科の活動と研究・教育指針にふれたあと、映像研究科出身者の作品をご紹介されました。彼らの作品の意義をレクチャーされました。当館ではレクチャー会場となった展示室全体をつかって映像作品をプロジェクションする機会はほとんどなかったことから、今回のレクチャーは、今後の展示室の活用方法を再考する機会にもなりました。
展覧会最終日に開催されたパンドラトークは、本学大学院映像研究科教授の桂英史先生にお願いしました。2005年に学部をもたない独立研究科として本学に設置された映像研究科は、従来の芸術諸分野を横断・統合し、映像に関する創造の現場という観点から新しいテーマに取り組んでいます。今回のパンドラ展では映像研究科修了制作は出展されませんでしたが、2007年度以降藝大コレクションとして収蔵されていることから、藝大コレクションの将来像を考える機会として、映像作品の状況をお話しいただきました。桂先生はまず、映像研究科の活動と研究・教育指針にふれたあと、映像研究科出身者の作品をご紹介されました。彼らの作品の意義をレクチャーされました。当館ではレクチャー会場となった展示室全体をつかって映像作品をプロジェクションする機会はほとんどなかったことから、今回のレクチャーは、今後の展示室の活用方法を再考する機会にもなりました。