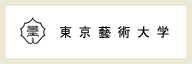リサーチ活動
Ⅲ.インタビュー集
6.ヨーロッパ音楽系大学の現在 ―菅野美絵子先生インタビュー
中村 美亜、中田 朱美
- 日時:2011年9月19日(月)14:00-15:30
- 於:北鎌倉「喫茶吉野」

- 菅野美絵子 Mieko KANNO
- ダラム大学音楽学部准教授。ヴァイオリニスト。ヨーク大学でヴァイオリン専攻の博士号取得。2008~2010年にはオルフェウス・インスティテュートに研究員として所属。現代音楽を専門とし、演奏と音楽研究を結びつけた活動を展開。
公開講座の開催に先立ち、イギリスを中心に活躍されている菅野美絵子先生に、ヨーロッパの音楽系大学の現状についてお話を伺った。以下はその時の記録である。
§1.ヨーロッパの音楽系大学の昔と今
- 菅野(以下K):
- ヨーロッパの音楽系大学は、日本と違って音楽院系と大学系の2つに分かれています。例えば、現在私の所属しているダラム大学 Durham Universityはいわゆる大学系ですが、私自身の出身校は音楽院系のギルドホール大学 London Guildhall Universityです。
近年、特にイギリスや、フィンランド、デンマーク等の北欧で、実技と学問をうまく混ぜてやっていこうとする所が増えてきました。例えば、ダラム大学はもともと学問系で、音楽学と作曲だけの所だったのですが、大学に広い意味での音楽が求められる今、幅を広げないと生徒が来てくれないという心配もあり、演奏が組み込まれるようになりました。 - 中村(以下Nm):
- そうすると、ダラム大学にはもともと演奏の人はいなかったのですね?
- K:
- いませんでした。そういう大学では大体60%は学問で、論文に重きがおかれます。一方、ロイヤル・アカデミーなど音楽院系では、論文の比重は30%位になるでしょうか。私は今、マンチェスターにある音楽院 Royal Northern College of Musicの外部審査員をやっているのですが、あそこは音楽院ながら結構音楽学のほうにも力を入れていて、それこそ芸大と同じで、本当に優秀な人が実技も学問もすごく良くやっています。
- Nm:
- それはどの段階ですか。学部?
- K:
- 学部の段階からですね。音楽を学問として捉えるという行為は、イギリスや北欧では18歳のときから始めます。むしろそれぐらいから始めないと難しい、やはり時間が掛かるということなのだと思います。いったん覚えると成長が早いとはいえ、2~3年はかかります。
§2.ヨーロッパで演奏家が博士号を取る背景
- K:
- 今から20年ほど前、私が大学を卒業した頃は、音楽院で学問をするということはあまりありませんでした。その必要がなかったのです。当時は、文化を支えるシステムがあったと言いますか、弾ければ、歌えれば、仕事がある時代でした。今では卒業しても仕事がないですよね。何か資格がないと仕事がないのではないかという不安から博士号を取る人がやはり一番多いのではないでしょうか。これをもっと積極的に解釈すると、やっぱり楽器が弾けるだけでは世の中でやっていけないということなのだと思います。才能と努力と運がすべて揃っていれば大丈夫でしょうが、これは常に期待できるわけではありません。ですから人生における様々な応用力を身につけるといった意味で、博士号を取る人が増えているように思います。
ヨーロッパの音楽院系の人たちの間で今、一番の問題は、ヨーロッパ中の沢山の音楽院の将来をどうすればいいか、ということです。そこでは、音楽だけでなく、いろんな意味ですごく優秀な学生たちが大勢勉強しています。でも彼らの身に付けている技術をうまく使える世の中というのが今はない、どうしようかという問題です。ヨーロッパの音楽院の将来を考える、ボローニャ・プロセスの一番の動機もそれだと思います。 - Nm:
- 学生さんたちの実技的なレベルは、どうなのでしょうか。芸大に限らずどこの大学もそうかもしれませんけれども、その学部でトップの人たちが大学院に行くかというと、必ずしもそうとは限らず、活躍できる人はどんどん外へ出ていきますよね。
- K:
- もちろん、仕事がすぐある人は外に出ます。ほかに仕事のある若い人たちに、それでも行きたいと思わせるほどのものが、今の大学院にはないのではないでしょうか。
教育というものは、本当に優れた人たちにとってはそんなに必要ではなく、その次の層の人たちのためにあるのかもしれません。優秀な人がいて、その次に、努力して何らかの形で貢献したいと思っている人たちがいる。そういった人たちにチャンスをあげるのが高等教育ではないでしょうか。そうした人たちが、3、4年をかけて論文を書き、世の中に出て、第一線での演奏活動という形でなくても、教育や、演奏社会のサポーター、出版業界などで活躍していきます。ですから、音楽を勉強したいというよりも、社会的な、自分の音楽家としての在り方、音楽家としてどのように世の中に貢献していきたいかということを考えるために、博士課程に進んでいる人が増えているように思います。
§3.研究テーマの見つけ方
- Nm:
- 自分たちの問題意識にかかわる研究テーマを学生はどうやって見つけていくのでしょうか。
- K:
- イギリスでは、やりたい分野を自分で探しなさいという姿勢です。音楽院の人たちの研究は、教育学系が多いです。自分たちが勉強してきた過程で知りたかったこと、例えば、なぜ先生の言う通りにするとこんなふうにうまく行くのだろうかとか、なぜ舞台では緊張してうまくできないのかとか、そういうことを研究するのですね。
一方、大学だと、ありとあらゆる研究の可能性が出てきます。私の場合は、楽器と結び付いた音楽の展開に興味があり、ヴァイオリンのアイデンティティが20世紀に入ってどのように変わったか、さらに将来どのように変わりうるか、という問題意識から出発しました。他の例としては、同世代の古楽奏者で、15世紀のポリフォニーの在り方に興味をもち、スコアがなかった時代に、どうやって一緒に演奏を行ったのかという問題を考えていく上で、自分で版を作っていった人たちがいました。また、ピアノでは、18世紀後半、ハープシコードがピアノへと変わっていく移行期に、モーツァルトのような作曲家がそうした楽器をどのように使っていたのかといったことを研究している人がいましたし、ペダルの使い方、ピアノの弦の使い方などを研究した人もいました。こういう研究は、聴き手のためだけでなく、自分たちの演奏経験をより豊かにするために研究するという姿勢だと思います。
§4.博士論文の指導
- Nm:
- 論文の指導は誰がするのでしょうか。
- K:
- 実技のPhD論文は今のところ、音楽学や作曲の教師がやっています。現段階では世界的に、実技専門のPhDを指導できる教師の人数が少ないと思います。どの大学でも生徒欲しさに、とにかく受け入れるという部分があるのを否定できません。
- Nm:
- 先生方はどのように学生たちを導くのでしょうか。
- K:
- 4年間ずっと積極的に研究を続けられるということはまずないから、離れそうになったときに、面白いものを見つけられるような方向に背中を押してあげる。専門が全く違っても、その生徒にやる気を持たせられる教師っていますよね。もっと調べたい、もっと知りたいって思わせるのが上手な先生ですよね。
§5.論文の審査
- Nm:
- 分かります。それではその論文の評価をするのは誰なのでしょうか?
- K:
- どういったPhDかによります。イギリスの場合、審査員は2人か3人からなります。15年ぐらい前だと、実技がとても良くて論文はまあまあというのがありましたけど、最近、変わってきました。最近は論文が悪いとダメですね。実技が悪くてもダメですけどね。審査が論文と演奏で50/50だとすると、それぞれのクオリティに加えて、関連の仕方が問われます。関連づけが甘ければ、書き直しとなり、合格しません。実技と研究の関連性が最も問われるからなのですよね。
- 中田(以下Nt):
- その関連性は、どのように審査されるのでしょうか。
- K:
- 演奏曲目と論文のタイトルだけでは分からないので、口述試問の際に徹底的に質問されます。書いていることを実際の演奏ではこうしていたとか、演奏ではこういう解釈をしていたがその解釈はどこから来たのか、論文で書いたこととはどんな関連があるのか、など。論文を熟読してから演奏を聞かなくてはならないので、質問する方も大変です。
- Nt:
- ヨーロッパで演奏家の方が社会に出た時、博士号の有無で違いはあるのでしょうか。
- K:
- 今のところは特にないように思います。あと10~20年たたないと分からないでしょうが。
§6.オルフェウス・インスティテュート
- Nt:
- オルフェウス・インスティテュートについて、どんな組織なのかお話いただけますか。
- K:
- PhDを授与する博士課程研究を行う部署と、私の所属した個人・共同研究を行う部署からなります。ヨーロッパにおける音楽院の人材の将来のあり方といった、先ほど申し上げた社会的・政治的な動機から設立されていますが、実際は広い意味で芸術の将来を考えるという、縛りのない研究が行われています。所長のペーター・デヤーンスPeter DEJANSの姿勢は、方向性を定めてそれを実施していくのではなく、柔軟な思考で新たな可能性を探究する研究者たちを集め、助成していくというものです。演奏家と演奏をしない人の研究の違いをいかに生かすことができるかなど、常に模索しながら動いています。
- Nm:
- どこがお金を出しているのですか。
- K:
- 今のところはベルギー政府ですが、年々少なくなっています。
- Nm:
- なぜ、ベルギー政府はそういうものに投資をしようということを考えたのでしょうか。
- K:
- 確かな標準がまだない研究から、ともすると物凄く面白い結果が生まれるかもしれないという期待から、投資しているのですよね。ただ、今はすごく難しくなっていると聞いています。この5月末、隣国オランダが芸術支援について新しい政策を打ち出しました。これまで別々だった、文化庁にあたる所と、芸術支援機構とが2013年の1月から合併され、各々の予算が半分位になることが決まったのです。そうすると、おそらくコンセルトヘボウや劇場は大丈夫でしょうが、小規模な、実験的なことをしている芸術家たちの予算が30%ぐらいに減ってしまうのですよね。そのため、オランダでは今大変なことになっていて、その影響はいずれベルギーの北部にも来るのではないかと言われています。ヨーロッパの芸術予算は、本当に年々削減されています。アメリカのような個人による後援システムの文化がまだ生まれていないので、若い人たちに仕事がなく、競争が激化しています。大学でも常勤ポストがありません。私のところは恵まれているほうと言われておりますが、生徒1学年50人ぐらいで、常勤が12人です。
- Nt:
- 非常勤の先生はいらっしゃるのでしょうか。
- K:
- 非常勤のポストは、滅多にありません。音楽院だと、学術系の常勤ポストはProfessor、Senior Lecturerで、実技ではProfessor、Instrument Teacherです。大学だとProfessor、Reader、Senior Lecturer、Lecturer。今は、本当に優秀な人たちが数少ないポストをめぐって殺到するので、審査する先生たちの方が比べものにならないほど劣るといったことも起きています。
- Nm:
- 日本でも先日、欧米で溢れている優秀な人材を配属するためのポストを作る必要がある、という話が出ていました。
- K:
- 本当にグローバル化して、仕事があれば世界中どこへでも行くという世の中になりましたね。
- Nm:
- オルフェウス・インスティテュートには、どんなきっかけでいらしたのでしょうか。
- K:
- 最初に訪れた時、演奏家で演奏についての研究経験がある者を募集していたのです。面接を経て、その後1年間、研究員となりました。2年目はイギリスの財団から研究助成を受け、2年が終わったところでダラムの常勤になりました。
- Nm:
- 博士号はどこで、いつ取られたのでしょうか。
- K:
- イギリスのヨーク大学で、2001年に博士課程を修了しました。昔から実技と作曲で有名な大学で、ここで現代音楽を始めました。PhD論文は作曲家の先生が指導してくれました。
- Nm:
- オルフェウス・インスティテュートには、その研究を継続したくて行かれたのですか。
- K:
- そうですね。私の場合、現代音楽を通して社会的に音楽がどのように変わってきているか、それによって演奏技術や、楽器製作の技術―今ですとコンピューター音楽―が、作曲行為をどのように変えているか等といった、技術とくっついた研究をしていたので、オルフェウス・インスティテュートから声をかけていただきました。
§7.クラシック音楽の今後
- Nm:
- これからクラシック音楽、音楽状況はヨーロッパでどうなっていくと思いますか。
- K:
- オルフェウス・インスティテュートに行く前にしばらく行っていたカナダのバンフ・センター【Banff Center】では、とても独創性のあるポピュラー音楽の人たちと出会いました。彼らの研究が、とても面白かったんです。ポピュラー音楽ですと、研究と作曲と演奏がすべて混ざっていますよね。実技の研究をもっと考えるとなった時に、そういう人たちの研究方法や、社会的なあり方から学ぶことはすごく大きいと思いました。あとは、民族音楽学。ほかの音楽文化のあり方をもっとよく知ることで、そこから学ぶところもあるのではないでしょうか。むしろそうしないと、将来はあまりないのではないでしょうか。一般的に、今、クラシック音楽はそんなに聴かれませんから。聴くとなると、自分たちの知っている音楽を聴くという風に、触れ合いの範囲が狭まってきていますよね。その間口を何とか拡げていきたいものです。
- Nm:
- 長時間に渡り、貴重なお話をどうもありがとうございました。