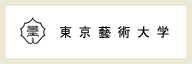リサーチ活動
Ⅰ.全体の潮流
3.実践との新たな関係を築く学位論文 ―シベリウス・アカデミーの実例から
吉川 文
作曲や演奏といった音楽実践は、博士課程における研究とどのような形で結びつくものなのか。作曲家や演奏家にとって、アカデミズムの中での研究活動はどう位置づけられるのか。当リサーチセンターではこうした問いに答えるために、国内外の諸大学における博士課程での様々な研究動向を調査してきた。博士課程における研究を考えていくにあたり、各大学・研究機関における制度的な枠組み、さらにはそれぞれの機関がおかれた国や地域の状況が、研究のあり方や内容にも大きく関わっていることが確認されている。ここでは、フィンランドのシベリウス・アカデミーの博士学位論文を具体例として取り上げ、演奏実践に軸足をおいた諸研究について報告する。こうした論文では、研究において様々な新しいアプローチの方法がとられ、芸術分野での博士学位論文の新たな方向性を考える上でのひとつの足がかりとなるものと考えられる。
シベリウス・アカデミーにおける論文を取り上げるのには、いくつかの理由がある。具体的な研究成果に興味深い事例が見られることはもちろんだが、博士学位論文が生み出される制度についても具体的な情報が得られていたこと1、さらにそれぞれの論文に、シベリウス・アカデミーの図書館のサイトからアクセスできたこと2などが挙げられる。論文の具体例を取り上げるに先立ち、シベリウス・アカデミーの博士課程プログラムの内容について、ごく簡単にまとめておこう。
フィンランド唯一の音楽大学であるシベリウス・アカデミーは、学生総数1300~1400人規模の大学で、博士課程の在籍者は140~150人程度、全体の約1割を占める。ここでの博士課程の特徴は、音楽学や作曲、演奏実技等の専攻をどのような形で深化させるかによって、3種のプログラム、すなわちArts study program、Research program、Development study programが準備されている点である。Arts study program は演奏や作曲の実践的スキルをさらに磨く方向を目指すもので、学位取得に必要な単位の多くは5回のコンサートの開催で充当され、付随する論文は短めのものとなる。ここで求められるのは何よりもアーティストとしての高いレベルである。Research program の場合は研究論文の占めるウエイトが大きく、内容・レベルとも一般大学の博士課程と同等程度、何より研究者としての資質が問われる。Development study programでは、実践的プロジェクトとその記録であるプロジェクト・ポートフォリオが学位取得要件の中心となる。これは、実際にコンサートを開く、あるいは教授方法をデモンストレーションする他、教材作成、ソフトウェア開発など様々な活動を含みうるもので、論文も必要とされる。ここで求められるのは新たな方法論を生み出し、展開していくあり方で、実践と研究との関わりという観点から注目される。
それでは具体的な最新の研究例を見てみよう。音楽実践が最も重要視されるのはArts study programであり、エリサ・ヤルヴィElisa Järvi 氏の研究 “A Turning Kaleidoscope. Aspects of György Ligeti’s Piano Etude Fém (1989).”は2011年のこのプログラムでの研究論文であり、リゲティのピアノ練習曲〈Fém 鋼鉄〉をテーマにしている3。120頁ほどの研究論文には学位取得に必要な5回のコンサートの記録も併記されており、たとえばソナタと変奏曲にジャンルを定め、スカルラッティから現代フィンランドの作品を取り上げるといった形で、それぞれコンサートのテーマが設定される。論文に取り上げられているリゲティの〈Fém〉は、実際に第4回のコンサートで演奏されているが、このコンサートはシューマンの《子供の情景》の中の1曲〈Von fremden Ländern und Menschen異国から〉をタイトルに据え、モーツァルトのソナタ、ノルドグレンの〈雪女〉(小泉八雲の怪談によるバラード)、バルトークにちなんだ自作曲等もとりあげている。コンサートと論文とはもちろん関連づけて考えられるものであるが、論文は対象を非常に限定しているのに対し、コンサートでは演奏家として多様な作品を積極的に取り上げる姿勢を明示していると言えるだろう。論文ではリゲティの〈Fém〉のリズム、拍節感をどう捉えるのかといった問題に焦点を絞り込んでいる。この曲に関してはリゲティ自身が「表記された小節線は便宜的なもので決まった拍子はない」としながら「様々なアクセントを自由につけて」演奏することを求めているため、演奏者としてどのような解釈が可能かを探求している。ここで論者はリゲティの残したスケッチなどの一次資料にあたる中で、彼が南アフリカの民族音楽やエッシャーの騙し絵、数理的幾何学的図像にいたるまで、多様な発想の源泉を持っていたことを明らかにしている。ある種の規則正しいパターンを持ちながら動的に変化し続けるリズムを、ここで筆者は論文タイトルにもある万華鏡に喩え、実際に〈Fém〉の拍節構造を円環の図像によって示している。さらに、文書資料に依るだけではなくリゲティの弟子へのインタビューを行ったり、ヨーロッパ出身とアフリカ出身の音楽家に対するこの作品の聴取実験を通じて、楽曲の多様な構造を炙り出そうとする。最終的に想定し得る拍節構造には、リゲティの抱いた関心の多彩さが反映すると共に、この複雑な作品に対する深い理解が演奏家としてのより自由な解釈を支えるものであることが示され、演奏実践へ直接還元される形で研究成果がまとめられている。研究を支えるものとして、従来の音楽学的な資料研究はもちろん、数理的原理や、あるいは音楽聴取の実験を行うにあたっては最新の音楽心理学的な動向への目配りもするなど、演奏者としての立場から広く学際的な視野をもって具体的な演奏実践を考えていこうとする姿勢を見ることが可能である。
音楽実践と研究との関係を考える上で興味深いDevelopment study programに属する成果としては、2010年に提出されたクリスティーナ・ユンツ Kristiina Junttu 氏の研究“Kurtág, György, - Játékok.”がある。ここでは氏が直接教えを受けた作曲家ジェルジュ・クルターグのピアノ作品《Játékok 遊び》を、新たな形での初等ピアノ教育の場で用いる実践例としてとりあげている4。この作品は初歩のピアノ教育に用いられ得る短い曲を集めたものだが、グリッサンドやトーン・クラスターなど、伝統的な演奏法には含まれないような手法を積極的に採り入れ、タイトルにもあるようにピアノという楽器をまさに「玩具」として扱い、身体全体を使って演奏するような意図がこめられている。この作品をひとつの素材として、ピアノの初歩の教育をどのような形で実践することが可能か、研究のポートフォリオとして提示されたプロジェクトは3つの形をとるものとなっている。第1のものは研究者自身の開設するWeb上のサイト5で、ここには《遊び》やそこから発展して即興で演奏する子供たちの様子、及び研究者自身の演奏の様子を記録した動画が、指導のポイント等の説明と共にアップロードされている。演奏する様子だけではなく、腕や肩を大きく回す体操や、リズム感を身につけるために2人で向かい合って行う手遊びの様子などの動画も数多く含まれ、演奏における身体の活かし方がひとつの重要なテーマになっている。第2のプロジェクトはクルターグの《遊び》を軸にピアノ指導法についてまとめた研究レポートである。これが研究論文の形に一番近い形のプロジェクトになり、クルターグの伝記的情報や《遊び》についての分析、ビアノの初歩的指導にあたってどのような形で《遊び》が利用できるものか、子供の自然な生理学的発達とも関連する形で言及している。このレポートも同じく研究者自身のサイトで閲覧することができるが、第1の動画を中心としたプロジェクト、そして第3のプロジェクトとなるコンサートと非常に密接に関連し合うものであり、論文のみが独立する形は意識されていない。第3のプロジェクトであるコンサートは〈Juhlat mustilla ja valkoisilla koskettimilla - György Kurtág 80 vuotta 黒と白の鍵盤でお祝い─ジェルジュ・クルターグ生誕80年〉と題され、2006年にシベリウス・アカデミーの室内楽ホールで行われた。ここでは研究者自身とともにヘルシンキ周辺の音楽学校に学ぶ子供たちが演奏しており、この様子も同サイトで確認することができる。実践と深く結びつき、身体論などの新しい知見も積極的に取り込んだ研究内容、そしてまたその成果を実際に音楽教育の場に還元し、インターネットなどの新たなメディアを通じて次々に発信している様子は、まさに新たな方法論を生み出し、展開していくというDevelopment study programに即した研究のあり方を示すものと言えよう。ユンツ氏は独奏や室内楽での演奏活動を行いながら、ピアノ教師への指導やマスタークラスでの教育活動にも熱心に取り組んでいるようで、2012年のコルスホルム音楽祭でもピアノ・スタジオ・プロジェクトのマスタークラスの講師を務めている。
音楽実践と研究との関係という観点から注目されるDevelopment study programであるが、シベリウス・アカデミー学長は今後の方向性として、このプログラムに沿った学位取得者は大きく増えていくことはないだろうとの見方を示している。1990年に最初の博士を出して以来2011年まで127件の学位取得件数のうち半数以上を占めるのがArts study program で74件、ついでResearch program が43件、Development study program は10件に留まり、他のプログラムのように順調に件数を伸ばしている様子は見られない。学長自身Development study programでの博士学位取得者であるが、このプログラムが音楽実践と研究活動の間にやや中途半端な形で位置づけられているため、学位取得者が研究と実践のどちらに軸足を置いて博士の学位を得たのか、外の社会から見てわかりづらく、それが不利益となりかねない点を指摘している。実践と研究との関わりという点では、むしろ今後は純粋な研究活動そのものの守備範囲が広がり、Development study programの多くはResearch programに含まれる方向に向かうのではないか、そして音楽に限らず、自然科学等を含む学問全般の研究を見ても、ポートフォリオ的な複数プロジェクトを総合した形で博士研究が行われつつある動向に言及している。今まで演奏や作曲とは非常に対立的に捉えられがちだった「研究」そのものが、大きく変化しつつあるという点は注目すべきであろう。
今後多様な研究方法の可能性を包括するとされたResearch programの具体例には、2011年の学位研究であるパイヴィ・ヤルヴィオ Järviö Päivi 氏の“A Singer’s Sprezzatura ? A Phenomenological Study on Speaking in Tones of Italian Early Baroque Music.”がある6。氏は、初期バロックのレパートリーを中心に活動する演奏家であるが、学位プログラムとしては研究論文に大きな比重の置かれるResearch programを選択している。350頁を超える学位論文の主題は、イタリア初期バロックの歌唱法、特にレチタール・カンタンドについてで、モンテヴェルディの《オルフェオ》を具体例に、音楽史や音楽理論、歴史的演奏研究を土台にした非常に専門性の高い学術論文である。特にここでは「語ること」と「歌うこと」との関係が大きなテーマであるが、その身体性に関わる部分で重要になってくるのが、研究者自身の演奏家としての豊富な実践経験であり、これが研究を進めていく上での大きな拠り所となっている。ヤルヴィオ氏は、演奏家として積極的な活動を行いながら、演奏実践を活かした研究活動にも意欲的に取り組んでいるようで、タンペレ大学での音楽研究プロジェクト“Music, Living Body and (E)motion”にも参加している。氏の場合、自身の演奏活動と研究活動とが相補的に深く繋がり、高め合うものとなっていることが窺われる。
シベリウス・アカデミーにおける博士学位プログラムとその最新の研究成果の具体例において、それぞれの演奏家=研究者が、自らの演奏実践を土台に、最新の研究動向にも目を向けながら研究を行っている点は共通しているが、その研究を演奏と関係づけながらどのような形 で提示し、社会に問うていくのか、アプローチの方法にはかなりの差異が認められる。演奏実践に対する研究の位置づけ、その発信のあり方を考えていくことは、博士学位取得後に、演奏家=研究者が自身の活動をどのような形で展開させていくのかという点にも関わってくる。学位取得者の側の意識と社会におけるニーズの双方に目を向けながら、博士課程のプログラムのあり方を考えていくことが重要と言えよう。
- 注
- 1:音楽研究科リサーチセンターでは、音楽学部と協定校の関係にあるシベリウス・アカデミーのデュープシュバッカ学長と2009年11月25日に懇談会をもち、アカデミーにおける博士課程のシステムや研究への具体的な取り組み方について直接伺う機会を得た。
- 2:シベリウス・アカデミーの図書館の論文検索サイトのアドレスは以下の通り。[http://ethesis.siba.fi/?language=en_EN&]
- 3:[http://ethesis.siba.fi/showrecord.php?ID=411828]
- 4:[http://ethesis.siba.fi/showrecord.php?ID=399313]
- 5:[http://www.junttu.net/kristiina/In_English.html]
- 6:[http://ethesis.siba.fi/showrecord.php?ID=412629]