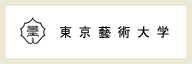リサーチ活動
Ⅳ.学内調査
2.邦楽科における博士研究
森田 都紀
リサーチセンターでは、これまでの海外調査や学内におけるサポート活動などを通じて、演奏実践と研究とが密着した新たな活動に注目し始めている。演奏実践と研究とが密着した活動とは、演奏実践の場で生まれた疑問を研究という形で分析検証し、その成果を再び実践の場で示すものである。しかし、こうした活動が注目される以前より、邦楽科の博士課程では演奏実践と研究とを一体化させた活動が行われていた。ここでは、平成20年にリサーチセンターが開設されてから昨年度までの邦楽科の博士学生の活動の一部を紹介することにしたい。
§1.博士研究のテーマの設定に至るまで
平成20年度から23年度の間に、邦楽科に提出された博士論文は下記の5本である。
- A.「山田検校の古曲についての研究」(平成20年度)
- B.「囃子の視点による《京鹿子娘道成寺》の楽曲研究」(平成21年度)
- C.「琴(箏)を通した上調子の発生と発達」(平成22年度)
- D.「日本舞踊演出論 : 新しい「素踊り」としての「現形式」の提案と検証」(平成22年度)
- E.「吾妻能狂言の研究:その芸態と後世への影響」(平成23年度)
AとBは、現行伝承においてこれまで明らかにされていなかった音楽実態を①資料調査や演奏家へのインタビューを通して調査し、②整理したもの。Cは、現行する技法の変容を①歴史史料を解読、②①と現行伝承とを照らし合わせて音楽分析、③分析して得られた成果を演奏会で実践して実験的な検証を行い、その成果をこれからの音楽実践への布石としたもの。Dは、現行伝承の目指す方向性に疑問を持ち、①新たな伝承の姿を求めて仮説を打ち立て、②それを検証するための「創作曲」を作曲して演奏会で実践・検証し、③得られた検証結果をふたたび机上で整理・考察して、新たな理論として提唱したもの。Eは現行しない過去の音楽伝承を①歴史史料を紐解いて明らかにし、②導き出された過去の音楽実態を「復元(創作)」演奏という形で演奏会にて検証し、それをもとに現在の音楽伝承の方向性について考察したものである。
C、D、E は、博士課程に入学する以前からの問題意識を扱ったもので、幼いころから抱いていた疑問を取り上げたり、修士課程の修士論文で論じきれなかった課題を発展させたりしたものである。博士研究のテーマは博士課程に入学する段階に設定されたというより、入学以前から日々の実践の場で温めてきたものであると言える。実践の場で問題意識としてもっていたものを解決し、その成果を演奏実践へ還元したいという思いが博士学生のなかに確固として在り、それが博士課程に入学する大きな動機ともなっていたようである。
研究の目的や意義、アプローチなどについて明確な指標を持つことができた背景には、邦楽の演奏家を取り巻く事情も関係しているかもしれない。というのも、演奏家が技法などの演奏実践に疑問を持ったり、疑問を学問という形で考究したりすることを、必ずしも邦楽に携わるすべての人が前向きであるとは言い難く、演奏実践と研究の両方から支えられた新しい活動を目指すには東京藝術大学に在籍していることが一助となっていたように見受けられるためだ。邦楽科の博士学生の一人は、自分の置かれた環境について次のように語っている。
私の所属している邦楽専攻は博士論文を書かれた先輩が極少ない分野です。だからこそ可能性は広く価値は高いものだと考えますが、現実はかなり厳しい状況です。古典芸能という閉ざされた世界であることによる研究の限界や、先駆者の少ない状況から興味や理解を示してくれる人のいない中孤独な戦いを強いられることもあると思います。演奏家が研究をするということ自体への反発もあります。しかしそんな中でも受け継がれてきたものの中に見いだせることが沢山ありますので、人のご縁を大切にしながら、いろいろに興味を持って接していくことが大切と、私自身、今も気を付けています(『東京藝術大学大学院音楽研究科リサーチセンター平成23年度活動報告』pp.112-113)
邦楽科の博士学生が厳しい状況のなかで演奏実践と研究を両立している姿が窺える。そして、東京藝術大学という場を最大限に活用して研究課題を遂行し、検証結果を自分自身や自分の専門分野へ還元したいという思いも伝わってくるのである。
§2.博士研究の進め方
演奏実践と研究を車の両輪のように捉えて活動を行うのに重要な場となったのが、学内において開催される「博士リサイタル」である。
「博士リサイタル」は、博士課程の学生が企画・運営する演奏会のことで、博士課程の3年間に3回開催される。指導教員と相談のうえ、学生が自由に曲目や共演者、舞台設備、上演形態などを決めていく。A~Eは、「博士リサイタル」を研究によって導き出された成果の検証の場として捉えた。3回の演奏会で実践して得られた考察結果は、博士論文の主軸に据えられた。
たとえば、D:「日本舞踊演出論:新しい「素踊り」としての「現形式」の提案と検証」は、日本舞踊専攻生が日本舞踊家の視点から日本舞踊特有の表現とは何かを考え、新しい演出の確立を目指したものである。先行研究や自らの体験、他の日本舞踊家へのインタビューなどをもとに日本舞踊の新しい舞台表現の案を組み立て、それを「博士リサイタル」で表現して検証した。検証をより綿密に行うために「創作曲」を委嘱し、自ら振りを創作して発表した。そこで得られた成果はふたたび机上に戻され、考察が重ねられた。
こうした研究のプロセスは博士論文の章立てにも反映している。具体的には、現在の日本舞踊の上演形式の成立を史料や日本舞踊家へのインタビューをもとに整理し(第1章)、それを踏まえ新たに日本舞踊独自の舞台表現の構想を提案(第2章)、第2章で提案した表現法を実際の「博士リサイタル」で実践・検証し(第3章)、その考察に基づき日本舞踊に独自の表現法を提唱して、今後の発展の可能性や課題について総括した(第4章)。「博士リサイタル」の録画映像は博士論文に付録として付し、実践的な検証の現場を公開した。こうして、「博士リサイタル」での考察をもとに築き上げられた提唱は、非常に説得力のあるものとなった。
実践の場でなされる試行錯誤を文字という形にしていくなかで、研究の整理に役立ったのが「博士リサイタル」で配布するプログラムである。プログラムは、リサイタルに集まる一般を対象に配布するものであるが、こうした配布資料を単なる曲目解説ではなく、研究成果の発表の場として捉え、その執筆に力を注いだ。プログラムには、博士研究の目的、研究対象、研究の意義などのほかに、今回の演奏会の位置づけや、今回の演奏を通して何を検証しようとしているかなどの専門的な内容も記述した。プログラムは研究論文の体裁を成すこともあったため、指導教員に配るものとはべつに、一般用に研究内容を噛み砕いたものを作成して配布した学生もいた。また、「博士リサイタル」は博士研究の主軸であったので、そのプログラムを丁寧に執筆することは博士論文の執筆に直接的に結びついた。毎回のリサイタルのプログラムを丁寧に書き重ねることによっては、研究のプロセスが明解になった。このことは博士論文の質にも大きく影響したのではないかと思われる。
リサーチセンターにおける個別サポートの場においても、プログラム執筆段階からサポートに従事した。文章の言葉使いや論理の展開なども重要であるが、それ以上に、実践の場で身体を通して感覚的になされている思考が言語という別の形で具現される難しさをサポートした。頻繁に対話を重ね、身体で感じている問題や関心を言葉に置き換える場を積極的に設定するように心がけた。
§3.おわりに
これまで演奏家は、自分自身の演奏実践について言語を用いて積極的に発信してこなかったが、演奏家自身が自らの演奏実践を言葉に置き換え社会へ伝えていくことは、音楽文化を豊かにし、支えていくことになるに違いないと考える。演奏実践と研究とが密着した活動を行った邦楽科の博士学生も、次のように語っている。
邦楽では研究という分野はあまり進んでいません。実演する人は研究するべきでなく演奏に徹するべきであるという風潮があります。しかし、これまでのような口伝による伝承に頼っていると残っていかないものもあると思われるので、文字として研究成果として残していくことが大切です。また、いわゆる研究者は実際に演奏することはできないので、私たち中間にいる者が具現化し、パフォーマンスとして表していくことが大切だと思います。その両方を行き来できる立場として、これからも研究を続けていきたいです。(「第2回Dコンサート」にて。2012年7月1日。於東京藝術大学音楽学部内第6ホール。)
演奏実践と研究とが密着した活動は実践から生まれ実践に還元されるため、実践と研究とがループ状に繰り返され、創造活動に常に新しい光が投げかけられる。したがって、実技系博士課程において演奏実践と研究とが密着した活動を行うには、これからの社会の行く末を見据え、社会に向けてどのような形で演奏実践を発信したいかということをイメージしていくことが重要だと考える。