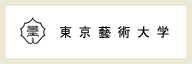リサーチ活動
Ⅰ.実技系博士学位授与に関する研究
2.実技系美術課程博士学位に関する将来の方向性について
美術研究科リサーチセンター主任 越川 倫明
東京藝術大学大学院美術研究科リサーチセンターは、平成20年度から文部科学省の特別研究経費(教育改革)の予算措置をうけて設置された(平成24年度までの5ヶ年計画)。その主たる目的は、実技系博士課程における課程博士学位審査および授与システムについて調査を行ない、望ましいシステムの姿を提示することである。同時に、学位取得のために不可欠な課題でありながら、実技系学生にとって必ずしも手慣れた分野とはいえない「論文」の執筆について、どのような指導体制・評価体制が可能かという、非常に切実な問題に対して、将来をみすえた回答を見出すことが求められている。
この平成21年度の報告書は、この調査計画の2年目の活動について報告するものである。21年度の調査においては、主として、
- ① 学内教員が博士学位についてどのような考え・イメージをもっているか
- ② 国内の主要な美術系大学における現状の把握
- ③ 海外の美術系大学における博士課程運用の実例
- ④ 20年度よりスタートした実技系学生に対する論文執筆支援プログラム(試行)の継続的効果測定
に関するリサーチを進めた。
平成20年度活動報告書の序文1において、本学における博士プログラムの検討課題の抽出を行なったが、それに引き続き、以下本稿では、より具体的に美術研究科における実技系課程博士学位プログラムの将来的方向性について、見解を述べることとする。
なにを評価して学位を与えるのか
大学院教育における現在の基本的な博士プログラムの形式は、従来、国内外を問わず純粋学術系の高等教育課程を念頭に設計されている。一方で、美術系大学院の実技諸領域の教育理念は、中核的には「優秀な実技者、アーティストを育成すること」におかれているのが通常である。もちろんそこには様々なヴァリエーション(「実技教育者の育成」、「高度な技法研究」、「新しい制作技術開発」等々)があり得るものの、学生の能力に対する実技系教員の評価基準は、多くの場合、作品の創作能力(creative ability)に重点をおくのが当然といえる2。
このような状況にあって、博士課程設置(本学では1977年)以来、実技系のプログラムは「作品と論文」を総合的に審査するという方式によって、制度と教育理念との齟齬を回避してきた。とはいえ、既存のプログラムが純粋学術系をモデルにしていることから、ともすれば「作品」は参考的な位置づけである、という認識が生じかねない。本学の学位規則第5条の文言でも、審査対象の定義として「博士論文(研究領域により研究作品又は研究演奏を加える)」となっており、これは読み方によっては、「博士論文を補足するものとして、研究作品を提出する」ともとらえられるだろう。
こうした認識は、課程設置当時においては避けがたいものであったかもしれず、また「博士学位はやはり学術系を主体とするものであり、そもそもアーティストを目指す者になぜ博士学位が必要なのか」という根強い疑念とも関連しているように思われる3。しかしながら、もはやこのようなあいまいな考えの下では、現に稼働している学位プログラムを効果的に運用することは難しいといわざるをえない。
国際的傾向としての博士学位の多様化
実技系博士プログラムは、いまだ国際的に一般化した存在ではない。平成21年度活動報告書Ⅶ章にあるように、欧米でも導入状況に著しい偏りが見られる。特にプログラムの設置が進んでいるのは、英国、および英国をモデルとするオーストラリアであることが分かる。一方、フランスやドイツなど、ヨーロッパの伝統的な美術アカデミー・美術学校系の高等教育機関では、博士プログラムを未導入なところが多い。しかし、いま現在はおそらくまさに過渡期にあり、EU内の高等教育システムの基準統一化をはかる「ボローニャ・プロセス」4の進行とともに、新たに課程を設置する機関も増えてくることが予想される。
際立って先行している英国の場合、1980年代以降、大学教育における博士課程のあり方全般について大規模な再検討が行なわれ、従来の純粋学術研究系の論文ベースの学位授与とは性格を異にする、多様な種類の学位認定のあり方が検討されてきた背景がある。そのなかで、美術(arts and design)領域は「実践に基づく博士学位(practice-based doctorate)」としての位置づけがなされたわけである5。このようなトレンドは、今後多かれ少なかれ欧米の各国に影響を及ぼしていくものと思われる。
こうした国際的状況に照らして、本学美術研究科における「作品と論文」を審査対象とする実技系の学位授与システムは、方向性としてなんら無理のあるものではない。むしろ現在の課題は、学位審査の対象としての作品の位置づけをよりいっそう明確化し、同時に、制作者による「論文」がもつ意味づけをも明確化していくことであろう。
コース区分の明確化の必要性
現在の本学美術研究科では、ふたつの専攻(「美術」と「文化財保存学」)に対応してふたつの種類の学位(「美術」と「文化財」)が授与されている。しかしながら、すでに昨年度の報告書でふれたように、そのふたつのなかで「作品と論文」による学位と「論文のみ」による学位は、いささか複雑な分布を示している。具体的には以下のようになる。
- a.「作品と論文」を提出する研究領域
- 日本画・油画・版画・壁画・油画技法材料・彫刻・彫金・鍛金・陶芸・漆芸・染織・木工芸・ガラス造形・デザイン・美術教育
- b.「論文」のみを提出する研究領域
- 建築理論・美学・日本東洋美術史・西洋美術史・工芸史・美術解剖学・保存科学
- c.「作品と論文」あるいは「論文」のみのいずれかを選択できる研究領域
- 建築設計・環境設計・構造計画・先端芸術表現・保存修復
「作品と論文」の場合と、「論文」のみの場合では、審査プロセスや審査委員構成などに顕著な相違がある。現行では両者が単一の学位規則・手続き書式を共有して学位授与プロセスが運用されているが、「作品と論文」による学位授与の独自性を明確化するためには、両者のコース区分を明確にした学位プログラムを(学位規則の下位規定として)作成する必要があろう。
さらに、学位の種類についても、再検討の余地があるように思われる。明確なカテゴリーをなす「文化財」は別として、一案としては、現行の「美術」で一括される学位種類を「美術DFA」と「学術PhD」に区分することが考えられる。(ちなみに本学音楽研究科では従来からそのような方針を採っている。)それによって、「美術」学位については「作品」の評価ウェイトが高いことを明確に打ち出す必要があると思われる。
「作品」の審査
実技系の学位認定が「作品」を重視して行なわれるのであれば、作品審査の質的保証が問題になることは論をまたない。しかしながら、この点でなんらかの統一的数値基準を無理に設けたり、単に形式的な「客観性」を求めることは、むしろ弊害をもたらすことになるのではないだろうか。質的保証は、主として以下の項目により行なわれることが適切と思われる。
- 適切な審査委員構成の確保
- 審査対象作品の公開性の確保
- 審査所見の公開性の確保
これに加えて、アーティストの場合、学位申請者の在学中の「実績」(受賞歴、展覧会出品歴等)に対する評価も、対社会的に有効なアクレディテーションの一部となるだろう。
「論文」の指導システムの必要性
一方、実技系学生が「論文」執筆に対して全般的に不慣れであることは昨年の報告書で述べた通りである。従来、「論文」の完成ができないために満期退学を選択した学生が多数いたことは容易に想像されるところであろう。したがって、この面に効果的な教育支援を提供するシステムが必要であることは明白であるが6、このような教育機能をもつ常設のシステムを設置している美術系大学は、本学を含めて国内にほとんど見当たらない。
平成21年度活動報告書のⅫ章に掲載した教育効果調査では、リサーチセンターによる論文執筆支援カリキュラム(試行)が、教員・学生双方から一定の積極的評価を受けていることが分かる。また、平成20年度以降の実技系美術学位取得者数の推移を見ると、20年=28名、21年=30名、22年=37名と、高い水準を維持していることが分かる。いちがいには言えないが、特に22年度におけるこれまでにない人数の学位取得者には、リサーチセンター発足時の博士課程入学者が多数含まれており、試行カリキュラムを通じて在学1年次から段階的に論文の完成へと方向付けを行なったことを、学位取得率向上の一要因とみなすことができるかもしれない。
以上を考慮すれば、実技系学生に対して論文作成の基礎的技術を教え、執筆のための調査方法と言語表現のアドバイスを与える教育機能は、実技系博士プログラムの不可欠な一要素と考えることができる。したがって、リサーチセンターの時限予算により現在試行カリキュラムとして行なわれている機能を、平成25年度以降もなんらかのかたちで存続させていくことは、本学の博士課程プログラムの効果的な運用にとって非常に重要な課題だと考えられるのである。この点では、すでに常設のリサーチセンターが定着し、実技系博士プログラムと緊密に連動して機能している英国の例を参考にできるであろう。
*
以上、美術研究科博士課程の将来的な方向性に関して、最も基本的ないくつかの論点について述べた。国際的に見ても、博士学位のあり方は活発な議論の対象であり、多くの変化がいままさに起こりつつある状況である。プログラム整備・改善の基本的なターゲットは、「精選された人材の入学」→「効果的な指導体制による教育」→「学位取得率の向上、学位の質的向上」というサイクルにつきるだろう7。重要なことは、本学のこれまでの伝統によって確立されてきた慣行的システムの優れた点を尊重しつつ、そこにできるかぎり明確な定義を与え、さらに時代の変化と多様性に対応できる柔軟な姿勢を保ちながら、教育課程にさらなる活力を付与していくことだと考えられる。
(平成21年度活動報告書序文)
- 注
- 1:『東京藝術大学大学院美術研究科リサーチセンター 平成20年度活動報告書』(平成21年9月)、1~6頁参照。
- 2:平成21年度活動報告書Ⅲ章に結果を掲載した学内教員アンケートでは、望ましい実技系博士学位取得者像として、「優れた実技能力をもち、かつ、言語による一定の理論的説明能力をもつ者」という一般的イメージがうかがわれる。
- 3:こうした疑念は国内的状況にとどまるものではなく、海外の伝統的なアカデミー系実技教育機関にも根強い考えと思われる。このことは、筆者がニューヨークのプラット・インスティテュートおよびデュッセルドルフ美術アカデミーの教員と意見交換した際にも感じられた。
- 4:ボローニャ・プロセスの概要については、木戸裕「ヨーロッパの高等教育改革―ボローニャ・プロセスを中心として」、『レファレンス』658号(2005年11月)、74-98頁(http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200511_658/065804.pdf)を参照。
- 5:Chris Park, Redefining the Doctorate, The Higher Education Academy, York, January 2007参照。特に「実践に基づく学位」については、pp. 32-33参照。なお、平成21年度活動報告書の附録に、現在はメルボルン大学の一部に編入されているVictorian College of the Artsを例として、博士プログラムの実技系関連記述の翻訳を掲載した。
- 6:本報告書のⅨ章に、こうした観点から本学の小松佳代子准教授によって実施された、実技系学生を対象とする論理的思考のためのワークショップの報告を掲載した。
- 7:付随して、本学の現行では行われていない「満期退学後一定期間における学位取得」の制度導入についての検討も必要であろう。この方式は一般の総合大学大学院では通常採用されているが、実技系大学院ではアトリエスペース提供の問題など整理すべき現実的課題が多く、慎重な議論が必要である。