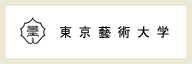リサーチ活動
Ⅰ.実技系博士学位授与に関する研究
5.美術研究科リサーチセンターの教育効果に関わるスタッフ・レポート1
本レポートは、リサーチセンター開設講座担当講師および論文執筆に関する個別指導担当者5名による、平成20年度の指導を中心としたリサーチセンターの活動に関する考察である。
リサーチセンター初年度における「論文作成技術特殊講義」の教育効果
中西 麻澄
本講義は、実技系博士課程1年次の学生が、自分の博士審査展出品予定作品と相関させた「博士論文」を執筆するために、論文の形式、参考文献の収集・整理、編集技術などを習得すること目的とする。講義内容は、第1回「論文作成の基本」、第2回「文献・資料の収集と整理」、第3回「文章の校正」、第4回「文章の編集」、第5回「章立て・要旨」とした。
前期に行った第1、2回授業では、学生は熱心に講義を聴いていたが、その質問内容や、個別に話を聞いた結果から、論文に何を書いたらよいかわからない、あるいは論文とは関係資料をまとめ引き写せばよいと誤解しているケースが多かった。このことが把握できたので、授業内容に逐次、「例えば陶芸の先輩で、こんな章立てをし、こんな内容を書いています」などと出来るだけ具体的に、過去の博士論文を紹介し、そもそも「論文とは何か」を理解できるように努めた。そして第2回の文献に関する授業では、講義室で実際にパソコン画面からOPACやNACSISで検索デモンストレーションし、学外文献の取り寄せ方なども講義した。そして夏休みの演習課題として、自分の関心のあるテーマを仮設定し、キーワードを5つ挙げた上で、20以上の文献を検索し、文献表を作り、提出させた。
後期に入り、課題の文献表の添削を返却しつつ、一人一人と出来るだけコミュニケーションをとり、質問しやすい環境づくりを心がけた。これは本学大学院美術研究科のほとんどが実技系の学生であり、制作行為という極めて個人的な表現の世界にいるため、何でも一人で解決しようとする傾向がわかっていたからである。そのため博士「論文」に関しては、気軽に相談してくれれば、他人(私を含めたリサーチセンター・スタッフ)が助けてくれること、相談してしまった方が一人で悩まないで早道であることを体感してほしかったからである。また私自身も、学生個々人の制作テーマが多岐にわたるため、論文の形式・章立てなどの論文作成には様々な、個別の解決策が可能であること、そこから一方通行の全体的講義だけでは不十分であることをこの頃実感した。加えてパソコン操作の習熟度も非常にばらつきがあり、ほとんど触ったことのない学生も数人いて、この文献表課題で初めてパソコンを使用したケースもある。また半数以上が、論文制作に必要なインデント等のワードの諸機能をこの1年次という早い時期に学べたことは、将来の論文執筆の際に必ずや役立つはずである。
第3回では文章の校正、編集、図版、キャプション、レイアウト等を講義した。その実践編として、仮のテーマ設定をし、それについて「A4用紙一枚に、タイトル、所属、名前、150字程度の文章、図版、キャプションをきれいにレイアウトする」という課題を出した。仮のテーマでよい、としたが、かなり真剣に課題に取り組んだことがわかった。添削、返却しながら個々にミニ面談をした結果、上述の文献表課題の時よりも、格段に問題意識が高まり、質問も論文作成上のより具体的なものとなってきた。実技系の学生なので、図版を選び、レイアウトをする、というまさにこだわりと自己表現の機会を与えた結果、論文に対するモチヴェーションを高める効果が予想以上にでた。これは今後のこの授業の進め方に、大いに活かすことが出来ると考えられる。
第4回講義は、特に「註」とはなにか、どのようにつけるか、という点に重点を置いた。もう11月になっていたので、学生も自分の制作が忙しくなってきた様子であった。それも考慮し、第3回授業の課題の添削を返却し、最後の課題として、この返却された課題の添削部分を自分で校正入力し、かつ文章に註を5つ付けさせた。この時点では註の内容は問題とせず、例えば引用の出典の記載の仕方等、その形式、技術的な面のみを指導した。
最後の第5回講義は、章立てや要旨に関するもので、より明瞭・簡潔に文章をまとめる演習もした。具体的には、博士展をテーマに、課題1として「展示を見る前に何を見ようと思っていたか/それはなぜか/実際に見てどうだったか/なぜそう感じたか/自分の博士展への課題」等について、各20字以内、という制限で箇条書きを作る。課題2として、それを400字詰め原稿用紙一枚に文章化する課題を授業中に行った。その結果、それぞれが「文章を書くこと」そのものに対する得意不得意をあらためて意識したり、作品や展示などから受ける感覚的・内面的なものを文字にすることの難しさに気づいたり、以前からの苦手意識をうったえる学生も半数以上いた。 その後、今まで自分が書いた文章を(修士の時や、博士課程入試の時に書いたもの)ぜひ見て欲しいという学生が3人いた。この様な個人的な文章の添削は授業の範囲外だが、こちらも初年度ということもあり、今後の授業に活かすため、あえて読ませてもらった。また、私も本年度は最終学年2名の博士論文(一人は留学生)の個人指導を行っていたので、感覚的なものを文字にすることの難しさに、学生が苦労していることもわかっていた。そのこともあわせて次年度では、短い文章(修士のときに書いたものなど)の添削も早いうちから同時進行するつもりである。個人的なモチヴェーションを高めることが、大局的には教育効果増大の近道であることがわかり、次年度これが実現できることを期待している。
以上のように、1年次を対象とした本講義に出席し、かつ課題にまじめに取り組んだ学生は、「タイトル、本文にあたる文章、註、図版、キャプション、レイアウト、文献表」という論文の各要素、章立て(目次)、要旨といった博士論文の全体構想の基本を理解できたはずである。更に教育効果のもう一つの面として、課題演習を通して「論文」を自分自身の問題意識とリンクさせ、またこれから自分が補足していかねばならないところ(個別の問題点:パソコンの使い方、文章の簡略化、感性的なものを文字にする訓練、先輩の論文や文献をより広く意識的に参照する等)についての自覚を促せたことも、挙げることができるであろう。
*
博士後期課程2年次を対象としたリサーチセンター開設科目「論文作成技術演習」に関する報告
五十嵐 ジャンヌ
平成20年度リサーチセンターでは、実技系博士課程2年次を対象に「論文作成技術演習」という授業科目を開設した。学生が執筆する博士論文のテーマや構想を明確化させるのが授業の目的である。演習形式の授業を通して、論文執筆を円滑に進めるための技術的な指導を行うよう努めた。31名の履修者(うち26名が最終的に単位取得)に対して、なるべく個別的な指導を行うために、少人数制の2クラスに分けた。本年度は各クラス5回ずつ授業、そして2月下旬には3日間にわたって博士論文の中間発表会を行った。以下では、授業の内容、中間発表会の形式を報告し、最後にこれらの成果、意義、今後の課題について触れる。
1.授業内容
リサーチセンターは本年度初めてこの演習と1年次対象の「論文作成技術特殊講義」を開設した。そのため、2年次学生は1年次の授業を受講していない。そこで、第1回目の授業では、論文作成の基本、文献・資料の収集と整理、文章の校正・編集など1年次に学ぶべき論文作成技術を講義した。
第2回目の授業では、論文の全体構想を考えるための契機とするために、過去の博士論文を参考にして、論文の流れを次の4つのタイプに分けて提示した。①研究対象が特定の物に限定されている場合、②研究対象がある事物に限定され、調査・実験を伴う場合、③抽象的な概念・事象を研究対象にする場合、④自らの体験・知見をもとに論を展開する場合。構想中の文章を今後どのようにすれば論文形式にまとめることができるのかという論文構成の面から、各自の論文がどのパターンに属するのかを再考してもらうのが授業目的の一つであった。
また、第1回目授業最後に与えた「博士論文の概要を現時点で書ける範囲でまとめよ」という課題を事前にチェックし、各学生の原稿に修正・コメントを加え、文体、引用の仕方、人名の書き方などの基本的事項についてのアドバイスを与え、テーマの絞り方、まとめ方についても個別指導を行った。
第3回目の授業では、夏期休暇中の課題「目次と参考文献表の作成」に対し、参考文献表の形式が各自統一されていなかったので、本、雑誌、新聞記事、カタログ、報告書ごとに日本語・外国語文献の一般的な表記法を紹介した。また、年度末の中間発表会に備えて、プレゼンテーションの仕方、パワーポイントによるスライド作成法、配布資料に必要な内容について述べた。
第4・5回目の授業では、論文発表の模擬練習として、学生5名ずつに10から15分ほどの発表を行ってもらった。各発表者の主旨が聞き手にどのように伝わるか発表体験を通して実感させた。発表者のプレゼンテーションによる一方的な授業展開を避けるために、聞き手にはフィードバック用紙を配り、発表者へのアドバイスを書かせた。このようにして、聞き手にも積極的に発表を聞き、学びとる姿勢を高めるように工夫を行った。
2.中間発表会の形式
2月20、24、27日の3日間で25名の論文中間発表を行った。論文発表者は博士課程2年次対象「論文作成演習」履修者かつ平成21年度課程博士学位予備申請手続を行った学生に限った。各発表には、論文主査、副査ら教員、博士課程学生、リサーチセンター指導員ら15から20名の参加者が同席した。1人30分の時間制限を設け、発表と質疑応答を行った。発表者はパワーポイントのスライドと、目次やレジュメなどを載せた配布資料を用意した。質疑応答では、主査・副査教員による内容に関するコメントや質問が中心であり、リサーチセンターからは主に論文構成についての指導が行われた。
3.「論文作成技術演習」科目の成果、意義、今後の課題
本授業、中間発表会を通して、各学生の論文執筆に対する意識は高まり、確実に論文全体の構想はまとまりつつあることを実感した。来年度の最終年次学生への個人指導を前に一定の成果があったように思う。
博士論文執筆は最終年次になると博士作品制作と同時並行して進めなければならず、学生にとって多大な負担にならざるを得ない。最終年次学生に集中する負担を分散させるために、2年次の段階から博士論文の準備を促し、少しでも余裕を持って論文執筆と作品制作が両立できるような環境作りの一環としてこの授業は意義があった。
しかし、論文執筆進行具合の個人差は否めない。履修者の中には、論文の構想段階でなかなかまとめることができず、メールや面談で何度か個人的に指導を行った学生が数名いた。リサーチセンターは、文章作成に不慣れな学生とっては非常に有意義な場所である。また留学生の日本語能力にも個人差がある。リサーチセンターが今後「翻訳センター」とならないように、さらに学生によって指導の入れ込み具合に差が出すぎないように、どの程度まで文章指導を行うのかについて共通認識を作った方がよいのではないかと思う。
授業課題提出や中間発表を通して2年次段階における論文の進行具合の把握、今年度の授業や個人指導での経験、そして特に個人差への対応を通して、来年度以降、クラス分け、課題の頻度などを通して指導の改善を計りたいと考えている。
*
論文指導ならびに「実技系論文」についてのレポート
粟田 大輔
2008年度、私が担当した実技系学生は計6名である(日本画1名、彫刻3名、文化財保存2名、うち留学生1名)。一重に「実技系論文」といっても、各専攻はもちろんのこと、各個人によって論文のテーマや内容、様式が異なるため、一概にそれを定義することはできない。しかしその上で、初年度の6名の学生に対して行った論文指導の経験を通じて、概観的ではあるがその傾向について述べたい。
論文指導の形式
まず、論文指導の形式であるが、4月末に担当学生が決定して以降、2週間程度を目安に適宜面接(面接時間は毎回1時間程度)を行った。最初に要旨ならびに論文レジュメを提出してもらい、論文提出までのスケジュールの確認、必要に応じて論文構成のアドバスを行った。その後は各々の進捗状況によっても異なるが、各節および各章ごとにある程度分量のまとまった文章を提出してもらい、「てにをは」などを中心に文字校正主体の指導を行った。なお現在リサーチセンターでは、論文内容についての指導は行わないことを前提としているが、学生によっては内容についてのアドバイスを求めるものもいる。その場合、こちらの意見を一方向的に述べるのではなく、ディスカッションを通じて論文の展開あるいは主旨に立ち返りながら、学生自身の言葉あるいは思考が自ずと引き出されるような指導を行うことを心がけた。
実技系論文
「実技系論文」において核となるのが、自作品についての言及である。実際、担当した6名の論文を概観して見ても、自身が掲げた問題設定を自作品によって「実証あるいは検証」していくという論の展開が多く見られた。しかしここで、大きく分けて二通りの傾向があげられるだろう。先に「実証あるいは検討」という言葉をあげたが、文化財保存専攻の作品制作は、まさに「保存研究」という観点に最も比重が与えられているため、時にデータ化あるいは数値化された資料を参照しつつ、具体的かつ実証的に論が進められていく。よって論文構成自体も、必然的に制作プロセスに焦点が当てられるため、制作の時系列に則るという傾向があげられる。結果的に、論文構成においてブレは生じにくい。2008年度に担当した文化財保存2名(日本画、工芸各1名)の論文様式もまさしくこれに当てはまるものだった(偶然だが、日本画専攻の学生もまた、漆の経年変化を作品制作の構成要素として取り入れていたため、文化財保存専攻の論文と同質なデータ解析を基にしたものであった)。ただしあえて問題をあげるとするならば、作品の完成自体が論文の結論部分の大きな要素を占めるために論文と制作とを同時進行しなければならず、それが論文の進捗にやや影響を及ぼしている点である。とはいえ、実作での経験を基にしながら論文によって言語化を図る試みは、技術を後世に伝達する意義において今後も大きな役割を占めると期待できる。
一方で絵画、彫刻、デザイン、工芸、建築、先端表現専攻の学生の論文においては、自作品による「実証あるいは検討」は抽象的な側面を呈している。そのため、論文構成にややブレが生じることもある。多くの場合、自身が興味を惹く哲学的言説あるいは芸術作品を参照あるいは分析しながら、結論として自作品の意義について再検証するといったモデルがあげられるが、主査や論文副査の指導に応じて論文構成の変更を余儀なくされるケースも見受けられた。こうした問題に対しリサーチセンターでは、二年次に中間発表を開催することにより、学生と主査との意思疎通を綿密かつ客観的に図る場を提供している。これにより最終学年次の論文指導においても、学生と主査との客観的議論を通じて、どのような点を解消、改善すべきかを共有できる利点があげられる。しかしながら、自作品と絶えず向き合いながら言語化していく意味において、学生一人ひとりの視座は非常にオリジナリティに富んでいる。実際、こうした「実技系論文」は、すでに作品分析を行う美術館学芸員あるいは研究者のための参照資料として用いられている。博士後期課程修了後の各々の芸術家としての活動によっても左右されるが、「実技系論文」は、後世の研究においても作品分析を行う上での貴重な一次資料として意義を兼ね備えていると言えるだろう。
以上、初年度の6名の学生に対して行った論文指導の経験を通じて概観を述べた。初年度ということもあり指導形式は手探りで進行する側面もあったが、二年次の中間発表開催など、指導形式における大きな改善も見られた。今後も、「実技系論文」の意義について常に立ち返りつつ、指導に励んでいきたい。
*
論文指導についてのレポート
石田 圭子
平成20年度、論文指導員として美術実技系博士学生の学位論文の個別指導に当たった。初年度ということで不安や試行錯誤もあったが、担当した学生が全員、博士号を無事取得することができ、今はそのことをなによりも嬉しく思っている。以下、初年度の論文指導の内容について報告し、気がついた点や今後の課題と思われる点をまとめたいと思う。
私が担当したのは、油画、版画、日本画、陶芸、デザイン、保存修復の各学科それぞれ1名、計6名の学生である。そのうち2名が留学生であった。
各学生の論文の進行状況や論文執筆能力に応じてさまざまではあったが、概ね2週間に一度くらいの頻度で面談し、論文の指導を行った。事前に書き上げた原稿を渡してもらい、次回面談時に文章や構成、論証上の問題点などを指摘し、さらに次回面談までに仕上げるおおよその分量を定めるというかたちで指導を進めた。
4月末の初回指導の段階では、テーマと要旨はおおよそ出来上がってはいるが本文執筆の段階に進んでいないという学生が大半であった。まず、各自に目次を提出してもらい、それに基づいておおまかな執筆スケジュールを立てて論文執筆を進めていくようにした。しかし、当然のことながら、思うように執筆が進まないという状況にしばしばつきあたり、ほとんどの場合は予定通りに進まなかった。その要因としては、なかなか自分の思うように文章表現ができないといった作文能力における問題のほか、制作の進行との兼ね合いという問題があったと思われる。全般的に論文の完成時期が予定よりもかなり遅れてしまったが、8月末には全員が論文を提出し、その後は比較的少ない面談回数で最終的な提出に至ることができた。
以上のような指導を経て感じたことは、まず、実技系の学生の場合、その経験や興味に応じて論文執筆能力にかなりばらつきがあるということである。文章についてかなりチェックを入れ、指導しなければならない場合もあったが、ほとんどその必要のない場合もあった。留学生に関しては、正しい日本語を書くためにかなりの労力を割かなくてはならず、文章作成自体に相当の努力を要する様子であった。それでも、昨年度私が担当した留学生は論文執筆や博士号取得に対する意識が高いように思われ、その点が印象的であった。また、留学生か否かに関わらず、単純に日本語の文章力というよりは、適切で十分な論理展開という点に問題が見受けられる場合も少なくなかった。また、参考文献の用い方や引用の仕方、自分の論への接続の仕方について理解が不十分である学生が多かったのも目立った点として挙げられる。
さらに、論文の進捗という点から、最終学年時までの準備段階が重要であると強く感じた。早い段階で構成がある程度まで固められている学生はその後の進行も比較的スムーズであったのに対し、要旨や目次が十分練り上げられていない学生は、なかなか思うようにはかどらない様子であった。また、とりわけ、論文を仕上げた後に作品制作のほうに集中するというスケジュールで作業を進めていた学生がほとんどであったので、作品制作の時間を確保するためにも出来るだけ早く論文に取り組む必要があると感じた。これには論文執筆に対する意識づけという問題が大きく関わっているように思われるが、この点はすでに取り組まれている1・2年次での論文授業への参加やプレ発表を通して大きく改善されると思われる。
内容構成という観点からみた担当学生の論文の傾向は、いくつかの特殊な研究領域を除いては、自分の作品制作にかかわる複数のテーマを立てて一般的・客観的に論じたうえで、自分の作品制作に関連付けて述べていくというスタイルのものが大半であった。その際に、一般的に論述するという部分にとりわけ難しさを感じる学生が多かったと思う。また、自分の作品について述べる場合も、作品制作において感覚というレベルで漠然ととらえているものを言語に翻訳していくという作業に困難を感じる学生が少なくなかったようだ。その際に、文章化作業が自らの制作に則した翻訳というよりは後付的な説明になってしまう傾向も多分にあるのではないかと思われた。
博士論文の執筆は自己の作品をあらためて客観的に見なおすことにつながるだろう。また、自分の作品に対する説明づけが外部からしばしば要請される今日では、学生にとって有益な経験になると思う。しかし、作品の文章化が作品自体と乖離したり、こじつけになってしまうならば、その意義も疑わしくなってしまうだろう。いかに視覚的な美術作品と論文とを有機的に関連づけられるかという点が実技系学生の博士論文をめぐる大きな課題であると感じた。さらに進んで、論文執筆が作品制作にフィードバックされうるものになるならば、実技系の博士論文はより意味ある制度になるだろうと考えた。
*
2008年度芸大リサーチセンターの仕事について
足立 元
2008年度、実技専攻の博士号を所得した学生のうち、私は7名を最後まで担当した(内訳は、油画2名、日本画1名、建築1名、工芸1人、保存日本画1名、保存工芸1名)。いずれも個性豊かなアーティストであり、そのおかげで、面談の時間をつうじてそれぞれの活動や考えを知ることは、私にとって愉しい時間であった。
しかし、面談の時間は、リサーチセンターの仕事の中でごくわずかな一部に過ぎない。学生たちの論文を逐次読んで直していく作業には、裏側でそれなりの長い時間と労力がかかっている。しかも、彼ら/彼女らが書いてくる論文は、実に多彩である。例えば、油画の学生による国際的な現代アートの分析を読んだ直後に、保存日本画の学生による鎌倉時代の仏画の専門的研究を読むようなことは、珍しくない。つまり、私の頭の中では、ひとつのところに落ち着くことなく、遠くかけ離れた様々な時代やテーマを常に往還する状態に慣れる必要があった。
さて、実際の校正作業として、現代アート系の学生たちの論文については、ときに哲学的・衒学的な言葉を多用することもあるが、それほど晦渋なわけではないので、理解して校正するのは比較的難しくない。一方、保存の学生たちの論文については、その論理構造は明快であっても、それなりに古美術の専門知識がないと、まともな校正やコメントは出来ないだろう。私は日本近現代美術史を専門にしながらも、幸い日本・東洋美術史研究室のなかで過ごしてきたので、いくらかは保存の学生たちにも対応できたのではないかと思う。それでも力及ばず保存の先生方にご負担をかけたであろうことは、お詫び申し上げたい。
担当した学生のうち、2名の留学生(工芸と保存工芸)の論文を読む作業には、当然ながら時間と労力が倍以上かかった。とはいえ、私が英語で文章を書くとき、そしてそれをネイティブの友人に直してもらうときの酷さを思い返すならば、彼女たちの日本語への取り組みは賞賛と驚嘆に値する。むしろ、留学生たちの凄まじい努力を見て、校正の大変さ以上に、力づけられる思いもした。
実は留学生より大変だったのが、日本人でありながら、制作しか興味を持てず、構造的に文章を書いてゆく作業にどうしても慣れなかった学生への論文指導である。しかもこの学生は、パソコンのトラブルや展覧会の出品もあって、ギリギリまでなかなか論文を書けずにいた。私は8月下旬に一週間ほどリサーチセンターで朝から晩までこの学生につきあって、なんとか提出に間に合わせることになった。
ときには、面談の時間に学生の悩み相談を受けることもある。例えば、主査教員との関係が難しくて悩んでいた学生もいた。何度も大幅な書き直しを指示され、主査教員の求めている内容に納得がいかなかったという。そのような悩み相談になったとき、私は敢えて自分の意見を挟まず、ひたすら学生の話を聞き続けるだけである。その学生は、論文を書き上げた後、主査教員との関係も好転したと報告してくれた。 それほど手間のかからない学生もいた。その学生は、8月半ばまで海外に滞在していて、4月からずっとメールのやりとりだけで指導していた。彼女は元々文章の表現力に長けていて、私の方が勉強になったくらいである。とはいえ、長い論文を何度も最初から最後まで読み通して、細かな誤字脱字や言い回しのチェックを行うことは、他の学生への指導と変わらない。つまり、学生の文章が上手いからといって、私の作業量自体が大幅に少なくなるわけではない。
ところで、実技系の博士論文を校正するというリサーチセンターの仕事は、傍目には単なる「てにをは」直しであろうが、実はそれに留まらない難しさがあると私は考えている。ひとつには、芸術学科出身の者が実技専攻の学生を指導することの難しさである。これは、一般的な「教える」と「学ぶ」の関係づくりでは、決して上手くいかないだろう。アーティストという存在を特別視するわけではないが、優れた批評家がアーティストと信頼関係を結ぶように、こちらが相手の本質的な部分を尊敬し理解しようとする誠意を示さないと、私のアドバイスは学生たちに伝わらないと思われる。7名の学生たちとは、関係づくりが上手く行ったという手応えをそれなりに感じている。ただしその他に1名だけ、6月にリサーチセンターの指導を受けないと決めた学生もいた。その理由が私の力不足なのか、学生のポリシーなのかは、未だに分からない。いずれにせよ、担当者と学生の間の相性の問題はどうしても避けがたく、今後の課題である。
もうひとつには、根源的な問題であるが、そもそも形式と内容は不可分であるという難しさだ。リサーチセンターの仕事では、学生の論文の内容には踏み込まず、論文の形式を直す。とはいえ、学生の論文の形式を触るときには、どこまで直したら良いのか、常にギリギリの判断を迫られる。たとえ不完全な形式であっても、その不完全な形式は、その学生が考えている内容を反映しているのは間違いないからだ。私に学生の論文の内容を直す権限はないし、そのつもりも一切ないが、にもかかわらず、結果として内容に触れているのではないかという恐れはある。
文章を良くするという作業は、まず文章の中で不完全な部分を探し出し、次に著者が伝えたくても上手く伝えられなかった内容を推察し、そして、明瞭な言葉で再構築することである。より具体的には、論文の不完全な部分において、学生が一体どのような言葉にならない「もどかしさ」を感じているのかを知る必要がある。そのために、適宜質問をし、作品を見せて貰うなどしてから、私が言語表現について例をいくつか示す。そうして、学生と一緒にふさわしい言葉を選択してゆく。この過程は、内容に踏み込むとまでは言えなくとも、喩えるならば、溢れ出る水の周りに土嚢を置いて、そこに目に見える形を与えるようなものであろう。
確かに学生が制作の思考を言葉で総括する作業は重要である。博論執筆は、その後の制作活動において大きな武器になるはずだ。ただし、もしこれがリサーチセンターの仕事でなければ、私はアーティストの不完全な言語表現に対して、こう言うかもしれない。わけの分からない言葉をもっと溢れさせ、長い時間をかけて、より大きな思考へとつなげてゆくべきではないか、と。
(平成20年度活動報告書)