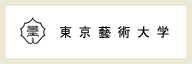リサーチ活動
Ⅰ.実技系博士学位授与に関する研究
6.美術研究科リサーチセンターの教育効果に関わるスタッフ・レポート2
本レポートは、活動の最終年度にあたっての、スタッフ7名によるリサーチセンターの活動記録である。
*
「作家」である学生の学位論文指導
―「論文作成技術特別講義」の総括と、これから執筆する方へのアドバイス
中西 麻澄
ここでは、5年間にわたり、実技系博士課程1年次生を対象とした「論文作成技術特別講義」を行なった総括と、3年次生の論文執筆を個人指導した経験からわかった、「作家」である実技系学生ならではの、特徴的ないくつかの問題点をまとめる。これをもとに、今後本校にて博士論文を執筆する、「作家」である博士課程の方へのいくつかの実践的アドバイスを提案したい。
1.「論文作成技術特別講義」の総括
本講義は通年、全5回の授業で、主に以下の項目について講義し、理解を確かめるために、授業内の基本的な演習や課題の提出をもとめた。
- 1.論文作成の基本:
- 論文の構成要素、全体の形式、形式の統一の重要性
- 2.資料収集技術の基本:
- 文献収集・検索の方法、図書館の便利な使い方、文献表の形式(日本語文献、欧文文献、欧文文献の翻訳本、インターネットからの資料等について)
- 3.本文:
- 校正の仕方、学術論文の文体について、記号(中黒、括弧等)の使い方
- 4.図版と注:
- レイアウト、引用文の記載の仕方、注とは、図版番号とキャプション
- 5.章立て:
- テーマ設定、章立て(目次)、要旨の書き方
この授業での課題とは、一つは論文に不可欠な「文献表」で、これにより文献検索を実践し、文献表を論文にふさわしい形式で、パソコンで作成する。もう一つは、論文に不可欠な要素―タイトル、自分の所属、本文となる文章、図版2枚、キャプション、注―を盛り込んだ、「作品解説」作成である。これは将来、博士展カタログに掲載する、タイトル、所属、要旨、図版、キャプションをまとめる予備的練習ともなる。これらの課題の提出を、単位認定では重視した。なぜなら、自分の手を動かして、パソコン上で作業してみて、はじめて実践的学習となり、1年次に経験しておくことで、3年次にゆとりを持って、論文を書き始められると考えたからである。
実際に授業を行ない、個々に話す機会も得、提出された課題を見て、何よりの難問は、「論文」というもののイメージができていなかったり、誤っていたりする事だと感じた。これは、文章ではなく、作品で語る「作家」である実技系の学生にとっては当たり前である。とはいえ他人の論文を読んだ経験がほとんどない状態で、論文執筆に取り掛かることになり、3年次の論文の書き始めにあたって、最終的には削ることになる、一般論の羅列や、普遍性のない言葉での思いつくままの記述に時間を割いてしまうことになる。実際、論文を前提とした短い文章を書いてもらうと、文章を書くのが苦手で非常に遅筆か、逆に友人宛のメールのように、構成やパラグラフのない文章をとりとめなく、たくさん早く書けるかのどちらかに、大きく分かれた印象がある。もちろん中には非常に簡潔明瞭に、書き言葉で自己表現できる方もあった。
もう一つの難題は、全体に向けての講義に加え、個人指導の必要性である。次年度からこれまでのような3年次の個人指導はなくなるが、既に1年次の時点で、論文作成に必要なスキルに関して、幅広いばらつきがみられた。例えば、パソコンを触ったことがなく、これから買います、という学生もいた。パソコン上の操作は何でもできるが、ワードやパワーポイントを使ったことがない学生もいた。また既に述べたように、文章力にも個人差があるだけでなく、これが留学生の場合は、非常に深刻な問題となる。また、ハード面のスキルのばらつきのみならず、文字で何かをつくるという行為に対する、完成度の意識にばらつきがみられた。文献表の課題を例にとると、実際に、虫眼鏡でなければ見えないような文字の大きさの文献表を提出してきたり、余白がほとんどなかったり、フォントやポイントが不統一であったりするものもあった。一方で、非常にレイアウトも見やすく、インデントもきちんと使用し、全体の形式が統一された、みごとな文献表もあった。パソコンのスキルのちがいというより、文字で表現したものの完成度に対する意識のちがいといえるであろう。これらの他に、各自の専門分野の多様性に起因する、論文のまとめ方について、個別に対応する必要性も強く感じた。このことは、再度文献表を例に挙げるなら、厳密には、各自の専門分野、論文の内容、文献の量により書き方が異なってくる。特に、欧文文献の多い場合や、韓国語文献、中国語文献が中心となる論文もあり、翻訳文献に原語をいれる場合、省略する場合、個展のデータを乗せる場合、インターネットや映画を文献表にまとめる場合などがある。いずれにしろ、各自の文献全体を見渡し、本文との関係も考慮し、いかにグループ分けし、どの形式で統一するかを、個々に決めなければならないからである。
このように、1年次から、それぞれの専門や作品、技法などが全く異なるため、個々に対応する必要性を強く実感した。翻せば、それだけオリジナリティーのある論文になる可能性を秘めているといえよう。
2.個別指導
筆者の、3年次生の論文執筆の個人指導の経験から、「作家」である彼(女)らの多くが突き当たる3つの壁についてまとめてみたい。
一つめは論文執筆の開始時期である。まず章立て(目次)をつくり、ほとんどの方は第一章一節から書き始めていた。その内容は、一般的な文明論や文化論、あるいは歴史である事が目立って多かった。四大文明の始まりや、ラスコー、アルタミラ壁画などがしばしば言及された。おそらく論文を書くと言う不必要な「構え」や、本を調べて書くものだという当初の誤解から、一般論を書き、写し連ねてしまうようであった。この解決策として、事前に諸先輩の論文を熟読することが挙げられる。このことを彼らにアドバイスすると、先輩の論文は見ました、という答えが返ってくることが多かった。しかし詳しく尋ねると、実際には手にとって、パラパラ見たという程度である。この時点で、この問題点に気がつかないと、そのまま本を調べて書き進めてしまい、その部分は最終的には大幅に削除することになり、3年次の限られた貴重な時間をロスしてしまう。このようにやみくもに書き始めてはいけない理由は他にもある。一つはこの時点で、論文全体の構成、つまり全体の論理の流れができていないからである。論文冒頭は、冒頭だからこそ書かなければならないことを書き、それが全体の中で、この位置にあるからこそ生きてくるものでなければならない。もう一つは、論文の主題である自己作品や論文全体のテーマとの関連づけがなされていないからである。これらの原因は、全体の構成をもった論文を書いた経験の浅さからのもので、また過去の先輩たちの提出論文や、あるいは良い学術論文をじっくり読んだことがないためといえるであろう。論文も―文字で表現する―一種の作品なのである。
二つめは、次第に第2、3章(あるいは複数章)と書き進めた時期である。このあたりで過去の自作品および提出作品について語ることになる。ここで突き当たるのが、造形作品や自分の感覚を言語化することの難しさである。この段階で「作家」である彼らの多くに筆者が勧めたことは、それぞれにとって大切なキー・ワードを取り出し、その言葉をどういう意味で使っているかを対話によって明らかにしてゆき、それを書いてもらうことだった。「作家」である彼らの多くには、それぞれが大切にしている言葉がある。本人はその言葉を使うことで、読者が自分の言いたい事や、自分の感覚を理解したり、感取してくれると思いこんでいる場合が多い。ところが本人は自明のことと思っているその概念が、実際の一般的な意味から「ずれ」ていたり、あるいはより限定的な意味で使っていたり、または全く一般的意味からかけ離れた特別の意味をもたせていたりした。これに気付いてもらう事が、この時点では大切であった。私の担当した方の例では、「ある」、「つくる」、「広がり」、「からだ」、「自然」、「軸」、「紫」、「もの」等の言葉があった。この「作家」ならではの造形に関する言葉の独自の定義を、うまく言語化し、説明できると、その論文は、造形作品と言葉が結び付いた、密度の高い、オリジナリティーのあるものに変容できる。つまりその作家自身や、作品を想起させる、まさに実技系博士論文になる。その際には、作品と離れない、密接な関係にある論文内容になるよう注意する必要がある。また蛇足だが、論文で作品を語ることは、作家本人の内面を語ることになる場合がある。非常に内面的、時にはプライベートな体験が、作品と緊密に係わっている場合も少なくない。それを公的な論文にどこまで反映させるのかを、客観的に判断し、論文や作品へ読者が近づく道しるべとなる範囲に、記述をとどめるようアドバイスした。これに関しては、いかなる点でその体験や感覚が、自己作品のどの部分と関連しているかを説明する必要もある。このように書いたのは、自己分析を延々と過度に書いてしまう場合もあったからである。
三つめは、博士審査展の時期である。このころには論文は7~9割がた書いてあるが、内容的にはまだ見直しが必要な方が多い。この時期は、提出作品の制作や展示、また論文発表会の原稿、パワーポイント作成のために、実際のところ論文に手をつける時間はほとんどないのが現実である。論文は、しばしば文献表を付していなかったり、注が不完全なまま、展示会場に置かれることになる。論文において、文献表は重要であり、これは1年次から本を手に取るたびに、入力しておけば、自然と出来上がるものなのである。文献表が重要である事を今一度、意識してほしい。文献表や注がきちんと書けているという事は、その論文の内容が、他人の意見と、執筆者のオリジナリティーとを線引きしている、という事を意味するからである。
3.これから論文を書く方へのアドバイス
- 1年次から、指導教官と頻繁にコミュニケーションをとる。
- パソコンに慣れておく。特にワードやパワーポイントを使えるようにする。また近頃では主査、副査に論文を見てもらう際、メールを使用する場合も多いので、メールも使えるような環境も整えておく。
- 最初は短くてもよいので文献表(ファイル)をパソコン上につくっておく。そこへ3年間かかって、新しい文献が見つかる度に入力し足していけば、文献表はおのずから出来上がる。
- 先輩の論文を複数、通して読んでおく。手にとってパラパラ見るだけでは十分ではない。よい論文とは、よい作品と同じで、全ての部分が必然であり、関連があり、部分から部分への論理の流れがあり、全体としてのまとまりと、オリジナリティーがある。また短くて良いので、きちんとした学術論文を読んでおくのもよい。例えば藝大の『論叢』等が適している。
- 図書館の利用に慣れておく。
- 早くから造形物を言語であらわす練習をしておくとよい。①自分の作品1点について、1000字ほど(A4用紙1枚程度)で、「語る」様に書く。その時は、同じ分野の後輩(例えば学部生や学部受験生)を読者としてイメージするとよい。練習し始めは、―無意識に論文調に書こうという「構え」が言葉を硬化させてしまいがちなので―書き言葉ではなく、話し言葉でよい。②①で書いた「話し言葉」の作品解説を、「書き言葉」に書き直す。
- 自分の書いたものを、人に声に出して読んでもらう。自分は原稿を見ず、聞くだけにする。これは筆者が初めての学会発表の時に先輩が教えてくれた方法である。実際、そのように自分の書いたものを「聞く」と、良い部分と、読者(視聴者)には伝わりにくいだろうという部分が非常によくわかった。文字原稿を自分で見るのとは全く異なり、非常に客観的に自分の書いた事の良し悪しがわかる。ぜひ試してみてほしい。もし読んでくれる人がいなければ、自分で原稿を声に出して読むだけでも、いくらかは客観的に判断できる。
- 最後に―これは非常に大切な事で、覚えていてもらいたいのだが―、書く練習をする時から、「常に読者の存在を意識する」事を心がけてほしい。これには、客観的に自分の論文(や書いた文章)を外側から見ることが必要となる。例えて言えば、自作品を制作中に、数歩下がって、あるいは別の角度から、離れて見ることに似ている。論文は、読者に、自分の言いたい事を理解してもらい、自分という作家独自の感覚を感じて、あるいはわかってもらえるように、文字という媒体を使って書かなければならない。論文には、読者の存在が必須の前提なのである。
以上の拙文が、これから学位論文を書き始める、「作家」である学生諸氏の一助となれば幸いです。そして精神的にも肉体的にも過酷な三年次が、より充実したものとなり、完成度の高い作品と論文になるよう、願ってやみません。
*
二年次学生対象授業「論文作成技術演習」と最終学年次学生への論文執筆サポートに関するまとめ
五十嵐 ジャンヌ
リサーチセンターでは、5年間にわたって実技系博士論文を準備する二年次学生対象に「論文作成技術演習」という授業を担当した。また同時に、最終学年次学生対象に論文執筆のサポートを行った。以下では、これら2つの経験をもとに実技系博士論文執筆サポートに関する課題と成果について考察する。
二年次学生対象の授業「論文作成技術演習」は、毎年20名から30名の学生が履修する。学生が論文執筆を円滑に進めるのが授業の主たる目的となる。年度末には中間発表という形で、学生に発表の機会を与える。この中間発表では、普段の授業の枠を超えて、指導教員や一般の学生も参加できる場を提供している。学生の論文のテーマ、内容、論文構成がまとまったかどうかを確認する意味がある。また、公の場で論文の主旨を発表することで、様々な意見を聞き、指導教員たちとのコミュニケーションを活発化させる場にもなっている。
中間発表を控えた二年次学生への授業内容は、学生が実際に論文を書き始められるように個別指導を心掛けている。論文の進捗には個人差があり、学生の論文のテーマによって進め方が異なるため、個人指導が有効である。前期の授業では、論文の構成パターンを紹介し、学生に論文の流れを意識して論旨を書くことを求める。後期の授業では学生に目次を提出させ、ゼミ発表を行ってもらう。各自が具体的に思考・作業を進めやすくするために、論旨提出や目次提出といった課題、ゼミ発表に対して、そのテーマにふさわしい論文構成パターンを複数提案したり、論文構成・テーマの方向性がおおよそ決定したら、それに則したさらなる課題を示す。そして最終的には、年度末の中間発表にいたる。
論文提出期限まで一年半弱という時期にあって、学生がテーマを絞り込み、論文の構成を実際に考え、目次が完成する段階まで論文が進むことが望ましい。この時期に、二年次学生は論文の構成要素を整理し、論文の流れを決めなければならない。論旨・目次の提出、ゼミ発表で、最も重要なのは、他者の意見を聞くことである。提出された論旨や目次に対してコメントや課題を与える。学生が陥りやすい状況としては、考えていることを断片的に示すことに終始しがちだということである。考えていることをアウトプットするのは最低限の条件であるが、アウトプットした内容を文章によってどのように他人に伝えるのかという論文執筆上の重要な作業が欠けがちである。学生が他者を意識して、他者が抱きそうな疑問にあらかじめ配慮して、論文の構成を考えることが論理的に文章を書くことに役に立つと考える。
ゼミ発表では、参加学生にフィードバック用紙が配られ、発表学生への感想、コメントが求められる。発表を準備することでゼミ発表者は論文のテーマ・構成を整理し、フィードバックによって複数の他者の意見が得られる。文章化された論文は後に不特定多数の人の目、読者に晒されるが、修正することができない。論文の内容があらかじめ複数の他者に晒されることによって、読者の立場や関心を意識し、さまざまな反応を予想して自説を強化させる機会となる。このようにして、論理的な弱点を補い、論文の説得力が増すことを期待する。
次に、最終学年次学生への論文サポートの経験から得た私見を述べる。担当学生の論文テーマの設定には大きく4つの傾向があると思われる。必ずしもこれらの分類に当てはまらない論文もあるが、設定したテーマの性質によって共通性が見られる論文の内容・流れを以下に述べる。
まず一つは、作品制作で表現したいと考える感覚や感情をテーマとした論文である。それは作家の体験に基づき、感情的なものを伴う、一つの言葉では置き換えられない、作家独自の視点に基づく感覚である。このような感覚を扱うのは日本画や油画、工芸の論文に多く見られる。例えば、孤独、枯れ、寂寥感などが挙げられる。作家はこの感覚あるいは感情を普段作品の中で表現しているが、論文執筆に当たっては、言葉で表現することが求められる。作品の中で具象的なモチーフが表されている場合は、モチーフを選択した理由について論文で述べる必要がある。モチーフの選択には個人的な経験と密接に関わっている。この論文テーマとも深くかかわる個人的な体験談を述べると、読者とその感覚を共有しやすい。すでに表現された過去の作家あるいは他の作家の作品、さらに過去の自作品を作家自らの視点で分析することによって、作家の感覚を読者に共有してもらう。こうして、表現された既存の作品と自作品とを比較することが可能となり、作家が生み出す作品の独創性がどこにあるのかを理解させることができる。最後に、表現手段としての自らの技法や自作品の説明を加えることで、作品に具体的に近づき、論文が構成される傾向が見られる。
二つ目には、上述した感覚でも、極めて抽象的な感覚あるいは状態や状況を扱う論文がある。これは油画、デザインの論文に見られた。例えば、更新、不在、共鳴、あいまいなどをテーマとしたものである。表現される作品には具体的なモチーフが見られない。作品が示す状態を観者に与える、もしくは共有してもらうことを作品制作の意図の一つとする作家である。この場合、具体的な体験談が示されることよりも、思想家や小説家などの文章が引用されることが多い。エピソードから得られる抽象的な感覚あるいは状況を構造的に把握するために、その仕組みやシステムを分析する。したがって、哲学や記号論、情報学など理論的なバックグラウンドのもとに論を進める。このような論文では個人的な経験よりも社会やそのシステムへの関心が強い傾向がある。
三つ目は、自らのアイデンティティーの問題が中心となる。制作行為を行うにあたっての背景や自作品の背景が自らのアイデンティティーの問題と直結していることを強く意識する論文である。そのため、美術史の中での自作品の位置を確認したり、留学生では自作品を自国の文化的背景と日本での経験のもとに生まれた作品と位置付けたり、歴史や現代を踏まえて自身が制作する作品の方向性の正当性を裏付けたりする。これらは工芸、デザイン、先端芸術表現の論文に見られた。
四つ目に、実験や調査に基づく論文である。保存修復や先端芸術表現の論文に見られた。研究目的を明記し、そのために有効な実験や調査を行い、得られた結果から考察をするものが一般的である。一方、フィールドワークで得られた事象や体験を整理・分析して考察を進め、フィールドの世界観の構造を分析し、この研究が自作品とどのように関わるのかを論じたものがあった。
以上のように、論文の構成要素を分類することは、実技系博士論文のあり方を考える上でも、以後の論文の指導にあたっても有益であると考える。
「論文作成技術演習」という授業を通して、論文の構成を決定しきれない学生に、実技系博士論文のパターンを提示したり、学生がゼミ発表や中間発表を行うことによって、学生が論文執筆にとりかかりやすい環境を整えている。実技で表現する作家にとって、文章を書くことは必ずしも容易ではない。作品制作をしながら、同時に論文をまとめなければならない。指導にあたっては、文章を書くストレスをどのようにしたら取り除けるかという課題が常につきまとう。授業を通して、論文執筆にあたっての学生の不安を少しでも払拭することに貢献できればよいと考えている。また、中間発表や演習を通して、学生が選んだテーマに関する多くの人の考えに耳を傾けることで、論文により客観性が増すことを期待できる。
*
芸大リサーチセンターの仕事について
足立 元
1.仕事の内容
リサーチセンターの論文指導では、月に1回から4回の面談を通して、実技科の博士論文のブラッシュアップに取り組みます。もっとも、芸大におけるこの仕事は、アカデミックな論文を人よりも数多く書き、そのいくらか技術に長けている、というだけでは勤まらないでしょう
言うまでもなく学生たちは個性豊かなアーティストたちであって、すでにそれなりの活動の実績を持ち、それぞれ独自の世界観を築いています。それゆえに、一般的な教える-教えられるの関係を作ることではなく、むしろ、じっくりと学生たちの話を聞くこと、彼らに心を開いてもらうことから仕事が始まると思います。
そうして、彼らに語らせながら、彼らが自らの言葉でこういうことがいいたかったのだ、ということに自分で気づいたならば、私の役割はほとんど終わったようなものです。中には、その時点でリサーチセンターに頼ることなく自らの力で論文を仕上げようとする学生もいました。
実際に、多彩な学生がいます。そして、芸大での面談の時間は仕事のごくわずかな一部に過ぎず、学生たちの論文を逐次読んで直していく作業には、自宅での長い時間と労力がかかります。しかも、彼らが書いてくる論文は幅広く、例えば、油画の学生による国際的な現代アートの分析を読んだ直後に、保存日本画の学生による鎌倉時代の仏画の専門的研究を読むことが求められたりします。こうして、リサーチセンターの仕事をしているとき、私の頭の中は、いつも遠くはなれた時代や場所やテーマを行ったり来たりする状態に置かれました。
5年間のリサーチセンターの仕事で、私が担当した学生の数は次の通りです。
2008年度は7人で、内訳は、油画2人、日本画1人、建築1人、工芸1人、工芸1人、保存日本画1人、保存工芸1人。
2009年度は5人で、内訳は、油画(壁画)1人、日本画1人、デザイン1人、先端1人、保存日本画1人。
2010年度は3人で、内訳は、油画2人、先端1人。この年からは日本学術振興会の特別研究員に採用されたために芸大での勤務時間を大幅に減らすことになりました。
2011年度は1人で、内訳は工芸でした。
2012年度は2人で、内訳は油画1人、油画(版画)1人です。
この数には、途中で来なくなった人を含めていません。
また、毎年1人の留学生を最初から最後まで担当いたしました。
2.仕事で面白かったこと
論文指導をしていて、芸大の専攻ごとに異なる学生のカラーというものを感じることが多々ありました。日本画、デザイン、工芸の学生については、内容も文体もシンプルでありつつ、真摯で好感の持てるものが多くありました。指導ということに対する学生たちの態度としても、素直な人が少なくなかったと思います。
ほとんど外国にいて、ずっとメールのやりとりだけで指導していた学生もまた、面談がなかった分、あまり手がかからなかったといえます。この方は元々文章表現に長けていて、私の方が勉強になったくらいです。とはいえ、長い論文を何度も最初から最後まで読み通して、細かな誤字脱字や言い回しのチェックを行ったので、作業量としては他の学生たちに比べて少なかったわけではありません。
油画や先端など、現代アート系の学生たちの論文は、ときに現代思想の言葉を用いて、敢えて分かりにくくしていることもあります。しかし、それらはむしろ私の得意とするところなので、理解して、整理することは比較的難しくありません。そして、実技の学生たちと、哲学について、あれこれと話したくなってしまう誘惑にかられてしまうこともありました。リサーチセンターでは学生の論文の内容について踏み込まない、ということは重々分かってはいたのですが。
実際、油画の学生とアリストテレスについて話し合い、先端の学生(といっても私よりだいぶ年上でしたが)とヘーゲルなどについての議論をして、論文の技法以上のことを学生たちと分かち合えたのは、とても楽しかった想い出です。一方で、ある油画の学生にジャック・デリダの本が参考になるかもしれないと話してしまい、その学生の頭を余計に混乱させてしまったこともありました。もし私がそんなことをいわなければ、彼はもっとすんなり論文を書けたのだろうか。それは分かりませんが、相手のレベルに応じて提供する知識を変えることの必要性を痛感しました。
保存の学生たちの論文については、内容は簡単明快であっても、前提とする専門知識は現代アート以上に求められると思います。これに対しては、油画や先端などとは違って、それなりに古美術の専門知識がないと、まともなことは言えないでしょう。私自身はそれほど古美術の知識に自信があったわけではありませんが、日本・東洋美術史研究室のなかで過ごしてきたことが、いくらかは役立ちました。
ただ、論文指導において、門外漢であることは、専門家であることよりもいいことだと思います。危険なのは、私の場合はなかったのですが、私と同じ専門の分野について書こうとする学生を担当して指導することでしょう。もし、実技の学生が日本近現代美術史について生半可なことを書こうものなら、私は容赦なく内容に踏み込んで直して、その学生のプライドを傷つけていたかもしれません。担当する学生が自分の専門と異なることは、寛容さをもって指導することにもつながるはずです。
3.仕事で難しかったこと
留学生の論文を読む作業には、日本人の学生の数倍の時間と労力がかかります。とはいえ、私が酷い英語で書いた論文をネイティブの友人に直してもらうときの恥ずかしさを思い返すならば、留学生たちの日本語への意欲的な取り組みは賞賛と驚嘆に値するものです。異国の不安の中で、どんなに拙い日本語であっても、とにかく自らの考えを日本語で表現しようとする姿勢には、胸を打たれる思いがします。
ただし、留学生のごく一部には、自分で日本語を書かず、母国語からGoogle翻訳という機械翻訳で日本語に訳した論文を私に渡す方もいました。それはあまりにも酷い日本語で、正しい日本語に直すのに大変苦労しました。また、最初から英語で論文を書いて、それを人に頼んで日本語に訳してもらう、という方もいました。機械翻訳や他人の翻訳を、日本の大学の博士論文として認めて良いものかどうか、私は内容に踏み込む権限はないので、何ともいえません。
実は、留学生より大変だったのが、日本人でありながら、制作しか興味を持てず、構造的に文章を書いてゆく作業にどうしても慣れなかった人の論文です。そういう方には、他の方以上に手厚いサポートをして、なんとかギリギリ提出まで持って行っていただく、ということになりました。
また、ときには学生の悩み相談を受けることもあります。指導教員との関係が難しくて悩んでいた学生もいました。何度も大幅な書き直しを指示されて、先生との求めていることに納得がいかなかったそうです。私は特に意見を挟まず、ひたすらその学生の話を聞き続けるだけでした。論文を書き上げた後にはその先生との関係も好転したそうです。
さて、実技科の博士論文を直すというリサーチセンターの仕事は、傍目には単なる「てにをは」直しに過ぎないかもしれません。しかし、実際はそれだけに留まらない難しさがあると私は考えています。
ひとつには、芸術学科出身の者=批評家が、実技科の学生=アーティストを指導するということの難しさです。一般的な批評家とアーティストの関係において、アーティストが批評家を警戒したり、批評家に対して自分を大きく見せたりすることは少なくないでしょう。そうした事態は指導にならないので、絶対に避ける必要があります
理想的なことを申し上げれば、優れた批評家がアーティストと信頼関係を結ぶように、相手の本質的な部分を尊敬し理解しようとする姿勢が必要ではないでしょうか。少なくともそうした姿勢を示さないと、私のアドバイスは学生たちに伝わりません。 私が担当した多くの学生たちに関しては、だいたい関係が上手く行ったと感じています。ただし、一部にはリサーチセンターの指導を受けないと決めた学生もいました。相性の問題はどうしても避けられないかもしれません。私との会話の中で十分に言葉を引き出され、自ら書けると自信を得た学生もいました。
もうひとつには、「形式」と「内容」は本質的に不可分であることの難しさがあります。リサーチセンターでは、学生の論文の内容には踏み込まず、論文の形式を直すことが仕事です。とはいえ、学生の論文の形式をさわるときには、いつもギリギリの場所をいじるような気分にもなります。不完全な形式であっても、それもまたその学生が考えている内容を反映していると思われるからです。
文章を良くするという作業は、まずは文章のなかで不完全な部分を探し出し、次に著者が伝えたくても上手く伝えられなかった内容を推察し、そしてその内容を明瞭な言葉で構築し直す、というプロセスから成り立っています。論文の不完全な部分において、その学生がいったいどんな内容を言いたくて言葉にならないもどかしい思いをしているのかを知るために、延々と話を聞いたり、作品を見せてもらったりすることがあります。そうして学生と一緒にふさわしい言葉を選んでゆく作業は、内容自体に踏み込まないまでも、溢れ出る水の周りに土嚢を置いて目に見える形を与えてゆくようなものです。
多くの場合には、そうやって言葉にしていくことは必要な作業だと思います。博士課程を終えたのち、自分の考えを言葉でまとめた経験は、自身のプロモーションにおいて大きな武器になるはずです。ただ、もし博論の締め切りが関係なければ、私はアーティストに対して、こうアドバイスするかもしれません。そこで考えを小さくまとめず、もっと訳の分からない考えを溢れさせて、長い時間をかけてより大きな思考へとつなげてゆくべきではないか、と。
もちろんそのようなことは決して口にしませんが、しかし言外のメッセージとして、私が担当した学生たち全員に対して思っていたことです。博士課程を終えた学生たちの何人かがプロのアーティストとして活躍するのを目の当たりにするとき、そうした思いが少しは伝わったのかもしれないと感じています。