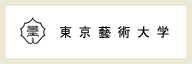リサーチ活動
Ⅰ.実技系博士学位授与に関する研究
6.美術研究科リサーチセンターの教育効果に関わるスタッフ・レポート2
本レポートは、活動の最終年度にあたっての、スタッフ7名によるリサーチセンターの活動記録である。
*
「実技系論文」について
粟田 大輔
2008年から5年にわたりリサーチセンターにて論文指導ならびに執筆に対するサポートを行ってきたが、ここでは日本画・油画・彫刻・デザイン・工芸・先端芸術表現専攻を中心とする、いわゆる「実技系」の学生(とりわけ初めて論文を書く学生)への指導経験を踏まえ、「実技系論文」にまつわる諸問題とその可能性について見ていきたい。
1.マンツーマンの指導形式
『平成20年度活動報告書』の「実技系課程博士学位授与の現状と課題」に記されているように、2005年以降に博士後期課程の学生の数が急増した状況のなかで本センターは設置された。私はそのなかで主に実技系の最終学年次を担当し、論文の形式的補助(文字校正)ならびに執筆に際して彼らが不安に感ずる細かな事柄の相談に応じてきた。こうした活動は、毎年度実施している利用学生へのアンケートにも示されているように一定の効果をあげたと思われる。とりわけ、何らかの形式で論考の発表を行ったことのある者は別として、論文の書き方や進捗度が個人の素養によって大きく左右される状況下において、本センターで採用されたマンツーマンの指導形式は適切であったように思う。
ここでその実態を簡単に記したい。学位申請年度の4月下旬にオリエンテーションが開催され、この時点で初めて学生と対峙する(私の場合、例年6?7名程度を担当)。その際に、論文の目次を目処に執筆のスケジュールを確認する。その上で、5月初旬以降から面談を行い(基本的に隔週おき)、書き上げられた論考をもとに文字校正を行っていく。ただし一重に文字校正と言ってもほぼ初めて論文を書く学生が相手であるため、「てにをは」や誤字脱字の修正にはじまり、かなりの労を強いられたのが実情であった。加えて主な傾向としては、一文が長くなることで論点が不明瞭になり、文章の意味自体が取りにくくなってしまう、あるいは同じフレーズやキーワードを多用する点などがあげられる。後者に関してはその度合を少なくすることで比較的簡単に対応できるが、「実技系論文」の形式的な問題点としては前者に集約されることが多かった。
ここには、端的にいうとふたつの問題が孕んでいる。ひとつはセンテンスそれ自体を書き上げることの技術の欠落であり、もうひとつはセンテンスとセンテンスを結びつける(論を展開させる)ことの技術の欠落である。私が立ち会ってきた学生をみても、この技術の有無が決定的な差異を生んでいた。ただし興味深いことに、学生のほとんどは口頭では一通り自らの意見を述べることができる。しかし、それを文字として記述することに慣れていないため、結果的に意味の取れないセンテンスが連綿と続くことになってしまう(私見を挟めば、先のふたつの技術を「訓練」することでしかこの問題は解決の仕様がない)。よって一回一回の面談では、必然的に不明瞭な点を本人に確認しながら校正を反映させていくこととなる。
2.聞き手としての役割と外部性
上記の問題点を踏まえると、私が行ってきたことは校正者であると同時にある意味で編集者としての役割も果たしていた。期日を設定して論文の執筆を促すことにはじまり、校正のフィードバックを積み重ねながら論文を「読める」ものへと仕上げていく。なおその際に、必要不可欠だと感じられたのが「聞き手」としての役割であった。一概には言えないものの、学生は「制作」に根ざした経験に即してプライドが高く、他方で自らの考えを文章化することに苦心しているため、自信の高さと低さが入り交じったかたちで論文に臨んでいる。こうした心理状態に対して、何よりもまず彼らの言うことを「聞く」という態度が求められた。たとえば論点が不明瞭な場合でも、単にこちらの意見や解釈を一方的に述べるのではなく、むしろ質問形式で問いを投げかけることで学生自身の発話を促していく。こうした「聞く」という姿勢は、言わば学生自身に「内なるもうひとりの自分」を宿させるような行為に近い。実際のところ「聞く」ことを徹底化することで、学生を自分自身の書かれた論考へと反省的に向かわせ、同時にそれは書き上げられていない論点へのモチベーションを高めることに繋がった場合も見られた(本レポートでは詳しく述べないが、留学生との言語的なコミュニケーションの問題もこういった観点から少なからず再考する必要があるようにも思う)。
ただし注意しなければならないのは、あくまでも「聞き手」に徹しているにもかかわらず、間接的にこちら側の意見が反映されてしまうという事実である。言うまでもないが「聞く」にあたって完全な中立性が維持されることはなく、こちら側の解釈が暗に含まれる。またマンツーマンの指導形式により、学生との関係は必然的に「密室性」を帯びてしまう。こうしたある種の危険性に対して求められるのが外部性にほかならない。本センターの枠組みの場合には、現在のところ論文第一副査の教官がその任を果さざるをえないが、学生との二人三脚の作業においてこうした外部性の存在は不可欠であることを記しておく。
3.制作と論述との連関
最後に「実技系論文」自体の構造的な問題点について私見を述べたい。ここで言う「実技系論文」とは「作品と論文」を審査対象とする学生が書く論文のことを指すが、『平成20年度活動報告書』においてすでに指摘したように、各専攻はもちろんのこと各個人によってテーマや内容、様式などが異なるため、それらは一義的に定義できるものではない。しかし、博士論文の執筆にあたりとりわけ初めて論文を書く学生の傾向を踏まえると、主に「自作品への思想的かつ芸術的影響」「自作品の展開」「自作品への言及」の3つの観点をもとに論述にあたる傾向が見られた(繰り返しになるがこれに該当する学生は、日本画・油画・彫刻・デザイン・工芸・先端芸術表現専攻が中心であり、芸術学専攻ならびに文化財保存学専攻はその例にあたらない)。
ここで指摘したいことが「自作品への思想的かつ芸術的影響」の論述における問題点である。そもそも初めて論文を書く学生にとって、限られた時間でその影響関係を言説化することは困難を極める。実際、学生の多くは論述にあたり哲学的なキーワードや影響を受けた芸術作品を列挙することに留まり、表面的な論点に終始してしまう場合も少なからず見られた。こうした傾向には、「制作者」であることの優位性が根ざしているように思われる。「制作者」という立場に依拠することで、その「影響」がある種の「内面性」として絶対化されて記されてしまう。結果として「自作品の展開」「自作品への言及」もまたその趣向を強め、論述の整合性は他者の見解を挟む余地のないものと化してしまう。
こうした問題に対して「制作学」という見地を踏まえて簡潔に考察したい。「制作学」の起源については、谷川渥の「制作学」(藤枝晃雄、小澤基弘、谷川渥編『絵画の制作学』日本文教出版2007年所収)に詳しい。谷川はここで、ポール・ヴァレリーの所論をもとに展開されたルネ・パスロンの「制作学」について言及している。パスロンは「作られつつある芸術の学(制作学)」「作品の特殊構造学」「消費される芸術の学(美学)」の3つに分割し、「芸術学」を体系づけているが、谷川はその上で「単なる構造論的分析」とは区別される「作られつつある芸術の学(制作学)」の本質を問うている。とりわけ興味深いのは、パスロンが「制作学」の対象を芸術家でなく、芸術家と作品を結びつけている力学的な関係にあるとしながらもあくまでも「制作者」(=「自らやってみなくてはわかりはしない」)という立場の優位性に依拠していたに対し、谷川が「作る〈我れ〉」と「見る〈我れ〉」を分裂させることで、「制作行為」や「作品」を「制作」と「享受」の往還として価値づけている点にある。
ここに「実技系論文」のひとつの可能性のヒントがあるように思う。私自身の指導経験に照らしてみても、彼らとの面談を積み重ねることで関心を寄せたのは「制作者」としての立場からの作品分析ではなく、「創造過程」の他者への「開かれ」であった(たとえば、彼ら自身による「作品」の構造分析よりも、「創造過程」へと敷衍されるような世界の見方への言及の方が論の骨子としてはるかに意義深く思われた)。よって問いは、単に「論文」としての体裁を形式的に整えるかという点だけでなく、彼らのうちにある「制作者」としての優位性を解体し、「制作者」であると同時に「享受者」でもあるという視点をいかにして論述として定着させることができるのか、という事態に引き継がれるように思う(無論、優れた制作者にはその視点が必然的に備わっている)。言うなれば「作品と論文」を審査対象とする現行のシステムには、「作品/論文」の分裂性を踏まえた上で、まさしく「作品『と』論文」といった「制作と論述の連関」のあり方が問われているのである。
*
リサーチセンターでの活動を振り返って
石田 圭子
2008年にリサーチセンターの仕事に就いて以来、さまざまな活動を行ってきた。そのなかには実技学生を対象とした論文指導のほか、国内外の美術大学における博士学位取得制度についての聞き取り調査や講演会開催のサポートなどが含まれる。こうした5年間の活動には報告するべきことが多くあり、個人的にも興味深いことが数多くあったのだが、ここでは自分の仕事のうちもっとも大きな比重を占めた論文の個別指導に限定して、自身のリサーチセンターの活動を報告するとともに、その活動を通して私が考えたことについて述べたいと思う。
私が論文指導を担当したのは博士課程の最終学年であり、1年度毎に約6~7名の学生の論文指導を行った。5年間で延べ約30名の学生の指導にあたったことになる。担当した実技学生の領域はさまざまであり、油画・版画、先端芸術、日本画、デザイン、工芸、保存修復など多岐に渡った。担当した学生のうち約2~3割が留学生であった。
年間の活動内容はおおむね以下のとおりである。指導期間は4月~最終的な論文完成までであったが、審査のための論文提出期限が8月末であるため、主に前期が論文指導員としての活動期間であった。4月の初回のガイダンスで担当を決め、各学生にアンケートを提出してもらった。アンケートでは論文を書くにあたって問題と感じていることや不安に思っていることを書いてもらい、これを参考にしてそれぞれの問題点を意識しながら論文指導を進めるようにした。初回のガイダンスでは目次と要旨も提出してもらった。これをもとに各論文のテーマと概要を把握し、例年5月の連休明けに第一回目の面談を行った。この最初の面談から8月末までの期間、学生の進行状況や執筆能力によってばらつきはあったものの、二週間に一回の頻度で面談を行うように心がけ、おおむね実行できたように思う。事前に書き上げた原稿をメールで送付してもらい、次回面談時に文章や構成、論証上の問題点などを指摘し、次回面談までに仕上げるおおよその分量を決めるというかたちで指導を進めた。9月に入ると多くの学生が作品制作の方に集中するため、論文指導の頻度は少なくなるが、学生からの相談があればそれに応じ、添削その他を行った。また、12月の卒業制作展での公開発表にあたって文章や構成について相談を受けることもあった。
以上のような活動のなかで論文の個別指導のポジティブな結果として私が考えるのは以下のことである。
第一に、初めにおおよそのスケジュールを決め、それに従って進行するため、論文完成までの見通しがつき、それによって論文を書き慣れていない実技の学生の心理的負担を軽減することができたこと。もちろん、実際には予定通り進むほうが少なく、遅々として進まないケースも多く見られたが、スケジュールの取り決めには一定の効果があったのではないかと思う。4月に行っていたアンケート調査では、論文執筆にあたって心配に思っていることとして毎回挙げられる事項に期日管理の問題があり、8月末までに論文を完成させることができるのか不安を感じている学生が多いことがうかがわれた。論文の進行スケジュールを指導員と共有することが論文執筆のペースメーカーとしていちおう機能し、学生の負担を軽減できたのではないか。博士号を取得するにあたって論文を書くということは制度的に定められたことであり、当然のことながら、各自が自発的かつ積極的に取り組むべきことである。しかし、学部や修士課程に進む段階で論文執筆の課題が与えられていない多くの実技学生にとって、一定の文章量を要求される博士論文の執筆は心理的にやはり大きな不安であり負担であると想像する。その不安をとりのぞき、論文執筆に邁進させることは意味あることだと考える。
また、論文指導によって学生が自身の作品や考えを客観的に見るようになり、それによって思索をまとめることができるようになること、これもメリットとして挙げられると思う。近年ではギャラリーや美術館などで作家が作品について観客の前で説明を要求される機会も増えている。また、博士課程にもなれば、ほとんどの学生が自分の作品を外部から評価される経験を経てきている。しかし、それでも自分の作品を言語によって説明させられる、しかも徹底的に説明させられるという経験が初めてだった学生の方が多いのではないだろうか。これは論文指導によってというよりは論文を書くこと自体によるポジティブな結果というべきかもしれないが、他の人間(指導員)を実際に前にして自分の考えを言葉でまとめて伝えるということは論文を書く前段階の作業として意味をもち、その後の論文執筆に取り掛かるためのステップとして機能していたように思われる。
さらに、きわめて端的な効果として挙げられるのが、留学生に対する日本語の指導である。現在、東京藝術大学の実技の博士課程には多くの留学生が在籍している。彼らは博士号を取得するために本学にやってくるのであるが、日本語で博士論文を完成させるうえで十分な言語能力を持ち合わせていない場合も多く見受けられた。ときとして口頭での意思の疎通すらままならないケースもあり、そうした場合、論文指導をスムーズに進めることは非常に困難であった。留学生の場合であっても日本語の博士論文提出が博士号取得の条件としてあらかじめ課せられている以上は、一定の日本語能力は入学の前提でなければならない。この点については今後留学生の入試制度の見直しなど改善を検討する必要があるように思う。しかしながら一方においては、実技の学生の場合、優れた作品を制作する能力を出来るだけ尊重するべきだという考えもあり、これまで多くの優れた作家を輩出し、いまやアジアにおける芸術の重要な発信地となっている東京藝術大学においてはその観点は十分に尊重されなければならないだろう。それを勘案するならば、とくに日本語での執筆が大きなハードルになる留学生に対しては論文に関するサポート体制が必要であると思われる。リサーチセンターの発足以前には留学生は自身の負担で校正を依頼するというケースが多くあったようだが、センターはこの負担をかなり軽減できたと思う。また、今後も留学生に対する論文サポートは何らかのかたちで継続的に行われるほうが望ましいと思う。
次に論文指導を通して私が感じた実技学生に論文執筆を課すことのネガティブな側面に関して述べたい。実は、指導期間中に論文を書くという経験が作品にマイナスの影響を与えることもあるのではないかという疑念を感じたことがある。そのことはリサーチセンターの指導を受けた後に学生に提出してもらったアンケートの結果に学生自身の実感としても表れている(割合としては少なく、良い影響が表れたとする学生の方が多いのであるが)。私が気づいた良くない影響とは、論文を通して作品や制作を言語化した結果、作品が以前のものと比べて観念的で説明的になってしまうということである。実際、博士展で提出された審査作品を見て、そのような感想を持ったことが一度ならずあった。個人的な感想ではあるが、観念的な傾向が作品の力を殺いでしまっているのではないかと感じられることがあった。しばしば言われることだが、アートとは言語化できない何かを伝えるメディアであって、それを無理やり言語という枠に収めようとするならば、そこで失われるものが必ずあるだろう。これは「作品」はそれ自体で成立するものであり、それに対する説明は要らないし、それ自体が優れていれば、それで十分であるという主張とも繋がってくる。また、美術の学位における「論文」の意味とは何かという根本的な問題とも繋がってくるだろう。
しかし、結論としては、私はこうした観点からの論文や作品の言語化のネガティブな側面は一時的なものであって、結局のところ肯定的な結果に転じるのではないかと主張したいのである。これはセンターでの指導という経験を通して自分が考えるようになったことである。これもまた主観的で個人的な事柄になってしまうのだが、私自身は論文指導を通して以前よりも同時代の美術を面白いと思うようになったし、「理屈」を通して作品を「感じ」たり、より楽しんだりするということができるようになったのではないかと感じているのである。自身の直観としては、ここにはなにか「昇華」とでもいうべきプロセスがあるように思う。以前はそれが作品と深く関連するものであったとしても、あくまでも「理屈」は「理屈」、言語は言語で完結していて、「言語」はそれ自体で独立し、それが語る作品と馴染むことがなかったのであるが、それらが作品と、あるいは作品経験のなかでひとつに溶け合うようになったという実感があるのである。そして、それによって作品をより面白いものとして捉えることができるようになったように思う。観念それ自体がアートにおいてネガティブであるのではなく、それが作品に力を与えることも十分にあると信じられるようになった。こうした実感を指導した学生から直接聞いた訳ではないので、確信は持てないのだが、アンケートで「作品に良い影響が表れた」と答えた学生はひょっとしたら自分と同じような感覚を持つようになったのかもしれないと考えるのである。学生にとって、あるいは彼らの作品を受容する人々にとって、博士論文が作品をより深い理解へと導けるようなものになったらよいと思う。そうした論文の内容はおそらく学生の個性に応じてさまざまであろうし、そうであるべきだと思う。しかし、それは同時に自分への、そして他者への「伝達」という目的を十分に果たせるものでなくてはならないと思う。
最後に5年間にわたって務めてきた論文指導員の仕事を終えるにあたって、これまでお世話になった先生方、そして同僚の方々に御礼を申し上げたい。仕事上でアドバイスをいただいたり、精神的に支えていただき、どうもありがとうございました。そして、何よりも論文指導をした学生のみなさんとの出会いに感謝したい。それぞれ短い間ではあったけれど、興味深い作品や個性に出会うことができ、5年間の仕事は思い出深く楽しいものであった。論文執筆の経験が、みなさんの制作の奥行きをより一層深め、発展させるひとつのきっかけとなることを願っています。
*
リサーチセンターにおける活動報告 ―論文指導を中心に―
和田 圭子
平成20年度より5カ年計画で設置されたリサーチセンターにおいて、平成22年度から3年間その活動に携わった。その中で主に美術実技系学生の博士学位論文の個別指導を担当した。以下、3年間の活動を論文指導を中心に報告し、気づいた点について述べたい。
私が担当した学生数は、平成22年度は計8名(工芸1名、文化財保存学7名、うち留学生4名)、平成23年度は計7名(工芸2名、文化財保存学5名、うち留学生1名)、平成24年度は7名(日本画1名、工芸2名、文化財保存学4名、うち留学生2名)、3年間で合計22名である。私自身の研究科目との兼ね合いから、特に文化財保存学および工芸の学生を中心に担当した。1人が担当する人数として、年間平均7人はやや多いと感じた。全員が論文提出時期を同じくしているため、特に提出期限直前は、時間的な問題から十分な指導ができないことがあった。
論文指導の手順、方法については、まず、4月末のリサーチセンターのオリエンテーション時に担当が決まり、それ以降、おおむね2週間に1回程度面談を行い、1回の面談には約2時間を費やした。平均よりもやや長い面談時間であるが、丁寧に学生の考えや制作等について話を聞きながら論文の方向付けを行うようにした。その上で、論文提出までの執筆スケジュールを確認し、その後、進捗状況に合わせて、あらかじめ提出された要旨や論文の基本的な文字校正や論文構成、問題点について指摘した。さらに次回の面談までに執筆すべき範囲を設定し、執筆した論文を面談前に提出してもらい、それを添削して面談で問題点を指摘するという作業を繰り返し行った。
論文の進捗については、実技系の学生は特に制作と論文執筆を両立させなくてはならず、時間的にかなり厳しい状況にあると思われた。基本的には、8月末日の論文提出締め切りまでは、論文を優先させる学生が多かったが、その期間中に展覧会があり、修了制作とは別の作品制作が必要であったり、夏季休業中に論文提出期限があるため直前の図書閲覧が難しかったり、あるいは就職活動があったりと、論文執筆に集中できない要素が多かった。また9月以降は12月の博士審査展に向けて作品制作が中心になるため、論文執筆にあてる時間を確保するのはかなり難しくなるようであった。また場合によっては、10月の中間審査で論文の大幅修正を指示されることもあるため、そのような事態を避けるためにも、かなり早い段階から論文の方向性を決定し、主査との意思疎通をはかる必要があると感じた。少なくとも博士課程2年時に行う中間発表会の時点では、おおよその内容が決まっていることが望ましいであろう。これまでの中間発表会を聞いても、その時点でほぼ論文の概要がまとまっていた学生は、その後の論文執筆も特に問題なく進んでいた。
実技系学生の論文を執筆する能力については、かなりの個人差があった。文章力には特に問題がない学生もいる一方で、しばしば主語の欠落、主語と述語が対応していない、一つの文章にいくつもの内容が盛り込まれているといった基礎的な作文能力に問題があったり、抽象的な言葉を羅列して、全体の意味が分かりにくくなったり、表現したい内容にふさわしい言葉が見つからず同じ言葉を繰り返し使用してしまうというような経験不足からくる問題点も見受けられた。ことに留学生については、日本語能力に大きな差があり、かなりしっかりとした日本語の論文が書ける学生から、正しい日本語を書くためにかなりの努力が必要な学生もいた。また、全体として文献の引用の仕方や注の付け方に理解が不足しているようであった。特に注の付け方は、文系、理系などのジャンルの違いで書式が大きく異なるため、データ分析などの科学的な分野と美術史的な方法論を合わせて参照するような論文では、混乱が生じやすかった。
論文内容の指導の在り方については、現在リサーチセンターでは、論文内容についての指導は行わないことを前提としている。確かに日本語の文章として形式的に整っていることが、まず求められることであるが、「てにをは」を直す場合でも、論文の内容に関わらずに添削指導を行うことは、論文全体の構成を考える上でたいへん難しい。また、学生から論文の内容について意見を求められることもしばしばあった。そこで、論文内容についての疑問は、できるだけ直接、または執筆する学生を介して論文担当第一副査の教員等に指導方針を確認し、それに沿った形で学生をサポートするように心がけた。実技系の学生にとって論文を書くことは、作品制作に比べ必ずしも得意なことではなく、不安を抱えていることも多い。そうした場合、教員や指導員が共通の認識を持って指導を行うことで、学生の不安は少なからず取り除かれ、執筆に対するモチヴェーションを高めることにもつながるのではないだろうか。実際に担当した学生の中には、執筆した原稿をリサーチセンターで指導、添削し、執筆者が持ち帰って再度推敲し、さらに論文第一副査に指導してもらうというローテーションをこまめに行った結果、提出までの数か月間に目覚ましく執筆技術が向上し、論文提出の頃には、自信を持って自分の文章が書けるようになった例もあった。
次に論文指導を通して感じた実技系論文の方法論と近年の変化について報告する。
すでに指摘されているところであるが、「実技系論文」の傾向については大きく分けて二通りの傾向がみられる。一つは、文化財保存学の論文に見られるもので、保存研究の見地から科学的なデータ分析に基づいて具体的で実証的な検証を行う論文である。またもう一つは、執筆者の制作に至る動機やテーマを掲げ、それについて客観的に論じながら自作品を検証していく論文で、文化財保存学以外の分野で多く認められる。
まず、前者の文化財保存学の論文の特徴は、模写や模刻等の制作が論文の重要な位置を占めていることであり、特に近年その研究対象とする作品は、国宝や重要文化財という一般的にも美術史的にも注目度の高い作品を扱っていることである。これらの非常に重要な文化財の模写、模刻を行いながらそれにまつわる問題点を見つけ出し、科学的な方法を利用しながら実証的に検証していく方法を取っている。かつては、その作品の来歴をまとめ、先学の研究史を整理するといった網羅的な研究が多かったが、最近は、様々な科学的な分析方法が開発され、それらを研究に取り入れることによって、作品の構造や根本に関わる問題が明らかになり、美術史とは異なる文化財保存学ならではの視点から本質的な部分に注目して論を進めるようになっている。たとえば、保存修復彫刻では、3Dデジタルデータを用いて彫刻の構造的な部分に問題点を見出し、史料や文献からだけでは分からない、実作者の視点から研究を進め、その内容に注目が集まっている。またこれらの研究方法を用いた博士論文の一部は、少しずつであるが紀要や論文集等に発表されるようになってきている。以上のことからも、文化財保存学において、独自の研究方法による博士論文の成果が評価されていることは、作品制作と論文がバランスよく収まり、論文の方向性も定まりやすいシステムができつつあると考えてよいのではないだろうか。
もう一方の論文の傾向は、自分の作品制作に関していくつかのテーマを立てて、それについて客観的にまたは一般的に論じながら自身の作品制作と関連付けていくものである。作品の制作工程や技法的な部分については、時系列に具体的に状況を書き進めればよいが、作品制作に至る動機付けや検証については抽象的な文言が多用されることになる。以前の論文では、過去の哲学者の言説によって自身の制作の意義を支えたり、客観的に表現する手助けにすることが多かった。それらの言説の理解が不十分である場合、その文章も生硬な表現となり、執筆者が表現したかった内容から乖離してしまう場合があったように思う。私が担当した論文の中には、難解な哲学的言説を借りて自分の作品制作について論じるのではなく、たとえば、子供の頃に抱いた様々な感情や心象に自分の作品制作の動機を見出し、そこから作品が作りだされたことを丁寧に説明するものが多かった。やや感覚的で自作品の客観的な検証には至っていないが、自分の言葉で自分の作品を論証したいという意思は感じられた。論文の方向性としては定まっていないが、これも新たな流れのひとつなのではないだろうか。自分の考えや思いあるいは作品について文章化する技術は、実技系学生にとって今後より一層重要性を増すであろう。このような論証の方法が成熟することを期待したい。
以上、リサーチセンターで3年間行った論文指導の経験を通じて、感じたことあるいは気づいたことについて述べた。リサーチセンターでは論文指導の他に、中国とアメリカの実技系大学院に対するヒヤリング調査に参加させていただいた。各国や、各大学の博士課程の学位審査および授与システムについてお話をうかがったが、それぞれがまったく異なる取り組み方をしていることに驚き、貴重な機会を得られたことに感謝している。その他、博士課程2年による中間発表会や博士展カタログの編集、リサーチセンター5カ年プロジェクトのまとめとして行われた「芸術実践と研究~実技系博士学位授与プログラムの研究成果発表会~」にも参加させていただいた。初年度は、論文指導に追われたが、その後いろいろな経験をさせていただいたことで、リサーチセンターの本来の目的についてより理解することができた。実技系の学生が作品に対する考えや思いを文章化していく技術を学び、実際の執筆にあたって随時論文指導やアドバイスを受けられるシステムは、論文の形式的な質を保つ上でも重要であるが、何より学生にとって作品を文章化していく作業は、自分自身が作品と向き合い、客観視することに繋がる貴重な経験といえるだろう。今後、なんらかの形で論文個別指導のシステムが活用されることを期待したい。
*
実技系博士プログラムをめぐって
安藤 美奈
2008年に始まるリサーチセンターの活動は、博士論文執筆に関するサポート活動と、実技系博士学位に関するリサーチ活動、そしてこの2つの活動をつなぐ成果及び情報発信とに大別できる。私は主にリサーチ活動を担当してきたが、芸術リサーチセンターについて構想の段階から知る機会があったので、5年間を経ての活動終了は感慨深いものがある。また、文部科学省による平成23年度国立大学法人等評価において、リサーチセンターの活動が戦略性が高く意欲的に目標・計画を定め、積極的に取り組んでいると評価されたことを、このリサーチセンターの活動に関わり、尽力された全ての方々に改めて報告したい。
以下、雑感であるが、実技系博士プログラムをめぐる状況を振り返ってみたい。
博士プログラムをめぐる国内外の共通点、相違点
5年間のリサーチセンターの活動を通して、学内をはじめ国内実技系博士課程を有する教育機関を対象に、アンケート調査や聞き取り調査を実施し、意見交換会を通して博士プログラムに関する問題を共有し議論を深めてきた。またその比較対象として海外の実技系博士プログラムを調べていく中で、リサーチセンターの活動開始と期せずして「実践に基づく研究」という領域について議論が高まっていること、ボローニャ・プロセスが進行するヨーロッパにおいて、イギリスが先行的に博士プログラムを確立し運用していること、アメリカ、中国などにおいても、実技系博士プログラムへの関心が高まっていることがわかった。
ここではこれまでのリサーチセンターの調査を通して、国内外の実践に基づく研究や実技系博士プログラムをめぐる態度や認識について、共通点と相違点をあげてみたい。
共通点
- ① 国によって教育制度は異なるが、学術分野において博士学位が最上位の学位であること。ただし、博士学位が最上位であることは共通の認識だが、国際的に確立した評価基準、定義があるものではなく、実技系博士学位についても、名称をはじめ各々の規則、慣習に従い規定し使用している。
- ② 博士課程の役割を、新しい知識の発見、創造とその知識を活用し社会に貢献することとしている。
- ③ 近年における博士学位授与数の増加。因果性をどちらに、あるいはどこに見い出すか答えを得ないが、博士プログラムにおいて指導する教員に、博士学位の取得が求められる傾向が強くなっている点。
- ④ 実技と論文の両方を指導し評価できる人材の不足。
- ⑤ 教育機関における学生の制作スペースの確保の問題。
相違点
- ① 博士プログラムを構築する視点。海外の視点は、実技系単科大学のように単独の教育機関としての存続、総合大学の一学部としての学内におけるプレゼンスの保持、ボローニャ・プロセスなどのようなグローバルな構造変革といった、影響力が大きく、競争原理が強く作用する環境、枠組みに立った視点である。
- ② 修士プログラムと博士プログラムの区別。博士学位授与数の増加だけでなく、領域を超えた研究活動や留学生の確保など、様々なグローバル化が進む環境の中で、「博士学位」は、美術博士などの専門職学位から、PhDに総称される博士学位に集約される流れがある。一般的に、日本では博士課程を前期(修士学位)と後期(博士学位)とに区別し、前期課程2年、後期課程3年という修業年限を設けている。このような日本の修士を経て博士へという段階的なシステムとは異なり、海外のプログラムでは、PhD学位取得のために5~7年といった年数をかけ、修士プログラムとの連続性は持たないPhDプログラムを構築している場合が多い。
- ③ 人材育成と獲得に対するアプローチ。共通点にあげた実践と理論の両方を指導し、評価できる人材の育成について、平成21年度に実施した本学教員対象のアンケート調査で、「実技系博士学位取得者としてどのような人材を輩出したか」という問いに対して、「アーティストとして優れ、かつある程度の文筆・理論的能力を持つ人材」という回答の選択が多数を占めた。こうした認識に対して、海外の実技系博士プログラムでは、人材育成をより明確な戦略の中で考えているといえる。多くの海外の博士プログラムの場合、プログラムが対象としているのは、既にアーティストとして活動実績、あるいはアートに関連する業績があり、より研究を深めたいと考える者である。そして実技を専門としながら研究に挑戦する意欲のある者に対し、従来の学術研究に沿う形のPhDプログラムにおいて指導していく。現段階では、実技と学術という分野の異なる教員がそれぞれ指導する体制であるが、将来、アーティストとして芸術実践の場と、研究員や教員として学術の領域で活動する人材が、指導する一人として博士プログラムの一端を担う体制となることが想像できる。そうして、このように他の領域と共通の価値観や評価方法を知る人材を育成することにより、他の領域や社会との対話や相互の価値観の共有が可能となり、実践に基づく研究が社会に貢献する新しい可能性も示されることだろう。
また、日本と比較して海外教育機関は、広く国際的に優秀な人材を集め、基礎的な研究から革新的な研究まで、多くの研究業績を蓄積し、発表、展開することにより、公的、民間を問わず資金の獲得につなげ、設備や研究、人材のさらなる拡充を図るという運営戦略サイクルを貪欲に実行している。そのサイクルの中では、博士プログラムも人材を集める重要な要素の一つである。
実践に基づく研究の課題と期待
ところで、様々な国で多様な学術領域で博士/PhD学位が授与されるようになった今日、最上位の学位授与のための共通した審査手段は、研究成果を文章で著した論文を審査することである。「文字に起こして伝える」ことは、どのような領域においても等しく適応する標準化された手段である。将来的に新たな審査手段や方法が加わったとしても、現時点においては、学位申請者は、研究成果を第三者に理解できるよう文章によって説明する。これが学術分野での共通認識である。海外のPhDプログラムにおいても、審査対象や審査体制について他の領域と同じ基準、方法に倣っていることからも、論文重視の傾向は明らかである。
実技系博士プログラムにおいて、「実践に基づいた研究」の作品が単体で審査対象になるために、障壁となっていることは何か。これまで述べてきたように、現行の博士プログラムの基本的なシステムが他の学術領域と同じく理論重視である点である。ではその障壁を取り外すために、実技系博士プログラムが最初に提示すべき事項は何か。それは実技系博士学位の定義と、作品の評価基準ではないだろうか。また障壁を超えるためには、議論が高まっているとはいえ未だ曖昧な位置づけである「実践に基づく研究」について、学術的・社会的な位置づけがなされること、さらに共通点にあげた、作品と論文の両方の指導、評価を行える人材不足の解消が必要であろう。
「実践に基づく研究」についての議論は、国際会議の場や研究論文や書籍の形で多くの意見が発表されている。本学は長い実技系博士学位授与の実績を有していることは既に述べた。そうして本学のそれぞれの研究領域が確立してきた指導方法や伝統を、他者と共有可能な形に理論化・体系化し、国内外に継続して発信、積極的に議論に参加していくことが重要である。客観性にとらわれない、自由が尊重される芸術を、博士課程をはじめとする学術というプロセスや様式とどのように調整していくか。本学ならではの「実践に基づく研究」の方法論の構築が急務である。芸術の実践による新たな「知」を提示することによって社会に貢献し、さらに芸術創造を深化させる。こうした「実践に基づく研究」の次なる展開を期待する。
(平成24年度活動報告書別冊)