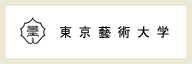リサーチ活動
Ⅲ.インタビュー集
3.英国王立音楽院のリサーチ・プログラム ―デーヴィッド・ゴートン先生へのインタビュー
中村 美亜
- 日時:2011年5月12日
- 於:Royal Academy of Music

- デーヴィッド・ゴートン Dr David Gorton
- リサーチ・プログラム副主任(Associate Head of Research)。作曲家。近年、作曲家と演奏家の共同作業による研究と創作を展開している。
§1.リサーチ・プログラムの概要
- 中村(以下N):
- こちらでは実践に基づく研究(Practicebased Research)を積極的に推進しているということですが、詳しく話を聞かせていただけますか?
- Gorton(以下G):
- わかりました。私たちのアカデミーは数年前に、ロンドン大学(連合大学)の一部になり、2000年に研究の学位を授与し始めました。2004年に最初の学生が博士号を取得しています。それ以来、このリサーチ・プログラムは年を追うごとに成長を遂げてきました。
プログラムは3つのコースに分かれています。一つめは、作曲の学生向きのものです。研究プロジェクトをベースにしたもので、博士課程にいるうちに、自分自身の充実したポートフォリオ(作品集)を作っていくことが課題になっています。また、ポートフォリオの他に、コメンタリー(論文)も書きます。コメンタリーというのは、自分が作曲する作品の概念的枠組を位置づけるもので、作曲のプロセスを通じて3年か4年にわたって取り組んできた課題を明確に文章として表すものです。例えば、さまざまな文化の楽器の使用に関することだったり、それが今日の作曲語法にどう変換されるかということだったり、さまざまなタイプの音楽的時間を生み出す音楽構成について探求することだったり‥。だからコメンタリーというのは自分の作品の位置づけを示すもので、主に作曲へと導く研究プロセスを文章化したものといえるでしょう。
コメンタリーの長さはだいたい15,000語から25,000語の間です。作曲ポートフォリオも充実したものでなくてはなりません。私たちは最低1時間と言っていますが。もちろん、作曲作品が博士レベルの質を保っていなければならないのは言うまでもありません。なので、長い文章である必要はありません。実際、もっとも出来のよいコメンタリーは、決して長いものではありません。肝心なのは、コメンタリーと実際の作品との間の関係です。コメンタリーが長くても、それが実際に作曲をした際の研究プロセスの内容から逸れているのでは意味がありません。
二つめは、演奏の学生向きのものです。作曲のプロジェクトに似ていますが、作曲のポートフォリオを作る代わりに、自分の演奏録音の充実したポートフォリオを作ることです。たとえば自分の演奏を収めたCD数枚を提出するとか。ただ、提出方法に関しては柔軟に対応しています。今のところ録音でなく生の演奏がいいという学生はいませんでしたが、もしそういう学生が現れたら、生演奏でも、それについて可能な記録などの提出を課すことで、そういう要求にも対処しようと思っています。ポートフォリオの長さは作曲と同じです。また同様に、コメンタリーは演奏によって明確に導かれた研究課題を探求し、それを実際の演奏とともに表現することです。
三つめは、歴史的演奏実践(演奏習慣)に関する論文で、従来の博士論文とほぼ同じ形式です。通常60,000語以上、だいたい80,000語から200,000語ぐらいです。自分の実演による録音資料を多く提出する場合は、少し短めでいいというように柔軟に対応することもあります。
§2.リサーチ・プログラムの歴史的背景
- N:
- 2000年に博士課程がスタートしたとおっしゃっていましたが、なぜその時期だったのですか?
- G:
- それは、この学校の歴史的展開やロンドン大学という認証母体に関わることです。アカデミーは1993年にロンドンのキングス・カレッジの認証で修士号と学士号の授与を始めました。その後、ロンドン大学の一機関になったのですが、その際に私たちもリサーチ・プログラムを設置しようという話になりました。
リサーチ・プログラムを始めた頃は、学生自身がプログラムを形づくっていきました。一人めは作曲専攻で演奏もする学生でした。彼は弦楽四重奏で第二ヴァイオリンをしていたので、第二ヴァイオリンについて調べ、それらを応用して作曲しました。その後もこうした実践に沿った形の研究が続きました。学生も演奏に関心をもっていますし、アカデミーは演奏中心の機関なので、こうした方向で研究が発展してきたのは自然なことでした。学生たちがここのプログラムを形づくってきたと同時に、ここのプログラムが学生の方向性を形づくってきました。また、そうした試みに触発された学生が入学するようにもなり、いい循環が生まれました。
過去40年の間に、イギリスの教育制度はかなり大きく変化してきました。このアカデミーはイギリスで最も古くからあるもので、長年すぐれた音楽家の養成に主眼を置いてきました。ヴァイオリンの学生は、最良のヴァイオリン奏者になれるように、といった具合です。その頃は、デュプロマ(免状)を出していました。1990年までは職業音楽家になることが重要なのであって、学部卒業の学位は重要だとは考えられていませんでした。しかし、ロンドン大学の一部になった際に、ヴァイオリン奏者にはデュプロマではなく、音楽の学位が授与されるようになりました。とはいえ、現在の制度でも、このアカデミーの強みであるすぐれた演奏の伝統が維持されていることは言うまでもないでしょう。
§3.指導体制
- N:
- 学生の指導はどのようにされていますか?学生一人一人にアドバイザーがつくのは理解していますが、チームとしてもなさっていると伺ったのですが‥。
- G:
- ここは小さな機関なので、学生は互いにいっしょに研究をしたり、共同研究をしたりしています。例えばピアノの学生は、ピアノの先生といっしょに共同研究をしたり、私は作曲家なので、彼のために作品を書くことがあります。それは、私の研究の一部ともなります。新しい音楽でのハイレベルな演奏技法を追究することとか、作曲家として境界線を探求することは、私の研究にとっても重要で、その成果が私自身の論文にも結びつくからです。その一方で、私の作曲とのコラボレーションは、彼の研究の一部になっていきます。ハイレベルの音楽作りに参画すると同時に、そのプロセスを体験することが彼自身の研究にもつながるからです。これは学生にとっても重要なことです。
このようにチームになって作業を進めていくやり方は、科学系の研究方法に似ていると言うことができるでしょう。伝統的な音楽学の方法では、学生は論文を書き、指導教員がそれを個人指導するというのが典型的ですが、ここのやり方はむしろ理系のモデルに近いのです。 - N:
- あなたは作曲家です。ヴァイオリンの学生の場合、だれが学生を指導するのですか?
- G:
- 複雑ですね。このアカデミーには、弦楽、ピアノ、作曲の専攻があります。それ以外にもリサーチ・プログラムの教員や、学部教員や大学院教員もいます。ヴァイオリンの学生の場合は、大学院の弦楽器主任、ヴァイオリンの先生、大学院プログラムの主任、大学院のチューターなどと共同する可能性があります。リサーチ・プログラムの学生は、リサーチ・プログラムの教員を主任指導教員にしますが、専門の先生からレッスンを受けることもできます。ピアノ・レッスンのための正規の学費を払う必要はないけれども、時折レッスンを受けたいという学生にはちょうどいいプログラムになっています。主任指導教員以外にも、他のリサーチ・プログラムの教員に指導を請うことは可能です。
リサーチ・プログラムの主任指導教員はたいていリサーチ・プログラムの教員ですが、多くのリサーチ・プログラムの教員は演奏もするので、演奏のことがわからないということはありません。リサーチ・プログラムには音楽学の先生も何人かいますが、彼らも演奏に興味があります。作曲の教員はみな博士号をもっているので、研究も作曲の指導も両方できます。作曲家は(演奏家と異なり)伝統的に学問の世界に属してきたので、研究と作曲の連携には抵抗はありません。演奏家はつい最近になって学問の世界の一員になりました。学生は研究系の教員にも演奏系の教員にも両方にアクセスできます。
§4.プログラムの履修要件
- N:
- 研究の学位を受け取るために、演奏の学生はリサイタルをする必要はありますか?
- G:
- リサーチ・プログラムの場合は、その必要はありません。学生はロンドン大学の規則に準拠した、次のような方法で評価を受けます。まずは修士課程を修了し、それからアップグレードしていきます。
修士を修了してリサーチ・プログラムに入る学生は、まずMPhil(哲学修士)課程の学生として登録され、最初の年の終わりに、45分のプレゼンテーションをおこないます。それは自分が書いた論文を読みあげるのでもいいのですが、多くは演奏の録音を用います。作曲の場合は、作品の録音を使います。そして、その録音について、口頭でプレゼンテーションをおこないます。プレゼンテーションが終わったら、指導教員とリサーチ・プログラムのメンバーから口述諮問を受けます。それに受かったら、次の年に進みます。
2年めの終わりに、MPhilからPhDへ進級するのですが、そのためには博士の最終プロジェクトの一部を完成させ、提出しなければなりません。作曲の場合は、15~20分の音楽とコメンタリー、演奏の場合は、演奏録音とコメンタリーを提出します。その後、口述諮問を受けるのですが、そこでは外部教員に審査を受けることになります。合格した場合に、博士課程に進むことができます。
§5.学生数、学生のタイプ
- N:
- リサーチ・プログラムの学生数はどのぐらいですか?
- G:
- 年によって違いますが、だいたい4~5人です。今まで一人だけMPhilを授与された学生がいますが、それ以外は博士まで進級しています。博士への進級試験に二度失敗すると、博士の資格を失います。博士課程はリサーチ・プログラムでの3年めに相当し、それから執筆仕上げの時間を余分にとることができます。博士の口述諮問は、ロンドン大学の教員と他の大学の教員が担当します。そのまま合格か、わずかの修正で合格、あるいは大幅修正を経て合格という3つの場合があります。博士は通常4年かかります。というのは、執筆の仕上げに一年余分にとることがほとんどだからです。学生はだいたい3年めから4年めの間に提出します。
- N:
- リサーチ・プログラムにくる学生にとってリサーチ・プログラムで学位を取ることには、どういうメリットがありますか?
- G:
- 学生には、非常に充実したコメンタリーを書き上げる学生と、比較的こじんまりとしたものを書く学生と二つのタイプがあるようです。学生にとってどういうメリットがあるかに関しては、私にはよくわかりません。
ただ、学生によってニーズはさまざまです。多くの学生はすでに音楽家として旺盛な活動を開始しており、リサーチ・プログラムにいる間にも忙しくしています。研究テーマによっては、コメンタリーを充実させる必要がある場合もありますし、CDとして提出する方が適している場合もあります。 - N:
- 先ほどプログラムには3つのコースがあるとおっしゃっていましたが、比率はどうなっていますか?
- G:
- そうですね。作曲専攻はだいたい2~4人でしょうか、毎年2~3人の学生が博士号をとっています。年によって差がありますが。演奏専攻のポートフォリオ・コースは最近になって始めたものです。これまで3~4人が博士号をとりました。今も何人か在籍していて、入学希望者も増えてきているので、これから博士は多くなるはずです。3つめの論文コースは、年に2~3人です。手元にリストがないので、はっきりしたことが言えないのですが、だいたいそんな感じです。
できるだけ学生のニーズに応えるように柔軟に対応しています。中には途中で休学する学生もいます。実際、演奏の学生は演奏活動が忙しいので、こういうケースはよくあります。学生によって、ずいぶん状況が違います。多くは4年で博士を終えますが、二年やって休学し、しばらくしてから戻って残りをするというケースもありますね。
§6.評価の方法

- N:
- 実技系の研究というのは歴史が浅いわけですが、どのように評価していますか?
- G:
- それに答えるのは難しいですね。作曲の場合は、比較的簡単です。先ほどお話したように、作曲はアカデミアに属してきたという歴史があるので、どういう博士研究が適しているかということに関して、それなりの経験の蓄積があるからです。ただ、演奏の場合はそうではないので。審査の先生による判断としか言いようがないですね。先生がいいといえば、それでいいといった具合に。ただ、審査をする先生は外部の先生なので、その先生が納得するものでなくてはなりません。
演奏の場合は経験の蓄積がないので、どのような先生に審査をお願いするかが鍵になります。ヨーロッパといえども、実践と研究の両方に通じている人はそれほど多くはありません。とくに実践に基づく研究となると。学術系の大学でも、実践に基づく研究が盛んになってきたのは、この十年ぐらいのことです。イギリスでは、現在、芸術人文学研究評議会(Arts and Humanities Research Council:AHRC)や演奏研究センター(Centre for MusicalPerformance as Creative Practice)が精力的に活動を展開しています。大陸の方でも同様な動きがあります。
大学の先生ではなく、演奏家に審査をお願いすることはあります。大学の先生ではないとしても、演奏家としての研究の蓄積がある人はいますから。それから、私たちの場合は、建築とかパフォーミング・アーツといった、実践に基づく他の研究分野の先生にお願いすることもあります。審査の先生の選定に関しては、かなり慎重におこなう必要があります。
MPhilからPhDへの進級試験の際の審査の先生と、最終試験の審査の先生は別の先生でなくてはならないので、合計3人を外部から選ぶ必要があるわけですが、研究の枠組さえしっかりしている人であれば、大学の先生である必要はありません。これまでのところ、アカデミーでは審査の先生の選定はうまくいっています。実践に基づく研究というのは、これまでの研究とは違うので、一つ一つのプロジェクトに対して相当いろんなことを考えながらやっていかなければなりませんね。 - N:
- 芸大の場合は、演奏の先生が博士研究の主任指導教員で、審査もしています。先生によっては、研究の経験がない場合もあるのでご苦労も多いようです。
- G:
- それはここのケースとは違っていますね。ここではプログラムの運営はリサーチ・プログラムの教員がしていますから。もちろん、声楽や演奏の先生にも研究のバックグランドを持っている方はいらっしゃるので、共同して運営しています。ただし、審査は外部の先生です。内部の先生が審査することはできません。
- N:
- 少し混乱してきました。合計3人ということでしたが…。
- G:
- そうです。3人です。一人は進級試験に、二人は最終試験に。たしかにアカデミーの規則は少し変則的かもしれません。博士の審査では、内部の審査員と外部の審査員が混ざるのが通常ですから。例えばリーズ大学では、リーズ大学の先生とヨーク大学の先生の両方が審査するというふうに。ロンドン大学は連合大学で、ロンドン中のたくさんの大学があつまってできているので、内部の審査員といっても、ロンドン大学内部ということになります。それなので、内部審査の先生は、同じロンドン大学内部のキングス・カレッジの先生やゴールドスミスの先生、あるいはホロウェイの先生ということになるのです。もちろん、アカデミーから一人選出することも制度上では可能かもしれませんが、何分アカデミーの規模が小さいので、そういうことはまず起こりません。
- N:
- 主任指導教員はリサーチ・プログラムの先生ということですが、学生は他の先生の指導を受けることも可能ですか?
- G:
- はい、可能です。作曲の先生は全員、研究のバックグランドがあるので問題ありません。演奏の場合は、研究の先生を主任指導教員に選び、副指導教員として他の先生を選ぶことができます。作曲の学生が演奏の先生のアドバイスが必要な場合は、演奏の先生の指導を請うことはできますし、その逆もできます。実際、演奏の学生は研究の一環としてレッスンを受けることがよくあります。必要な指導は自由に受けることができます。
§7.学生のニーズ
- N:
- リサーチ・プログラムに入学してくる学生というのは、どういう学生なのでしょうか?もうすでに演奏家として活動しているのであれば、あえて学校に残る必要もないかと思うのですが…。
- G:
- 学生は何らかのプロジェクトをもっていて、それを遂行したいために入ってきます。ただ、アカデミーでは、リサーチ・プログラムといえども、実技の成績は非常に優秀でなければなりません。入学には他のプログラムと同じレベルの実技能力が要求されます。たしかに、そういう学生はもう外で十分活躍ができる能力を身につけています。しかし、中には教授法に興味があったり、オーケストラの中での演奏に興味があったり、さまざまな関心があり、それをさらに追究したいと考えている学生がいます。もちろん数としては多くはありませんが、そういう学生はいます。作曲の場合は、演奏に比べるとスタートが遅く技量をあげていくのに時間がかかります。修士を終えた学生の多くは、もう少し学校で勉強したいと考えます。そういう学生がリサーチ・プログラムに入学してきます。
- N:
- 修士のMA(人文学修士)とMMus(音楽修士)は、どのように違うのですか?
- G:
- このアカデミーでは、MAは実技と3000語のポートフォリオの二つを修めなくてはなりません。MMusでは、実技とポートフォリオに加えて、10,000語のコメンタリーです。博士のミニ・ヴァージョンといった位置づけです。リサーチ・プログラムには、MMusを終えた学生が入ってくることがほとんどです。作曲の修士は、リサーチ・プログラムの構成とよく似ています。
- N:
- そうですか。MAが実践指向でMMusの方がリサーチ・プログラムに近いのですね。反対かと思いました。
- G:
- たしかに反対の場合もありますね。学校によって随分異なっているので。
- N:
- 少し話しが戻りますが、修士の人数はどれぐらいですか?
- G:
- 修士は1~2年で、毎年300人ぐらいがMAプログラムに、50人ぐらいがMMusプログラムに在籍しています。合計でだいたい400人弱です。
§8.リサーチ・プログラムの意義

- N:
- そろそろ時間が迫ってきたので、これを最後の質問にしたいと思います。アカデミーには歴史がありますね。芸大の場合もそうです。日本で最も古くからある学校で、優れた演奏家の養成校として強固な伝統をもっています。演奏家は演奏だけをしていればいいし、それこそが演奏家の使命であると考えている先生も多くいらっしゃいます。音楽家に研究は必要ないと。アカデミーでもそういう考えをお持ちの先生方はいらっしゃると思うのですが、いかがでしょうか?研究も重要だと考える先生との間に緊張が生じるということはありませんか?
- G:
- そういう緊張が生じるのは、きわめて自然なことだと思います。どの音楽学校でもそうでしょう。イギリスでもそうです。しかし、それは創造のために必要な緊張だと考えています。そのような二つの考え方に接することは、学生にとってもいい経験になると思います。もし研究肌の先生であれば、学生に論文を読ませたい。また、演奏の先生なら、少しでも実技の練習に時間を割かせたい。それなので、私たちのリサーチ・プログラムは、可能な限り学生のニーズに合わせて柔軟に運営することを心がけています。
音楽の学生はこれまで実技の練習にほぼすべての時間を費やしてきました。しかし、私たちのプログラムは、それとは少し違ったタイプのもの、学究的な能力、教育的な能力の向上も目指しているのです。学生がどういうプログラムが自分に適切なものかを選択すればいいのです。学校側は学生の将来的展望をきき、それに沿ったプログラムを紹介してあげることが大切です。なので、進路に関するアドバイスはとても重要になってきます。多くの学生は演奏家になることを望んでいますが、少数とはいえ、大学で教えたいと考える学生もいます。もしやりたいことがあれば、それを追究すればいいのです。
アカデミーのような学校は、実践に基づく研究をしたいという学生のニーズに応えることが重要だと考えています。イギリスには音楽学のある大学はたくさんあるので、音楽学を研究したい学生は、そちらへ行けばいいのです。しかし、アカデミーはそれとは違うプログラム、アカデミーの特性にあったプログラムを運営していくことが適切ですし、それが使命だと思っています。私たちのプログラムが望んでいる学生は、非常にユニークなニーズをもった学生ということになるかもしれません。実際、私たちがやろうとしていることは、とてもユニークなことですから。そういうユニークなプロジェクトに私たちは挑んでいるのです。