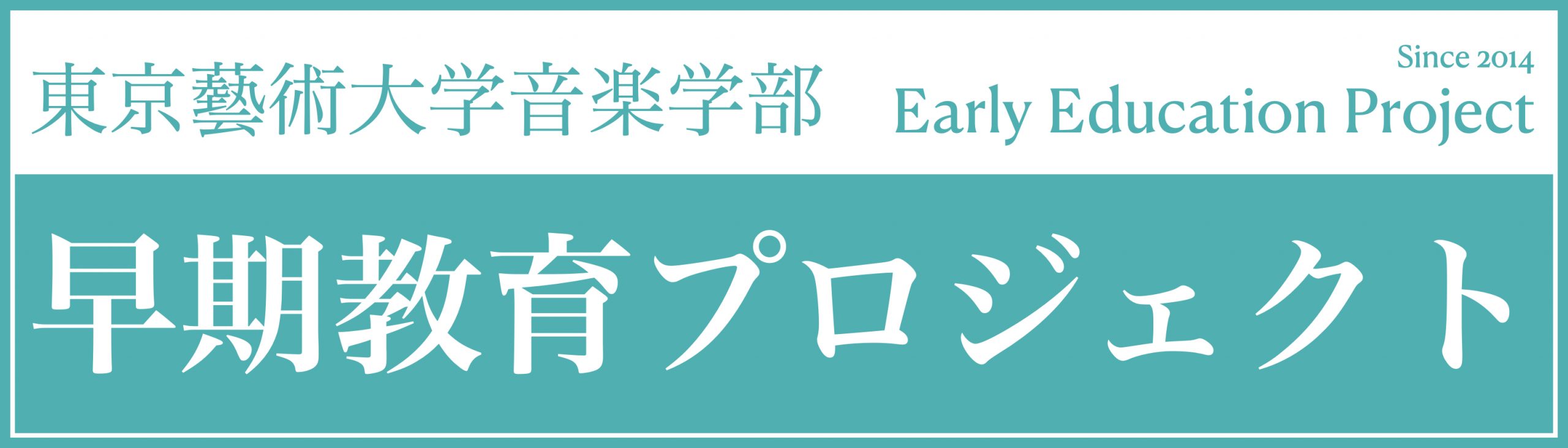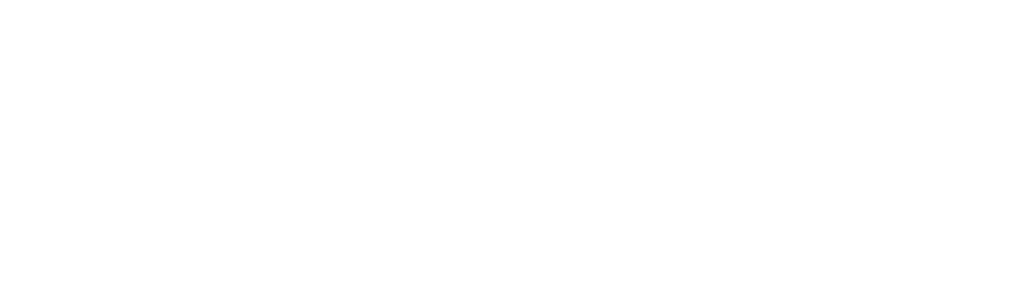- 大学概要
- 学部・研究科・附属機関・センター等
- 展覧会・演奏会情報
- 広報・大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般・企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第八十八回 岩田広己「想いを映し出すこと」
東京藝術⼤学の⾨をくぐってから、気づけば 39年という歳⽉が過ぎ、来年には 40年を迎えます。振り返れば、教育という現場と、表現という問いや答えを探す世界と共に、あっという間に年⽉が過ぎました。私が所属する⼯芸科彫⾦は、東京美術学校開学当初から続く歴史の⻑い学科であり、⾃⾝の歩みとも重なります。⼯芸の学びは、最初から⾃⾝の作品として完成を⽬指すことから始まるわけではありません。まずは作品制作に必要な道具を⾃らの⼿で作るところから始まります。その道具は⼿⾜の延⻑のような存在であり、その感覚や癖は、扱う⼈の⾝体や意識と深く結びつきます。さらに、古くから受け継がれてきた技法を⽤い、先⼈が残した⼿本を基に、彫⾦では⾦属素材の特性を体感しながら、表現に必要な技術を⾝に付けます。そこには、礎を⾃らの体に刻み込むという姿勢があり、時代を超えても変わらない⼯芸の原点があります。
⾃⾝の制作においては、これまで⽇常における体験を通し、想いを映し出す⾏為ということを意識してきました。例えば、⾦属の鏡⾯仕上げは、磨き上げた者の姿や周囲を映し出します。しかし、その映り込みは必ずしも鏡のようにまっすぐではありません。形によって揺らぎや歪みが⽣まれ、その素材と向き合った時間や⼿の痕跡を物語ります。
数年前、⾃⾝の展覧会で訪れたシカゴのグラント・パークにある、アニッシュ・カプーアの「クラウド・ゲート」と呼ばれる巨⼤な鏡⾯の⾦属彫刻を⽬にしました。その鏡⾯には、映し出された街並みや⼈々の姿が歪み、揺らぎながら広がり、景観と調和し、圧倒的な⾦属の存在感を放っていました。そこには、造形的な形体だけではなく、その瞬間の空気や作品と向き合う⼈々の存在感までもが映り込み、⾦属は時の流れまでも取り込む不思議な素材だと改めて実感しました。

シカゴ クラウド・ゲート(アニッシュ・カプーア)に映った人々
また⼀⽅で、偶然が⽣んだ形や⾊、質感には、意図して⽣み出せない深みや表情があり、⾦属素材は時代や状況にも影響を受けます。私の住む街には、震災と戦災の犠牲者を供養する東京都慰霊堂があり、その脇には被害・救援・復興を表す東京都復興記念館があります。そこには、災厄によって建物や道具、⽣活の中の⾦属が焼け、溶け、変形し、錆びたものが多数展⽰されています。それは破壊や悲しみの痕跡でありながら、素材に宿る歴史や記憶を留める存在でもあります。このような点から、発想から素材を扱い、作品に⾄るまでのプロセスには、様々な想いが反映され作品という形になるのだと感じています。
こうした思いを抱きながら、表現の軸となるイメージの⽐喩として、これからも素材が持つ特性や魅⼒を感じ取り、その反応に応えながら作品制作を続けられればと思います。想いを映し出す⾏為の結果が、観る⼈や使う⼈に少しでも伝わればと願います。

東京都慰霊堂

東京都復興記念館の「鉄柱の溶塊」
写真(トップ):様々な切削用のタガネ
【プロフィール】
岩田広己
東京藝術大学 理事(研究担当) 美術学部工芸科教授
1965年東京都江戸川区出身。1990年同大学美術学部工芸科彫金専攻卒業。1992年同大学大学院美術研究科修士課程彫金専攻修了。1992年から2008年同大学大学助手、非常勤講師、内2000年~03年同大学常勤助手。2008年から神戸芸術工科大学芸術工学部准教授、東京藝術大学非常勤講師(集中講義)を経て、2017年4月より東京藝術大学准教授。2023年4月から同大学大学教授。
制作活動では彫金はもとより、金属にガラス粉を焼き付ける七宝などを用いて装飾的な手法を用いた作品制作、研究を行っている。国内展はじめ、SOFA(アメリカ)、Schmuck(ドイツ)、ロンドンのCollect、Masterpiece London、PAD、Artefactなどのヨーロッパ、アメリカ、アジア、オセアニアのアートフェアなどに毎年出品。東京藝術大学大学美術館(卒業制作買上げ)、スコットランド王立美術館、アバディーン美術館(スコットランド)など作品収蔵。The Enamelist Society America、Society of North American Goldsmithsのメンバー。公益社団法人 日本七宝作家協会理事長。