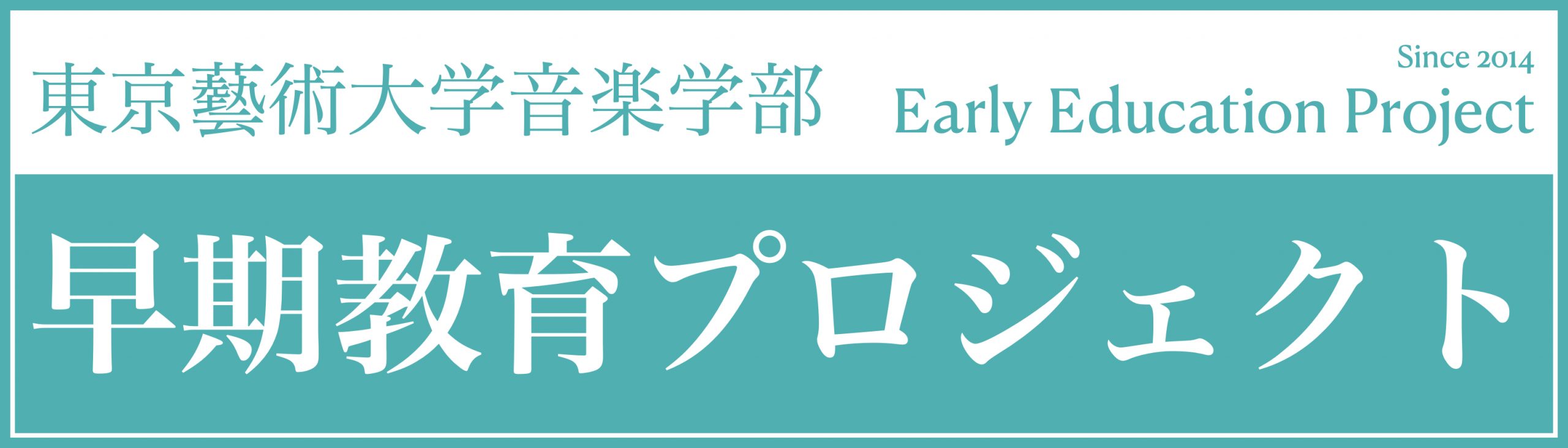ピアノ
◆学科・専攻概要
 ピアノ専攻は、東京音楽学校創立当初から西洋音楽の吸収、国内への広い普及を目指し、更に世界に向けての活躍のレベルを目標に歴史を積み重ね、多くの優れた人材を輩出してきました。近年では殊に、全世界規模での本学の存在が注目され、本専攻も国内外で活躍できるトップレベルの人材養成を目標とした専攻であることを期待される状況です。そのような中で、自由な発想のもと、伝統と進取を重んじながら、若い才能が大きな花を咲かせられるように、また人間性豊かな芸術家として歩めるよう、如何にサポートできるか、模索しつつ努力しています。
ピアノ専攻は、東京音楽学校創立当初から西洋音楽の吸収、国内への広い普及を目指し、更に世界に向けての活躍のレベルを目標に歴史を積み重ね、多くの優れた人材を輩出してきました。近年では殊に、全世界規模での本学の存在が注目され、本専攻も国内外で活躍できるトップレベルの人材養成を目標とした専攻であることを期待される状況です。そのような中で、自由な発想のもと、伝統と進取を重んじながら、若い才能が大きな花を咲かせられるように、また人間性豊かな芸術家として歩めるよう、如何にサポートできるか、模索しつつ努力しています。
◆カリキュラム
ピアノは、低音から高音まで幅広い音域をカバーし、オーケストラを思わせる大音量から、 人のつぶやきのような弱音までを同時に扱うことのできる、大変優れた楽器です。本専攻では、この優れた楽器から多彩で自在な表現を引き出す能力を高め、音を通して多くの人々とコミュニケートできる人材を育成することを目指しています。そのために実技、理論の両面で質の高いカリキュラムが組まれています。
○カリキュラム(学部教育)
専攻楽器の個人レッスン、1年次・2年次の合奏(弦楽器または管楽器とのデュオ)、伴奏が実技に関わる必修科目です。さらに選択科目として3年次以降に合奏、室内楽の授業が組まれており、ピアニストとして幅広い見識と能力を養います。1年次の前期には「バッハ演奏実習」、後期には「古典派ソナタ演奏実習」が、2年次の後期末にはバッハ作品と、バロック、古典、ロマン、近現代から異なる1つ以上の時代を選択し、約40分のプログラムを演奏する実技試験がそれぞれ課されます。3年次前期には、奏楽堂で20~30分程度の自由に選曲したプログラムを演奏する「学内演奏会」、後期には協奏曲一曲の全楽章を準備する「協奏曲オーディション」が行われます。4年次の12月には、奏楽堂で30分程度のプログラムを演奏する「卒業演奏会」と、同じく30分程度のプログラムを用意して臨む「レパートリー試験」の2回で、4年間の成果を発表します。こうした課題を通して、卒業までにリサイタル複数回分のプログラムが仕上がるようになっていますが、学生個々の資質、研究計画に対応したレッスンにより、幅広い選択肢の中から自由に可能性を追求できるカリキュラムとなっています。
〈学部カリキュラム〉
1年次[必修科目]ピアノ実技、合奏、伴奏、西洋音楽史、和声、鍵盤音楽史、古典舞踏、管弦楽概論、ソルフェージュなど
2年次[必修科目]ピアノ実技、西洋音楽史、和声、対位法、音楽分析、鍵盤音楽史、古典舞踏、管弦楽概論
[選択科目]合奏、伴奏、ソルフェージュなど
3年次[必修科目]ピアノ実技、学内演奏、対位法、音楽分析、鍵盤音楽史、古典舞踏、管弦楽概論
[選択科目]室内楽、合奏、伴奏など
4年次[必修科目]ピアノ実技、卒業演奏、対位法、音楽分析、鍵盤音楽史、古典舞踏、管弦楽概論
[選択科目]室内楽、合奏、伴奏など
○カリキュラム(大学院教育研究)
大学院ではより高度な、演奏と理論両面での研究を行い、ピアニストとして、音楽性、人間性を深めた自立した音楽家を目指します。50 〜 60 分の自由なプログラムを組んで演奏する「修士リサイタル」「博士リサイタル」を行うほか、学位審査に際しては、論文の提出と、論文のテーマに沿った内容を半分以上含む40 〜 45 分程度の演奏を行います。
指導教員
>> 教員一覧
教育科目
>> 履修案内
>> シラバス
>> カリキュラム・ガイド
◆学科・専攻概要
 オルガン専攻は、音楽学部発足と同時に開設され、ルネッサンス期から現代まで約700年にわたる幅広いレパートリーを学んでいます。我が国の洋楽導入とともに取り入れられたオルガンは、本学の前身である音楽取調掛でも「風琴」の名で伝習に用いられ、東京音楽学校時代には明治33年以降、オルガン専門の枠が設けられました。オルガンは主として欧州で教会の建物に付随して建造されてきた楽器であるため、オルガン演奏技術の習得と並行して、作品の書かれた地域や時代の事情を反映した建造様式と、各時代の作曲様式ならびに演奏習慣などを同時に学習しなければなりません。本学には、クオリティの高い、建造様式の異なる3つのレッスン楽器、ならびに小規模の練習楽器が4台備えられており、幅広いレパートリーを習得するための環境が充実しています。
オルガン専攻は、音楽学部発足と同時に開設され、ルネッサンス期から現代まで約700年にわたる幅広いレパートリーを学んでいます。我が国の洋楽導入とともに取り入れられたオルガンは、本学の前身である音楽取調掛でも「風琴」の名で伝習に用いられ、東京音楽学校時代には明治33年以降、オルガン専門の枠が設けられました。オルガンは主として欧州で教会の建物に付随して建造されてきた楽器であるため、オルガン演奏技術の習得と並行して、作品の書かれた地域や時代の事情を反映した建造様式と、各時代の作曲様式ならびに演奏習慣などを同時に学習しなければなりません。本学には、クオリティの高い、建造様式の異なる3つのレッスン楽器、ならびに小規模の練習楽器が4台備えられており、幅広いレパートリーを習得するための環境が充実しています。
◆カリキュラム
○カリキュラム(学部教育)
毎週1回60分のオルガンのレッスン、やはり毎週行われる通奏低音(1・2年次)・アンサンブル(3・4年次)の実技授業に加え、4年間を通じて学部生全員で学ぶオルガン様式研究、1年次で必修のオルガン概論(オルガン建造法)、4年次に30分のリサイタル2回(学内演奏、卒業演奏)などの専門必修科目のほか、音楽家としての基礎を築く科目として、ソルフェージュ、和声、音楽史等の音楽の基礎科目、また、文献研究に必要な外国語や、教育科目を学びます。また、外部から講師を招いて行う特別講座(マスタークラス)や、オルガン調律法実習、種々のセミナーやワークショップなども活発に行っています。
○カリキュラム(大学院教育研究)
大学院では、学部で培った基礎の上に、さらに高度な演奏技術と表現を習得することを教育の主眼にしています。大学院器楽特殊研究では、毎年年度初めにテーマを定め、学部の様式研究で得た知識をベースに原書講読や資料研究を行い、さらに高い専門的知識を身に付けます。修士リサイタルでは、各自がリサイタルのテーマを定め、個人のソロリサイタルを行う準備を教員とともに整えます。また、修了時に行う学位審査演奏会においては、修士論文の研究と関連したプログラムの演奏をリサイタル形式で行います。
指導教員
>> 教員一覧
教育科目
>> 履修案内
>> シラバス
>> カリキュラム・ガイド
弦楽
◆学科・専攻概要
 器楽科弦楽専攻は本学でも長い歴史を持っています。本学における弦楽をさかのぼれば、1881(明治14)年2月、お雇い外国人L.W.メーソンの注文により、ボストンから「バイヲリン」「ビヲラ」「ビヲロンセロ」「ダブルベイス」があわせて10挺到着し、音楽取調掛に備え付けられたことに始まります。東京音楽学校時代以降、日本の音楽界を支える数多くの優秀な演奏家を輩出してきました。
器楽科弦楽専攻は本学でも長い歴史を持っています。本学における弦楽をさかのぼれば、1881(明治14)年2月、お雇い外国人L.W.メーソンの注文により、ボストンから「バイヲリン」「ビヲラ」「ビヲロンセロ」「ダブルベイス」があわせて10挺到着し、音楽取調掛に備え付けられたことに始まります。東京音楽学校時代以降、日本の音楽界を支える数多くの優秀な演奏家を輩出してきました。
これまで主にソリストのレパートリーを中心に教育が行われてきましたが、近年は弦楽奏者として必須のアンサンブル能力を身につけるための教育にも力を入れています。
弦楽専攻にはヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、ハープの5つの楽器種があります。
◆カリキュラム
教育の基本方針として次の2点を掲げています。
(1)個人レッスンを中心とした弦楽器奏法の研究と演奏解釈
それぞれの楽器演奏の技術向上をソロ作品や二重奏ソナタのレパートリーを中心に学び、同時にその作品の様式感や和声感等を基にして演奏解釈を学びます。
(2)オーケストラ、室内楽におけるアンサンブル能力の向上
弦楽合奏、オーケストラ、三重奏以上の室内楽の授業を履修することで、さまざまな形態のアンサンブルに対応する能力を身につけます。
○カリキュラム(学部教育)
学習の成果発表の場として、前期には各教員のクラス単位での発表会があり、各人の演奏時間も十分に取ることでさまざまなレパートリーを集中して勉強ができるようになっています。
後期には、定期試験が行われますが、1年次のそれは「福島賞」奨学金のためのオーディションを兼ねています。3年次は学内の栄誉賞である「安宅賞」、そして4年次はオーケストラとの共演する「モーニングコンサート」出演のオーディションを兼ねています。4年次の「卒業試験」は奏楽堂で行われ、4年間の勉強の成果を発表する場となっています。また各種の新人演奏会出演のオーディションも兼ねています。
また3年次後期には、「学内演奏」として奏楽堂で演奏会があります。
○カリキュラム(大学院教育研究)
大学院では、学部で培った演奏技術や音楽表現をさらに高度なものになるよう発展させ、プロフェッショナルな音楽家としての自立を目指します。また学部に引き続きアンサンブル教育も重要視され、室内楽、チェンバーオーケストラの授業や、さらに藝大フィルハーモニアへのエキストラ出演も単位として認められています。
弦楽専攻では修士課程の修了要件として2つの選択肢があります。修士論文を書いて演奏審査を受ける場合と、演奏審査のみの場合です。前者ではテーマを絞って論文にして表し、それと密接な関係をもった演奏を求められます。また後者の場合は、より高度な演奏内容が求められます。
博士後期課程では課程修了の要件として、演奏審査と博士論文の提出が義務付けられています。
○その他(国際交流、留学生の受入れなど)
国際交流への取り組みとしては、特別公開講座を年に数回開催し、海外から著名な音楽家を迎えたマスタークラスを行っています。
また特別招聘教授として、場合によっては数週間から1年間、期間を定めて来日していただき、個人レッスンの指導やオーケストラの指揮をしていただいています。
外国人に対しては、修士課程に「外国人修士入試」を受ける門戸が開かれています。
指導教員
>> 教員一覧
教育科目
>> 履修案内
>> シラバス
>> カリキュラム・ガイド
管楽・打楽
◆学科・専攻概要
 日本における管楽器の歴史をひもとくと、管楽器は1897(明治30)年頃から宮内省(当時の名称:宮内省式部職雅楽部)の伶人を中心にフルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、コルネット等が教授されていたそうです。軍楽としての管楽器の伝習は、明治初期より陸・海軍軍楽隊において開始されましたが、唱歌教育の実施を急務として始まった本学では、むしろ声楽・鍵盤楽器・弦楽器が管楽器よりも優先されていました。
日本における管楽器の歴史をひもとくと、管楽器は1897(明治30)年頃から宮内省(当時の名称:宮内省式部職雅楽部)の伶人を中心にフルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、コルネット等が教授されていたそうです。軍楽としての管楽器の伝習は、明治初期より陸・海軍軍楽隊において開始されましたが、唱歌教育の実施を急務として始まった本学では、むしろ声楽・鍵盤楽器・弦楽器が管楽器よりも優先されていました。
1931(昭和6)年プリングスハイム着任後は管楽器の強化が図られ、1935(昭和10)年には生徒吹奏楽団も新設され、1936年にはホルンのW.シュレーターが着任しました。しかし、演奏会に際しては、金管楽器奏者の不足を補うため、海軍軍楽隊が加わることが常で、5度にわたるマーラーの日本初演も海軍軍楽隊とともに行われました。
東京音楽学校の管楽器専攻第1回生は1935(昭和10)年に予科に入学した3名で、フルート、オーボエ、トロンボーンを専攻しました。オーケストラに必要な管楽器の専任教師が揃ったのは、1949(昭和24)年の東京藝術大学発足以降になります。
現在、管楽器専攻はフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、サクソフォーン、ホルン、トランペット、トロンボーン、ユーフォニアム及びチューバと10種の楽器に分かれ、打楽器はパーカッション及びマリンバアンサンブルを通して、すべての打楽器に精通し、それぞれの専攻を通して、芸術家として高い人格と感性あふれる人材を育てることを目的としています。



◆カリキュラム
演奏技術の基本、理論と実践を徹底させ、ジャンルを超えて様々な音楽へのアプローチを試み、より高度な技能と深い音楽表現へのステップの場が用意されています。
○カリキュラム(学部教育)
授業の内容は、教員とその人間的、精神的交流を重視した個人レッスンを主体に、演奏家として必要なソルフェージュ、ピアノ実技、音楽理論、音楽史等が用意され、オーケストラ、吹奏楽(年2回の定期演奏会を行います)、室内楽等による合奏研究を行っています。
○カリキュラム(大学院教育研究)
修士課程では、さらに専門的な研究を目指し、より高度な芸術性の追求と管打楽器の関わるあらゆる分野における研究が行われます。
博士後期課程では、より専門性を深めた研究テーマを設定した上で、研究が行われます。
修士課程・博士後期課程とも、中間発表として修士リサイタル・博士リサイタルが義務付けられています。
○その他(国際交流、留学生の受入れ、卒業後の進路など)
本専攻は、国際交流もさかんに行っています。
近年では、
2023年度にはサクソフォーンのアルノー・
また、2022年度にシベリウス音楽院の学生1名(ホルン)
卒業生の多くはオーケストラ奏者、室内楽奏者、ソリスト、
指導教員
>> 教員一覧
教育科目
>> 履修案内
>> シラバス
>> カリキュラム・ガイド
室内楽
 本学における室内楽教育の歴史は古く、1900(明治33)年、東京音楽学校研究科に週2回「合奏練習」の時間が設けられて以来、「室楽」「器楽合奏」などの名称でカリキュラムに取り入れられてきました。室内楽講座の前身は1964(昭和39)年に設置されたアンサンブル研究室で、同年旧奏楽堂で室内楽研究演奏会が開催されました。その後、1972(昭和47)年に設置された室内楽合奏講座を経て、1978(昭和53)年に、より充実したアンサンブル教育をめざして現在の室内楽講座が開設されました。また、室内楽定期演奏会は、1974(昭和49)年11月に第1回が開催されて以来、2009(平成21年)2月で35回を数え、本学で開催されるコンサートの中核的存在となっています。室内楽講座では、音楽を学ぶ上で原点ともいえる室内楽を研究し、アンサンブル感覚を磨くことで、学生間の音楽的交流が活発に行われ、豊かな音楽性が育まれると考え、自発的な室内楽への興味を喚起させるためのよりよい環境を整備し、高度で専門的な室内楽研究を望む学生に対しても細やかなサポートをする体制をとっています。
本学における室内楽教育の歴史は古く、1900(明治33)年、東京音楽学校研究科に週2回「合奏練習」の時間が設けられて以来、「室楽」「器楽合奏」などの名称でカリキュラムに取り入れられてきました。室内楽講座の前身は1964(昭和39)年に設置されたアンサンブル研究室で、同年旧奏楽堂で室内楽研究演奏会が開催されました。その後、1972(昭和47)年に設置された室内楽合奏講座を経て、1978(昭和53)年に、より充実したアンサンブル教育をめざして現在の室内楽講座が開設されました。また、室内楽定期演奏会は、1974(昭和49)年11月に第1回が開催されて以来、2009(平成21年)2月で35回を数え、本学で開催されるコンサートの中核的存在となっています。室内楽講座では、音楽を学ぶ上で原点ともいえる室内楽を研究し、アンサンブル感覚を磨くことで、学生間の音楽的交流が活発に行われ、豊かな音楽性が育まれると考え、自発的な室内楽への興味を喚起させるためのよりよい環境を整備し、高度で専門的な室内楽研究を望む学生に対しても細やかなサポートをする体制をとっています。
◆カリキュラム
○カリキュラム(学部教育)
音楽学部1年次の管弦打楽器専攻学生を対象として、室内楽の基礎を学ぶ必修科目「室内楽Ⅰ」、2年次からの学生が自主的にグループを組み履修する選択科目「室内楽Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」と、年次順に研究を発展させるようにカリキュラムが組まれています。「室内楽Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」ではグループごとに1人ないし2人の教員が担当し、レッスン形式の授業が行われます。
「室内楽Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」は毎年70組を超えるグループが履修しており、学生の室内楽への継続的な高い関心を示しています。また、11月に室内楽オーディションが行われ、そこで選ばれたグループは翌年2月に開催される室内楽定期演奏会をはじめ、さまざまなコンサートに出演する機会を与えられます。また、この授業は大学院音楽研究科においても「室内楽実習」として開設されています。
※令和5年度の「室内楽Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」「室内楽実習」
○カリキュラム(大学院教育研究)
大学院音楽研究科器楽専攻室内楽研究分野では、個々の学生の研究テーマに沿って担当教員がきめ細かい指導を行いますが、それに加えて、より専門的、かつ実践的な研究を進め、高い表現力と洗練された室内楽感覚を身につけるために、第一線で活躍する室内楽奏者と共演しながら指導を受けるリハーサル、担当教員のレッスン、年二回の研究発表会、学位審査会という一連のカリキュラムを組んでいます。
室内楽・ピアノ・弦楽器を専攻する学生が履修対象の「室内楽特殊研究」では、テーマとなる作品についてセミナー形式で分析・演奏解釈を行い、「室内楽実習」では自主的にグループを組み、弦楽四重奏やピアノ三重奏など、各講座単位の授業では取り組むことのできない幅広い室内楽領域の研究も活発に行われています。
導教員
>> 教員一覧
教育科目
>> 履修案内
>> シラバス
>> カリキュラム・ガイド
◆学科・専攻概要

本専攻では主に、バロック時代の音楽を中心とする1500年代半ばから1800年頃までの音楽を、その時代にふさわしい方法で演奏することを学びます。作品が生まれた時の響きや奏法に一度立ち帰り、そこを出発点として現代における新たな演奏の可能性を探ることが目的です。そこで、各作曲家の属する時代の楽器や演奏様式について可能な限り研究しながら、作曲家の意図を尊重し、かつ現代にふさわしい演奏様式を見つけていきます。
学部ではチェンバロ、リコーダー、バロックヴァイオリンの3専攻を、大学院修士課程、博士後期課程、別科ではバロックチェロ、バロック声楽、フォルテピアノ、バロックオルガンを加えた全7専攻を学ぶことが出来ます。
◆カリキュラム
○カリキュラム(学部教育)
 学部では、和声やソルフェージュなどの音楽の基礎能力を高める授業や、音楽研究に不可欠な語学や音楽史などの授業を履修しつつ、「実技レッスン」を中心とする専門科目を学んでゆきます。本専攻では特に、「古楽アンサンブル」、「通奏低音」に重点をおいて学ぶほか、当時の文献から情報を得る力をつける「古楽文献研究」や、当時の楽器について研究する「古楽器概論」を学びます。演奏の成果を発表する場として、ソロ及びアンサンブルの演奏会が行われています。これは各自のレパートリーを充実させると共に、卒業時までに様々なスタイルの曲を勉強して、偏ったものとならないようにすることが目的です。そして4年次になると、これまでの勉強の成果として前期に「学内演奏会」、後期に「卒業演奏会」を行い、ソリストとして30分程度のプログラムを演奏します。
学部では、和声やソルフェージュなどの音楽の基礎能力を高める授業や、音楽研究に不可欠な語学や音楽史などの授業を履修しつつ、「実技レッスン」を中心とする専門科目を学んでゆきます。本専攻では特に、「古楽アンサンブル」、「通奏低音」に重点をおいて学ぶほか、当時の文献から情報を得る力をつける「古楽文献研究」や、当時の楽器について研究する「古楽器概論」を学びます。演奏の成果を発表する場として、ソロ及びアンサンブルの演奏会が行われています。これは各自のレパートリーを充実させると共に、卒業時までに様々なスタイルの曲を勉強して、偏ったものとならないようにすることが目的です。そして4年次になると、これまでの勉強の成果として前期に「学内演奏会」、後期に「卒業演奏会」を行い、ソリストとして30分程度のプログラムを演奏します。
○カリキュラム(大学院教育研究)
修士課程では各専攻ごとにより広いレパートリーの獲得を目指しつつ、専攻の枠を越えて様々なアンサンブルを経験することを通じ、それぞれの様式についての理解を深めてゆきます。また、古楽演奏をめぐる諸問題の中からテーマを選び、修士論文の執筆を通じて各自の問題意識を客観化してゆきます。さらに、「修士リサイタル」、「学位審査会」においては、プログラムの選択、共演者の依頼、楽器の手配やプログラム冊子の作成など、演奏会に関わる全ての準備を自ら行うことで、将来演奏家として活動していくために必要なノウハウを学びます。
○その他(国際交流、留学生の受入れ、卒業後の進路など)
上述のように本専攻ではアンサンブルの授業を重要視しているため
本専攻の卒業生については、
指導教員
>> 教員一覧
教育科目
>> 履修案内
>> シラバス
>> カリキュラム・ガイド