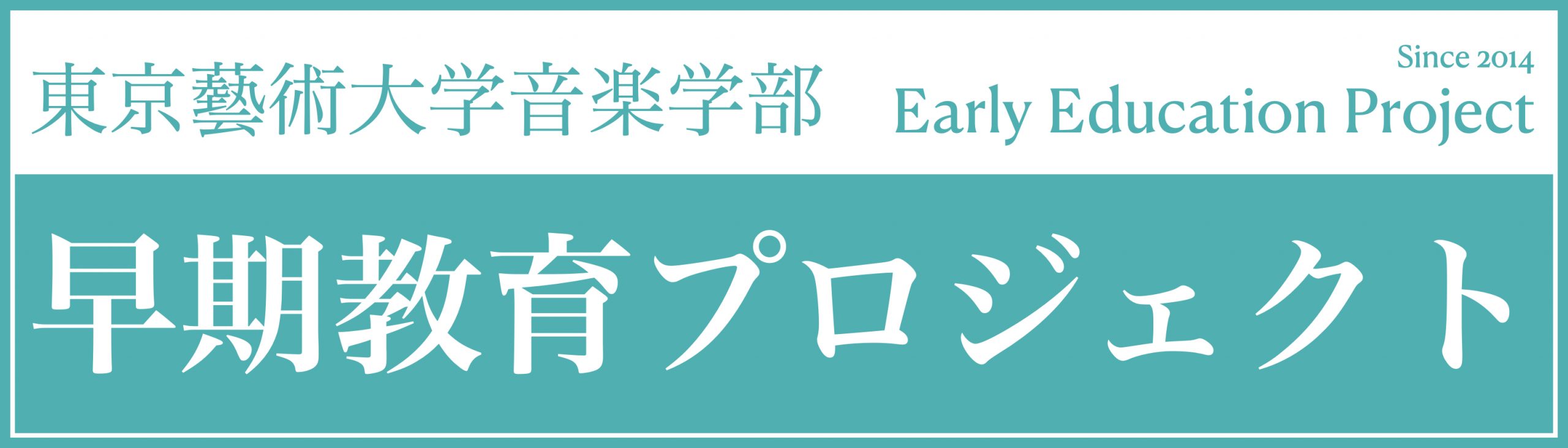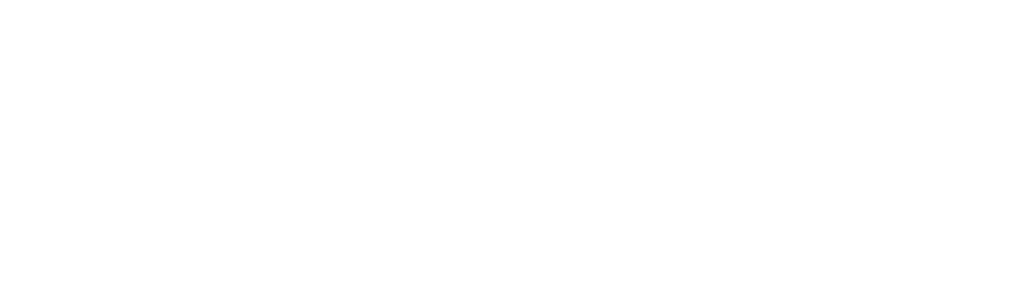- 大学概要
- 学部・研究科・附属機関・センター等
- 展覧会・演奏会情報
- 広報・大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般・企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第八十九回 深田麻里亜「聖年のローマを眺めて」
美術学部芸術学科の教員に着任してからおよそ半年が過ぎました。授業などで学生たちの造形作品にたいする積極的な態度――作品を見ること、つくることへの感覚を研ぎ澄ませようとする強い意欲――に接することができるのは、藝大ならではと言えるように思います。
作品を鑑賞することは、美術作品を学ぶための第一歩と言えるでしょう。加えて、ただ漫然と眺めるだけでなく、関連する文献資料をひもとき、その背景や周囲にあるさまざまな要素を知ることで、作品自体は変わらないはずなのに、不思議と作品の見え方が変わってくることがあります。私自身、こうした知識と鑑賞の一種の相互作用に面白さを覚えたことが、美術史という学問に憧れを抱き藝大を志望する契機となりました。学部生のときにイタリア・ルネサンス美術史を学ぶと決め、卒業論文から博士論文まで研究テーマとなったローマのラファエロとその工房の作品は、今でも最大の関心事の一つです。
実は今年は、ラファエロ作品の重要な修復事業が区切りを迎えた年でもあります。代表作であるヴァティカン宮殿の教皇居室のうち、最後に制作された「コンスタンティヌスの間」壁画が、10年にわたる修復期間を終えたのです。科学的研究調査を通じ、技法に関する様々な事実も明らかとなりました。
さらに2025年は、ローマ・カトリック教会の重要な行事・式典の開催年でもあります。本年5月、システィーナ礼拝堂での教皇選挙を経て、新教皇レオ14世が選出されたことは記憶に新しいところですが、何よりも今年は、聖年と呼ばれる25年に一度の機会にあたります。聖年には、聖堂の「聖なる扉」(イタリア語で「ポルタ・サンタ」)が開かれ、扉を通過した者は罪の赦しにあずかることができるため、世界各地から信徒たちがローマへ巡礼に訪れるのです。
私は修復が完了したラファエロ壁画を見るという「美術の巡礼」も兼ね、9月に聖年のローマを訪問しました。サン・ピエトロ大聖堂へ向かった日は期せずして教皇の誕生日だったため、広場で「教皇レオ14世、誕生日おめでとう」とスペイン語で書かれた旗を掲げる信徒に、カメラとマイクを構えた報道官がインタビューをする様子も目にしました。一方ヴァティカン美術館は、内部が大変に混雑し、なかなか落ち着いて作品を鑑賞できる状態ではありませんでしたが、それでも往時の色彩表現を取り戻した「コンスタンティヌスの間」壁画を実見することができました。ローマという都市には、今も昔も、実に多くの人々がそれぞれの目当てのものを求めて、押し寄せるのだろうと感じます。長い歴史と伝統のある都市の歴史文化、美術作品について、学ぶべきことは尽きませんが、少しでも授業や研究に還元できるよう、これからも作品を見て本を読み、考え続けたいと思います。

ローマ市内のグレゴリアーナ通り。この通りにあるヘルツィアーナ図書館には、各国から美術史研究者が集います。写真右手前のプレートは、フランスの画家ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングルが1806~1820年にかけてこの通りに居住したことを伝えます。
写真(トップ):初代ローマ司教ペトロの墓上に建つサン・ピエトロ大聖堂。巡礼者の団体は、聖堂から少し離れた場所にあるピア広場に集い、列をつくり聖堂へと向かいます。
【プロフィール】
深田麻里亜
東京藝術大学 美術学部芸術学科准教授
東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。博士(美術)。
著書に『ヴィッラ・マダマのロッジャ装飾』(中央公論美術出版、2017年)、『〈カラー版〉ラファエロ』(中公新書、2020年)、共著に『システィーナ礼拝堂を読む』(河出書房新社、2013年)、『あやしいルネサンス』(東京美術、2016年)、『ラファエロ』(河出書房新社、2017年)などがある。訳書『レオナルド・ダ・ヴィンチの生涯』(チャールズ・ニコル著、白水社、2009年、共訳)、『美術家列伝』(ジョルジョ・ヴァザーリ著、中央公論美術出版、2015年、共訳)ほか。