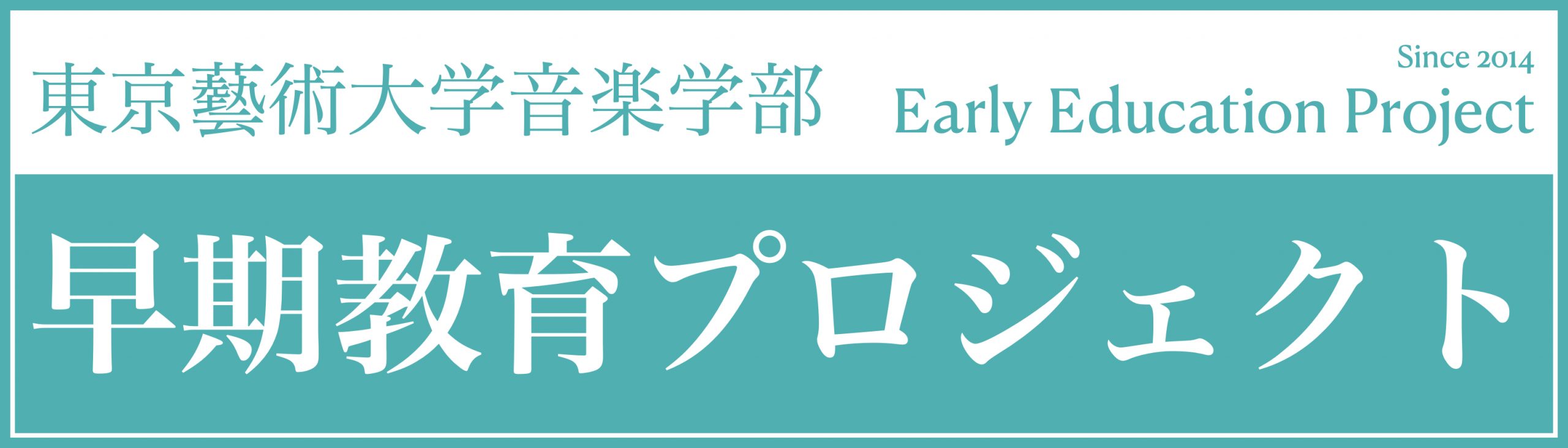- 大学概要
- 学部・研究科・附属機関・センター等
- 展覧会・演奏会情報
- 広報・大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般・企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする
藝大21〈和楽の美〉 邦楽絵巻「ヒミコ」
| TOPページに表示
| 日時 | 2015年9月11日(金) 18:30開演(18:00開場) |
|---|---|
| 会場 | 東京藝術大学奏楽堂(大学構内) |
| 入場料 |
全席指定 |
| 主催 |
東京藝術大学演奏藝術センター |
| チケット取り扱い |
東京芸術大学生活協同組合(店頭販売のみ) ヴォートル・チケットセンター 東京文化会館チケットサービス チケットぴあ イープラス(e+) http://eplus.jp/ |
| お問い合せ | 東京藝術大学演奏藝術センター TEL:050-5525-2300 |
藝大21 演奏藝術センター企画公演〈和楽の美〉
邦楽絵巻「ヒミコ」
無から生み出す苦しみ
中村 雅之(脚本・演出/横浜能楽堂館長・明治大学大学院兼任講師)
今回、まったく何も無いところから物を生み出すことの苦しさを実感した。
前回、「和楽の美」の脚本・演出を担当した時は、名作『西遊記』を下敷きにしたから楽だった。三蔵法師、孫悟空、猪八戒、沙悟浄、いずれの登場人物も、今風に言えば「キャラが立っている」。夜、静かな中で、『西遊記』の世界に潜り込みさえすれば、彼らは勝手に動き出し、新たな物語を次々と生み出す。私は、それをただ書き留めていれば良かった。
しかし、今回の「ヒミコ」は、そういう訳にはいかなかった。
「ヒミコ」という人物、日本の歴史上では、超が付くほどの有名人だが、実態がほとんど分からない。支配していたヤマタイ国の正確な場所さえ、未だ特定出来ないのだから無理はない。教科書にも出ている『魏志倭人伝』のわずかな記述をもとに人物像を考え、物語を組み立てて行った。結果的に、最後の能「高砂」の抜粋の外は、すべての詞を書き下ろした。
どんな「ヒミコ」か、詳しいストーリーは、見てのお楽しみとしたい。
「くらい」「あける」 命の世界
三田村 有純(美術デザイン/東京藝術大学美術学部工芸科教授)
日本列島に住んでいた人々は「イロ=色」に付いてどのような認識を持っていたのであろうか。縄文遺跡からは朱色と黒色の色彩を持つ漆器が夥しく出土する。一般的には赤が炎、太陽、命の色であり、黒は闇、夜,死の色であると言われている。しかし日本列島において黒土はたくさんのバクテリアを宿して命を生みだすが、赤土は命を生まない。黒色にも命が宿っているのである。
この二色の呼び名は「あける」から「あか」となり、「くらい」から「くろ」となった。これは相反する色では無く、日本人は生まれ変わる色彩世界として捉えていた。夜になり、光が閉ざされた闇になると、わずかな炎の光が際立つ。
ヒミコはカミである。このカミは上であり、神であり、髪であり、紙なのである。今回の舞台を、和紙を中心に構成することとした。和紙に黒漆と、赤漆をしみ込ませ、金で命を表現し、未来へと続く光を表したのである。
【脚本・演出】
中村 雅之
【音楽監督・制作統括】
萩岡 松韻
【副音楽監督】
小島 直文
【美術デザイン】
三田村 有純
【総合監修】
千野 喜資
【作 曲】
小島直文 萩岡松韻 吉川さとみ
関根知孝 武田孝史 長谷川千春
野村正也 三浦元則 松下 功
【作 調】
盧 慶順 春日徹彦
【振 付】
露木雅弥
【指 揮】
澤 和樹
【出 演】
小島直文(長唄三味線)
味見 純(長唄)
萩岡松韻(箏曲山田流)
吉川さとみ(箏曲生田流)
関根知孝(能楽観世流)
武田孝史(能楽宝生流)
盧 慶順(邦楽囃子)
露木雅弥(日本舞踊)
東京藝術大学音楽学部邦楽科・器楽科教員・学生ほか
【照 明】
(有)ライズ
【舞台監督】
増田一雄
【音 響】
岩崎 真
【録 画】
田川めぐみ 鈴木勝貴
※スケジュール、曲目、出演者等は、都合により変更になる場合もありますのでご了承ください。
交通案内

東京藝術大学奏楽堂 [大学構内]
〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8
■JR上野駅(公園口)・鶯谷駅(南口)、東京メトロ千代田線根津駅より徒歩10分
■京成線上野駅、東京メトロ日比谷線・銀座線上野駅より徒歩15分
■台東区循環バス「東西めぐりん」
【2】上野駅・上野公園 から(東京芸術大学経由)⇒【5-1】東京芸術大学下車[30分間隔]
※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。