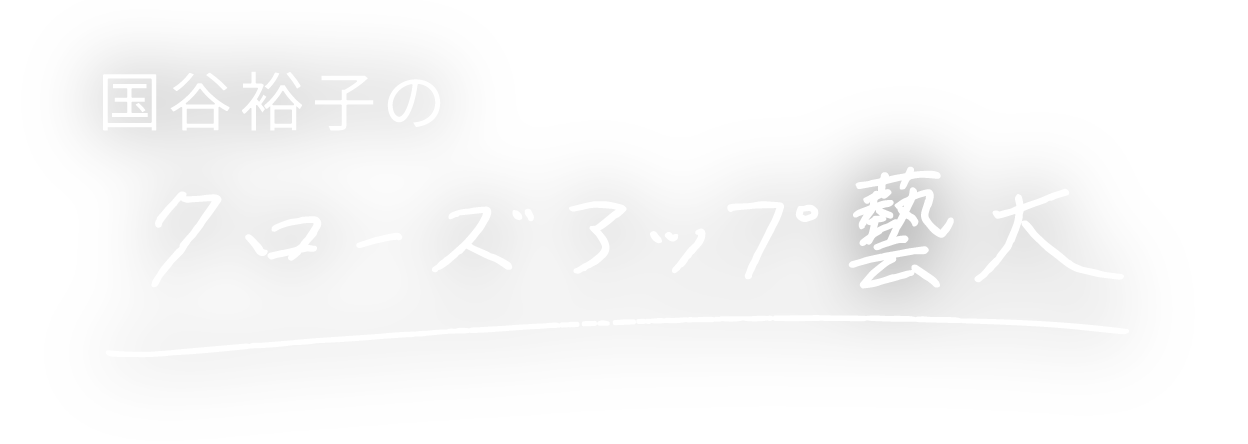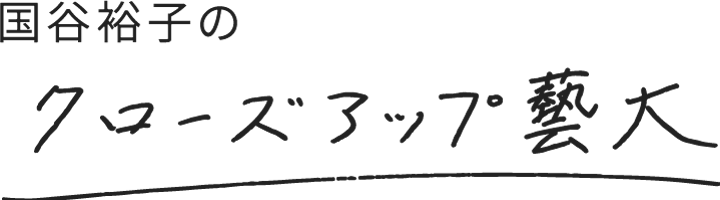- 大学概要
- 学部・研究科・附属機関・センター等
- 展覧会・演奏会情報
- 広報・大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般・企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第五回 江口玲 音楽学部器楽科(ピアノ)教授
| >> 前のページ 作曲の理論も知らず、附属高校受験では楽しく遊んでしまった |
|---|
今ままでのピアニスト江口玲が完全に消えた瞬間。
人生の中で一番大きな出来事だった

国谷
江口先生はその後、ピアニストとして活躍されますが、1887年製造のスタンウェイのピアノ(ローズウッド)、それもホロヴィッツが実際に弾いていたピアノと出会って、非常にショックを受けたそうですね。
江口
ものすごいショックを受けました。そのピアノは、これが同じ“ピアノ”というカテゴリーの楽器なのかと思うくらい全然違いました。実際にホロヴィッツのピアノを調律していたフランツ・モアさんに施してもらい、いきなりそれを渡された時に、自分が思っている楽器の概念とは全然違っていたんです。こういう楽器であれば、こうやればこういう音が出ると思っていたものが、全く通用しない。形も機能も同じはずなのに、全然違う。自分が慣れている音を、とにかく何としても出そうと思って、やればやるほどどうにもならない。いい音どころか弾けない。もう指がそれ以上動かない。 これは自分のやりたいことをこの楽器に押しつけても駄目だ。この楽器から何かをもらうしかないという発想をしました。「この楽器は、ここからどういう音が出るんだろう。こうするとどういう音が出るんだろう」っていうところから始めました。でも、翌日がレコーディングでしたから本当に数時間しかない。
国谷
かなり危険な状況ですね。
江口
もう絶対に無理だと思いました。そんな中、こういう力具合でこういうふうにやれば、この楽器はこういう音が出るんだ、だったらその音を使ってこの曲を組み立てたらどうなるんだろうって。こっちの言うことを聞かせるんじゃなくて。いつもと反対ですよね。 料理に例えれば、ここにある食材で料理を作る。食材がそろってないのに自分の作りたい料理を作ろうとするのではなく、ここにある食材でどういう料理が作れるだろうかという反対のプロセスです。
国谷
通常、コンサートホールごとにピアノが違う訳ですよね。
江口
だいたい似通っているんです。誰が弾いても支障がない状態のピアノになってます。だから、そういうのに慣れていると、個性的なピアノに出会った時にどうにもならない。
国谷
なぜ、そのピアノはそんなに言うことを聞かないんでしょうか?
江口
その当時のピアノの構造上の違いも少しあるんですが、それ以上にホロヴィッツが気に入っていた仕様だったところですよね。彼がいいと思っていたことが、他のピアニストにとっていいかどうか分からない。彼が一番いいと思った状態に整えてもらったんです。本来だったらホロヴィッツしかそういう調整にしない。それをホロヴィッツが気に入っていたピアノだからと無理やりお願いして調律してもらいました。だから、皆さん、「大丈夫? 大丈夫?」って心配してくださっていました。特に調律師であるフランツ・モアさんが心配してくれました。彼が一番よく分かっていたんだと思います。ホロヴィッツじゃないと音を出すことすら難しいと。 それでも、途中からは、自分で「あ、なるほど」って分かり、それこそ「目からウロコ」どころじゃなくて、身体全体から何かが剥がれ落ちて、なんかもう別人ですね。自分の中で別人になりました。その瞬間に今までのピアニスト江口玲は消えたというぐらい別人になりました。
国谷
それくらい楽器の存在は、演奏家にとって大きいものなのですね。

江口
大きいですね。あのピアノに出会わなければ昔のままの江口玲だったと思うんだけど、出会った瞬間にそれまでの江口玲は完全に消えましたね。 その後は、「あの楽器では、それまで考えたこともなかったようなことができる。では、この楽器でこの弾き方は、歌い方はどうだろう?」と指の練習というより、音のイメージの練習をするようになりました。
国谷
ソリストとして自分の中の演奏の幅が広がり、それが今も続いているわけですか?
江口
そうです。元々、基礎練習をあまりやって来なかったせいで、変な演奏スタイルではあったと思うんです。それを一生懸命、近づける努力をしていたんですよ。日本の人がいいと思ってもらえるようなものを目指そうと思っていた。自分の中で、そうやらなきゃいけないって。 それが、その楽器に出会った時に、普通に弾いたらつまんない。というより普通には弾けない。この楽器が一番よく鳴るためには、こういう弾き方をして、こういう歌い方をして、こういう音の作り方をすればいいのかが見えて。本当にあの出会いはピアニストとして人生の中で一番大きな出会いだったかもしれません。
国谷
演奏家はそのピアノが持っているポテンシャルを引き出して、楽器と共に音を作っていくわけですね。
自分は伴奏者とかソリストとかでなく、ただ単にピアニストです
国谷
江口先生はソリストだけでなく伴奏者としても、世界から声がかかると聞いています。
江口
伴奏もいっぱいします。アンサンブルは本当に大好きで。ソロを弾くのとアンサンブルを弾くのと、自分の中ではあまり境目がなくて、どちらも楽しい。だから自分は伴奏者とかソリストとかじゃなくて、ただ単にピアニストなんです。
国谷
ソリストと伴奏は、全然違うのではないかと思い、ジェラルド・ムーアが書いた『お耳ざわりですか―ある伴奏者の回想―』を読みました。1962年に書かれたものですが、伴奏者は技術者や職人的に捉えられていて、芸術家として見てもらえていない。地位が低かったと書かれています。
江口
そういう時代が長かったですね。かつては、メロディーを歌う人が舞台に立ち、伴奏者は見えない場所で弾くこともあった。ここ数十年でその地位も改善されて、「ピアノも合わせて、ひとつの音楽が成立しないと駄目だよね」とピアニストを選ぶようになり、アンサンブルを生み出す芸術家として扱われるようになってきました。 そもそも「伴奏」という言葉自体が良くないと疑問を呈するピアニストもいます。どちらかが「主」でどちらかが「従」ではないと。
国谷
今では対等の立場で、芸術家として正当に扱われるようになったと。
江口
ただ、演奏者同士での関係性は改善されつつあっても、演奏会の企画者側の捉え方は、やはり従前のままだったりします。数年前に、ある国で、ヴァイオリンとピアノの演奏会を行ったのですが、企画者側はヴァイオリンのみを主役にしたポスターを作っていました。それを取材に来た記者から、何故このようなポスターなのかと指摘されました。その時は、「うーん。自分たちには答えられない。プレゼンターとかプロモーターが考えたことなので」と。 結局、演奏者同士で対等に演奏していても、こういうところの意識が変わらない。少しずつ改革したいと思いますね。まだ壁は高いところにあります。

ピアノだけで世界を作り上げるのではなく、
ある時は、相手を一番美しく輝かせる背景に徹することもできる
国谷
先生が伴奏する時に、一番大切にされていることは何でしょうか。
江口
自分としては、相手がメロディーを弾いている時は、相手が一番美しく輝いてくれれば嬉しいと感じます。この人のメロディーが一番きれいに聴ける方法で弾いてあげたい。背景をしっかり作ってあげたい。そんな時に、「私が背景です」といって前面に出たらおかしいですよね。その曲に合わせて、背景にもなるし、黒子にも徹します。もちろん、対等の立場で、音を譲り合ったり競い合ったりしながらアンサンブルもできないといけないです。そのどちらも大切にしています。
国谷
アンサンブルの時には、お互いがバランスを取り合う訳ですね。よく「息の合った演奏だね」という言葉が聞かれますが、「息が合う」というのは当事者からするとどういうことなんでしょうか。
江口
そうですね。学生の頃は、時間があるので何度も練習して、分かり合うことができましたが、今は、皆忙しくて、数回しか合わせることができない。そんな中で、最初はバラバラでも、2~3回くらい通すと、互いにやりたいことが分かってきて、大まかな地図ができる。その地図さえあれば、寄り道ができてしまう。向こうが寄り道しても、「ああ、寄り道しているね。じゃ、一緒に行きましょう」となる。本番でも、いつもと違うことをやって、それも面白いよねと寄り道する。多分その余裕を「息が合う」というのでしょうね。
国谷
ソロの場合と違ってアンサンブルは相手に合わせるので、相当神経を使いますよね。「聴く」と「弾く」を両方やらなくてはいけない。
江口
相手の音も聴かなくてはいけないし、自分の音も聴かなくてはいけない。 それも練習すればできるようになります。時々、ヴァイオリンとピアノのレッスンの時に、ヴァイオリンの学生に「ピアノが絶対に付いて来られないように弾いてみて」と、一方ピアノの学生に「ヴァイオリンに、何が何でも付いていって」と言ってみます。全身の神経を張り巡らせて、ピアノの学生がヴァイオリンに付いていくことができるようにさせます。そして、自分のピアノの音も聴けるように訓練していきます。
国谷
江口先生が伴奏することで引き立てた演奏家がたくさんいると伺います。ギル・シャハムさん、アン・アキコ・マイヤーズさん、竹澤恭子さんというヴァイオリニストが世界に羽ばたいていった。
江口
いやいや、そんなことないです。自分としては彼らが気持ちよく弾けたと思ってくれたらそれでいいんです。自分のピアニストとしての資質を、どれくらい彼らと競い合って、一緒に高めていけるか。音楽的にも芸術的にも高めていきたいですし、自分の能力を維持し、そのための努力は続けていきたいと感じます。
国谷
これからもどっちもやっていかれるんですか?
江口
そうですね。自分ではどっちも違和感がないので。伴奏者としても、もっとやって行きたいですよね。相手から得たものはものすごくたくさんあるので、彼らの演奏をどうやってピアノで鳴らせるかなって。例えばこの曲で10枚のカードを使おうと思ったら、10枚持っている中の10枚を使っちゃうより、100枚持っている中から10枚選んだほうがずっといいじゃないですか。そういう色々なカードは伴奏相手からもらったって思いますね。
世界にただ1人しかいない自分という存在をどう表現するか
国谷
ここで学生たちに一番教えたいことって何ですか? 一番大事なこと。
江口
一番大事なのは、作曲家がどういうことを考えてこの楽曲を作ったのかっていうことを、ちゃんと楽譜から感じ取ってあげること。それを世界にただ1人しかいない自分という存在がどうやって表現するか、ですね。 それが、演奏を聴いた時に、上手だったけれども誰が弾いてるか分からない演奏だったらつまんない。だからコンクールでも、絶対に後悔しないように、自分がやりたいように弾いておいでって送り出します。完璧にミスもなく、ファイナリストになったけれども忘れ去られる演奏より、予選で落ちても強烈な印象を残して落ちたほうがずっといいよって。 何とかすり抜けてファイナリストまで残っても、演奏家・芸術家としての価値なんてそこにあるかどうかわかんない。世界に1人しかいないんだから、作曲家が聴いて喜ぶような、世界に1つしかない音楽を表現しなきゃって。

【対談後記】
ご自分のキャリアは寄り道がとても多かったと語る江口先生。
子供のころはピアノで遊んでいただけ、藝大の附属高校を受験した時も「自分は楽しく遊んじゃった」と振り返り、伴奏が好きになっていったのは初めて見る楽器と一緒に弾くことが「楽しかった」から。「一人で弾くのも楽しいけど一緒に弾くのも楽しい。自分は伴奏者とかソリストとかじゃなくて単にピアニスト。ただ脳天気に楽しい! それだけでいいんです」。対談の中で「楽しい」という言葉を連発、その表情も本当に明るく楽しそうでした。
江口先生の眼差しが真剣になったのはコンクールを受ける学生たちへアドバイスを話された時でした。「ミスなく完璧な演奏をするより強烈な印象を残す演奏がずっといい」感性を磨くことがいかに大切かを語る表情が印象的でした。
【プロフィール】
江口 玲
音楽学部器楽科(ピアノ)教授
1963年東京生まれ。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て東京藝術大学音楽学部作曲科を卒業、その後本学にて助手を務めた後、ジュリアード音楽院ピアノ科大学院修士課程、及びプロフェッショナルスタディーを修了。
ピアノをハーバート・ステッシン、外山準、金沢明子、伴奏法をサミュエル・サンダース、作曲を佐藤眞、北村昭、物部一郎の各氏に師事。
ニューヨーク市立大学ブルックリン校、洗足学園音楽大学大学院、神戸女学院大学等でも教鞭を執り、2011年より本学器楽科准教授、2019年より現職。
アメリカ、アジア、ヨーロッパ諸国等、演奏で訪れた国は25カ国以上。ラジオ、テレビへの出演も多く、40枚以上のCDをリリース。現在もニューヨークと日本を行き来して演奏活動を行っている。
撮影:永井文仁
- 1
- 2