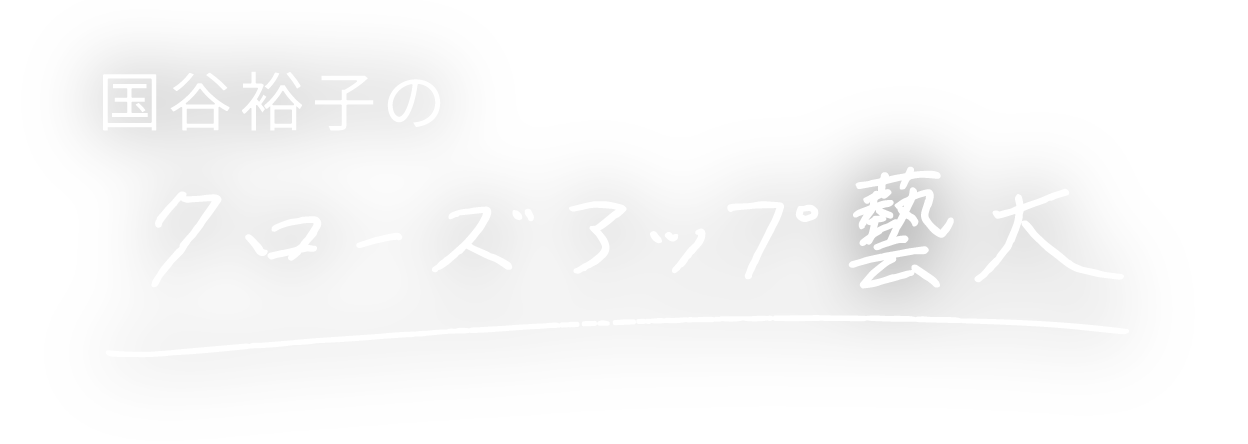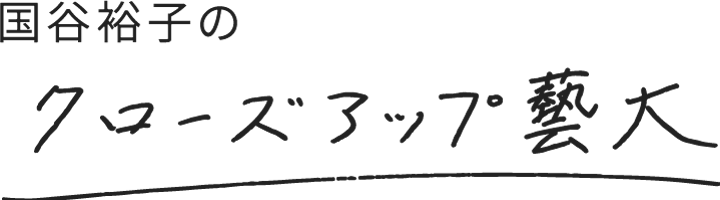- 大学概要
- 学部・研究科・附属機関・センター等
- 展覧会・演奏会情報
- 広報・大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般・企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第六回 黒沢 清 大学院映像研究科映画専攻教授
予期しないような偶然は現実に起こりうる。それが映画の醍醐味
国谷
先生は、「誰も見たことがないことが画面で起きていて、それが起こりうると皆が信じて観てくれるというのが映画で。それが実現できた時に途方もない感動がある」と書いてらっしゃいます。
黒沢
例えばですが、あるシーンを撮っていて、俳優が何度かリハーサルして、さあ本番だとなり、俳優があるセリフを言った後に、ばぁ~と風が吹き、後ろの木々がざわざわと揺れる。あるいは、曇っていたのに、ある瞬間ぱぁっと日が差してくる。予期はしていなかったけれど、そういうことがいつか起こると信じていると、ある時やはり起こるんですね。映画を撮っていて。意図的にそれを起こすこともできますが、意図せずそれを呼び込むっていうのが、多分アニメーションではできないんですよ。実写だからできる。この瞬間、風が吹くとは誰も思っていなかったっていうときに風が吹く。これは何にもかえがたい感激する瞬間ですね。おそらくこの感覚って、小説で書くことも難しくて、演劇でやることも難しい。ある現実世界にカメラを向けて起こった出来事のすごさだと思うんです。
国谷
言葉にならないことを映し出す芸術、でしょうか。誰も観たことがないことをスクリーンに映し出したい、それを観ている人が本当に起こったことの如く感じとる。
黒沢
それが映画を作る最大の醍醐味というか魅力ですね。あの手この手でハリウッドはお金をかけて再現しようとするし、お金のない人は風が起きることを待ち構える。そういう根源的なすごさを撮りたいという欲望が映画を作りたいという根源にあると思いますね。

『サウンド・オブ・ミュージック』は何度観ても大傑作
国谷
黒沢先生が追いつきたい映画とは、どんな作品ですか。
黒沢
例えば、小津安二郎監督の『風の中の牝雞』です。『晩春』の一本前で、戦後すぐに撮った映画で、僕からすると小津の最高傑作です。まあ悲惨な現実を映していて、戦後すぐ、まだ焼け跡が残っている東京で撮っています。あらすじは、戦争に行った夫が帰って来ず、妻が一回だけ身売りをしてしまって、その後、夫が帰ってくるというものですが、残念ながらそんなにヒットしなかった。小津はその反省から、その次の年の『晩春』は、戦争なんかなかったかのような、絢爛というか一種独特な世界を撮っていますが、実はその一本前はけっこう生々しかった。どうやったって手の届かない大傑作ですね。
外国映画ですと、小津とは全然違いますが、『サウンド・オブ・ミュージック』。何度観ても大傑作です。
国谷
私も『サウンド・オブ・ミュージック』は繰り返し観た大好きな映画です。
黒沢
何がすごいって、あれはミュージカルですけど、“歌っている人”の映画なんです。同じ監督の『ウェスト・サイド・ストーリー』は完全なミュージカルで、歌が始まるとミュージカルシーンに切り替わり踊り出す。一方で『サウンド・オブ・ミュージック』は歌が始まるんですけれど、ミュージカルシーンにはならない。歌っている人を撮っている。それが不自然じゃなく成り立っている。それがすごいと思うんですよ。
国谷
黒沢先生の最新作『旅のおわり世界のはじまり』でも前田敦子さん演じる葉子がラストシーンで歌います。
黒沢
はい。あれもミュージカルシーンではなくて、“歌う人”を撮りました。
国谷
黒沢先生は、21世紀はもっといいことが起きると思っていたけれど、こんな時代になるはずじゃなかったとおっしゃっていたことがあります。私も共感します。どんどん悪い方にというか、ギスギスして社会の中の寛容さも無くなってきて、何か変に歯車が回り出している。皆が自分のことを守るのに精一杯という感じもします。
黒沢
そうですね。他者への思いやりというものがこうまで無くなって行くの?っていう、驚きます。
国谷
電車の中で遭遇する風景、ちょっと肩が当たっただけで怒鳴るとか、一昨日もタクシーに乗っていたら、バイクに乗った30代ぐらいの人がニコニコしながら文句を言いに来て怖い思いをしました。
黒沢
本当に、他者というものをどうしてこんなに警戒し出し抜こうとし、自分と自分の周りのごく一部の人だけで固まろうとするのか。いつこうなったんだろう、何で垣根を作ってしまったのということは日々感じています。本当にそれは、どうしたものかと思いつつ、そんな事態に対して何もできなかった自分を深く反省するばかりです。
実はこの間作った『旅のおわり世界のはじまり』という映画も、そういう思いも働いて作った映画です。他者との間にものすごい境界線を作ってしまった主人公が、ほんの少しその境界線を緩やかにできないかというテーマ。
国谷
言葉にならない気持ちを映画にしていただきたいと期待をしています。
昔あった撮影所のように、若い人につなぎ綿々と残していく
 撮影用セットが組まれた馬車道校舎一階のロビー
撮影用セットが組まれた馬車道校舎一階のロビー
国谷
2005年に藝大に映像研究科が設置され14年経ちましたが、撮影所システム、映画を制作するのに必要な領域が全部ここに揃っていてプラットフォームとなっていくという当初目指したものはできてきましたか?
黒沢
ある程度できていると信じています。それは簡単なことではないですし、完璧な撮影所の再現は難しい。撮影所に専属でいた俳優たちがここにはいないので、そこに大きな違いがありますが、今の日本映画界の中に、撮影所に必要な人材を、わずかずつですが生み出せていると信じています。
国谷
いまでは様々な大学に映画学科とか映像学科とかありますが、藝大が特にこだわっているところはありますか?
黒沢
藝大の一つの特色だろうと思うのは、監督領域は一学年4人しかいない。ですから必ず一人一本撮ります。入学しさえすれば絶対に撮れる。それはラッキーなことでもありますが、他の3本と比較され厳しい場に立たされることでもあるんです。それでも撮らないわけにいかない。撮影所ってそういうことだと思うんですね。あなたが撮らないとあなたの問題だけじゃないんだ。カメラマンも録音技師も皆が困るんだと。
国谷
監督が撮らないと、カメラマンも録音技師も仕事がない。
黒沢
そう。学生であっても、かなり追い込まれます。それが他の大学と違うところです。
国谷
先生方が入試で学生を選ぶのも、大変ではないでしょうか。
黒沢
これまでに撮った作品を提出してもらって面接もあります。短い脚本を与えて撮れとかいう課題もあります。だから何パターンかの試験を経て最終的に残った若者の質はかなり高い。その人の作った作品を観て、駄目なものは最初の1分でまあ分かりますね。他の試験官も同じ感覚です。ある程度ふるい落とした後、最終的に4人に選ぶのは難しいですけどね。
国谷
そんなにすぐに分かるものですか。
黒沢
我々は目利きなんですよ(笑)。最初からどこに行ってもうまくやるであろう人を、いち早く見つける。だから、本当は教えることは何もないんですけどね(笑)。
国谷
そんなことはないでしょうけれど(笑)。修了生の濱口竜介さんや月川翔さんも活躍されています。
黒沢
そうですね。我々が教えたことになっていますけど、本当は選んだだけです(笑)。
国谷
優れた監督さんになる学生の素質というものはあるのでしょうか?
黒沢
まず、こういう映画が面白いという感覚を何となく分かり、目指そうとしていることがうかがえること。それと、映画は皆で作るものですから、人が何をしたいか、何を望んでいるか、それを理解して自分に取り込んでいける能力でしょうか。能力というかキャラクターですね。
国谷
日本の映画界に人材を送り込めているという実感は持てますね。
黒沢
それはそうですね。彼らのうち何人かは藝大に来なければ全然違った人生を送っていたかもしれない若者を無理やり、まあ本人が望んだからなんですけど、僕がかつて蓮實さんからされたように、もう映画から逃れられない人生にしてしまったという自負と若干の罪悪感(笑)。

馬車道校舎入口
映画は個性を発揮する場所ではない。
しかし、思い通りにいかないところに個性が出る
国谷
学生にはそれぞれの個性を活かして映画を制作するよう指導するのでしょうか。
黒沢
自分の個性を発見してほしいですが、映画は個性を発揮する場所ではないんです。難しいところですが。映画は多くの人の力が集結してできるものなので、自分の個性を出そうと思うなと。でも、映画史上の傑作を目指して、狙っても狙っても思い通りにいかない、思い通りにいかないところに個性がでてきます。
国谷
う~ん。それは、難しいですね(笑)。
黒沢
個性というのは難しいもので、自分で3、4本映画を撮って、思っているようにはいかず、他人から「あなた、またこんなことやっていたよ」と指摘されるようなものですね。自分が目指しているものでは全くないもの、ある時、人に言われて気付くもの。それが個性でしょうか。背負っている運命のような、逃れたくても逃れられないようなもの。「もう個性だと思って諦めよう」となる。
国谷
無意識にも繰り返しているもの。それが個性ということでしょうか。
黒沢
そうしようと思ってないのにやってしまう。後から分かってくるのですが。
絶望しないでほしい。
どんな状況でも「絶対にできることがある」と信じてほしい
国谷
学生にこれだけは教えたいという事はありますか?
黒沢
ものすごい、あっと驚くような瞬間を作り出して、多くの人に感動してもらうことが、映画の最大の使命ということを忘れないでほしい。それと、映画は共同作業なので、いろんな人の意見が入ってきます。ああやりたいこうやりたい、ああしろこうしろ、これはできないやらせない、これだけしか予算がないとかですね、そうした中で絶望しないでほしい。こんなに何もできないのかと絶望しないでほしい。そんな中でも「絶対にできることがある」と信じてほしい。これは言い続けています。

【対談後記】
この時代どうやったら監督になれるのですか?と尋ねると、黒沢先生は「まず自分で撮ることでしょうか。今はデジタルで撮ることができます。傑作を撮って映画祭に出す。それがヒットすることもありますから。映画を撮ることは仲間もお金も最低限必要ですけど、友達に声をかけて一本映画を撮ってチャンスをうかがうことが近道だと思いますね」と答えてくれました。
先生が好きな映画として『サウンド・オブ・ミュージック』と答えられて正直驚きました。えっ大監督が私と一緒!? 私事ですが「I Have Confidence」と歌うジュリー・アンドリュースにこれまでどれだけ励まされてきたかわかりません。何にもかえがたい観る人が感動する瞬間を追い求めて作り続ける。黒沢先生の映画へのパッションが静かにほとばしっている授業を想像しました。
【プロフィール】
黒沢 清
大学院映像研究科 映画専攻(監督領域)教授
1955年、兵庫県神戸市生まれ。1980年、立教大学社会学部産業関係学科卒業。大学在学中より8ミリ映画を撮り始め、『しがらみ学園』で1980年度ぴあフィルム・フェスティバル入賞。長谷川和彦、相米慎二らの助監督を経てディレクターズ・カンパニーに参加し、1983年『神田川淫乱戦争』で商業映画デビュー。以降、『CURE』(1997)、『回路』(2001)、『トウキョウソナタ』(2008)、『岸辺の旅』(2015)等監督作多数。カンヌ国際映画祭をはじめ、国内外で高い評価を得る。2018年に『散歩する侵略者』で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。
1997年より 映画美学校講師、2005年より東京藝術大学大学院映像研究科教授。
撮影:新津保建秀
- 1
- 2