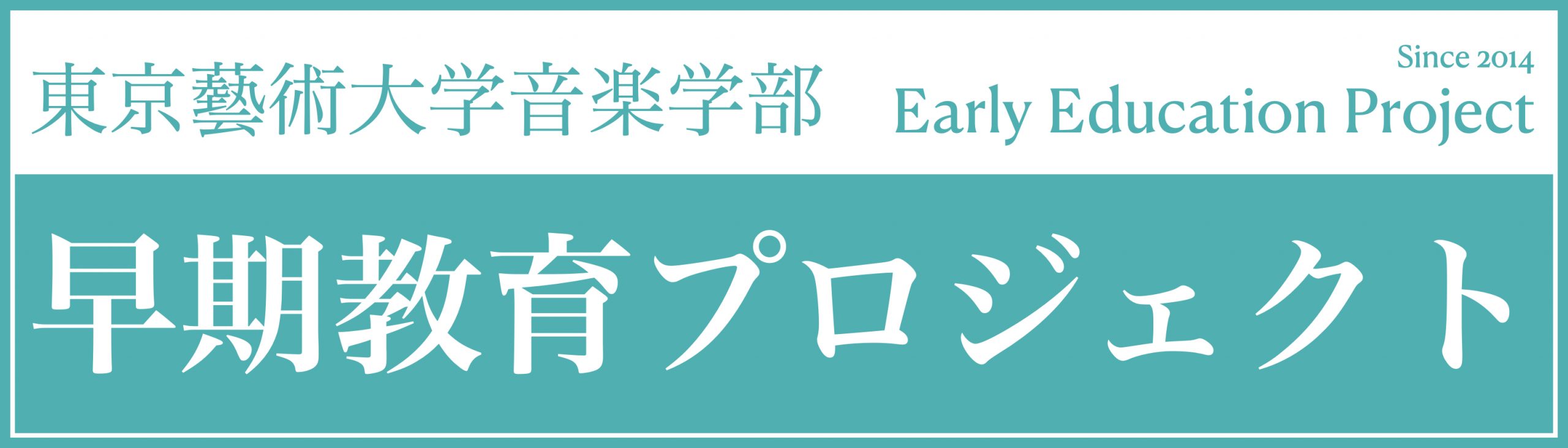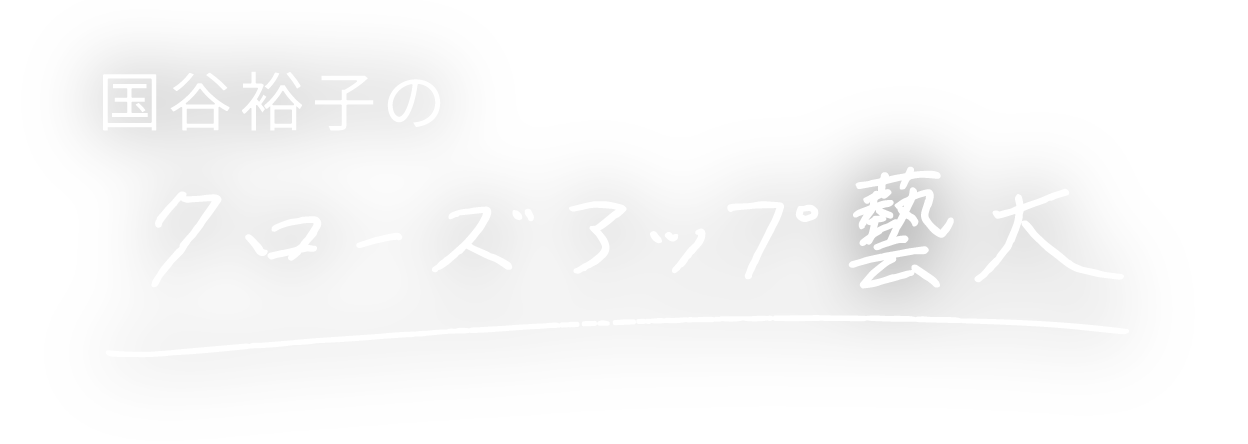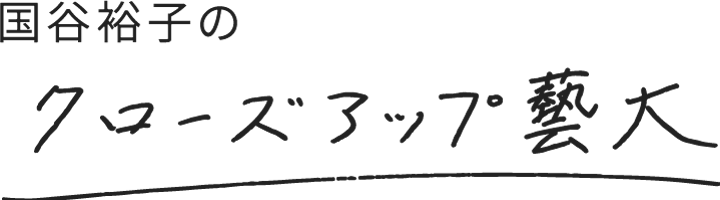第二十二回 藤原道山 音楽学部邦楽科(尺八)准教授/副学長(伝統継承・150周年担当)
>> 前のページ
人生を音に重ねていくことができる楽器
国谷
藤原先生は中学生の頃から現代音楽にとても関心があり、お好きだったそうですね。尺八と現代音楽はどのようにしてつながったのでしょうか?
藤原
師匠の山本邦山先生の活動のひとつで、現代音楽も制作されていらっしゃいました。僕も最初は全然よくわからなかったのですけど、聞いているうちに段々とわかってきたというか。その後ある時に、日本のシンセサイザーの第一人者である冨田勲先生と一緒にアルバムを作らせていただきました。
冨田先生は日本で初めてモーグ・シンセサイザーというものを輸入した方です。いろいろな音色を作る中で、今まで聞いたことのない音色を作った際、それは他人からすると雑音にしか聞こえないと言われたそうです。というのは、最先端のものって認識できないものなのです。認識できたらもはや最先端ではない。人は今あるもののちょっと先にあるもの、延長線上にあるものに対して新しいと感じるんですよね。よく「10年早かった」なんて言われますが、10年早くやってないと、10年後にはそれが先端にならない。まず現時点では理解されないものを作って、10年ぐらい経ってやっと先端に降りていくものです。現代音楽をやっていると、そういう風に感じてきていて、そうした要素が今やっとポップスにも採り入れられるようになってきたと思います。
国谷
幼い頃からいろいろな音楽に触れながら、違う道に行った可能性もあったのではと思いますが、ずっと尺八の道を進んでこられたのは、それほど尺八に魅せられていたということですね。その尺八の最大の魅力は何でしょう?
藤原
音色の多彩さというか、声だと思っています。そういういろんなことを表現できる楽器だと思いますし、精神的な部分も出てしまう、ある意味怖い楽器でもある。嘘がつけないというか、一瞬の隙が反映されてしまうというか。
国谷
そこは演奏家にしかわからないと思うので、もう少し詳しく教えていただけますか?

藤原
そうですね、内面的なものや思想的なものも含めて自分の人生を音に重ねていくことができる楽器だと。その分、自分の積み重ねたものがダイレクトに出てしまうので、まだまだ僕は浅いなと思います。どうしたら深みのある音が出せるのだろうとか、あの先生のあの音、あの表現はどうしたら出せるのだろうかと。やはり人生を経たからこそでもあるので、憧れる部分と、まだ自分が至っていない部分があるからこそ、僕はそこに向かうのでしょうね。
国谷
尺八は精神的なものまで全て出てしまう楽器だと。しかし、尺八は本当にシンプルな構造で、表に穴が4つ、後ろに1つ。マウスピースのない、エアリードと呼ばれる楽器です。シンプルだから精神状態が出やすいということなのでしょうか。
藤原
そういうこともあると思います。すべて自分でコントロールしないといけない、楽器頼りにできないところがありますから。
相手の演奏を「見はからう」
国谷
構造はシンプルですが、穴の押さえ方、息の吹込み方、そして首の動かし方で音色が変わる。
藤原
はい、そのすべてが関わってきます。先ほど申し上げた「言葉」というところにつながるのですけど、ちょっとした発音の違い、方言みたいなものを、音楽でも表現する。
ウィーンフィルのメンバーと一緒に最初に「アンネン・ポルカ」という曲を演奏したときは、やっぱり独特なノリがあるなと感じました。我々邦楽家は「見はからう」ということをいたします。空気感を纏うというのかな。それを重要なこととして捉えています。「こう来たらこう行くよね」っていうような、ウィーンフィルのメンバーと何か共通の音の会話をしていたような気がします。ですから「僕たちの音を理解してくれてありがとう」って言っていただいたときは、非常に嬉しかったですね。
国谷
ウィーンの弦楽四重奏団と共演されたCDや、チェロとピアノとのトリオを聴いていて感じたのは、西洋の楽器と一緒に演奏されるときは、「ムラ息」とか「風音」のような尺八ならではの音をあまり強調しすぎると、なにか西洋楽器のなかで孤立してしまいそうですし、逆にそうした独特の音を抑えすぎると尺八が尺八ではないように、まるでフルートのようにも聞こえてしまいます。さきほど共通の音による会話と話されましたが、どのように楽器としての自己主張のバランスを取っているのですか?
藤原
それは今でも悩みますね。若い頃は極端に強調したり、それこそ分かりやすさも追求していましたし、みんなが知っているような曲を演奏することも散々やってきました。そのなかで本当にこの曲を尺八で演奏する意味があるのか?という疑問も出てくる。でもやってみないとかわからないので、まずはやってみる。1回、制限を取り払った時に何が生まれるのだろうと考えることが重要です。ただ守っていくだけではなく、既存の枠組みを離れたら、次のステップが見えてきたりするので。行き過ぎそうになったら、ちょっと古典の方にいきますし。さきほど申し上げた真ん中の道です。伝統的なことと先端的なことと、両方をうまく見えるような位置にいないと、その世界は壊れていくのではないかと思っていますので。
足の裏から呼吸するようなイメージ
国谷
武満徹さんは『ノヴェンバー・ステップス』や『エクリプス(蝕)』などの、尺八を採り入れた音楽を作曲されましたけれど、尺八について面白いことをおっしゃっています。「洋楽の音は水平に歩行する。だが、尺八の音は垂直に樹のように起る。」私はよく理解できなかったのですが、藤原先生はこの言葉をどう解釈されますか。
藤原
音楽の作り方について、でしょうか。洋楽の場合は、例えばオーケストラはメロディがあってリズムがあってハーモニーがある、積み重ねるような音楽。それが横に動いていくような感じです。邦楽はそうではなく、特に尺八の音楽というのは、地中の根から水を吸い上げて上に上がっていくようなイメージなのかなと。そこにはリズムがあるわけではなく、自分の呼吸とか、間合いとか、それで音楽を作っている。外から統制されたものではなく、自分の中で統制されたもので音楽をやっているということを言っているのかな、と思います。
でも、想像力ということで言うと、このように分かりやすく解説をするのも、先ほどお話したようにあまり良くない気がするのですけども…。
国谷
でも、地中の根から水を吸い上げるというのは、なかなかできない解説です。
藤原
尺八の呼吸について、僕はよく「足の裏から呼吸するようなイメージ」と言っています。そうすると意識が下に落ちて重心が下がる。頭で考えて何かやっていると、どうしても意識が身体の上の方に行って、呼吸も浅くなってきますよね。
国谷
とても身体的ですね。現代では、頭ですべて考えてコントロールしている感じがありますが、だいぶ違う感覚ですね。
藤原
案外、人間って、そういうものだと思っています。例えばよく「お腹で息をするように」って言いますけれど、お腹に息が入っているわけではなく、肺に入っている。でも肺のあたりを意識すると、もっと上に意識が行くんですよね。それを下げることによって、ちょうどいい力の使い方ができる。そういうイメージを持つということです。もしかしてもっと科学的に分析されていったら、「〇〇筋を意識して」とか言うようになるかもしれないけれど。音楽っていうのは、自分の感情で動かしている部分もある。そこを自分とどう折り合いを付けていくかですよね。

伝統的なものの格好良さも見せたい
国谷
藤原先生は伝統を大事にしながら、一方で現代的なことにもチャレンジしています。オリジナリティを大切にしつつ、普遍的なものも追求する。オリジナリティと普遍性のはざまで揺れつつ、しかし伝統は守っていかなければいけない。そういう伝統が持つ宿命と向き合っていらっしゃるのではないでしょうか。
藤原
そうですね。分かりやすさとともに、人間としてつないできたもの、伝統の持つ力を理解していただいた上で、次の世代に伝えていかなければいけないのですが、人が何に惹かれるのか、何に感動するのか見極めることは、なかなか難しい。
僕も若い頃は、分かりやすい表現とか高いテンションとか、そういうものに対する憧れもありました。でもある程度年を重ねてくると、その奥にあるものが大事なのだと、しみじみと見えてくる瞬間があって、最近やっとわかってきた気がします。
若い人たちに対しては、分かりやすいものとか、時代性を纏わせることも必要なのかもしれません。でも、伝統的なものの格好良さもやっぱり見せたいですね。この前も野村萬斎さんの「能 狂言『鬼滅の刃』」に私も音楽で参加させていただきました。そこから能の世界、能の表現というものを知ってもらおうというチャレンジですよね。2022年にも「ONE PIECE ×人形浄瑠璃 清和文楽「超馴鹿船出冬桜」」の総合演出と音楽監修を担当させていただきました。
伝統的な技は使いつつも、その表現として今につながるものを見せることは必要だと思います。伝統的なものも作られた当時は現代アートだった、最新だったからこそだということを忘れてはいけないと思います。
邦楽の普及活動を次につなげる
国谷
今、邦楽が置かれている状況に対して、変革が必要だと考えていらっしゃいますか?
藤原
然るべき教育をしなきゃいけないと思っています。あまりにも邦楽に触れる機会が少ないのと、触れたあとにそれが次のステップにつながるような環境が整っていない。我々は邦楽の普及活動というのをやっていますが、点で終わってしまうことが多い。公演をやって、それを観た人が邦楽をやりたいと思っても、その地域に邦楽を教えられる人がいなかったら習えません。楽器をどこで買ったらいいかもわからない。だから普及活動を次につなげるための活動も少しずつ始めているところです。それもあって大学で教えていて、そのことで指導する人たちも増えていってほしいですね。
国谷
もっと多くの人たちに尺八を広めたいという、強い想いですね。
藤原
そうですね。それだけでずっとやってきているような気がします。

国谷
今後の目標として、師匠の山本邦山先生のように名人としての道を究めたいという気持ちはやはりおありですか?
藤原
そうですね…そういう世界を伝えてつなげていくことも大事ですし、演奏家としても、もっと掘り下げていきたい。大学で教えながら指導法についても考えていきたい。あとせっかく他大学と連携もしているので、どうやって我々が音楽をしているのかを科学的に調べてみたいと思っています。いくらでも実験台になりますよ(笑)。
国谷
本当に多彩な活動をなさっていますが、さらに今年度から、藝大の伝統継承・150周年担当副学長に任命されました。
藤原
それが一番、自分の力不足を実感しています。非常に重いものを背負っていると思っております。藝大がどんな学校か知ってもらい、足を運んでもらうために、取り組んでいかなければならないと思います。
国谷
古典から現代アートまですべてを備えている唯一の国立の芸術大学が150周年を迎えたときに、どうあるべきか。持続可能な教育を行い、それをさらに高め、そして社会から必要な大学であると認識してもらえるように在り続けなければならないですよね。
藤原
はい。150年のために何をやるか。大学だからこそ伝える、表現することを見せていく。もう育て始めなければいけない時期に来ています。最終的に150周年の時に何をするか、その到達点に向け、今何をするかですね。
国谷
よろしくお願いします。

【対談後記】
尺八の最大の魅力は、音色の多彩さと語った藤原先生。声や言葉、発音の違いや方言という表現を使いながら尺八がいかに豊かな表現ができる演奏楽器であるかを、実演も交えて伝えていただき、私が持っていた尺八という楽器のイメージは大きく変わりました。
藝大で得たものはと尋ねると、先生はきっぱりと「ご縁、人ですね」と答え、「藝大は人と人の出会う場所。超一流の人たちと出会えたことに感謝しています。その人たちがいろんな場所で活躍されていて、またつながっていくことがとても大きいことだと思います」と話されました。伝統的な分野以外でも多彩な活動を拡げられている背景には、こうした藝大での出会いから生まれた“ご縁“があるのです。このつながりが、藝大150年へ向けてもきっと大きな力になっていくのだろうなと思いながら、インタビューを終えました。
【プロフィール】
藤原 道山
音楽学部准教授/副学長(伝統継承・150周年担当)
東京藝術大学卒業、大学院音楽研究科(修士課程)修了。皇居内桃華楽堂において御前演奏(宮内庁主催)。安宅賞、芸術選奨文部科学大臣賞、松尾芸能賞新人賞、服部真二音楽賞ほか受賞。伝統音楽の活動と共に、尺八の可能性を求め、ソロ活動の他、音楽制作や監修、洋楽器とのユニット、尺八アンサンブル「風雅竹韻」の監修、メディア出演、音楽雑誌連載など多角的な活動を展開。小学及び中学音楽教科書の執筆及び出演、後進の育成など普及・教育活動にも力を注ぐ。2025年11月30日に東京藝術大学 奏楽堂にてオーケストラとのコンサートを企画。 現在、公益財団法人都山流尺八楽会所属・竹琳軒大師範。都山流道山会主宰。公益社団法人 日本三曲協会会員。
撮影:新津保建秀
- 1
- 2