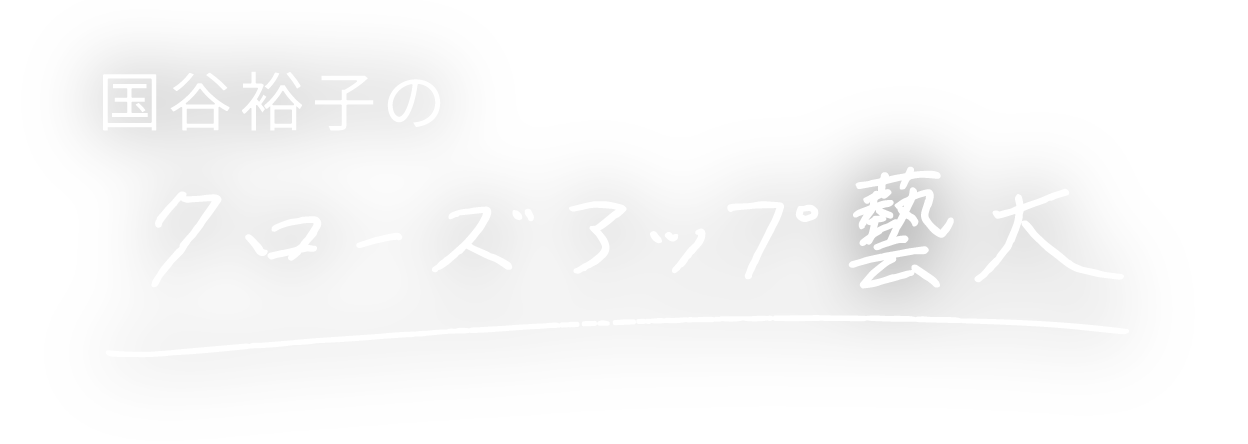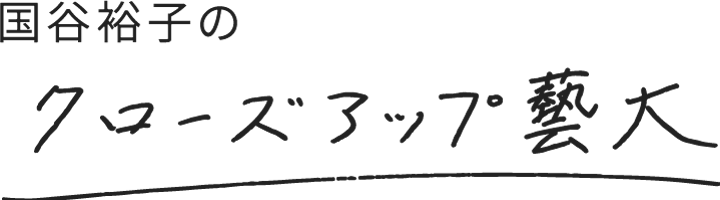- 大学概要
- 学部・研究科・附属機関・センター等
- 展覧会・演奏会情報
- 広報・大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般・企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第二十二回 藤原道山 音楽学部邦楽科(尺八)准教授/副学長(伝統継承・150周年担当)
クローズアップ藝大では、国谷裕子理事による教授たちへのインタビューを通じ、藝大をより深く掘り下げていきます。東京藝大の唯一無二を知り、読者とともに様々にそれぞれに思いを巡らすジャーナリズム。不定期でお届けしています。
>> 過去の「クローズアップ藝大」 |
|---|
第二十二回は、音楽学部邦楽科准教授の藤原道山先生。尺八の演奏家としての活動のほか、異分野のアーティストとのコラボレーションや、全国各地での尺八の教育・普及活動など、多彩な活躍をされています。2025年8月、能ホールにてお話を伺いました。
【はじめに】
尺八というと時代劇に出ていた虚無僧が息を力強く吹いて出す尺八の音色を思い浮かべる人が少なくないと思います。今回、藤原道山先生にそれは尺八の特殊奏法である「ムラ息」あるいは「風音」とも言われる、敢えて息の音を含む独自の音色だと教えていただきました。
伝統的和楽器とのイメージが強い尺八ですが、藤原先生は積極的に活躍の分野を広げ、より幅広い人々に尺八の魅力を届けています。
藤原先生がインタビューの場所と指定されたのが音楽学部の建物の2階にある能舞台。先生は羽織袴の正装。私は靴下を脱いで、あらかじめ持参するように指示されていた白足袋をはき、磨き上げられた能舞台に上がりました。舞台の上には能や狂言の小道具として使われる黒漆塗りに蒔絵がほどこされた円筒形の桶、蔓桶(かずらおけ)が二つ置かれ、丸くつるつるしたこのお道具にこわごわと腰を下ろしました。藤原先生は「足袋は必ず履かなければなりません。足の脂がついてはいけないと言われています。神聖な場所であるということもあって道具も決まったモノだけしか置くことができません」と強調されました。邦楽科がある唯一の芸術大学ならではの学びの場で、藤原先生が熱を込めて語ったのは伝えることへの想いでした。
藝祭で感じた「伝えようとするパワー」
国谷今回の対談の場所として、藤原先生からこちらの能舞台をご提案いただきました。この場所は、日本の国立大学法人の中で唯一の邦楽科がある藝大としては、象徴的な場所でもあると思います。藤原先生にとってここはどういう場所ですか?
藤原学生時代は副科で能の授業をとっていたのでここで稽古をしましたし、尺八の学内試験が行われたりしていました。いろいろな意味で思い出深い場所です。
国谷
藤原先生は10歳で尺八を始めて、山本邦山先生(初代)に師事されてきましたが、あえて藝大にきて勉強をしようと思ったのはなぜですか?
藤原
中学1年生のときに藝祭に来たことがきっかけでした。藝大生の知り合いに誘われて来てみたら、ビッグバンドからガムラン、オーケストラも邦楽もある。「こんな世界があるのか! なんてすごいんだ!」って。美術学部のほうに行けば展示をやっていたり、お御輿があったり。ある意味カルチャーショックでしたね。
国谷
藤原先生のご家族もジャズが好きだったり、お祖母様がお箏をなさっていたり、音楽好きなご一家の中で育ちましたが、藝大は特別な刺激でしたか?
藤原
そうですね。学生たちが一生懸命表現をしている姿に、何かを伝えようとする想いというか、パワーを感じたのでしょうね。それで、僕もここで学びたいと思いました。
国谷
「伝えようとするパワー」、いい言葉です。
名人と言われる人に師事して技を磨いていくのが邦楽の在り方ではないかと思っていたのですが、先生への師事一筋でいくということと、大学で学ぶことのはざまで葛藤はなかったのでしょうか?
藤原
当時は山本邦山先生も藝大で教えられていましたし、葛藤はありませんでした。さきほどお話した藝祭で尺八とオーケストラの演奏会があって、それを見て「この学校に来れば、こういうことが出来る」、オーケストラと演奏するという目標ができていましたし。

藝大で得たご縁を次世代につなげる
国谷
それで、入学されてからは他科の学生ともいろいろなコラボレーションをなさっていたわけですね。そこから学部、大学院、助手時代も含めて8年以上藝大に在籍されていましたが、振り返ると学生生活はどのようなものでしたか?
藤原
学部はあっという間でしたね。高校までは受け身の勉強だったのが、能動的なものに変わったというのが非常に大きくて。自分でこういうことを学びたいと思ったときに、それがどんどん学べる環境でした。あとは、他の科とか西洋楽器の人とも積極的に交流したかったので、いろんな授業を取っていました。作曲科の人に新しい尺八の曲を書いてもらいたくて、作曲科の授業も取ったり。
当時は松下功先生(元音楽学部作曲科教授)がまだ非常勤でいらして、「管弦楽法」というオーケストラの授業を担当されていました。オーケストラの楽器を知って、その次の年ではオーケストラの曲を創作する授業でした。
国谷
作曲もされた、素晴らしい。
藤原
邦楽科の学生で作曲の授業を取る人が少なかったので、松下先生が非常に目をかけてくださいました。そういうご縁もあって、卒業後に一緒にお仕事をさせていただく機会につながりました。作曲科に友人も出来て、それが今にもつながっています。
国谷
8年間藝大にいらしたあとしばらく大学からは離れていましたが、2013年に改めて非常勤講師として戻られ、今では准教授としてまさに藝大の尺八を率いています。演奏活動やプロデュース、作曲など、本当に多彩な活躍をされている中で、どうして大学で教鞭を執るという選択をされたのでしょうか。
藤原
やはり次の世代に伝えるということですね。自分がやっていることは、5年 10年の話ではなく、 何百年、何千年とつながっていく。伝統ってそういうことだと思います。雅楽の方がよくおっしゃるのは、「千年後の人たちに申し訳ないことをしてはいけない」と。後世の人に「あの時代がなかったら良かったのに」と言われないようにと。
そのためには根本的なことを伝えていかないといけない。演奏表現は根本的なものにその時代の衣を纏わせることが大事なんですが、今はその中身と衣がごっちゃになっている部分もあるので、変わっていくものと、変わらないものとがあるということは、しっかり伝えていきたいと思います。
国谷
今の時代は、邦楽にとっては逆風のような状況ではないかと思います。今、藝大で尺八を学ぶ学生は何人ですか?
藤原
学部生が5人と大学院生1人、別科生4人の学生がいます。非常に少ない状況ではあります。やはり経済的なことばかりが優先されてしまう中で、卒業後の進路も含めて心配される方も多いと思いますが、尺八に対する想いとか、自分が何を伝えたいか、それがあればやっていけると思います。それに充分な勉強をこの学校でしていただきたい。そうやって身に着けた基礎に、自分の衣とか時代の衣を着せていくということを考えてほしいと思います。
いろんな演奏の形がある
国谷
現在の藤原先生のご活躍を見ていると、変幻自在というか、軽やかにいろいろな衣を纏っているような印象ですが、やはり基礎というところでは山本邦山先生のもとで、「名人から盗む」ような学び方をされてきたのでしょうか?
藤原
そうですね。僕が習い始めた頃、山本先生は本当にご多忙で、レッスンは月に1回でした。先生のレッスンの他に、「代稽古」といって先生のお弟子さんから教わっていました。レッスンでは、先生はほぼ何もおっしゃらない。おっしゃらないからこそ、お弟子さんたちは先生の演奏を分析する。それを僕に教えてくれました。そういう形で稽古を受けられたのは、僕にとって大きかったですね。何人もお弟子さんがいたので、先生からどう教わってきたのか、どういうところを見ているのか、いろんな目線を教えてもらうことができました。
国谷
藤原先生はかつてインタビューの中で、「とにかく演奏をたくさん聞いて、その音にどう近づけていくのかを探して、そこから音が生まれる」とおっしゃっています。
藤原
そうですね。山本先生の舞台はなるべく観に行って、いつも一番前の席で聴いていました。レッスンで知れることは自分の出来ないことの一部です。実際に舞台を観ると、その都度毎に先生が違う演奏をされている。同じ曲でも共演者が変わることによって、そこでの役柄がちょっとずつ変わる。いろんなシチュエーションで聴くことによって、いろんな形があることがわかりました。

流派は言葉
国谷
邦楽の世界には、独特の流派というものがあります。尺八にも流派があり、藤原先生は都山流でいらっしゃいます。尺八を学ばれる方が少なくなる中で、流派の存在はどこまで重要なのでしょうか。門外漢の質問で恐縮ですが。
藤原
流派は言葉だと思っています。東北弁や関西弁みたいな。やっぱり、その土地や風土に馴染みのない人がしゃべると、言葉のイントネーションが違ったりする。流派も言葉の違いと同じで、そういったちょっとした違いを大事にしたい。日本全国で標準語が喋れるようになっても、その土地の言葉の個性が存在していることが重要だと思います。
国谷
それが面白さだったり豊かさだったりする。
藤原
今はそれが失われそうになっていることに対して、みなさん危機感を持っています。どこの地域の言葉も自在に操れる方がいるように、どの流派の演奏もできるという方が出てくるかもしれませんが、やはりその土地本来の言葉となると、ネイティブスピーカーかそうでないかでどこかしら違ってくるのと同じではないかと思います。他流を習ってもどうしても最初に習った表現が自然と出てくるものです。
国谷
流派を守ることは伝統を守ることにもつながりますね。一方で尺八の世界は国際的になってきていて、国際的な尺八のフェスティバルも開催されています。海外の若い世代が尺八に魅せられ尺八を手に取るようになってきたのは、なぜなのでしょう。それに比べて日本の状況はどうですか?
藤原
今年の5月に米国テキサス州で開かれたワールド尺八フェスティバルに行って参りましたが、皆さん非常に面白いアイデアで、パワフルにそれぞれの演奏をしている。伝統的なものも大事にしてくださっていますし、同時に自分たちの音楽をちゃんと持っているのがすごいなと思いました。嬉しかったです。
国谷
演奏楽器としてグローバルに定着してきているのですね。
大事なのは想像力
藤原
日本の状況について僕が思うのは、今はあまりにも物事を具象化しすぎて、すべてを見せてしまっている。そうでないと物足りなくなってしまって想像する力が失われてきている。
想像力は我々が非常に大事にしているものです。例えば落語にしても、扇を箸に見立てて蕎麦を食べたりしますよね。実際には蕎麦はないけれど、あるように見せる。能もそうです。自分のなかの想像力、自分のなかにある美しさで、素晴らしい建物があるように舞台上に置いていく。観客に高度なことを求めています。それが、具体的に見せないと物足りなくなっている。想像力を伸ばすことができないものかと感じています。

国谷
日本の若者たちに、もっと邦楽や尺八について知ってもらう、興味を持ってもらうということにおいて、想像力の乏しさがハードルになっているのでしょうか。
藤原
ひとつの側面として、そういう部分があるのではないかと思います。古典の場合は曲にしても表現にしても、単に分かりやすくはせず、具象ということをあまりしません。個性についても、個性は出るものであって出すものではない。繰り返し真似てやった上で出てしまうものであって、「自分がこうだ」と表現するものではない。その部分を補ってくれるのが観客だという考え方です。
国谷
しかし、観客の方も、感じる力を養う機会が少ないのかもしれません。
藤原
そうですね。常に何か回答が提示されていると、考えなくなってしまいます。自分の中で、どういうことだろうと考え、見つめ直していくことが重要になってくる気がしています。
国谷
私もかつて報道番組を担当していたときに、同じようなことを感じていました。分かりやすく伝えることが求められるけれど、それはとても危険というか、間違ってしまう恐れがある。分かりやすく伝えて、わかった気になった途端に、人々は考えることを止めてしまう。やっぱり、物事はそんなに簡単ではなくて奥深い複雑なものだから、その複雑さも含めて伝えるべきだし、気持ちの中にザラザラしたものが残ることによって、その人にとってもっと深く考えるきかっけになるのではないかと思っていました。分かりにくさのその奥を見つめることによって、もっと深みが出てくるというか、知が生まれるというか。
藤原
まさにそういうところだと思いますね。分かりやすく表現すればするほど、その人の我が予期せぬ形で入ってきて、フィルターがかかってニュートラルな伝え方できなくなってくる。

やはり極端な面があることによって両面が見えてくる。その両方の間を行き来しながら積み上げて行くものだと思います。何事もそうだと思いますが、一方に行き過ぎたら絶対に揺り戻しが来る。人間というものは、それをずっと繰り返している。だからこそ真ん中のところから常に両方を見て、揺れながらも歩いていくことが大切だと思います。真ん中にいることは一番難しいことですが。
- 1
- 2