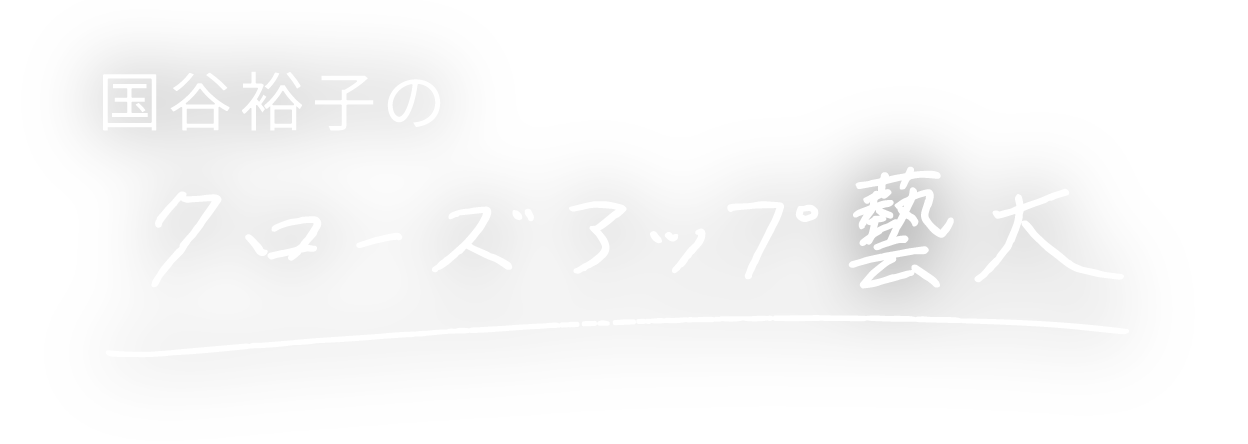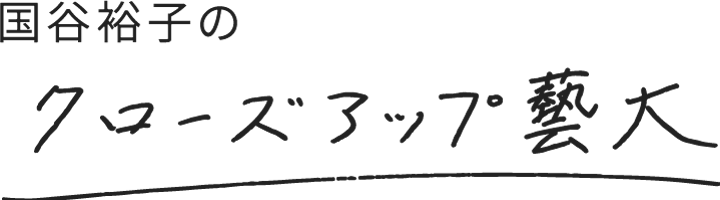第二十三回 吉井瑞穂 音楽学部器楽科(オーボエ)准教授
>> 前のページ
そこに行かないとわからない“場のエネルギー”
国谷
いつも音楽の話をするときに吉田秀和さんの書いていることを引用するんですけど。
吉井
あー!ご近所だったんです。吉田先生はいつも奥様と手をつないでお散歩されて、よくうちの前を通っていらして。子供の頃から「有名な先生なんだよ」って教えられていました。亡くなる前に2回ぐらいお宅に遊びに行かせていただきました。ずっと憧れの先生だったので。
国谷
その吉田さんが半世紀以上前、1960年代にヨーロッパに行かれて、そこで活躍している日本人演奏家の音楽を聴いてこう書かれています。「自分の感覚とそれ以上の何かで、新しく自分の音楽をするという足場を日本人はどこに築いたらいいのか。それを発見するためには、園田高弘や豊田耕児ほどの才能でさえ、10年以上のヨーロッパ暮らしを必要としたのである。」吉井先生がヨーロッパで活動されていた時代は、吉田さんがこう書かれてから25年以上あとのことで、かなり時代は変わったと思います。でもやはり、クラシック音楽を学んで力をつけるためにはヨーロッパという場が必要というのは、今でも変わらないのでしょうか。全体を俯瞰してみて、どう感じられますか。
吉井
そうですね。いろんな意見や考え方があると思いますけれど、やはり場所の持つエネルギーというものがあって、そこに行ってみないとわからないことも多いと思います。
ドイツに住んでいたときに、アウシュビッツに行ったんです。ユダヤ人の作曲家の作品を演奏していて、やっぱりアウシュビッツに行かなきゃ絶対にわからないなと思って。ちょっと感じるものがあったので、きちんとここで清算しようと。2回行きました。
これは、どんなに映像を観て本を読んだって、行かないとわからないと思いました。行かないと、体験しないとわからないことってこれだなと思いましたね。戦争を推し進めようとするような方たちは一度そこに行けばいいですよ。行ったらわかるはずです。

国谷
ヨーロッパには、クラシック音楽を学ぶ上で重要な“場のエネルギー”があるということですね。
吉井
はい、それもありますし、ここにベートーヴェンが住んでいましたとか、ここでメンデルスゾーンが住んで作曲をしていました、ブラームスがここバーデン=バーデンにいてシンフォニーを書いていました、そしてこの辺を散歩していました、というところに行くと、その場でパッとわかる、体感できることはたくさんあるわけです。言葉では表せないインスピレーションというか、それが伝わってくる。それはその場に行かないとわからない。そこで演奏する空気感は行かないとわからないなと思いました。
国谷
そういう意味では、ヨーロッパに行くことはとても大事ですね。
吉井
そうですね。大事だと思います。
ただやはり、私の年代はすごく恵まれていて、「音大に行ったら留学しましょう」みたいな、誰もかれもが留学をするような雰囲気でした。今は時代も違いますし、いろいろな条件も重なってきますので、それが叶わない若い世代の方たちもたくさんいると思うんですね。だから、闇雲に行けばいいというわけではないけれども、なるべくそういう現場の雰囲気とか香りとかを体感してもらえたら嬉しいなと思いつつ、叶わない学生たちには、私がありがたい経験をさせていただいたので、それを伝えられたらいいなと思って、毎日トライしています。まあ、行ってしまった方が早いとは思いますけれど。
感覚を言語化し続けた「鍛錬の15年」
国谷
音楽だけではなく、吉井先生は書くということも続けて来られました。月刊誌の連載では本当にいろんな出来事をユーモラスに語っていらっしゃって、面白く読ませていただきました。
でも、書くことは簡単なようで苦しいというか、好きでないと続けられないことだと思います。吉井先生にとって、書くとはどういうことですか?

吉井
控えめに言っても、大変苦手でした(笑)。今は休刊になってしまった「パイパーズ」という管楽器専門の月刊誌に連載をしていたのですが、編集の方がものすごく熱心にオファーしてくださって。もしかしたらご縁なのかもしれないし、ではちょっとやらせていただきますという感じで始めてみたら、大変でしたね。やっぱり。
お引き受けして本当によかったなと思ったのは、それまではいわゆる感覚で演奏したり毎日の生活を送っていたのが、書くとなったら言語化しなければいけない。「あっ」と思ったら、その「あっ」を表現する言葉を見つけてみましょう、という感じになるわけです。書き始めてからは、「すごい!」と思ったときに、ではその「すごい」はどういうふうに書くのかと考える習慣がついて、すごく勉強になりました。
国谷
感覚とインスピレーションから言語化に行ったわけですね。
吉井
ほんの少しですけれど。でもお恥ずかしい限りで、あれは「鍛錬の15年」と呼んでいます。自分をまとめるための機会をいただいたということで。
国谷
でも、感覚的なものから言語化というのは、かなり大きな変化だと思います。それは音楽に影響というか、音楽の表現に具体的な変化をもたらしましたか?
吉井
私はわからないです。周りの人がわかるかもしれないですけれど。
国谷
以前「クローズアップ藝大」のインタビューでフルートの高木綾子先生が、楽譜に言葉とか物語を書いているとおっしゃっていました。そうすると演奏しながら楽譜に反応しやすくなる、ある意味表現しやすくなると。
吉井
わかる気がします。脳が各所に指令を伝えるので、言葉を見たほうが脳が伝えやすい。例えば「共感覚」という現象があって、音を聞くと色が見えるという特性を持つ人がいます。私もそうなのですが、反対に、楽譜に「青」と書いておくと、青色に聞こえるような音が出しやすくなるということがあります。
国谷
言葉と演奏がどう影響し合っているのかなと思ったのですが、面白いですね。
25年を経て故郷・鎌倉へ
国谷
吉井先生は藝大入学後1年足らずでドイツへ行き、2017年に帰国されました。帰国直前にお書きになったエッセイには、「自分の人生の転換期を迎えているような気がしてなりません。これからの私は戴いたものを皆さんに還元するような毎日を過ごさせていただけたらと思っています」と書かれています。先日のテレビ番組の中でも、「愛する母国で還元する日が来た」とおっしゃっていました。人生を転換する、何かきっかけがあったのですか?
吉井
帰国する前は、オーケストラの活動が一番楽しい時でしたが、ずっと心のどこかで、一番楽しい時に辞めようというか、区切りをつけたほうがいいかもしれないと思っていたんです。こう(下がって)きたときに辞めるより、一番楽しくて、「あーもったいない!」という時に。
他にもいろいろな要因が重なって、「これは今かな」と思ったんですね。もともと自分の故郷・鎌倉がとても好きで、海の近くで育ちましたので、海の近くに戻りたかったということもありました。
帰国を決める前に、病気になったんですね。病気になるのは神様からのお便りだと言われています。本当はお便りが来る前に気がつかないといけないのに、ずーっと神様の声を聞かないでいると、病気になって気づかされるという。実は病気になる前から、「帰ったらどうですか?」という神様の声が聞こえるよう気がしていたんですけれど、無視し続けていて。そうしたら病気になってしまった。でも、「これはお便りだ」と思って帰ることを決めたら、治ったんです。
国谷
不思議ですね。
吉井
そうなんです。不思議です。
まあ他にも理由はあって、子供をどこで育てるかと考えたときに、主人はイギリス人なんですけれど、どちらかの母国で育てたいと思って。そうすると、鎌倉かなと思いまして。
国谷
それで4歳の息子さんを連れて鎌倉に戻られたのですね。ヨーロッパで25年過ごされたことが、むしろ鎌倉愛を強めましたか?
吉井
まさしく。そもそも外国に出た理由は、自分の国を外から見てみたかったからなんですね。外に出て客観的に見ると、それまで不満に思っていたことも考えが改められて、日本は素晴らしい国だということが、実感として体験としてわかった。もちろん外に行かなくてもわかる方もいますけれど、私は外に行かないとわからなかったので、外に出るように神様に仕組まれたのだと思います。そのきっかけがたまたま音楽活動だったのでしょう。

幸せのきっかけを一つでも作れたら
国谷
帰国される2年前から、鎌倉で地域に根差した音楽祭 レゾナンス『鎌倉のひびき』のプロジェクトを始められます。ヨーロッパは、音楽が市民にとってすごく身近で、地域に根付いている。やはりそういう経験を日本に還元する活動の1つが、ご自身で始められた音楽祭なのでしょうか。
吉井
昔から、地元で小さな音楽祭ができたらいいなと思っていて、たまたま協力してくれる友達が見つかったので、そこから手さぐりで始めました。手作りなので至らないところが多すぎて反省点ばかりなんですけれど、細く長く続けていけたらなと思っています。
あと、鎌倉は神社仏閣が大変多くて、200ぐらいあるのかな。そういう磁場が他の町とはちょっと違うところで音楽を鳴らしたらどなるのか、興味がありました。もちろん雅楽や日本古来の音楽もあるけれど、そのなかで西洋のクラシック音楽を演奏したら……。そういうイベントは鎌倉ですでに行われていますけれど、自分がそこで演奏したらどんな感覚になるのか、実験してみたかったんです。
我々は通常はホールで演奏しますけれど、そうではない場所。私が子どもの頃にお世話になった神社仏閣や、地域の皆さんがよく足を運ばれるような身近な場所で、わざわざ行くというよりはたまたま通りかかったら音楽が鳴っていたというような。そういう、ふとした偶然で出会うことが重要だと思うんですよね。私がテレビをつけたらルービンシュタインさんのドキュメンタリー番組をやっていたように。そういう、皆さんが幸せになるきっかけを、一つでも作れたらなと、僭越ながら思います。
国谷
“場のエネルギー”がそこで作り出される音楽にも影響するとおっしゃっています。音楽祭の会場についても“場のエネルギー”を重視されているのでしょうか。
吉井
地球のシューマン共振(地球が自然に発する周波数)のような感じで、その場所ごとに共振があると思うんです。我々が音楽をすることで、その周波数がちょうどよいところにピタッと合うような場所で演奏したいですね。それこそ、音楽を、行って見て体感できる音楽祭ができたら。
国谷
来場者は何か“気”のようなものを感じるんですね。きっと。
日本の音楽教育環境についてどう思われますか? ヨーロッパと比べるとどうでしょうか。
吉井
大変恵まれていると思います。
本場で教育を受けること自体がプラスですから、ヨーロッパはすでに恵まれていますが、日本は様々な外国のアーティストやオーケストラが来たり、マスタークラスをしてくださったり、勉強できる場がたくさんある。それはやはり戦後の高度経済成長期に一生懸命働いてくださったご先祖様たちのおかげだと思います。将来どうなって行くのか不安もありますが、この教育環境を残せるようにしていきたいです。
国谷
今ここで教えてらっしゃって、ヨーロッパの経験を本当に豊富にお持ちの中で、何をその学生達に伝えて、何を一番学んでほしいと思いながら、向き合っていらっしゃいますか?
吉井
音楽が本来持っているエネルギーみたいなものがあります。音は私たちが生きてる証でもある。それを私たちは演奏するというアクションで体験しているわけです。
なぜ音楽があるのか、なぜ音楽を演奏しているのか、わたしも自分に問いかけ続けていますので、大きなことは言えませんが、「音楽がもたらす喜び」を多くの方に分かち合えるような、そんな演奏家になって欲しいと思っています。
学生の皆さんは、本当に素晴らしい才能を秘めた優秀な方ばかりです。多感な十代二十代の時期に、何か少しでもサポートできたら、役に立つことがあればと、おせっかいおばさんとしていろいろ言っています。

【対談後記】
お話を伺いながらとても印象的だったのは、吉井先生が熱っぽく“場所の持つエネルギー”について語ってくれたことです。
その場を体験しないとわからないこと、行けばわかるはずと例に出して話されたアウシュビッツ。その記憶を思い起こしながら話されていた目には涙のような影が浮かんでいました。
場所から放たれるエネルギーや空気感から得られるインスピレーションの大切さを実感されてきただけに、吉井先生はいま神社仏閣の多い故郷鎌倉において、人々が偶然音楽に出会えるような場を作り出したいと挑んでいます。そして藝大でも、自らが体験したヨーロッパという場が持っていたエネルギーを伝えたいとの思いで指導にあたっているのです。
インタビューを終えて、藝大を、そこで学ぶ学生たちに、さらに大きなエネルギーを与えることができる場にするには何が必要なのだろうかと、大きな宿題をいただいたような気がしています。
【プロフィール】
吉井 瑞穂
音楽学部器楽科(オーボエ)准教授
1973年、神奈川県鎌倉市生まれ。
5歳よりピアノを始め、14歳からオーボエを井口博之氏に師事。東京藝術大学入学後に渡独し、カールスルーエ国立音楽大学を首席で卒業。国内外の主要コンクールで入賞を果たす。
カラヤン財団より奨学金を授与され、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のエキストラ奏者として活躍。その後、2000年より約22年間にわたりマーラー・チェンバー・オーケストラの首席奏者を務め、ヨーロッパを中心に演奏活動を展開した。クラウディオ・アバド(共演200回以上)をはじめ、ギュンター・ヴァント、ニコラウス・アーノンクール、ピエール・ブーレーズ、ダニエル・ハーディング、グスターボ・ドゥダメルといった巨匠の指揮のもとで演奏を重ねている。
欧州の主要オーケストラやアンサンブルから客演首席奏者として頻繁に招かれる一方、ソロおよび室内楽奏者としても精力的に活動。NHK交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、九州交響楽団のほか、テツラフ弦楽四重奏団、レイフ・オヴェ・アンスネス、内田光子らと共演を重ねている。
2017年3月に日本へ拠点を移し、現在は地元・鎌倉を拠点に活動。鎌倉では「レゾナンス 〜 鎌倉のひびき 〜コンサートシリーズ」を主宰し、地域に根ざした音楽活動にも力を注いでいる。
https://resonance-kamakura.com/
ニューヨーク・マンハッタン音楽院をはじめ、イギリス、スペイン、ドイツ、イタリア、ノルウェー、南米など世界各地でマスタークラス教授として招かれ、後進の指導にもあたっている。
ルツェルン祝祭管弦楽団設立メンバー。
東京藝術大学准教授。
第49回JXTG音楽賞(現ENEOS音楽賞)奨励賞受賞。
2026年度出光音楽賞・推薦委員。
公式サイト:https://mizuhoyoshii.com/
撮影:リトル 太郎ピーター
- 1
- 2