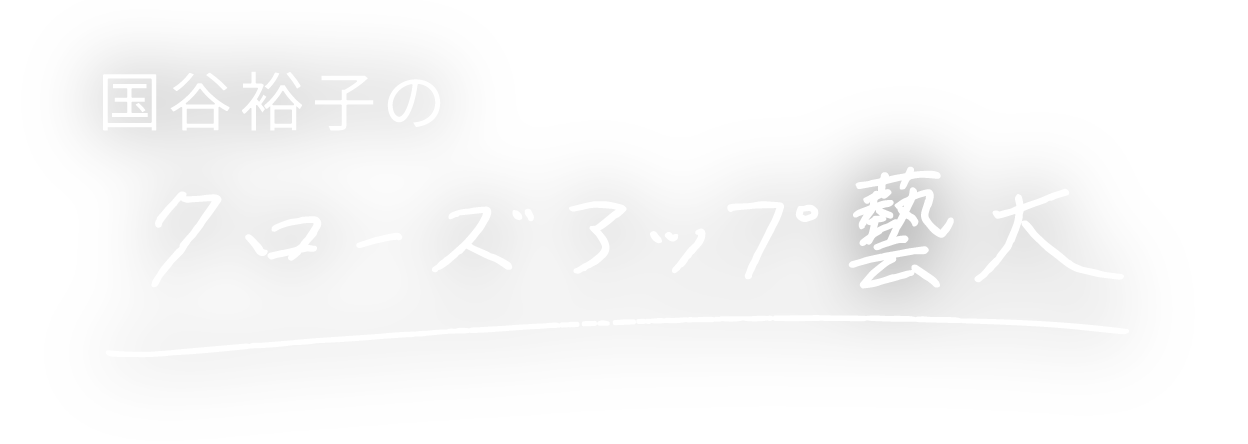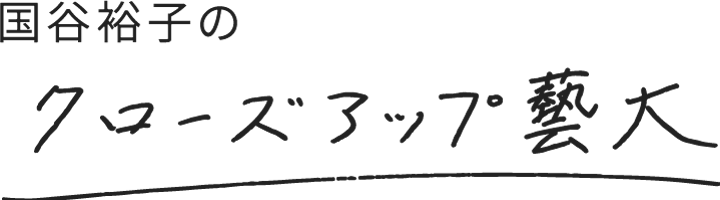第二十三回 吉井瑞穂 音楽学部器楽科(オーボエ)准教授
クローズアップ藝大では、国谷裕子理事による教授たちへのインタビューを通じ、藝大をより深く掘り下げていきます。東京藝大の唯一無二を知り、読者とともに様々にそれぞれに思いを巡らすジャーナリズム。不定期でお届けしています。
第二十三回は、音楽学部器楽科准教授の吉井瑞穂先生。オーボエ奏者として25年間、ドイツを中心にヨーロッパで活動し、2017年に帰国。現在は後進の育成のほか、自身の演奏活動や故郷・鎌倉での音楽祭主催など、多方面で活躍されています。2025年11月、レッスン室にてお話を伺いました。
【はじめに】
ヨーロッパの第一線、マーラー・チェンバー・オーケストラで長年主席オーボエ奏者として活躍してきた吉井瑞穂先生は2017年に拠点を日本に移し、藝大で後進の指導にあたっています。
オーボエを専攻する藝大の学生は現在19名。この19名の学生を非常勤講師の方々と共に、専任で指導しているのが吉井先生です。レッスンが行われる吉井先生の部屋にはグランドピアノが置かれ、指導はピアノ伴奏の方を伴ったり、学生と1対1で進められることもあるとのこと。
壁には吉井先生の師、オーボエ界の巨匠モーリス・ブルグの写真が、吉井先生の指導ぶりを見守っているかのように飾られていました。
吉井先生との対談は、オーボエのやわらかで膨らみのある癒しの音色を生み出すまでの手仕事の難しさと、その美しい音を作り出すことの厳しさから始まりました。
神経を削る楽器、オーボエ
国谷
オーボエという楽器は、本当に癒される音色なのですが、こんなにデリケートな、とても演奏が難しい楽器だということは知りませんでした。
吉井
リードの調整をしなくてはいけないので、音が出るまでにすごく時間がかかるんです。そのことを知っていたら、おそらく始めていなかったと思います(笑)。中学生までは先生からリードが常に供給されていたので、リードはいただけるものだと思い込んでいましたが、蓋を開けてみたら、自分で作るとういことが判明しまして。びっくりしました。
国谷
気候や高度、温度、湿度など、演奏する空間の条件によって、リードのご機嫌が変わる。
吉井
全然変わります。このレッスン室と奏楽堂とでも違うし、隣の部屋でも違う。本当に左右されるので、常に天気予報を見て温度や湿度、演奏するホールの状況を考えながらリードを選んでいます。
乾いていると音が出ないので、必ず湿らせないといけないのですが、湿気があり過ぎると重くなって音が出なくなってしまう。この加減が難しいし、ほんのちょっとのゴミとか埃が入っただけで、音が出ない。だからある意味、本当に神経を削る楽器です。
国谷
リードは全部ご自分でお作りになる。ひとつ作るのにどれくらい時間かかりますか?
吉井
工程が何段階かありまして、材料は葦の茎なんですけれど、これを三つ割にして、長さを整えて、鉋をかけてかまぼこ状にして、そこから舟型という型で形を整え、それをチューブというものに巻き付ける。巻き付けてからちょっと置いておいたほうがいいので、私はだいたい一年間置いています。
国谷
一年間!
吉井
はい。だから常に一年スパンで作っています。一年置いて、それからナイフで削って行きます。チューブに巻き付けてからすぐに削る方もいますけれど。
国谷
手先が器用でないとオーボエ奏者にはなれないですね。
吉井
確かにそうですね。だから我々はちょっと職人的な部分があります。常にナイフなどの工具の吟味もしていますし、すごくマニアックな世界です。

国谷
吉井先生は、最初は5歳でピアノを始められて、いろいろな楽器を転々とトライしていたそうですが、なぜこんな難しい楽器を選んだのでしょうか。
吉井
実は私はオーボエのことをよく知らなかったんです。持ち運びのできる小さな楽器を探していて、ピアノの先生に相談をしたら、「オーボエという楽器はいかがですか?」って鎌倉に住んでいらっしゃるオーボエの先生を紹介していただいて。「持ち運びできますか?」と聞いたら、「はい、小さいです」って言われて、試してみたのがきっかけでした。
国谷
知らなかったのですね。
“神経を削る楽器“ということですが、先日テレビ番組に出演された際に吉井先生は「神経質じゃないオーボエ奏者はいない」とおっしゃっていました。吉井先生も神経質なのですか?
吉井
はい、神経質だと思います。
おそらく、交感神経と副交感神経のバランスが理想的ではないのでは、と思います(笑)。年を重ね、少しは慣れてきたとはいえ、シビアなコンサート前ともなると、リードのことを考えるだけで自然と心拍数が上がります。そんな私を思い遣ってか(笑)、周りからは潮が引いたように人が少なくなることもしばしばです。
国谷
エッセイにも書いていらっしゃいます、家族や同僚など周りの人に当たる、ピリピリしているって。でも、その音色はやわらかで牧歌的で……。演奏する方の置かれている状況と音色の落差が大きいですね。
吉井
音を出すまでが結構ストレスフルですね。例えば、1週間ずっとリードを作り続けても、ひとつも良いものができないことがあります。そうなると、やはり心が折れますし、頭の中はリードのことでいっぱいになります。
でも、これは本当に幸せな「プロブレム」だと思います。食べることにも事欠き、紛争下で生死をかけた日々を送っている方々が、この地球上にはいらっしゃるのですから。
歌手みたいな気持ちで吹いています
国谷
前回の「クローズアップ藝大」では尺八の藤原道山先生にインタビューさせていただいたのですが、尺八は思いっきり息を吹き込む楽器です。それに対してオーボエは細いリードを通して、息を思いっきり吹いてはいけないというか、半分息を止めながら演奏しているような。息をコントロールしながら吹いていらっしゃると思いますが、息継ぎはどのようにするのですか?
吉井
例えばチューバとかトロンボーンとか、クラリネット、フルートもそうですが、管が太い、息を入れる容積が大きい楽器は、息が大量に必要なんです。オーボエの場合はその容積が小さく、ほかの楽器に比べると息が余るので、これぐらい吐いたら吸うという感じで。そのタイミングは演奏しているとわかってきます。フレーズに合わせた必要な息の量が、練習をすることで自然とわかってきます。
国谷
吐いてから吸うわけですね。
吉井
はい、吐いて吸う、がワンセットです。その按配は個人個人の身体状態にもよりますが。
循環呼吸という、吐きながら吸う技法もあります。これはイタリアのベネチアン・グラスを作る職人さんたちの技法で、鼻から入れて口から吹き続きける。ガラスは吹き続けないと固まってしまうので。その技法を使った曲もあるんです、マニアックなんですけれど。循環呼吸ができると永遠に吹くことができますが、それはちょっと不自然なので、循環呼吸ができる方でもきちんと吸って吐いて、余ったら吐いて吸ってということをやっています。

国谷
吉井先生は、「オーボエの魅力がまだ多くの人に伝わりきっていない、できる限りいろいろな場で演奏を続けて行きたい」とお書きになっていますね。一方で、「オーボエはオーケストラの中ですごく存在感がある、料理でいうと塩みたいな存在で、音の軸を作っている」とも書かれています。それはオーボエの音色のせいなのか、それとも他の要因があるのでしょうか?
吉井
オーボエはヴァイオリンとユニゾンで被ることが多いのですが、オーケストラをメロディーとしてリードしていく(バスとしてリードするという役割の楽器もあります)役割という意味で「軸」になり得るし、またオーボエ特有の振動数が「軸」としての役割を担っているかもしれませんね。あと、同じオーケストラでも、オーボエの人が変わると全体的に印象が変わる気がします。自分がオーボエをやっているから特別感をもって見ているかもしれませんが、これはよくプロの方たちもおっしゃることですね。
国谷
オーケストラの音合わせするときに、オーボエの「A」の音を基準にしますよね。なぜオーボエなのでしょう。
吉井
オーボエの真ん中の「A」の音が、一番安定しているからだと聞いたことがあります。
国谷
オーボエをずっと演奏されてきた吉井先生から見て、オーボエの最大の魅力は何ですか?
「オーボエを通じて癒しのエネルギーを伝えたい」ともおっしゃっていますが。
吉井
人間の歌声のような音が出るからでしょうか。
リードのご機嫌をうかがいながらも、歌手になったつもりで演奏しています。
オーボエの音色を聴くと、セロトニンが分泌されやすい、と聞いたことがあります。以前、コンサートにお越しくださった方が、「終演後、花粉症が楽になっていました」とおっしゃってくださって、もしかすると無関係ではないのかもしれませんね。
国谷
オーボエ用の曲というのは、あまり多くはない気がします。
吉井
おっしゃる通りで、ヴァイオリンやピアノ、フルートに比べたら断然少ない。オーボエ用に編曲されたものもありますが、ソロ曲は圧倒的に少ないです。
現在活躍されている作曲家の方々に、少しでも多くオーボエ作品を書いていただけるよう、これからも力を尽くしていきたいと思っています。
アルトゥール・ルービンシュタインに衝撃を受けて
国谷
吉井先生は藝大に入学後、1年足らずでドイツのカールスルーエ音楽大学に留学されます。そして、結局藝大には戻らずにドイツの大学を卒業されました。なぜずっとドイツで学ぶという決断をされたのですか?
吉井
高校生までオーボエは趣味としてやっていて、だんだん好きになって行きました。でも、大学で進みたかったのは、実は経済学部だったんです。どうして人間の社会に貨幣が必要なのか、貨幣経済の起源とか存在意義とか、そういうことをきちんと学びたいと思っていました。それを世界史の先生に言ったら、「君は経済学部か商学部に行きなさい」って言われて。
世界史を見ると、お金が原因で戦争になったりする。私はカトリック教徒で、幼い頃から聖書をずっと読んできましたが、そのなかにもやっぱり争いがある。争いの原因は一つではないけれど、常に損得やお金といった、マテリアリスティックなことが原因にある。お金が無い世界というのは可能なのかなって、ずっと思っていたので、経済とかそちら方の学問に憧れていました。でも、音楽が大好きな家庭でずっと育ってきましたし、オーボエもやればやるほど、「私はこっちかな」と思って。それで藝大を受けることになりました。
藝大を受ける前、高校生の時にオーボエ奏者のトーマス・インデアミューレ先生の草津の音楽祭での夏期講習会に参加しまして、「ドイツに来るならなるべく早く来た方がいいけれど、将来のことを考えると日本の大学に一度入っておいたほうがよいのではないか」とアドバイスをいただきました。それで一度大学に入ってからドイツに行ったんです。
国谷
経済の勉強をしようか考えながら、結局は音楽の道を進むことになったわけですね。その頃でしょうか、テレビで、ピアニストのアルトゥール・ルービンシュタインさんのドキュメンタリー番組を見て、「芸術家ってこういうものなんだ」とすごいインパクトを受けたとお書きになっています。そのインパクトとは具体的にどういうものだったのでしょうか。
吉井
私は当時、中学一年生ぐらいで、土曜日の朝たまたまテレビをつけたらやっていたんです。ルービンシュタインさんの生涯がモノクロの映像で紹介されていて、第一次、第二次世界大戦の頃のヨーロッパが映っていました。彼はユダヤ人で、20世紀の歴史を体現していらっしゃるような方です。まあ、当時の私にはよくわからなかったんですけれど、後から考えてみると、その歴史の重みというか、深さというか、そういうものを感じたんだと思います。どうやってスターになって行ったのか、彼自身がその生きざまについて語っていたんですが、表面的なことではなくて、その言葉の裏に確固たる信念と経験があるということが、子どもながらに心に響いたんだと思います。それに加えて、彼の演奏はやはり群を抜いて素晴らしいです。あとにも先にもああいう方は出ないのではないかなというぐらい。

国谷
少女時代は、貨幣はなぜ必要なのかと探求心を持ちながら、一方で、ルービンシュタインの演奏を聞き芸術家への憧れを強めて行った。そのギャップは面白い。
日本を背負っている感覚はない
国谷
ドイツで大学に通っている間も、日本でのコンクールで優勝するなどの経験をされながら、やはり日本には帰ってこず、ドイツの大学を首席で卒業されました。ドイツで大学を卒業すると思っていましたか?
吉井
そうなるだろうなと思っていました。ほぼ外国人がいないような環境で、学部1年生として入学して。帰ることはほとんど選択肢になかったですね。目の前にやることがたくさんありすぎて、日本というキーワードが入れないくらい忙しかったし、慣れるのに必死でした。それで気がついたらかなりの年数が経っていたという感じです。
国谷
卒業後も帰国はせず、ドイツを拠点にヨーロッパで演奏活動を続けて来られました。
大学を卒業した後、まずは日本に戻って日本を拠点に演奏活動をしようとは考えなかったのですか?
吉井
不思議とその考えには至らなかったんです。戻るというオプションが頭の中にまったく無かった。19歳の時に行って、帰ってきたときは45歳。25年もいてしまいました。びっくりしました(笑)。
国谷
クラシック音楽の演奏家として極めて行こうと思った時に、活動の場所としては日本ではなくヨーロッパの方がよいと思ったのでしょうか。
吉井
本場ですから、そういう考えは少しあったかもしれません。例えば、歌舞伎を学ぶなら日本で学んだほうがいいですよね。クラシック音楽はもともと西洋で生まれたものですし、やはり根本的・精神的な理念を実感するために本場に身を置くことは良いことだと思います。
国谷
その後、マーラー・チェンバー・オーケストラに入り、主席演奏者プリンシパルを務めた。
マーラー・チェンバー・オーケストラのメンバーは、やはり特別に選ばれた人という感じがします。ルツェルン音楽祭のオーケストラも、いろんなオーケストラから選び抜かれた人で構成されています。そういうメンバーに選ばれた時は、日本を代表するというか、日本を背負うような感覚があるのでしょうか?
吉井
日本を背負う感覚は、実は全くありませんでした。
「一音楽家」という感覚で欧州に住んでいましたので、少々手厳しい状況だったり、差別をされたり…そのような時にはじめて「ああそういえば、私は日本人だったなぁ」と思いました。
国谷
差別的な体験をなさった?
吉井
はい、ありました。例えばオーディションで、投票では私が一位だったのに、別の人が受かるということがありました。主催者に理由を聞きに行くと、「今はちょっと女性とか外国人は……」とはっきり言われました。当時はそういう、今だったらすぐ問題になるようなことがけっこうあって、ちょっとトラウマ的になっていた時期もありました。私の実力が足りなかったのかもしれないとも思いましたけれど、やっぱり理不尽で腑に落ちない。どこかモヤモヤする。でもその経験は、今になってみると、かけがえの無い肥やしになっています。
ほとんどの方は親切でしたし、いいことの方が多かったんですが、やっぱりマイナスの経験がちょっとあると、それがフォーカスされて心の傷になって残る。でもそういう経験をすることで、相手の気持ちを考えるようになります。どうしてそう思うのか。見かけや言葉が違うからなのか、今まで前例がなかったからなのか。
どうして差別が起こるのか不思議でたまらなくて、いろいろ考えました。それぞれの社会(グループ)のテンプレートというものがある。例えば 10人いたらそのなかのシステムがあって、傾向があって、キャラクターがある。それはグループごとにある。そこに私がそぐわなかったという話なんです。
マーラー・チェンバー・オーケストラは、もともとマーラー・ユース・オーケストラという東ヨーロッパ人中心のユースオーケストラから派生したオケで、(ヨーロッパ室内管弦楽団がヨーロッパ・ユース・オーケストラから派生したように)いわゆるアジア人100%は私が初めてだったようです。ハーフの日本人は何人かいらっしゃいましたが。
国谷
吉井先生が切り開いたのですね。
吉井
当時受け入れてくれた人たちが、国籍とか見かけとかをあんまり気にしなかったんだと思います。

>> 次のページ そこに行かないとわからない“場のエネルギー”
- 1
- 2