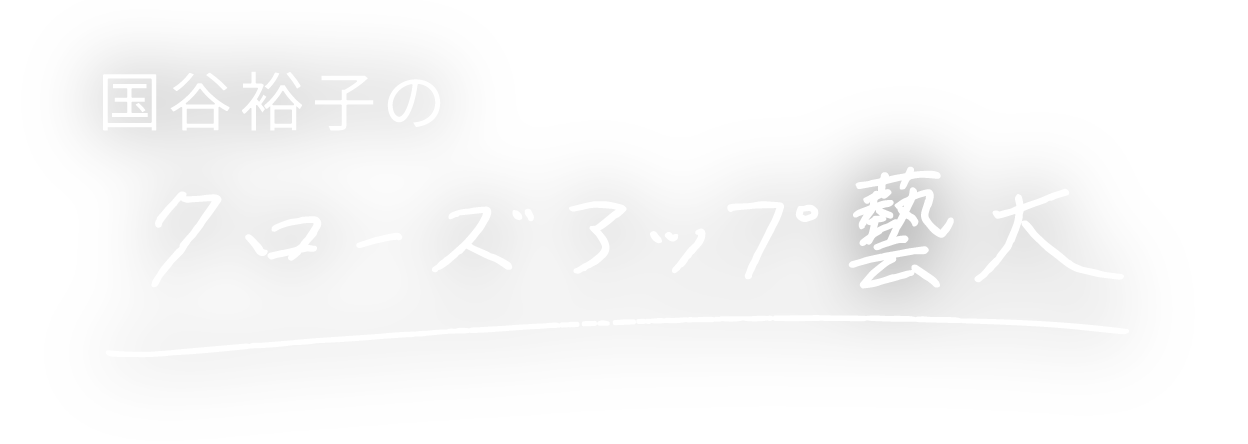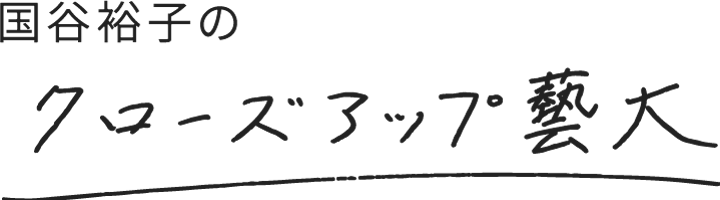- 大学概要
- 学部・研究科・附属機関・センター等
- 展覧会・演奏会情報
- 広報・大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般・企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第八回 黒川廣子 大学美術館教授
「美術」を輸入し、「美術品」を輸出
国谷
私は本当に、芸術について知らないことばかりで…。先生の文章のなかに、「幕末には無かった美術の概念が明治になって初めて西洋から日本に紹介された」と書かれていて、びっくりしたんです。
黒川
「美術」という言葉はウィーン万博(明治6年)の準備過程で、明治4年に翻訳されたものなんです。明治時代までは「美術」という言葉も概念もなかったんです。
国谷
それまでは、素晴らしい茶器とかお道具も美術ではなかった。お茶碗はお茶碗、お軸はお軸という感じで、アートという概念がなかったんですね。それでは日本における「美術史」のスタートは?
黒川
「美術史」っていうと東京美術学校でアーネスト・フェノロサや岡倉天心たちが教え始めてから、となりますが、その前から文献はあるんですよ。だけど美術史とは呼ばなかったんです。
国谷
日々の実用品から発展した工芸が、明治以降いつしか美術とか芸術と呼ばれるようになった。日本には民芸もありますが、先生の目から見て、工芸と美術の境目はどこなんでしょうか?
黒川
よく最近論じられるところなんです、美術と工芸って。境目を作るのかどうかも含めて。そんなにはっきり分けられないと私は思っています。
当時は、それこそ東京美術学校の先生や指導者たちを先頭に、「日本の工芸は世界の工芸とは違う。美術工芸だ!」と声高に唱える人が多かった。彼らは自分たちの作品といわゆる工芸品は別物という意識があったとは思います。実際の技や素材とか、見かけは同じでも作り方が違うとか、あるいは造形そのものの美的センスとか、そういったところに自分たちは違いを見出していた。でもそれはわかる人にはわかるし、わからない人にはわからない(笑)。
その一方で、造形的に難しいとか複雑なことをやっているわけではない簡素なものにも美を見出すことが、多分古くから日本人の美意識のなかにある。簡単な器であってもそれが美しい、だから芸術なんだっていう。何の違和感もなくそう思っている人たちが多い。それで、自分たちの身の周りで作られていたような器も芸術の域に達している、という思いもあったのではないでしょうか。
その後の展開を現代の学者たちは、やっぱり今でも研究をしているんですよね。不思議な展開というか、わかりにくいということもあって。
国谷
そうなんですか。論じられているということも全然知らなくて…。
明治になって海外のいろんな博覧会に日本が出品しだすと、人気が高まってどんどん輸出されるようになった。自分たちが作っているものの価値を海外から教えてもらったのでしょうか?
黒川
そういうことは往々にしてあると思いますよ。いわゆる「お雇い外国人」と呼ばれる明治初期に来日した外国人たち、フェノロサもそうですが、彼らが日本のすごさを日本人に教え、受け入れた人たちが海外の博覧会に出品したり輸出用に作るべきだと思い付いた。そしたらまあ、けっこういい反響があった。それがジャポニズムにつながっていくと言われています。金工に限らず、自分たちが作るものはなかなか海外にはないと気付き、海外の人たちから評価されて、日本人も思い直したのではないでしょうか。
幅広く勉強するうちに、誰も研究していない分野へ

国谷
先生は藝大の美術学部芸術学科を卒業されていますが、どのような人材を育成する学科なんでしょうか?
黒川
芸術学科出身の人は学芸員だったり研究者だったり、美術館・博物館に勤めている人が多いですね。私は明治時代を中心とした日本近代工芸史が専門ですが、現代とかいろいろな作品に広げて研究をしています。
国谷
藝大を目指していたんですか?
黒川
目指したわけではなくて、そこまで学芸員になりたいとも思ってなかったんです。工芸を勉強したいというのはありました。
私の祖母が佐賀錦を織っていたものですから、母もそれを継いで教室を開いたりしていました。そういう関係で家には工芸の本などもありましたので。
国谷
佐賀錦を研究したくて藝大に入った。でもそこから広がっていく。
黒川
面接試験でも佐賀錦をやると言って入学したんですが、入学後に指導教官に、「そんなに狭く見ないで、世界はすごく広いんだからいろんな分野も勉強しなさい」って言われて、いろいろなところに首を突っ込むようになりました。
せっかく藝大にいるのでもっと他の分野のことも知りたい。工芸のなかにも漆とかやきものとか金工とかいろいろありますし。それで、当時の指導教官に相談して、大学院は実際に作ることも課程のなかに入っている美術教育に進みました。そうしたら美術教育の指導教官が鍛金の先生だったので、なんか金工のほうに道が逸れたというか。
国谷
工芸のなかでも特に金工なんですね。
黒川
あと東京美術学校のことも調べていました。東京美術学校設立時の工芸科は金工と漆しかなかったので、その2つは歴史と基本的な技術を一生懸命調べました。それが私のバックグラウンドの一番べースにあります。
大学院を修了したあとは縁があってお隣の東京国立博物館に勤めました。そこにはまさに明治の工芸界を振興するための、海外の博覧会だとか輸出に関する資料がたくさんあって、それまでほとんど誰も研究していませんでした。日本の政府側からの資料とか、かなり広くいろんな分野にわたる作品に関する資料があったので、それを一生懸命研究していました。
展覧会企画の醍醐味
国谷
先生は美術館の教員でありそして学芸員でもあります。
黒川
はい。ですから、教えることの他に作品を管理・研究したりしています。で、その研究に基づいて展覧会で見せることが一番の本業でしょうね。
国谷
いろいろ調べて作品を理解したうえで、学芸員なら展示を企画する。同じ作家でも何をテーマに企画をするかで全くその展示が変わってきますものね。どういうプレゼンをして何を集めてどう並べるかというのは、学芸員の腕の見せ所ですよね。
黒川
そうですね。展覧会企画の醍醐味です。すごく大変ですけどね。相当なネタを集めて、それを示すための根拠や裏付けを調べたりとか、時間はいくらあっても足りない。展覧会の場合は期日があるのでどうがんばってもそこまでなんですが、そのあとにわかることもたくさんあるんですよ。展覧会をやったことによって観に来た人から情報をいただいたりして、私たちではわからなかったことがわかるようになる。これが素晴らしい。そういった情報が蓄積されて次の企画に結びつくこともあるし、アーカイブしていけば私が在籍しなくなったあとも後輩が有効活用できるかもしれない。

国谷
学芸員の方々はちゃんと他の機関と関係性をつくって、自分のところにない作品を貸していただかなければならない。もちろんこちらから貸し出すこともあるでしょうし、そういう連携能力みたいなものが必要ですよね。
黒川
はい。例えば海野勝珉の作品で、ここにはない素晴らしいものをよそから借りてくると、うちのコレクションと一緒に展示して、これらの作品は同じ作家だと観てもらえる。そうやっていかにすごいかを示せるという意味では、よそから作品を借りてきて展覧会を組み立てられるのは一番の理想的な関係です。
お互いに協力し合って、必ずしも展覧会という形でなくても、調査研究の場合でも他の美術館・博物館の研究者・学芸員の方たちと研究を持ち寄る研究会みたいなものもけっこうありますし。そういったことから得られる視点も大きいですね。
伝え手の役割
国谷
美術史を学んでいる学生たちに、美術史をしっかりと自分のものにしていく上で一番大事なことは何だと思って教えていらっしゃるんでしょうか。
黒川
時代によって違うんですけれど、近代以降はかなり作家がはっきりしています。明治とか江戸以前は作家がわからない作品が多いんです。
国谷
みなさん分業で作ってらした、江戸時代は。
黒川
明治もその流れが残っていました。名前が出てくるのは親方だけだったり。それは仕方がないことですけど、結局ものが出来上がっていく背景がものすごく大事ですよね。作る目的も当然ありますし、どうしてこういう造形ができたかや作品のテーマなどに対する理解ですね。そこを含めて全部勉強しないと作品の本当の理解はできないと思います。ただ見て好き嫌いではなくて、その背景と作家の置かれた状況につながる周辺の情報を調べ上げていくと、その作品がすごいものに見えてくる。そういうことを大事にしています。
国谷
日本の現代の工芸をどう見ていらっしゃいますか?
黒川
いろんな分野の人たちが切磋琢磨して頑張って作っていらっしゃる。そのなかから抜きん出ることは大変だと思うけれど、国内外から高く評価されている人が何人もいる。まだまだ日本の工芸は世界に誇って見せられる技・造形を持っていると感じます。
国谷
工芸は実用品とか日用のもので磨き抜かれてきたものですけれど、今は“シンプルライフ”とかが主流になってきていて、そういう技を残すことが難しくなっているんじゃないかと思うのですが。
黒川
はい。残念ながら作品だけを作って生活していける人はわずかだと思います。
国谷
複雑な技法で作られていることを、今の人はなかなか気付かない。だから伝え手の役割はすごく大きいと思います。
私は京都に実家がありますが、蔵のあるような町家がどんどん維持できなくなっています。みんなマンションになったりホテルになったりしています。そこに住んでいらっしゃった人の話を聞くと、自分たちでは整理しきれなくてトラックで粗大ごみみたいにして出さざるを得ないと。でもそのなかには美術・工芸品がたくさんあるわけです。悲しい…。硯箱とか、箸置きだったり、お椀だったり、お膳だったり…。おそらく明治時代のものが多いと思いますが、その頃のものには、日本人の尊厳を感じます。日常のものにこれだけこだわって、細部も。
黒川
そうなんですよね。ちょっとした飾りとか。
国谷
おろそかにしない。
黒川
そういうところも楽しむ。根付とか身の回りの小さいものなど、日本人のDNAにあるのではないかと思うくらい、ちょっとした飾りに拘りを持っている。現代のライフスタイルのなかで生活の道具として使い続けることは難しいかもしれないけれど、そのものの価値を知ればもっと大事にするし、大事にされるものももっと多くなると思います。

【対談後記】
この日、私は日本の工芸に敬意をこめて、京都で暮らす母から受け継いだ印籠に小さな穴をあけチェーンをとおしたネックレスをつけていました。対談の終盤、黒川先生に「そのネックレスは蒔絵の印籠ですよね」と聞かれました。「開きますか?」「銘はありますか?」。ネックレスを先生にお渡しすると専門家らしくすぐにルーペのようなものを取り出して「あ、書いてある。信定? 下の字が見えにくいですが、調べればわかるかもしれない」とニコニコしながらおっしゃいました。そして「工芸品をそうやって愛用し続けることが大事なのですよ」と言われました。
【プロフィール】
黒川廣子
大学美術館教授
専門は日本近代工芸史。
1985年、東京芸術大学美術学部芸術学科 卒業
1987年、東京芸術大学大学院美術研究科修士課程芸術学美術教育専攻 修了
東京国立博物館資料部研究員を経て1999年より東京藝術大学大学美術館へ。2016年より現職。
写真撮影:永井文仁
- 1
- 2