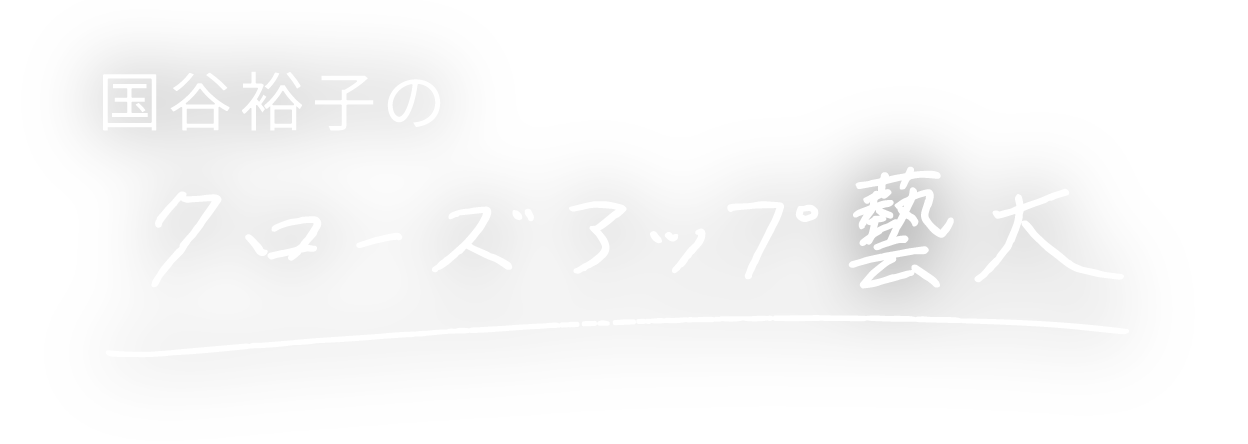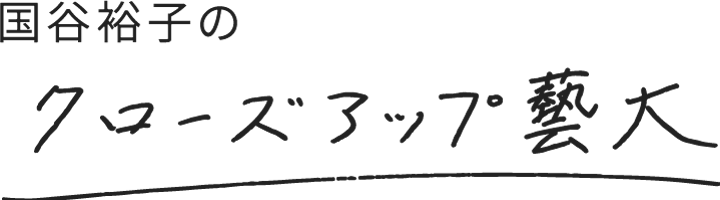第十四回 廣江理枝 音楽学部器楽科(オルガン)教授
クローズアップ藝大では、国谷裕子理事による教授たちへのインタビューを通じ、藝大をより深く掘り下げていきます。東京藝大の唯一無二を知り、読者とともに様々にそれぞれに思いを巡らすジャーナリズム。月に一回のペースでお届けします。
>> 過去のクローズアップ藝大
>> 「クローズアップ藝大」が本になりました
第十四回は、音楽学部器楽科(オルガン)教授の廣江理枝先生。オルガニストとして、コロナ禍前までは日本とヨーロッパを行き来して演奏活動を行っていました。令和3年5月、奏楽堂ホワイエとレッスン室にてお話を伺いました。
【はじめに】
藝大のホール、奏楽堂で行われる入学式、新入生の歓迎はまず荘厳なパイプオルガンの音色で始まる。演奏は藝大唯一のオルガン教授、廣江理枝先生。ホールの舞台正面にそびえるパイプオルガンはその存在も音色も聴く人々を圧倒する。
パイプオルガンとはどんな楽器か。たったひとりの演奏者が大きなホールを音で満たすことが出来るこの楽器には、手鍵盤と足鍵盤があり、オルガン奏者は両手両足を自由自在に使って鍵盤を押し、またオルガンの横に備わっているいくつものストップと呼ばれるレバーから出したい音色の組み合わせを選ぶ。管楽器系、弦楽器系、あるいは人の声や天上の声とされる音色もある。奏楽堂のオルガンには76のストップ(音色)と5380本ものパイプが備わっていて、オルガニストはオーケストラ的なことをひとりで行うのです。
身近な楽器とは言えないパイプオルガンに廣江先生はどのように出会い、大学卒業後、本格的に取り組み始めてから、どのようにしてアジア人で初めてフランス・シャルトル大聖堂国際オルガンコンクールで優勝するなど国際的に高く評価されるオルガニストとなられたのかを伺いたいと思いました。
お客さんは待ち望んでいた
国谷
コロナ禍になってから、廣江先生の日々の活動へはどのような影響がありますか?
廣江
去年は演奏活動の場はかなり少なくなりました。でも学内の演奏会が全てストップしたときに、最初に再開したのはオルガンの演奏会でした。オルガンはひとりで弾けるし、客席まで遠いし、反対側を向いているから飛沫は飛ばない、究極のソーシャル・ディスタンス楽器なんです(笑)。半分冗談ですが。
教育活動という意味では、オルガンは他の楽器以上に大学に来ないとレッスンができないので、まだ他の科の学生がリモート授業すらできていない時から対面での授業を始めていました。オルガンはあまり制約を受けることがなかったと思いますが、楽器によって全然事情が違うので…。
国谷
そうですか。でも芸術にとっては逆風です。
廣江
そうですね。とにかく人を集めて演奏会をするのが難しい。でも、それだけにありがたみを本当に感じますね。奏楽堂で去年何回か演奏をさせていただきまして、1回目は8月に行われた「学長と話そうコンサート『和樹の部屋』」での澤和樹学長、さだまさしさんとの共演でした。あのときは200人ぐらいしかお客さんを入れることができなかったんですけど、「1000人入っていますか?」っていうぐらいの拍手で、本当にびっくりしました。皆さん喜んでくださったんだなって。その後に行われたコンサートでも、お客さんが待ち望んでいたということが手に取るようにわかりました。
これは弾く人も聴く人も皆さんそうおっしゃっています。芸術は意味が無いものではなく、むしろその逆だということを、このコロナ禍で証明できたって。その後をどうつなげるかを考えて行かなくてはいけないですね。

国谷
今年の2月に松本で行われたコンサートはチケットが完売になったそうですね。
廣江
数が少ないから完売になるんです(笑)。そのときは定員の半分だったかな。それが早々に完売になりました。
そのコンサートで、涙ぐんで帰られた方がいたとか。それはオルガンが良かったとかじゃなくて、こういう、集まれない、出かけられないという状況で、他のお客さんと一緒に音楽を聴けたことを、「なんて素晴らしことなんだろう!」ってあらためて感動されたんだと思います。そういう気持ちを忘れないように、芸術が生きていけるような環境を整えていけたらいいなと思います。
国谷
3月にはCD『バッハ讃 ― J.S.バッハ: 青年期のオルガン作品』を出されました。バッハはオルガンにおいては本当に天才的な作曲家で、バッハに始まってバッハに終ると解説に書かれています。
廣江
私たちはバッハを避けては通れない。こう言うとネガティブに聞こえるかもしれませんが、当たり前に弾くレパートリーなんです。でもレッスンで一歩引いたところから見ると、やっぱりすごいなって思わされるところがたくさんあります。
例えば、今回のアルバムは初期の作品ですが、そのなかに「パッサカリア」という曲があります。後にロマン派時代の音楽学者のグリーペンケルルが、まだそんなにバッハ研究が進んでいない頃に、「この曲は資料的には初期に作られたようだが、あり得ない」と評した作品です。晩年のライプツィヒ時代の作品と思わせちゃうような出来具合なんですね。
それと、バッハの作品はひとつひとつ全然作風が違っていて、似ているものが無いんです。普通だったら、1回うまく行ったら次の曲も似たような感じにしてやろうと思いますよね。でもそれが無いんです。形式からしても本当にバラバラで、ひとつひとつが面白い。他の作曲家の作品は、巨匠と呼ばれるような人でも、作風などが似ています。
国谷
オルガニストからそうやって解説していただくと、面白いですね。
廣江
実は「パッサカリア」は今回いろいろいきさつがあって、録り直しをしたんです。奏楽堂のオルガンで演奏したんですが、スケジュール的にもコロナ禍だから録り直しができたようなものです。
「パッサカリア」の最後のほうはフーガになっていますが、フーガって主題が必ずあって、主題と組み合わされる対主題というものがある。それにバッハらしからぬ、バッハの時代だったらここにスラーは付けないんじゃないかと思われるスラーがあって、常々変な感じがしていたんです。今回、CDにするので調べたところ、現存している20以上の資料のなかで、3つしかスラーが書いていなかった。これは何かの間違いでスラーが付いてしまったのだと思って、スラーなしで弾いて録音しました。それで、夏中かけてそれを論文にまとめることになった。いつもだったら夏休みはドイツに行って演奏会ばっかりやっていたから、これもコロナ禍だからできたことです。そうしたら最終的には、51対49ぐらいで、そのスラーはバッハが書いたんだろうっていう結論に達してしまい、「申し訳ありません!」とお願いしてもう一度録音させていただいたんです。そういう訳で私にとっても思い出深い曲です。
国谷
そんなことがあったのですね! もう一度聴いてみます(笑)。
エンターテインメントとして弾いたっていい
国谷
オルガンを学んでいる学生は何人ですか?
廣江
学部生は昔は1学年に3、4人が普通だったのですが、段々減ってきまして、1、2年が3人ずつ、3年がゼロで4年が1人、大学院生は9人です。
国谷
減っている。オルガンが学生たちにとって遠い存在になったのは、どういう理由だと思われますか?
廣江
第一に、オルガンに限らず音楽を志す人が少なくなってきているとは思います。音楽学部を受験する人数も減っていますし。そういう単純な考え方以外に、オルガンって他の楽器以上にマイナーというか、どこにでもある楽器ではなく、どこでも知り合える楽器ではないことも理由のひとつかと思います。
90年代以降、コンサートホールにオルガンがすごく増えて行って、コンサートホールでオルガンスクールを開いたり、そういう啓発活動はすごく盛んにやっていただいていて、オルガンを知っている人は増えてきています。でも、専門を志そうと思っても、ピアノのようには家に置けないし、どこで練習するんだろう、将来どうするんだろう、という不安があるのではないかと思います。全般的に見て音楽の世界を志す人が減っているなかで、オルガンはさらに特殊な事情があるのです。
国谷
オルガンは紀元前からスタートして、ローマで格闘技の応援に使われたり、いろんな歴史がありますけれど、やっぱりキリスト教やヨーロッパの文明・文化との関わりが強いイメージです。日本でオルガンが定着するうえでの文化的な壁みたいなものは感じますか?
廣江
そうですね。宗教的な楽器だということはやはりひとつ大きいかもしれないですね。ただそれは、先ほどコンサートホールの話をしましたけれど、コンサートホールって全然宗教色が無いんです。そういう宗教色の無い場所でオルガンをに出会う人が多いので、「オルガン=クリスチャンの楽器」と考える人は、ヨーロッパほどは日本にはいないかなと思います。
これは実はロシアでも同じような状況です。ロシアは一応キリスト教国ですが、ロシア正教の教会にはオルガンは無くて、コンサートホールとかロシア正教以外の教会にオルガンがある。演奏会としてのオルガンはすごく人気があって、宗教的なことではなくて音楽として楽しむことが定着しているようです。日本もその路線で、こだわらなくていいというような、寛容な捉え方をされている気がします。
国谷
どのように文化的な壁というものを考えていけばいいのか?
廣江
難しいですね…。私たちが演奏しているレパートリーは、あの時代にこういうふうに作られ、そして演奏されていたということは、やっぱり厳然としてあります。それはわかった上で弾かなくてはいけない。
でも一方で、エンターテインメントとして弾いたっていい気もしますので、あまりこだわらずに楽しんでいただきたいという気持ちで啓発活動していきたいと思います。
国谷
日本においてオルガニストとして生きていくことの難しさを、学生たちはどうやって乗り越えて行ったらいいのでしょうか?
廣江
これも難しい…。オルガンだけじゃないですけれど、やっぱり仕事が無いんですね。オルガニストとしてのいわゆる安定した就職が日本には無い。
国谷
ヨーロッパにはありますか?
廣江
あります。教会はひとつの就職口なので。例えばドイツだと教会音楽家という資格を持っていると教会の職に応募できます。教会自体がどんどん少なくはなっていますが、それでも伝統がある国なので、ある程度のことをして生きていくことはできる。でも日本にはそういう伝統が無いので、オルガニストあるいはオルガン周辺のことだけをして生きていくのは不可能に近い。
ですが他の楽器も、似たような状況だと思います。とりわけオルガニストはオルガンがなければなれないので、私たちの役目は、オルガンのある場所にできるだけ定職を設けるようにしていくことだと思います。
パイプオルガンという楽器

鍵盤の左右にストップが並び、それぞれに名前が書かれている

パイプオルガンの裏側

裏側にもパイプがぎっしり
国谷
オルガンはみんな同じようにできているかというとそうではなくて、ストップやパイプの数が違ったりする。ひとつひとつ異なるオルガンに合わせて演奏を設計しなければいけない。ですから、「すごいな、オルガニストって」と思いました。
廣江
ありがとうございます。
国谷
演奏会のときはどのような準備をされるのですか?
廣江
弾く曲によってレジストレーションが一切変わってきます。レジストレーションとは、オルガンの音色選択機構である「ストップ(音栓)」の組み合わせを決定する作業のことですが、個々のオルガンに合わせて、曲に合わせて、初めての作業になります。でも、この名前のストップはだいたいこんな音がするだろうとか、パイプの長さが8フィートだったらこういう音、4フィートだったらこういう音と、ある程度の予測はできるので、それを曲に合わせて選択していきます。残響とか空間の大きさとか、それから客席に人が入ったらどうなるかを考慮しながら。これがけっこう影響が大きいんですけれども。
国谷
客の入り具合を考えて演奏!
廣江
人が入ると本当に音が吸われるので残響がかなり変わるんですね。教会だったら空間が大きいので、そこまで変わらないところもありますが、奏楽堂だと満席になると響きが全く変わってしまいます。
オルガンの演奏台に座ると、パイプは真上とか真横にある。そこから音が聞こえてくるんですけれど、客席にはそれが立体的に届く。つまり私たちは実際の音は聞こえない状態で弾いている。ですから、選択したパイプから出る音が客席でどう聞こえるかを、自分以外の誰かに聞いてもらうとか、あるいは誰かに弾いてもらって自分が客席で聞いてみるとか、そうやって確かめる作業もします。
国谷
リハーサルはとても大事ですね。
廣江
初めて弾く楽器は必ずその確認作業をやりますし、奏楽堂でも毎回やります。
国谷
演奏しながらストップの操作もするのですか?
廣江
ほとんどの場合、日本では譜めくり兼ストップを操作するアシスタントがいます。レジストレーションを書いておいてアシスタントの方にお願いするんです。それができるのもすごい能力なんですけれど。
国谷
パイプとストップのコンビネーションは無数ですよね。
廣江
ストップの数の順列組み合わせとしては確かにそうですが、組み合わせが無数にあるかというと、そこまでは無いんです。その時代のやり方とか慣習があって、ある程度のベースからはあまり逸脱しない。現代曲は例外ですが。
オルガンは、その楽器のために描かれたレパートリーがたくさんあります。例えばフランスのロマン派時代のレパートリーだと、カヴァイエ=コルが作った楽器がすごく支配的にフランスに広まっていて、その楽器で弾くためのレパートリーがたくさんある。わりと中央集権的な国ですから、どこに行ってもそのカヴァイエ=コルの楽器って同じような音がするんですよ。
逆に言うと、例えばセザール・フランクの曲を弾く場合は、あの響きを再現するように、そういうレジストレーションを作るんです。
国谷
そのレジストレーションは記録に残っているのですか?
廣江
そうですね。作曲家自身が、ここではこういうふうにストップを使う、という資料を残しているので、それを使ってレジストレーションをしています。
すごく不思議なんですけれど、全く違うタイプのオルガンに対しても、その響きを知っているオルガニストは、なんとなくそういう響きのレジストレーションにしちゃうんです。これができるようになるには本当にヨーロッパに行って、ヨーロッパの楽器とその響きを知っていないと難しいなあと、痛感しています。
国谷
日本にあるパイプオルガンはみんな新しいですよね。そうすると奏楽堂で慣れたオルガニストがヨーロッパに行って、そういう歴史的なオルガンを弾くのは大変ですか?
廣江
そういう各地にあるオルガンに関しての情報は、3、40年前の私が学生だった頃とは違って、ずいぶん行き渡っています。このコロナ禍以前は誰もがどこにでも行けましたし、動画とか音源とか、いくらでも情報として入手できる。もちろん体験してみないとわからないこともありますけれど。
例えば奏楽堂の楽器は教育用にいろんなレパートリーが弾けるようになっていますが、ベースはバロック時代のものです。ほかにも、バッハしか弾けないとか、もっと前のルネサンスのものしか弾けないとか、すごく制約がある楽器も日本にたくさんあります。あるいは、新宿文化センターにカヴァイエ=コルタイプのオルガンがありますが、それは確かにカヴァイエ=コル的な音がします。
情報もあるし、日本の制約のある楽器や特徴のある楽器も経験したうえでヨーロッパへ行くので、最近はそこまでギャップを感じなくて済むようです。
国谷
廣江先生が最も好きなオルガンのひとつは、北ドイツのノルデン聖ルートゲリ教会のアルプ・シュニットガー製作のオルガンとのことですが、どのようなところがお好きなのでしょうか?
廣江
シュニットガーというのは北ドイツのバロック時代の、オルガン界では誰でも知っているような楽器作りだった人ですが、どこが好きなんでしょうね…。ノルデンの楽器は中規模だったと思います。私が最後に行ったのが、それこそ30年ぐらい前なので…。

ドイツ留学中、ルートゲリ教会のシュニットガー製オルガンの前で
バロック時代のレパートリーをそこで弾くと、パイプとストップとを組み合わせたときに溶け合うんです。孤立して聞こえなくて、音楽に非常にマッチする。音が先にあるのではなく、音楽が先にあるのでもなく、一緒に生まれたみたいな。
国谷
反対に言うと、なかにはそれぞれが主張し合うような楽器もあるということですね。
廣江
そうですね…。主張し合うんですけれど、合わさったときに音が喧嘩にならなくて、非常に心地よい音がするんです。なかには心地よくない音がするオルガンも無くは無い(笑)。そういった意味で非常にバランスがとれていて、何時間、何十時間弾いていても飽きない、そういう楽器でした。
いろんなことを多角的に見る視点が重要
国谷
音楽評論家で水戸芸術館館長でもあった吉田秀和さんが、オルガンではないのですが、ピアニストについてこう書かれています。「ピアニストの卵は音楽に対してもそれ以外のことに対しても、他の楽器学習者よりどこか知的なものがある。ピアノは楽器の音そのものの魅力は、とても弦にも管にも及ばず、タッチによる音色の変化や音の充実、軽妙等の操作も大切ではあるが、まずは楽曲の構造とそれから和声の流れを重層的に捉える能力が無ければ話にならない。」『わたしの音楽室 : LP300選』(新潮社、1961年)。
廣江
非常によくわかります。というのは、ピアノもオルガンも旋律楽器ではないからです。ひとつの旋律だけを演奏する楽器はたくさんある。ヴァイオリンとか弦楽器もそうだし、管楽器もそうです。私たちはたくさんの線を弾くので、例えばこの声部の線はヴァイオリン的なとか、この声部の線はヴィオラ的、足はコントラバス的とか、それぞれの奏者の気持ちになって弾かなくてはならない。線の音楽を多層的に作っていくので、そういった視点は非常に重要ですね。
国谷
これを読んで、ピアノがそうなのであれば、オルガンはピアノ以上の知的作業が要求される楽器なのではないかと思いました。楽曲の構造・和声を重層的に捉えることに加えて音声の選択もしなければいけないし、組み合わせて新しい音色を作ったり、演奏に至るまでの知的作業が本当に大変な楽器です。
廣江
うーん、そこまできちんとわかっているオルガニストがどれぐらいいるかわかりませんけれど(笑)。逆に言うと、ピアノもそうですがオルガンはストップを引き出せば音が出ます。これは諸刃の剣というか、安易に弾くことはできるんです。ただ、いい演奏をするためには、今おっしゃったような作業が必要ですね。ピアノもよく、「猫が弾いても音が出る」なんて言われますが、そんなことは全然なく、芸術的なことをきちんとやろうとしたら、音を出す以上のことを全部わかっていないといけない。いろんなことを多角的に見られないとオルガニストにはなれません。
国谷
オルガニストが演奏に至るまでにする知的作業は、指揮者が楽曲を時間をかけて読み込んで、楽曲を自分のものとして作りあげていく作業に非常に似ているのではないでしょうか。

廣江
本当はそうなんですが、そこまでできている人はあまりいないかもしれません。自分も含めて。指揮者は自分で音を出せないので、おそらくもっとプレッシャーが強いと思います。私たちは弾けば音を出せる。でもその一歩先へ行くというか、本当の意味での音楽をするためには、重層的に勉強をしなければいけないと思います。
他の楽器と比較すると、オルガンは一旦音を出してしまったら、変えられないんです。オルガンの鍵盤は、空気がパイプへ送られるときの弁の開閉をするもので、鍵盤の操作では音量も音色も変えられない。ピアノは音を出した瞬間は変えられますし、管楽器とか弦楽器だと自由自在に大きくしたり小さくしたり、音質も変えられたりしますよね。私にとってはそういうことができないのはものすごいコンプレックスで、悲しいことだと思っています。オルガンはそういう楽器だということを受け入れつつ、でももっと生き生きした演奏方法を見つけていきたい。
国谷
それは実際にどうやってコントロールするのですか? 鍵盤の微妙なタッチですか?
廣江
はい、まさに微妙なタッチでコントロールする部分なんですが、それはヨーロッパのおおざっぱな空間や楽器ではなかなか難しくて、できるんですけど残響で消えてしまったり。
国谷
日本はオルガンがあるのはコンサートホールが多いという、世界でも特殊な場所です。
廣江
はい。ですから反対に日本はそういうことができる環境が整っているので、そのタッチの微妙な差でいろんな音の違いを出すことを、私たちもたくさんやっていきたいですし、聴衆の方にもそれを聴いていただきたいと思います。
国谷
ひとりで弾くというのはコンサートマスターをしているような感じですか?
廣江
そうですね。私は多分、ひとりで演奏したくてオルガンを選んだんじゃないかという気がします。人に迷惑をかけなくていいし、すごく大きな音が出せるし、オーケストラ的なことをひとりで全部やりますから。
国谷
あれだけの音をひとりで出して、場を支配できる。
廣江
それは快感ですね。
- 1
- 2