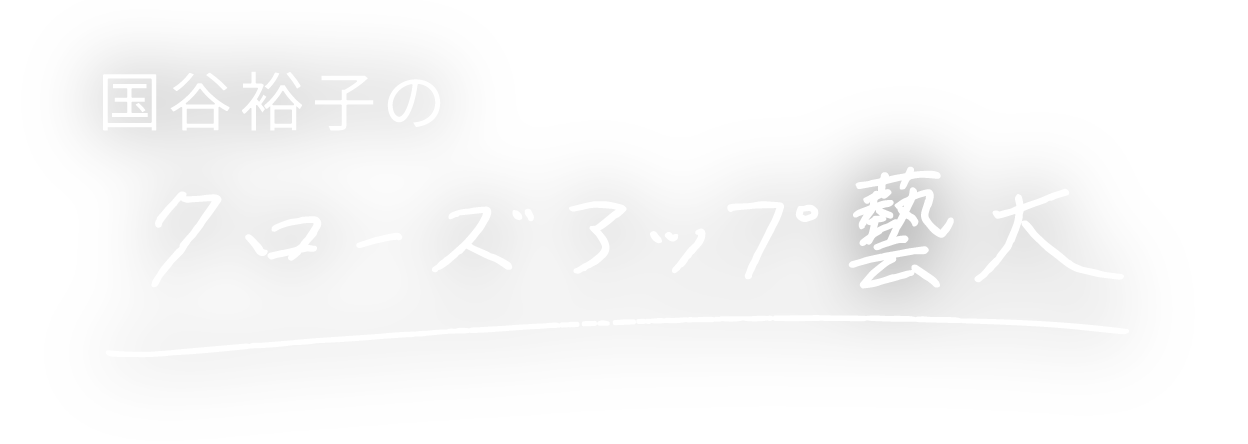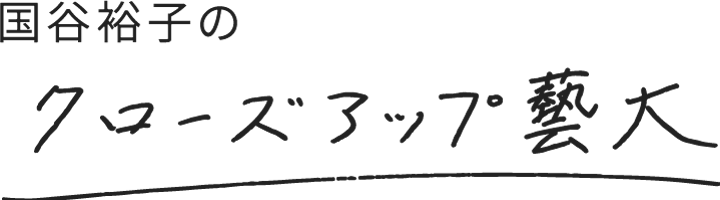第十五回 小鍛冶邦隆 音楽学部作曲科教授
「うけ」なければだめ
国谷
正直、現代音楽はとても難しいと感じます。とっつきにくいというか。私を含めて多くの人が敬遠してしまう。
小鍛冶
いろいろ理由はあると思います。まず、現代音楽とはどの辺りか。ある時期までは、モダン・ミュージックという言い方はしていたかもしれないけれど、コンテンポラリー(=現代)という言い方はしていなかったと思うんですね。20世紀の初め、1907、8年にアルノルト・シェーンベルクという作曲家がはじめて無調の音楽、調性がない音楽を作って、それが一般的な聴衆であった市民階級にショックを与えた。それは普通の音楽のレトリックというか社会的な言葉じゃなくて、社会的に抑圧された部分で語っていると。無意識ですね。潜在的なものにはじめて目を向けて、その結果、音楽が無調になった。シェーンベルクは非常に直感的に抑圧された部分に関心を持っただけで、狙ったわけではないようですが、そこから現代音楽が市民の敵になったのは事実です。だからその延長線上です。まだ1世紀ちょっとですけど。
表現すること自体が持つ、それを受容する側とのギャップというものに対して、作曲家はもっと敏感であるべきだったんだけど、それも結果論ですよね。そういうものを書けば向こうもそういうふうに反応する。それがどうしてそうなんだという理由を探してもしょうがないんですけれど、そういう行為が行われるがゆえに出てくるものというのを現実的に見ていくわけです。
フランスの詩人、シャルル・ボードレールは、モダンというのは古いものと新しいものが半々にある状態だというようなことを言っていますけれど、そういう意味でいうと、コンテンポラリーとは、この時代において共有できるものとできないものがいろいろある状況のことかなと思います。本来創作というのは状況的なところで意味を持ってきたわけです。極端な話、モーツァルトだってベートーヴェンだって非常に状況的で、ギリギリのところで音楽を書いていますよ。社会を受け入れると同時に極めて批判的なところも同居するようなやり方で作曲家のプレザンスを示していた。創作の新しさは状況との深い関わりがあるので、状況を理解しようとする姿勢は必要かなと思います。

国谷
音楽評論家の吉田秀和さんが1972年頃に、「現代音楽を考える」という連載のなかでこう書かれています。「人々は音楽と直接触れ合うことで畏れを感じるようになった。それはひとつは新しい音楽家たちがそれまでの音楽に慣れた公衆の耳に強烈なショックであるような作品を投げつけ続けてきたことと無関係ではあるまい」と。
小鍛冶
吉田秀和さんはまさに教養主義的な評論家だから、当然、ヨーロッパの歴史的な音楽を前提とした視点を持っていると思います。西洋音楽のように何世紀にも亘って伝統が定着したものに対しては、ある種のテロリズムが必要だと言っているわけですが、それを日本でやった場合にどうなるかはまた違う。日本は西洋音楽的な基準はないし、社会のなかで音楽が受け入れられて評価されるような地盤はないですよね。だから日本の社会のなかでの現代音楽は、乱暴といえば乱暴ですね、確かに。でもヨーロッパにおいては、現代音楽は意図的に何かを否定するというところから始まった。さらに言えば否定するやり方そのものを自分の芸風にしたわけです。だから単純に否定するんじゃなくて否定の仕方も大事ですよね。でも、当たり前の話ですが、それは否定するものが明確だからです。演奏会に来る人たちのための音楽があり、それを一般市民が共有しているからできるんです。ただ日本では無理ですよ。
国谷
元々ないですから。
小鍛冶
だから日本は新しいやり方でやったほうがいい。そういう今日の状況に合わせた、一種の挑発の仕方みたいな。藝大で最初の僕の教え子の渋谷慶一郎くんなんかはその辺のことをきっと考えているんでしょう。もっと若い世代は最初からもう現代音楽の業界はしょうがないと、自分たちがそこで一から足場を作っていくような価値はないと見放している…かどうかは知りませんけれど、彼らは小器用だからけっこうポップスの業界だと重宝がられるんですよ。何でもできる。そこでもっと自分のやりたいような、新しい感性で音楽作りができると思っているんじゃないかな。ちょっと甘いと思いますけれど、彼らが考えるのはそういうことですよね。そういう才能がこれからちょっとずつ増えて行くかもしれないですね。
国谷
20世紀以前の芸術音楽も、生まれた当時はコンテンポラリーだったわけですよね。それは音楽として広く受け入れられていた。
小鍛冶
そうですね、シェーンベルク以前は。もっともシェーンベルク後にもそれ以前のスタイルで作曲している人はたくさんいました。18世紀とか19世紀にその時代の音楽が問題なくコンテンポラリーとして受け入れられたとしたら、それは作曲家がそういう作曲をしていたからですよね。つまり作曲というのは、一方で慣習的に書くことが一番重要でみんなが知っているものしか書いちゃいけないんです。だからみんなが知っているものをどう違うふうに見せるかというところで創作性を発揮したんですね。ですがシェーンベルクの無調以降、そのスタンスが変わった部分がある。おそらく今日の現代音楽の作曲家たちはその変わった部分だけを継承しちゃっている。だから一方ではもっと受け入れやすいような現代音楽を作曲する作曲家もいますよ。でもやっぱり現代音楽ということに的を絞ると、ズレというか読み違いが出て来ているのは確かです。
だから僕が学生に言っているのは、ともかく「うけ」なければだめだと。「うけ」たあとで、あれは何だったんだろうと思われるのはいいと。それを実践したのが渋谷くんです。
現代音楽のこれから
国谷
日本の主要なオーケストラが定期演奏会でどんな曲を演奏しているかを調べてみたら、日本人作曲家の現代音楽は滅多に登場しませんでした。1年間のプログラムを見ても、現代音楽は数曲です。やっぱり聴く機会が与えられていないというか。そこはすごくハンデだと思いました。
小鍛冶
仮に聴く機会がもう少し多いとしても、聴衆がそこまでのってくるかどうかも問題でね。現代音楽はシェーンベルク以降、作曲家の視点を非常に固定してきた。というかそこしか見てない。一方、日本的な状況でそれを見てみると、作曲家は今日、大半は業界向けに「自分は現代音楽の作曲家だ」というところで書いている。もっと聴衆に近づいてポップなものを書くと、現代音楽的ではないと言われちゃう。その辺の戦略というか、やっぱり現代音楽というものを歴史的に見直さないといけない。コンテンポラリーという意味において現代音楽をどの時点に設定するのかということを、本来は藝大なんかが教育の目的のひとつに持つべきだと思うんですね。できる範囲で僕もそういうことをやってきましたが、ここから先はやっぱり作曲する人、学生のひとりひとりの意識が大きいんじゃないかなと思います。
国谷
現代音楽はこれからどうなってしまうのでしょう?
小鍛冶
ヨーロッパだと、作曲を学ぶことは必ずしも創作をするというわけではないんです。作曲家というのは音楽全般に対して一番見晴らしがきく地点にいるものです。だから例えばフランスなんかではパリ国立高等音楽院を優秀な成績で出て、作曲家になる人ももちろん多いけれど一番多いのは文化省とか音楽局の官僚なんです。あるいはプロデューサーとして放送局に入るとか、たくさんある高等教育機関を束ねるディレクターになる。それが一番の出世コースなんです。作曲家は元々そういう位置づけにあったわけだから、作曲を通して何かを目指していくとは限らないんですね。
藝大の作曲家教育、アカデミズムというのは融通が利くんですよ。だから音楽の世界での何か方向性を作っていくというか、そこに関わる人材を育てるのもひとつなんです。一方では創作家として、今まで人があまりやってこなかったこと、あるいはいっぱいやってきたことを通して、どういうふうにおもしろおかしくコミットしていくかということも教育のひとつの重要な部分だと考えています。
現代音楽が生き残るかどうかということでは、西洋経由で受け継いだので現代音楽自体についての定義が日本ではまだ明確ではない。日本は1950年ぐらいに盛んにヨーロッパの前衛的なものを取り入れましたよね。二十世紀音楽研究所とか、武満徹さんたちが最初に創作活動をした場は、ヨーロッパの新しい傾向に関心があって始まったわけです。ただ日本ではそれ以前のものが完全に抜け落ちてしまっていたから、本来的に前衛的なものかどうか、当時の人たちがどこまで理解していたかはわからないですよね。そういった歴史的検証もふまえて藝大のアカデミズムは生き残っていくわけです。
作曲は技術。そのためのアカデミズム

国谷
藝大の作曲家教育はアカデミズムを踏襲しています。学生から、もっとコンテンポラリーなものを学びたいという声はありますか?
小鍛冶
アカデミズムなんて言うと口はばったくなってしまうんですが、アカデミズムって藝大でやっている教育の基盤のこと。それを教育しているだけで、学生はいくらでも他のものと接触できるわけです。藝大で教えているのはひとつの基準なんですよ。ただその基準を習得するのがけっこう大変なわけです。
結局、作曲というのはそれで何をやるかではなくて、技術です。技術を習得するのはアカデミズムしかないというわけです。それは別に悪い話じゃない。でもかつては藝大アカデミズムは批判の対象だったけれど、今は「勝手にやってろ」ってことですかね。言うほどの価値もないと。まあ、ずっとやり続けたほうが勝ちですから大丈夫です(笑)。
国谷
藝大の作曲科は学部が1学年15人で計60人、修士課程が14人、全部で70数名の学生がいます。彼らは卒業後にどんな道を歩むのでしょうか? 必ずしも作曲ではなくてもいいとおっしゃいましたが、どんな分野を目指し、そして実際にどのような道でキャリアを築いているのでしょうか?
小鍛冶
創作者になりたい人間は少なくないと思います。大半は作曲家になる夢を見ているでしょう。オーケストラから委嘱を受けるような。そのための手段としてコンクールに応募するとか、留学してキャリアを付けるとか、そういった道を考えるわけですけれど、そのあとに来る荒野はあまり想像できないでしょうね。僕らとしても、それはやってみないとわからないことだから、必ずできるとも言えないしできないとも言えない。僕は「やってみたら」って言うだけです。やってみるかどうか、うまくやれるかどうかはその学生の才覚ですよね。それは教育の範囲ではないです、作曲科的には。その学生が持っているものをできるだけ見てあげることは必要だと思います。荒野を切り開く勇気を与えるというか。
基本的に僕は邪魔しません。究極の無責任ですけれど。だから逆に成功したって、僕の指導があったからだなんて言いませんし、そういう人は僕の指導があってもなくてもどこかでやると思います。藝大の作曲科で劣等生だからといって、本当に劣等生というわけではないし、自分はすごいと言っている人ほどだめだったりしますからね。成績とか能力は簡単には判断できない。だからとにかくやってみて、自分でチャンスを獲得していく。勇気を持ってそこに飛び込むことが大事です。そういう学生たちとの状況とか未来が、ギリギリのところで存続しているという感じです。
国谷
受け入れる裾野はもっと広がってもいいんじゃないかと思います。
小鍛冶
そういうことも含めて藝大はもっと積極的に関わっていかなくてはいけないと思います。
国谷
そういう場を作ることも藝大はやっていくべきですよね。荒野に出て行方不明になる人が多いんじゃないかと心配しているんですけど。
小鍛冶
行方不明にはならないで、すぐ自分たちの村に帰ってきて、そこで楽しくやっているんじゃないですか。トップを走っている奴は、屍を乗り越えて行くわけです、この業界というのは。だから生きていくには勇気が必要ですよね。勇気はなるべく与えたほうがいい。まあ「死んでこい」みたいな話ですね。何もしないよりはいい。
国谷
先ほどのお話で、フランスでは作曲を学んだ人たちが受け入れられる裾野がすごく広いなと思いました。
小鍛冶
作曲という分野は非常に限られているけれど、作曲をするために学ぶ音楽理論というのは音楽教育において非常に重要です。例えば和声とか、対位法、分析、あるいは初歩的な作曲とか、ソルフェージュなんかも実際にはそうですね。音楽理論を学んだ人はいろんな場で活躍できる可能性がある。藝大のやり方でそういう教育的な資質を与えられたなら、それを他の人に教育することができるぐらいの、人材としての価値はないといけないとは思います。もうひとつは、そういう場が必ずしも提供されているわけではないので、そこは藝大のようなところがもっと積極的に関わってもいいんじゃないかと思います。人材を提供するという意味で。

現代音楽の演奏会を定期的に開催
日本のなかでも藝大は現代音楽に対して大らかで、年に4回、モーニングコンサートで作曲科の学生の作品が取り上げられるし、2年毎に「創造の杜」というコンサートで大学院生と教員の作品が演奏されます。でもやっぱりキャパシティがあるから、たくさんやったからといって裾野が広がるわけではないので、あまり現代音楽が普及されていない部分で少しずつ増やしていくしかない。結局は資金の問題になってくるけれど、そういう資金を出すことが当たり前だというふうに考え方を変えていかなければいけない。ホールとか音楽祭とか、そういうところに関しても藝大は発言力があると思うから、もうちょっと意識してやってもいいんじゃないかと思います。

【対談後記】
やはり小鍛冶先生の話は私には難解な部分があり、今、読み返してもきちんと理解出来ているのか自信はありません。
お話で一番驚いたのはフランスで作曲を学んだ人々の最も多く進むキャリアが、文化省の官僚、あるいは高等教育機関を束ねるディレクターであり、それが一番の出世コースとされているということでした。この背景にはフランスでは幅広い分野で音楽的教養が大事にされているというバックグラウンドがあるとのこと。
日本において作曲を学んだ人々を受け入れる裾野は狭く、また行政職を志す人も少ない状況です。多くの学生が作曲家を目指す。小鍛冶先生の言葉を借りれば作曲の学生には“荒野を切り開く勇気”が必要とのことです。
本来は作曲や音楽理論を学んだ人は“音楽全般に対して一番見晴らしがきく地点にいるもの”、ヨーロッパのように様々な場で活躍できる可能性があるはず、藝大はキャリアのすそ野を広げるためにもっと関わっていくべきと小鍛冶先生がおっしゃっていたのが印象に残りました。
【プロフィール】
小鍛冶邦隆
音楽学部作曲科教授
1955年三重県生まれ。
東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。在学中より指揮者・山田一雄のアシスタントをつとめ、 同大学院を経て、パリ国立高等音楽院作曲科、ピアノ伴奏科でO.メシアン、H.ピュイグ=ロジェほかに、およびウィーン国立音楽大学指揮科でO.スイトナーに学ぶ。パリと ウィーンでコレペティトア(オペラ・コーチ)、オペラ指揮を学ぶとともにシエナ、 ローマでフランコ・フェラーラに師事、またマルケヴィッチ、ロザンタル等に指導を受ける。
東京都交響楽団で自作を含むプログラムで指揮デビュー以後、新日フィル、 日フィル、東響、東フィル等を指揮。2003年度にサントリー芸術財団第3回佐治敬三賞を受賞。また2017年、第86回日本音楽コンクール作曲部門本選の指揮・演奏に対して、委員会特別賞をアンサンブル・リームと受賞。作曲家として、クセナキス 作曲コンクール(パリ)第1位、入野賞、文化庁舞台芸術創作奨励賞、別宮作曲新人賞、 国際現代音楽協会(ISCM)「世界音楽の日々」他に入選。CDに《ドゥブル・レゾナンス》、銀色夏生の詩による《マドリガルI~VI》(以上ALM records)他、著書に『作曲の 技法 バッハからウェーベルンまで』、ベルリオーズ・R.シュトラウス『管弦楽法』 監修(以上音楽之友社)、『作曲の思想 音楽・知のメモリア』、訳書にケルビーニ『対位法とフーガ講座』、ボワヴァン『オリヴィエ・メシアンの教室』監修(以上アルテス パブリッシング)等がある。
2007年より東京藝術大学にて教鞭を執る。東京大学教養学部講師、慶應義塾大学院講師等を歴任。
撮影:新津保建秀
- 1
- 2