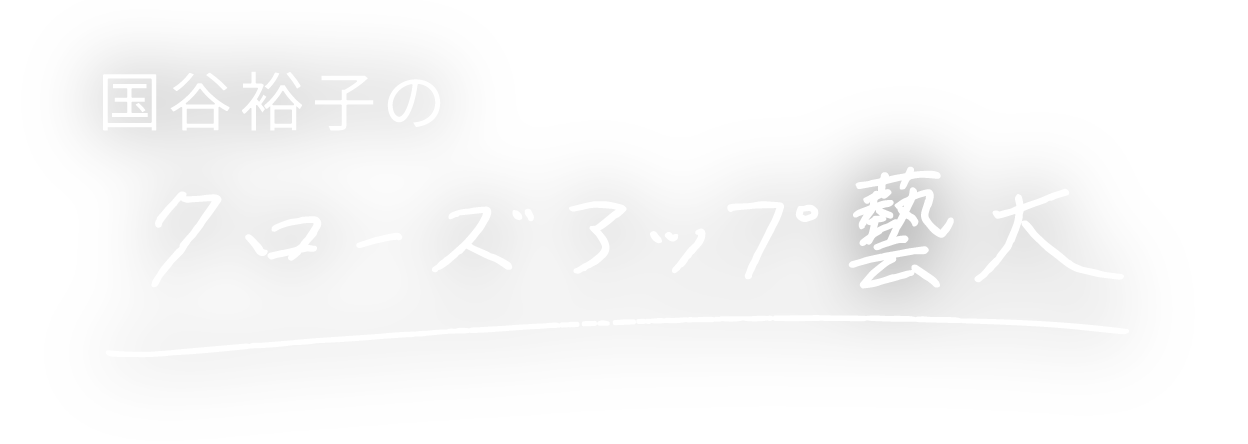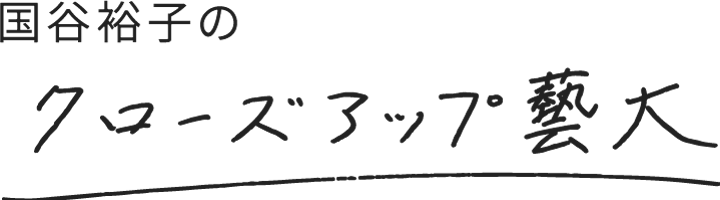第十五回 小鍛冶邦隆 音楽学部作曲科教授
クローズアップ藝大では、国谷裕子理事による教授たちへのインタビューを通じ、藝大をより深く掘り下げていきます。東京藝大の唯一無二を知り、読者とともに様々にそれぞれに思いを巡らすジャーナリズム。月に一回のペースでお届けします。
>> 過去の「クローズアップ藝大」
>> 「クローズアップ藝大」が本になりました
第十五回は、音楽学部作曲科教授の小鍛冶邦隆先生。現代音楽の作曲家として、また指揮者としても活躍しています。令和3年10月、研究室にてお話を伺いました。
【はじめに】
この「クローズアップ藝大」という企画を通して、今まで出会うことのなかった様々な芸術家の方々と初めて話をする機会を得ていますが、現代音楽の作曲家は正直とても遠い存在だと感じていました。コンサートでも、日ごろメディアを通しても現代音楽をあまり耳にすることがないこともありますが、現代音楽については難しい話になるではとの予感があり、小鍛冶先生との対談にむけて大変緊張していました。
先生のレッスン室は狭く、細長く、二台のグランドピアノがぴったり壁と壁の間に並んでおかれ、ピアノの前には長方形の机と3~4脚の椅子が残りのスペースを埋めていました。
緊張が高まるなか、とてもにこやかに迎えていただき、少しほっとしました。まずは音楽学部のキャンパス内を散策しながら撮影を行うことになり、想像していたよりも気さくな先生の人柄にふれて、気持が楽になったところでレッスン室での対話に移りました。
《トリスタンとイゾルデ》に衝撃を受けた中学時代
国谷
これまでいろんな方にお話を聞かせていただきましたが、実は作曲家の方は初めてです。作曲家になりたいと、いつ頃から小鍛冶先生は思っていたのでしょうか?
小鍛冶
作曲家って、最初から作曲をしようという人はあまりいないんです。たまに作曲少年みたいなのがいるんですけれど、でもだいたい最初はピアノを習っていたり、一応音楽をやっていてある程度の年齢になってからが多いです。僕は中学生になってから少し作曲の勉強を始めた感じです。ある程度、自意識が生じてからということでしょうね。
例えば、音楽教室みたいに子どもの自発性とか何か作りたいという衝動から入って行く方法もありますけれど、本来作曲って基本的な技術を学ばないといけないんですよ。和声とか対位法とかフーガとかね。それをやっているとかなり時間がかかるから、そのうちに作曲のモチベーションが下がってしまう人もいっぱいいます。ちゃんと勉強すればするほど遠ざかってしまう。最初から好きで作曲をやっていると、その距離が乗り越えられないこともある。
子どもながらにおもしろくてやってきた人たちと、専門的な技術を学んできた人たちのスタンスは明らかに違うから、最初の時点ではそういう問題がやっぱり大きい。ただ、どっちがいい作曲家になるかは全く別問題ですよ。
国谷
先生はどちらですか?
小鍛冶
僕は中学生のときに、それなりに作曲を勉強するというところから入ったので、中学・高校あたりは技術的なことばっかり学んでいたかもしれません。自分で何か作曲することもありましたけれど、まずはやっぱり基本的な技術を習得することに追われたような。まあでもピアノでもヴァイオリンでも最初は同じですよね。
国谷
おもしろかったですか?
小鍛冶
そうですね。そこはある種の相性みたいなものがあって、そういうことが好きな人もいるし。僕はそれほどでもないですけれど、楽譜を書くのが好きだという作曲家もいますよ。
国谷
特に衝撃を受けた作品とか作曲家はいますか?
小鍛冶
中学生のときにたまたまワーグナーの《トリスタンとイゾルデ》を聞いたんです。内容的にませていますけれど、音楽的には非常に衝撃というか感銘を受けて、さっそくその楽譜を取り寄せた。楽譜といっても、オーケストラスコアじゃなくてピアノ編曲の楽譜、ヴォーカルスコアです。それを自分で弾いて、その曲を体験するというか、より知ろうしたんです。
国谷
中学生のときから作曲指導を受け始めた。そういう歩みが作られるような家庭環境だったのですか?
小鍛冶
私の父親が高校の音楽教員をやっていましたので、授業で鑑賞するためのレコードが家にあったんです。学習用だからいわゆる音楽史的に編纂されたものでした。それを家でよく聞いていて、そのなかに《トリスタンとイゾルデ》第二幕の一番有名な「ブランゲーネの警告」が入っていたんです。当時はなんで警告なのか全然わからなかったですけど、古今東西その場面に惹かれる人は多い。音楽の表現力というかイマジネーションみたいなところに。それで僕もその曲に関心を持って、全曲を聴いてみたいと思ったんです。あとはリヒャルト・シュトラウスの《エレクトラ》というオペラの「エギスト虐殺の場」とか、そういうところも大好きで(笑)。音楽というのはけっこう際どいことを包容していて、強烈な刺激になりうる。あんまり子どもの頃からいろんなことを知っているといけないという意見もありますが、その頃はよくわからないで聴いていました。
国谷
強烈な刺激といえば、先生が思春期を迎えていた頃、それまでとは全く違ういろんな音楽が出て来て、ロックとかビートルズとかも世の中を席巻していました。そこに惹かれてポピュラー音楽の作曲に向かってもおかしくはなかったですよね。
小鍛冶
確かに、そういう音楽に興味があってもなくても聞こえてきましたよね。聞こえてくる分には聴いていて、それなりに興味はあったかもしれないけど、特にそれ以上はなくて、ああいう音楽を作ってみたいとか歌ってみたいというのはなかったですね。
藝大のアカデミズムは、まだまだ

国谷
ヨーロッパ的な芸術音楽に触れて、楽譜まで取り寄せて弾いていた青年が、なぜ現代音楽の作曲を目指していくことになったのでしょう?
小鍛冶
確かに、作曲の勉強を始めた段階では、現代音楽の創作をしていくという刷り込みはないですよね。むしろヨーロッパの伝統的なものとか、自分が好きだからその世界を知ってみたいとか。
《トリスタンとイゾルデ》の次にヨーロッパの音楽史で重要なオペラはクロード・ドビュッシーの《ペレアスとメリザンド》で、これはいわゆる象徴主義ですね。その次は1920年代に作曲されたアルバン・ベルクの《ヴォツェック》。これはもう社会派のオペラと言っていい。最下級の兵士が軍隊のなかで抑圧されて、軍隊の外でも最下層の市民として抑圧されて、そこから最終的に自分の内縁の妻を殺すという殺人事件に至る。そういうものを中学から高校にかけて聴いていたんです。人間の衝動を音楽的なことでしか表現できないからこれらの音楽は生まれたわけですよね。そういうところから、自分がこの先何をやればいいかという見通しを、どこかで感じたかもしれないですね。
国谷
1973年に藝大音楽学部作曲科に入学されて、徹底的なアカデミズムに浸ることになります。電子音楽が登場し、より多彩な音楽が展開されるようになってきたなかでアカデミズムの環境に入って行くと、藝大の授業は世のなかの最新の動きと差があるとか、ここまでアカデミックでいいんだろうかとか、そういったことは思わなかったですか?
小鍛冶
あの…こう言っちゃおしまいなんですけれど、つまり僕はアカデミックな人間だったんです(笑)。藝大に入ってまず、ここのアカデミズムは十分じゃないなと思いました。それは別に僕がどうとかじゃなくて。最近亡くなられた永冨正之先生という、藝大でソルフェージュと作曲を長年担当されてきた方が、僕が中学校のときに習った先生だったんです。元々ピアノを習っていて、ピアノの副科というかソルフェージュや和声を習うという形で永冨先生に教わり、最終的には作曲のほうに行きたいということになったわけです。永冨先生を含めて僕の周囲ではフランスに留学してから作曲活動をしている人が多かったし、そうすると“おフランス臭”みたいなものが染みついちゃうんですよね。
藝大の作曲科も元々、池内友次郎先生という方がいらして、矢代秋雄先生に至るまでフランスのアカデミズムの影響は非常に強かった。外から「藝大は悪しきアカデミズムだ!」と言われたのはその延長線上なんですね。そういう意味で藝大がアカデミックなのは当然だし、僕もそういう勉強をしていた。でも入学して周りを見回すと、他の学生はそんなにアカデミックじゃない(笑)。
ただ、同級生に西村朗くんという、今や日本を代表する作曲家のひとりがいた。彼は全くアカデミックじゃないというわけではないけれど、本能的にどんどん作曲をしていく。それも当然作曲のひとつの在り方だけど、そこまで本能的じゃない人は勉強するしかないじゃないですか。作曲家というと何となく頭でっかちなものだと皆さん思いますよね。でもすごく本能的な部分もあるわけですよ。一種の身体的な感覚というか、そういうものに優れている人が作曲家になって行くケースは非常に多いですね。
国谷
小鍛冶先生にとっては、藝大のアカデミズムは十分ではなかったのですか。
小鍛冶
自分のことは差し置いて、ですけれどね。藝大に入る前から基準というものは知っていたから、それに合わせて勉強をしてきたわけですが、ここに入ってみたら「やっぱりまだまだだな」と感じたんです。
国谷
藝大には現代音楽に照準を合わせた授業はなかったわけですよね?
小鍛冶
その時代の音楽が藝大にリアルタイムに入ってきたわけではなかったですね。ただ、それも聴こうと思えば聴けたわけです。だから先ほどの西村くんなんかは、大阪万博(1970年)のときにカールハインツ・シュトックハウゼンやらなんだかよくわからない現代音楽の洗礼を受けている。やっぱりそういうのってすごく大きいと思う。でも学校としてはそういう方向ではなかったですね。
ヨーロッパでは音楽を学ぶ必然性が違う
国谷
以前、楽理科の土田英三郎先生(現・名誉教授)との対談で、小鍛冶先生はこうおっしゃっています。「結局ぼくらの世代は、ヨーロッパというものがひとつの基準だったのは確かだね。行ってみて初めて、だめだこりゃ、自分たちが勝手に音楽と思いこんでいたものとは全然違う」。留学して、何が「違う」と思われたのですか?
小鍛冶
普通みなさんは「音楽を学ぶ環境」とかって言っちゃうんですけど、そんなに簡単なものではなくて、音楽を学ぶ必然性、音楽を学ぶことによって自分がどうするのかという、本当の切羽詰まった意味みたいなものは、やっぱり自分たちが思っていたものはヨーロッパでは全然違うと。
よく、ヨーロッパでは音楽が社会と密接な関係にあるとか、みんなが音楽を理解しているとか言いますけれど、それは基本的には嘘です。だって音楽というのは非常に階級的なものだし、同時に階級を差別するものですよね。ヨーロッパでどうやって階級が生じるかというと、音楽的教養を持っているか持っていないかです。音楽的教養を持ち得る階級が音楽を再生させてきたわけです。あるいは、歴史的に見ると音楽家たちはそういう上流階級に属しているわけではなく、むしろ下層のほうに属してそういう特定の階級のために仕事をしてきた人たちです。音楽をやること自体にすでに世界が含まれているというか、階級から経済的・政治的問題に至るまで、すでにそこにシステムができあがっているわけです。音楽家は基本的にそれを受け入れてきた種族ですから、決して反抗はしない。
国谷
先生がヨーロッパにいらしたのは1970年代末です。その時代でもそういうものをビリビリと感じたわけですか?

小鍛冶
おそらくフランスは今でもそんなに変わっていないと思います。そういう文化というのは、何があっても変わらない質を持っているんですよ。音楽は決して政治的なものじゃないけど、政治経済的な背景を背負ってしか生じないようになっている。今日それは、王様とか貴族とか教会じゃないかもしれないけれど、基本的に国家とか放送局、フェスティバルといったところがパトロンですよね。それは個々の音楽をひとつひとつ成長させていこうというよりも、もっと大きなくくりで音楽と世界の在り方を管理している。日本は幸いそこまで行っていない。だから違うと。
国谷
反発を覚えなかったですか?
小鍛冶
特に反発も同感もなかったです。それはヨーロッパで演奏会に行ってみるとすぐわかりますよ。フランス人は音楽が好きだとか言いますよね。確かに放送とかを通して聴いている方はいっぱいいますよ。でも演奏会に行くことは、労働者の階層にとってはかなり縁遠い。ご存知のように、フランスは最も階級制の強い国ですからね。まあ学生はちょっと違いますけれど。
国谷
あまり語学もできない状態でフランスに行き、オリヴィエ・メシアン先生の元で現代音楽の世界に飛び込んだわけですよね。
小鍛冶
というか、あんまり思い切ってやったという意識はないんです。その世界に入ってみれば、確かにわからないことばっかりだ、みたいな。だから、わからなくて大変だ、ではなくて、いろいろわからないことが世のなかにはあるもんだと、楽天的といえば楽天的に(笑)。こういうことは理解すべきなんだろうなって。どこまで理解したかはなんとも言えませんけれども。
国谷
藝大ではアカデミックな教育を受け、一方フランスは当時、現代音楽の最先端ですよね?
小鍛冶
メシアン以降という意味ではフランスは重要なところだと思います。70年代から80年代にかけて。
国谷
若い作曲家としてはすごく刺激を受けたのではないですか?
小鍛冶
そこで普通に刺激を受ければよかったんですけど、ちょっと事情が違っていて。フランス的なものの漠然としたイメージはあったんですが、フランスに行っていろんな音楽会で聴いたりしていると、フランスのオーケストラが演奏するドイツ的な作品というのは、僕が知っている範囲では、何かおかしいんですよ。全然メンタリティが違うから。ドイツの音楽はドイツ人が演奏すればいいというわけじゃないけれど、少なくともフランス人が演奏すると変なことがいっぱいあったんです。それは日本人がヨーロッパの音楽を演奏するのとはちょっと違うけれど、ある意味共通している面もある。僕はたまたまドイツの作品に興味があったから、頻繁にミュンヘンやウィーンに行って演奏会とかオペラを聴いていました。そうすると違いがわかるわけです。
ヨーロッパというのは本当に多様な文化の混合なんですよね。だからどこに焦点を当てるかによって全然、見え方や基準が変わってくる。確かに今日、歴史的に見てもその時代のフランスでの作曲家たちの活動は非常に重要だったと思います。でも、それよりもドイツ語圏に行ってみたいという気持ちのほうが強かったですね。
音楽は人類のひとつの在り方かもしれない

国谷
パリで作曲、ウィーンで指揮を学びました。
小鍛冶
大学時代から、指揮者の山田一雄先生のアシスタントをやっていたんですが、指揮者になりたいというよりも、音楽を理解するために指揮を勉強してみたかった。例えば交響曲を理解するとかオペラを理解するとか、演奏を通してしかわからないことはたくさんありますよね。あと、演奏というのはマナー=流儀ですから、流儀は知るしかない。それでフランスに行ってすぐにドイツ語圏に行きたい気持ちが強くなってきて、結果的にウィーンに移ったわけです。だからどちらかと言うとフランスの音楽文化を批判的に見ていたところはあります。だけどウィーンに行ったら行ったで、「なんてダサいんだ!」って思った(笑)。まあ観点が違うと感じることも全然違う。でも、それぞれに流儀があるということは知らなければいけない。
例えば、ルネサンス以来、音楽家は仕事があれば自分の生まれた国以外でも、どこの国にも行ったわけです。生まれた国でずっと仕事をしたのはバッハぐらい。同じ年代のヘンデルがイタリアで活躍して、最終的にロンドンで決定的な地位を得たように、どこへでも行くわけです。音楽家はどこに行ってもそこの流儀に合わせるし、同時にいろんな流儀を知っていると得だということはあると思います。
国谷
アジア人、日本人というものはどう受け止められていましたか? ベトナム戦争でたくさんのベトナム難民がフランスに来ていた時代です。
小鍛冶
アジア系に対する差別はすごかったと思います。僕はたまたま音楽をやっていたから、先生とか周りの人たちはまったくそういうことはなかったですけどね。でも外に出ればそうです。だから非常に緊張して生活していました。
やっぱり、音楽は世界共通だとか言いますけど、嘘ですよね。
国谷
先生が言うとすごく説得力があります。
小鍛冶
例えばベートーヴェンの交響曲第9番とか、多くの人に親しまれる曲はありますけれど、人類的視点で見たら、「音楽は共有されている」とは僕は信じていないんです。ただ音楽というものが持っている文化としての側面は、その国の政治経済に基づくものだけじゃなくて、人間の本質の、特に“知”の部分―知ること、“知”全体のこと―はやっぱり人間に共有しているものだし、音楽が一番深く関わっているということも事実だと思うんです。だから音楽というのは人類のひとつの在り方かもしれない、とは思います。
国谷
アカデミズムのなかで音楽がそこまでリスペクトされている、高い位置にいるという認識は、おそらく日本ではまだないですね。
小鍛冶
ないですね。
国谷
だからそういう環境のなかで学ぶ、あるいは流儀を勉強するという体験は、相当貴重だったのではないかと思います。
小鍛冶
確かにそうです。音楽というものを介して、世界や国家、民族といったものと、自分の居る位置との距離を測るという意味ではね。
国谷
そういう深い抽象的な学習というのは、日本ではちょっと…。
小鍛冶
そうですね。フランスのパリ国立高等音楽院はアカデミズムの中心地だったわけですが、EU統合以降そういったものがだいぶ薄れてきたのは事実です。だから民族とか国家レベルで小細工をしてアカデミズムを作り上げているわけですね。アカデミズムは抽象的ではありますが、抽象性と実際性と両方理解する必要があるし、音楽家というのはある意味ポリティクスがないとだめかもしれないですね。そうすると藝大のように翻弄されなくて済むかもしれない(笑)。
構造主義から出発し、音楽がもつシステムに目を向けた
国谷
先生はどんな物事から音楽に影響を受けていらっしゃるのでしょうか?
小鍛冶
いろんなものを構築しているシステムから、ですかね。
僕の学生時代に日本で流行っていたのはフランスの構造主義。レヴィ=ストロースとかミシェル・フーコーとかです。レヴィ=ストロースは文化人類学で、世界における人間の在り方の構造性に目を向けたんですよね。一方フーコーは、文化というのは文化を編成するものだというところに目を向けた。基本的な構造性みたいなところですよね。だから音楽も、基本的な政治経済とかそこでの民族的な問題のなかから、ひとつの芸術を編成する方法というのを創り出していて、ヨーロッパはそれを割と大きなまとまりで為し得た。それが西洋音楽だということです。そこを僕の場合は出発点としたんですね。
国谷
作曲をされるときは、何が最初に浮かぶのでしょうか? ポピュラー音楽の場合はメロディが浮かぶという話をよく聞きます。
小鍛冶
作曲するというのは、先ほども言ったようにかなり本能的な部分がある。何か書きたいとか、漠然とこういうものを作りたいというのは、わりと大きな衝動としてあると思います。演奏家も自分のやりたい放題に弾いたら、批判されたり評価されなかったりして失敗する可能性がありますよね。だからみんなそこそこのところでやる知恵を教育されるわけです。
でも作曲の場合は、はっきり言ってこれが何なのかわからない場合がある。ショスタコーヴィチが旧ソ連体制下で体制に批判的な意味を込めて作曲しても、誰も理解できなかったわけです。理解できないんだからやってもしょうがないというところもあるんですけれどね。

僕の場合は、人間に知のシステムがあるように、音楽にもシステムがあるべきじゃないかと思っていて、何かをそこで表現するからシステムを作るんじゃなくて、システム自体が何かを生み出すような作曲の仕方に関心があります。作曲は自分で方向性を考えて創り上げていくものではあるけど、これが自分のスペースだという決定的なものではなくて、人間の在り方を通して何か創造的なものが生まれるようなシステムというか、そういうものを作曲に反映したいと考えています。出てきたものがすべてだという考え方も当然あるし、それは一種の音楽作品の宿命みたいなものです。ただそこにおいて何を見ているか、極端に言えば何を夢見ているかっていう話です。そういう意味で創作というものを考えて、それを原点に創作したいと思うわけです。
国谷
そこに人間の知のシステムがあるということが前提で、先生はそのことを周りの人に感じてもらいたいのでしょうか。あるいはそのシステム自体を先生が描きたいのでしょうか。
小鍛冶
僕が書いた音楽に対して、共感というか共有すべきものがあると感じてもらう必要はあると思っています。そうでなければ自分で勝手なことを言っているだけですから。それは僕だけじゃなくて、例えばベートーヴェンも、ブラームスも、あるいはシェーンベルクも、やっぱりそういう人間と世界、あるいは人間と音との独自のシステムを所有しているわけです。その辺になってくると分析が不可能なんだけど、ただ分析の先にはおそらくそういうものがあるはずなんです。だからそういう意味では、ヨーロッパ的な音楽思考というのはおそらく地球上で唯一そのレベルに到達したものだと思います。たくさんの民族音楽とかがあって、それぞれ多くの人が共感する音楽というか文化があるわけですけれど、それを越えてより普遍的な人間の在り方に至るものに関心を持ったのがヨーロッパ音楽だと思うんですね。それを僕はヨーロッパで学んだというよりは、ヨーロッパ音楽を通して学んだと確信しています。
アカデミズムは人間の知のシステムと全く異なったものというわけではなくて、システムとしてのひとつの現れがアカデミズムなんです。アカデミズムとの距離感というか、そこを参照しつついろんなシステムを正確に見ていくことが必要なので、基準という意味ではアカデミズムは重要なんじゃないかと思います。
国谷
うーん…すごく深いお話ですね…。先生がおっしゃっているようなことを考える人は、日本では少ないでしょうね。
小鍛冶
音楽家は考えないんですよ。変にものを考えてはいけないって、音楽家はまず教えられます。特に器楽はそうですね。順応性がもっとも大事です。結局それで自分の社会的な価値付けが決められていくわけじゃないですか。評価というのはかなり恣意的なものですよね。評価は作られる。だから評価の方法を音楽家は学んでいくわけですけれど、なかなかうまくいかないですよね。
国谷
音楽家は考えてはいけないとおっしゃいましたが、先生はすごく本質的なことを考えて、自分の本能あるいは衝動をベースに作曲をしていらっしゃるようですけれど…。
小鍛冶
そう、だから結果としてこんなもんです(笑)。失敗したとは言いませんけどね。
- 1
- 2