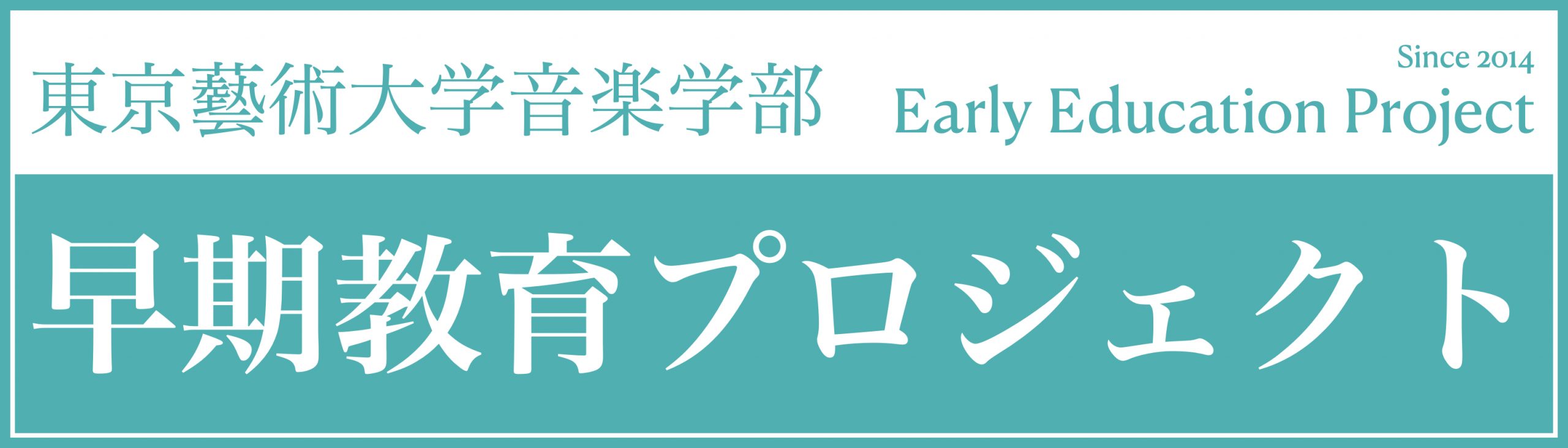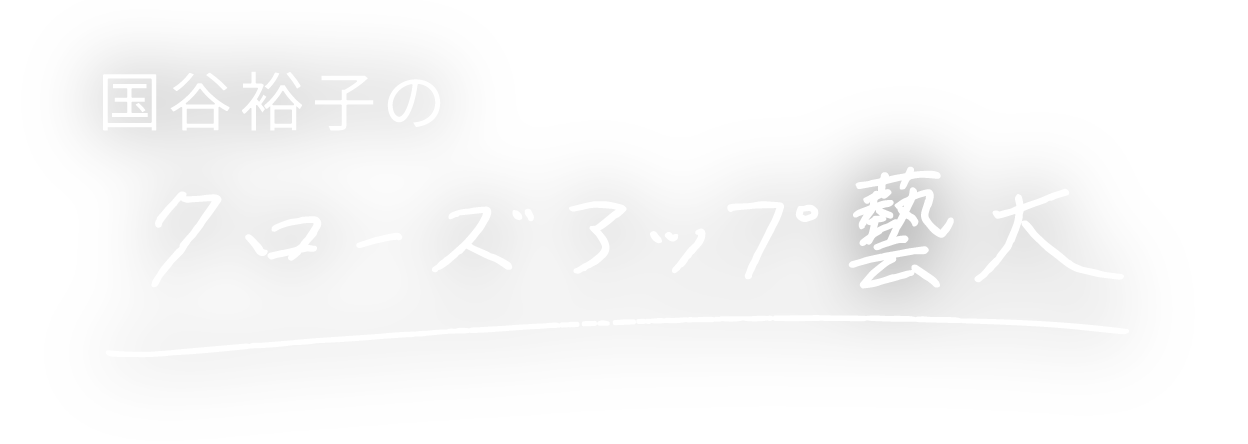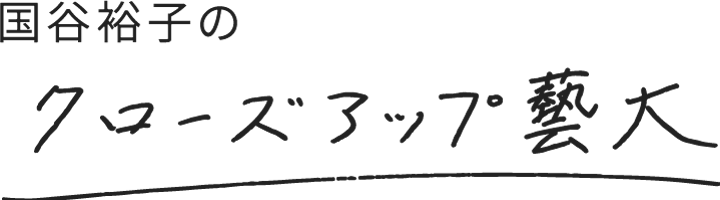第十七回 薄久保香 美術学部絵画科准教授
>> 前のページ
作家は自分中心的な考えに陥りがち
薄久保
岡倉天心先生はすべてのアーティストにつながる大事なことを語っています。「自己中心的な虚栄というものは、芸術家、鑑賞者いずれの側であっても共感を育むうえで致命的な障害となる。」。それぞれが自由に考えることは大切ですが、勝手に自由にしっぱなしなことによって、独善的になる危険がひそんでいます。
ドイツの社会学者のエーリヒ・フロムも、これに繋がるような言葉を残しています。「私たちはナルシシズムにゆがめられた世界を見ている」と。私たちは知らないということによってバイアスがかかった状態で物事を見てしまう。無知が原因の恐怖によって世界はゆがめられてしまう。けれどもナルシシズムの対局には客観性があって、客観性は世界をありのままに見る能力と言えるかもしれません。世界をきちんと見る力を、ナルシシズムと客観性という言葉を使って説明しているんですが、本当に重要なことだと思います。
なぜ重要かというと、客観性の元で作品を考察すると、必ず過去の歴史や作家との接点を見つけることが出来ますが、作家は自分の表現が何なのかを一人の感覚の中だけで考えていると、自己中心的な視点に陥りがちなんですね。これは、自ら可能性を狭めることにもなるし、けっこう怖い。だから知識を身につけたり、あるいは発表することによって鑑賞者と対話したり、いろいろな視座から作品を見ることによってその恐怖から離れて行けるし、成長できるのかなと思います。
国谷
恐怖から解放されるのでしょうね。
お話を聞いていて、アメリカで911のあとにインタビューしたマーティン・スコセッシ監督の言葉を思い出しました。アメリカが初めて国外から本土を攻撃された大事件の直後です。スコセッシ監督は、「無知は恐怖を生み、恐怖は憎しみに変わる」とおっしゃっていました。当初アメリカは、自分たちがなぜこんな憎しみの対象になったのかと反省して、相手を理解しようという気運もあった。しかし、やがて愛国心、ナショナリズムがどんどん高まって、恐怖が憎悪に変わり、アフガニスタンやイラクへの攻撃につながっていった。いまおっしゃったナルシシズム、恐怖に向き合うなかで客観性が失われていく。

薄久保
すごくわかります。そうなんです。知らないことによって襲い掛かる恐怖と、そこから生成される憎悪というものが、作家を建設的に成長させる上で危険な存在になると思うんですね。そういうものが面白い表現につながるという見方もできるんですが、やはり我々アーティストは多角的に考えて世界をとらえるべきだと思います。
作品は自分の分身のようなものでもありますが、いったん距離をおいて客観的に見てみることが必要だと思います。いろんな意見や考え方にさらされることによって、作品はそのポテンシャルを超えて真の強さに到達できる。だから、そういう視点の持ち方はやっぱり訓練すべきだと思います。
国谷
そういうことを学生に伝えていらっしゃるのですか?
薄久保
徐々に、ですけれども。自覚的であるにせよないにせよ、誰かが作る表現というのは、脈々と受け継がれてきた美術史の、どこかに絶対に接点を持つんですね。作品を作ることはゼロから1を生み出すみたいな言い方をされることがあるけれど、私はそうは思いません。むしろ既に起こっている100の、100を丸ごと知ることは難しいかもしれないけれど、100を知っていく中で次の数字というか、何を新たに提案できるかということだと思っています。あと、個々の表現者は分断された存在ではなく、我々は地続きでつながっているということも大事だし知ってほしい。グローバルな表現をしていく中で日本人としての考え方も問われますし、自分の作品がどういう位置にあるのかを考えて、作家としてどんな言葉で、どんなふうに発信すればいいのかを考えることも、学生には重要なテーマとして話していますね。
河井寛次郎に気づかされた視点の転換
国谷
若いアーティストは自分の思いとか主体的な表現を目指す傾向が強く、こう表現したいと自分を突き詰めると思っていたのですが、薄久保さんは「主体的なことには限界があってむしろ我を手放し、未知の世界で生かされているということを認識するほうが豊かなのだ」と、我を手放したときにはじめていろんな可能性が開かれてくるということを繰り返しインタビューなどでおっしゃっています。どのようにしてそういう思いに至ったのでしょうか?
薄久保
これは私の作品にも精通する重要な考え方です。私という一人称の世界から制作は始まりますよね。私が描く、私が活動する、私が展示発表して、私の作品が好きな人、嫌いな人みたいな。そういう一人称でしか考えられない、ゆがめられた世界からどうしたら自分を救済できるのか。この問題を考える中ですごく気づかされたことがありました。京都に民藝運動の立役者の一人でもある河井寛次郎の記念館があって、そこに初めて行ったときのことです。河井寛次郎記念館は彼の生家で、アトリエもあって庭もある。そこに「鳥が選んだ枝、枝が待っていた鳥」という寛次郎が書いた詩があって、本当に庭の木の枝に鳥が止まっていたんですね。それを見たときに「これだ!」って。すごく言語化しづらいんですけど、ヘレン・ケラーが水のことをwaterって認識したときみたいに、自分の中ですごく気づかされたんですよね。私は鳥で、一生懸命どこかの枝に止まろうとしているけれども、枝のほうが私を選んでいるって、すごい視点の転換だなと思って、「アートはこれなんだ!」って。

国谷
主体ばかりではないと。
薄久保
頭ではわかっていたけれど、寛次郎の詩と庭の風景の中で実感したんですね。
一人称で考えると対立構造が生まれ、対立構造が発展していってやがて戦争のような大きなものにもつながっていく。特に悪か正義かという二元論は非常に危険な考え方です。
国谷
911のあとでは、あなたは私たちの見方か敵か、どっちなんだといった考え方が広まって行きました。
薄久保
でも生活していると免れられないことも多いですよね。子どもの頃から二択のうちどちらかを選択してきた思考の習慣もある。例えば学生の中でも、作品が「売れる、売れない」「有名か、無名か」とか、二元論的な考え方に陥りやすい。まったくそういう単純は話ではないし、やっぱり思考の仕方を基本から考えないといけないと思います。
国谷
受け身だと思われている枝や草花が、実は自分たちの思考や行動を動かしているかもしれないと、若いときにそういうものの見方ができるようになった。薄久保先生はまるで若くして老成されているみたいです。
薄久保
そういうことを意識的に考えようとしたのは、欧米で作品を発表するようになったことが大きかったですね。国内にいるときは欧米的なものを見ようとするけれど、欧米に作品を持って行くと文化的な思想とか意識がすごく問われます。その最初の経験が二十代で、そのときに私は自分のバックグラウンドを何も知らないし、自分なりの思想を無意識には持っていたと思いますが、言語化することができなかった。それで意識的に探そうとしていたんだと思います。
アートがものの見方を教えてくれる
 “neko and matière” Oil on panel 130x130cm 2021
“neko and matière” Oil on panel 130x130cm 2021
Photo by:Kotomi Yamagami
 “The bird mask” Oil on panel 90x90cm 2021
“The bird mask” Oil on panel 90x90cm 2021
 “the branch chosen by the bird, the bird the branch was waiting for”
“the branch chosen by the bird, the bird the branch was waiting for”
Oil on panel 2019 Photo by: Nobutada Omote
国谷
薄久保さんの作品は、写真を映し、それを元にCGドローイングで画像を再制作されて、最後はアナログで自分が肉体的に筆をとって描くという方法で生み出されていますが、アナログ的なものにこだわるのは何か理由があるのですか?
薄久保
そうですね…。つまるところは、私たちの魂がこういうアナログな肉体に収まっているということにつながっているのかなと思います。デジタルなのかアナログなのか分断しないことが重要で、スマホの中のリアリティもひとつのリアリティ。私の作品をスマホで見ると何なのかよくわからないんですよね。
国谷
写真にも見えるし、CGっぽくも見えます。
薄久保
写真なのかな、CGなのかなって。そして実物を観たときに、「違うんだ!平らなイメージじゃないんだ!」とわかる。スマホの画面の中にも実物と対峙した瞬間にも、それぞれのリアリティがあるんですよね。これは多角的であるということにもつながります。それと、私が人の作品を観るときに勝手に思っていることなんですけど、作家が長い時間をかけて向き合ってきた作品には、オーラというか何かよくわからないものが宿っていたりします。もちろん筆致の痕跡とか、そういうものを追うこともひとつの見方ですし。
この世界が映画の『マトリックス』みたいに完全にメタバース的な世界で完結するようになったらわからないけれど、今はまだ私たちは人と人であり、肉体を手放さないで生きている。そういうところとペインティングという形態がこの時代の重要なフックになるような気はしています。
国谷
世界の課題解決に対しても、アートの力やデザインシンキングが有効だとかいろんなことが言われています。薄久保さんは「AIの時代、これからは必ずクリエイティブな思考が求められる。アートはこれからの時代を切り開いていく大きなヒントになると思う」とおっしゃっています。なぜそう思われるのでしょうか?
薄久保
人工知能については私もプロフェッショナルじゃないので明確には言えませんが、人工知能は、合理性を持った問題に対しての解決は非常に優秀に働くのだと思うんですが、いかんせん我々人間は矛盾しているし、心とか感情という数値化することが非常に難しいものを抱えています。そういうこと自体を考える装置としてアートがある。アートがいろんなものの見方を教えてくれると考えています。
私は絵を描いていますが、文学や詩も好きで、そういったすぐには役に立たないとされるものから、結果的には一番大切なヒントを得ていたんじゃないかなと思います。これからのことを考えようとするとどうしても最先端のことに目を向けるけれど、その根底にある考えはすごく昔からある。紀元前ローマ時代から対話されてきたこともあるし、寛次郎の詩の中にもあらわれています。いろんなところにキーになる課題はあると思うんですね。そういうものとアートって常につながっているし、そのあたりのことを多分言いたかったのだと思います。
国谷
人々の感情を揺り動かしたり、先ほどおっしゃったナルシシズムや未知なるものへの恐怖といった葛藤を抱える人に寄り添ったり、癒やしたり、考えるヒントを与えたりすることは、AIにはできないと思いたいです。そういう、人間にしかできないことをないがしろにしてほしくないですね。

薄久保
考えなくていいことが増えるのであれば、その分できた時間で本を読んだり作品を観たりするといいと思います。なんでかというと、すぐには役に立たないところが魅力なんです。役立つことはすぐに提供してもらえるだろうし、解決されちゃうので。我々は、すぐに解決しようもないような、まったく役に立たないようなことをもっと考えたほうがいいのかもしれません。絵も役立つものではないし詩も読む必要はない、生活しているとどんどん遠ざかっていくものですけれど、こういう時代のなかでもう一回近づいてみるのもいいかなって。
アートの面白い部分と貫通する
国谷
今の学生たちに一番伝えたいこと、これだけば学んでほしいと大事に思っていることはどんなことですか?
薄久保
まとめて言うと、魂を耕すことが重要だと思います。「cultura animi(魂を耕す)」というローマのキケロの言葉について、最近はよく考えています。魂は元々自分に備わっているものですけれど、それを耕すことが重要なんですよね。「Cultura」は英語やフランス語の「Culture」の語源でもあります。Cultureは文化だし、もちろん教養という側面もあって、教養はキーワードになると思うんですね。持っている素養とか才能を放りっぱなしにしておかないというか、それがやっぱり耕すことにつながっていく。美術史的なこともそうですけど、外からの知識をきっちり取り入れたうえで、自分が何なのかということを、客観的に見られるようにするのが大事だと思います。小さな畑はひとりでも耕せるけれど、文化はひとりではできない。そうやって得た興味や表現は、あとあと見てみると自分以外の何かとつながって、ひもづけられている。そこから新しい文化がつくられていくんじゃないかなと。学生たちにはそういうことを伝えたいと思います。
国谷
素晴らしいと思います。薄久保先生ご自身も、自分の作品は何なのかって、ずっと研究していらっしゃいますよね。
薄久保
そうですね。今も。
国谷
自己研鑽というか、耕すことをご自身も続けていらっしゃる。
薄久保
続けているとアートの本当の面白い部分と貫通する瞬間があるんですよ。表面的な面白い面白くないを超えて、本当のうまみの部分に到達できるというか。このポイントというよりは、ずっと続けてきているから感じられるようなものかなあと思います。
国谷
なるほど。すてきな感覚でしょうね。自分の作品と他の何かが通じていると感じる。
薄久保
自分のことをいいように言い過ぎちゃったかもしれないですけど。
国谷
いいえ、同じようなことをデザイン科の箭内道彦先生もおっしゃっていました。箭内先生は、貫通ではなく、開通とおっしゃって。開通するとエンドレスモードに入ってクリエイションができるんだというお話をされていて、薄久保先生の今のお話と箭内先生のお話が私のなかでは貫通しました(笑)。
薄久保さんの授業は、一緒に答えを導き出すスタイルで学生たちからの信頼も厚いと聞いています。
薄久保
学生と歳は離れていますけれど、私も同じように一人の表現者として完成されていないし、今も模索中です。なので、上に立って何かを教えてあげるのではなく、制作は勝ち負けじゃないですけど学生のエネルギーに負けないようにしようというか、そういう気持ちも大事だと思います。対話というか、彼らの話を聴くことを大事にしています。学生たちはいい刺激をくれるし、逆に大事なことを伝えてもらっているから、本当にサンキューっていつも思っています。

【対談後記】
2時間近くに及んだ会話で最も多くの時間を費やしたのは、薄久保先生が最も大事にされている「魂を耕す」思考の仕方、物の見方でした。
「アートというのは世の中に山と積まれている物事から、まだ課題かどうかもわからないものを抽出して、それに対して何かリアクションをし続けること」と主体的に考えることの大事さを強調していた薄久保先生。その一方で主体的な考えがゆがめられた世界という危うさを持ち限界があるとして「我を手放す」ことでより豊かになれると自らの体験を通したその気づきについて熱心に語ってくれました。
【プロフィール】
薄久保香
美術学部絵画科准教授
栃木県生まれ。東京造形大学造形学部美術科絵画専攻を卒業後、ゲーム会社に就職。その後、退職し、東京藝術大学院美術研究科にて博士号を取得。現在は、東京と京都に活動拠点を置いて制作をしながら、東京藝術大学美術学部絵画科で准教授を勤める。
主な展示に、「Wandering season」(TARO NASU、東京、2007)、「crystal moments」(LOOCK Galerie、ベルリン、2011) 、「横浜トリエンナーレ2011」(横浜美術館,横浜2011)「Kaoru Usukubo, Hannes Beckmann」(LOOCK Galerie、ベルリン、2017)、「Kaoru Usukubo and Daisuke Ohba」(LOOCK Galerie、ベルリン、2020)、「SF-Seamless Fantasy-」(MA2 gallery、東京、2021)
などがある。
https://www.kaoru-usukubo.com/
撮影:新津保建秀
- 1
- 2