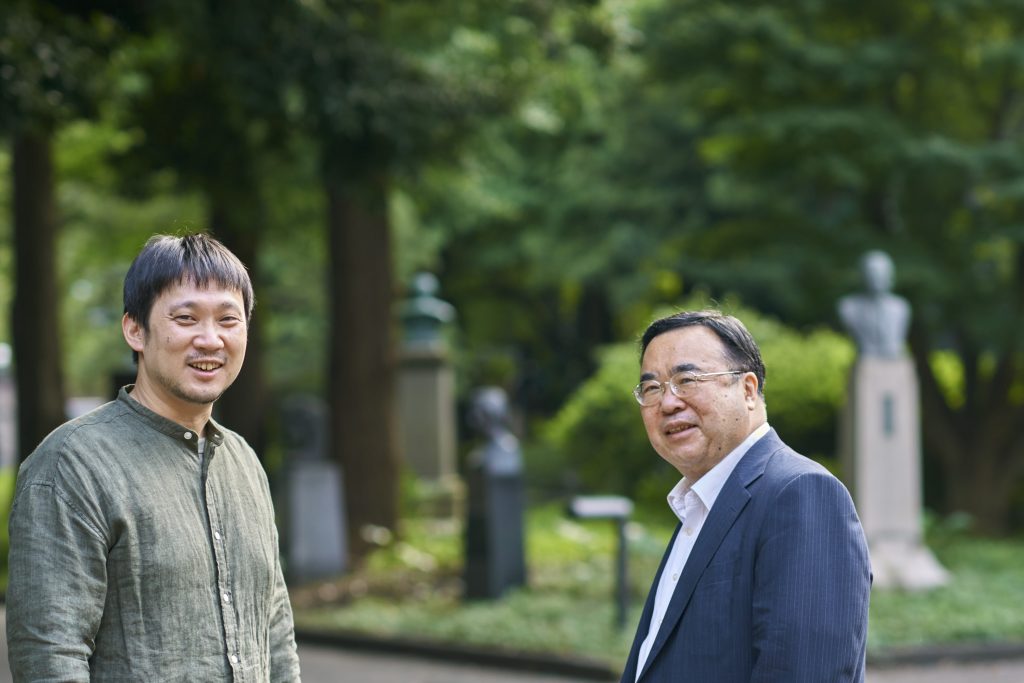
第五回 濱口竜介
澤
ここで映像研究科映画専攻の学生の皆さんからも質問をしていただきたいと思います。脚本領域の菊地真里那さんからお願いします。
菊地

先ほど、どんなキャラクターを描くときでも、まったく自分と違う人間だとは思わずに描くとおっしゃったのが印象的でした。私は普段脚本を書いていて、キャラクターの関係性を作るのがすごく難しいと思っていて。『ドライブ・マイ・カー』で主人公の家福を演じた西島秀俊さんがインタビューで、演出の中で家福として濱口さんから質問を受けて答えることがあったとおっしゃっていました。それはその人物に近づいたり、その人物を掘り下げるための手段なのかなと解釈したんですが、キャスティングをする前の脚本段階で人物を掘り下げるときに、濱口さんはどういうことをなさっているのかお聞きしたいです。
濱口
脚本はいつまでやっても本当に難しくて、正解がないなと思います。今から言うこともうまくいく時といかない時があります。まず構成の段階では僕の場合はあまりリアリスティックに考えずに、面白くするにはどういう構成が必要かを考えます。そうすると、こんな行動しないだろうという人間がたくさん出てくる。リアリスティックに考えると何も起こらないこともあるので、何かを起こすために変な行動をする人物がたくさん出てくるわけです。じゃあこの人物たちがこう動くのには一体どういう背景があるのかということを、構成ができた時点で考えます。そのために、『ハッピーアワー』という映画を作ったときに開発した17ぐらいの質問があります。仕事は何をしているかとか、何が好きで何が嫌いかとか、登場人物に対して質問をする。構成ができているってことは登場人物は何か行動していて、行動してるってことはその背景にその人物の行動原理があるはずなので、その人物の行動原理を、物語構造に即して想像しながら17の質
それは一人相撲みたいなところもあるけれど、人物の肉付けみたいなものができるし、自分にとってその人物に関する情報が増えていくっていうことが、その先に改稿なんかをしていく上でも重要なんですよね。ただこれは絶対的なものじゃなくて、構成が変わって行動が変われば書き直さなきゃいけない。でも架空の人物とはいえ、その人物のことをよく知っている方が脚本として書きやすくなります。僕はあんまり人物そのものからは発想できなくて、たとえすごく非現実的な物語構造であったとしても、その構造の中でその人がある程度現実的に行動するとしたらどうするかということを考えます。そうすると観客も、変なことをするけれど何か理由があるんだろうと思えるようになる気がします。そういう現実的な厚みや立体感を登場人物が持つようになる気はします。
菊地
すごく参考になります。質問をするっていうのをやろうと思ってがんばっているんですけど、やっぱりいろんな登場人物の差異を出そうとすると、自分の中から出てくる言葉も載ってしまうので難しくて。でも今お聞きして、構造も考えつつやろうと思いました。
濱口
そうですね。構造の中にはそもそも自分ではない人物がいるはずなので、自分とはまったく違う人物がどう行動するかも、結局自分自身のものの見方の中で考えるしかない。それはまあ、脚本の面白いところと思ってがんばる。あと、他の人と一緒にやるのも1つの手だと思います。映画ならではの共同作業というか、他人の視点が入るだけですごく立体的になることは経験上あるので。
菊地
先ほど幼少期のお話で、ひとりで極める趣味が軸になっていて映画にもつながっているとおしゃっていました。実際に映画を作るのは全くひとりではなくて、共同作業も多くて矛盾するところもあるじゃないですか。ひとりで孤独に突き詰めなきゃいけないところもあるし、人と一緒にやることで豊かになるところもある。でも、元々ひとりで極めることが発端だったとすると、心の負担というか、バランスみたいなものをうまく保てなくなるのではないかなと思って。
濱口
これはおっしゃる通りで、人とやるのは大変ですよね(笑)。僕はそもそもは内向的で、ひとりでいる方が楽な人間なので、共同作業というのは常に気が重いというか、企画を考えるときはまたあの辛い日々が始まると思うと嫌になるっていうのが正直なところです。でも、楽しいことと辛いことってかなりセットでして。映画は本当に自分ひとりじゃできなくて、自分を無理やり開いてくれるようなところがある。自分にとってはその制作をやることでバランスが取れているようなところもあります。大変ですけど、それはやっぱり代えがたいことなのかなと。辛いことはありますが、それに勝るぐらいの楽しさを感じられるか否かだと思います。

菊地
映画作りの中で辛いことも楽しいこともありつつ、でもやっぱりスランプとかで行き詰まったときに、濱口さんは何をされていますか?
濱口
行き詰まった時はもう進まないってことなので、何か別のことをするしかない。それは別のプロジェクトをやることかもしれないし、多くの場合はインプットですよね。映画を観るでもいいですし。ものすごく大量にインプットすると何か体が変わってくるような、自然と物事が進みだすような感覚があるので。ただこのやり方がこれからも通じるのか、わからないですけどね。
菊地
そのインプットっていうのは映画に限らず他の趣味とかですか? 映画以外の濱口さんの趣味は何ですか?
濱口
映画以外の趣味か…。恥ずかしながらあまりない(笑)。いやいや、でも本を読んだり美術館に行ったり、人と話したりすることもあります。
菊地
濱口さんは脚本について、原作を逐語的に脚本にしていくということではなくて、読み込んでインプットしてそこから出てくるものだと、以前お話されていました。『ドライブ・マイ・カー』は具体的にどういう時間の流れで、初めて読んでから脚本まで行ったのかをお聞きしたいです。
濱口
最初に文芸誌で発表されたときに読んで、さらに出版された時にも読んで、企画を立てる段階でもう一度読みました。小説の文章をそのまま映像に移し替えるのは不可能ではないけれど、それで面白くなる、文章の魅力が再現できるということはほぼないと思うので、この小説のどの部分が映画になるのかを見極めるために、まずは何度も通して読むことですね。その際に逐語的に拾って読むタイミングもあります。気になったところをメモするような形で読むということをしました。ただ、やはりそれもそのまま映像化することはしない。こういうのは全部「時間をかけてそれと付き合う」方法なんだと思います。時間をかければ自然と小説の言語化できない部分が自分の体に馴染んできます。それが書く原動力になる気はしますね。大きな改稿が何度かあったんですけど、その都度そのような読み方へと戻りましたね。
書くときは、何が原作だとかそんなに考えないというか、キャラクターや大まかな出来事程度は決めておいて、自分の考える映画的なものになるように脚本を組み立てるという感じです。でも『ドライブ・マイ・カー』の場合は映画的にという以上に、単に面白くなるように考えましたね。それで書いていくうちに、拾っておいた要素が必要なところにはやってくる、ハマっていくという感覚があります
菊地
とても参考になります。ありがとうございました。
澤
では監督領域の木村愼さんお願いします。
木村

まず1つ目は、言語による対話をどのくらい信じていますか?という質問です。映画制作の課程においては役者さんやカメラマン、技術者とかと言語でやりとりをしないといけない。そこにはジレンマみたいなものがあると思うんですけど、そのやりとりにおいて言語をどのぐらい信じているのかをお聞きしたいです。
濱口
信じるも信じないもなくて、具体的なことは具体的な言葉で伝えてやってもらうしかないですよね。でも例えば「なんかここで大きな悲しみがこの画面全体に宿ってほしいんだ」みたいなことを言うと、スタッフがポカンとするわけです。抽象的な言葉遣いをすればそれだけコミュニケーションは難しくなるけれど、具体的なコミュニケーションをしている限りはそんなに間違いは起こらない。だからまずはその具体的な言葉にどの程度自分のやっていることを落とし込めるかという問題があります。そこは自分はある程度自覚的にやっていると思います。抽象的な言葉遣いは基本的にはあまりせず、具体的な言葉とか行動が最終的に自分の考えている映画になるように、できるだけ言葉を選んでいます。共同作業をする上では、間違いのない言葉を増やしていくのはとても重要だと思います。
とはいえそれだけではコミュニケーションは成立しないし、やはり貧しいものになってしまう可能性もあるので、すごく抽象的なことを話さなきゃいけないときもあるとは思います。言語化できないことは言語化できないこととして表現したほうがよいこともあります。そういうときはやっぱり難しいなとか、なかなか伝わらないなって思います。でもそれはそういうものですよね。
相米慎二さんという監督がいて、昔そのスタッフの方にインタビューをしたんです。監督に「真っ白いスクリーンがある。お前の仕事はそのスクリーンの上で何になるんだ?」とよく聞かれたそうです。それを考えろと、ひたすら相米慎二は言っていたと。これは具体的なコミュニケーションと抽象的なコミュニケーションの間みたいな感じですよね。言っていることはわからなくはない。ただ問いかけだけがあって、何か正解があるわけでない。でもそれはスタッフに考えさせることになるし、確実にそのスタッフの仕事が最終的にスクリーンに反映される。そういう言葉の使い方は自分にはすごく難しいけれど、憧れるところはありますよね。
木村
技術者さんとか役者さんとかとはそういう話があるとして、次に社会に対して、要するに映画を観る人に自分が伝えたいものがあったときに、その伝えたいものが抽象的で、固まったものではない場合はどういうふうに映画に落とし込んでいきますか?
濱口
個人的には、何か抽象的なテーマがあって、それを映画で表現しようとは全然考えていないんですよ。脚本を書いたりする中で、手触りとしてこうなった方が面白いなということの積み重ねなので。それはやっぱり抽象的なものを映像に変換することが難しい、と言うかあまり面白くないということを、僕自身が考えているからだと思います。具体的に出てきたものが観客にどう作用するのかだけをひたすら考えるというか。なので、メッセージをどう伝えるかということを、実はあまり考えていない。たださっきも言ったように、人物たちがちゃんと動いていけば、自然と観客が読み取る何かが生まれるとは考えています。
ただ、おそらく企画をプレゼンする、という局面を想定されていると思うんですけど、ここでも一番いいのは抽象的じゃなくて、できるだけ具体的な形に落とし込むことですよね。映像化の前の段階では脚本ですけど、それだけでは映像化したものが上手くイメージできなかったりする。そこで「過去作」というものがあると、プレゼンを受ける側がこの場面をこういうテイストで映画化するんだな、面白そうだな、と思えたりする。重要なのは、自分が抽象的に想像しているものを他人と共有するのはほとんど不可能だ、という前提に立つことだと思います。
後はやっぱりそもそも「話のわかる」人にプレゼンする、ということですね。自分と元々価値観が近しいとか、「あの映画のあの場面」と言ったら具体的にパッと想像し合えるとか、よくわからないけど信頼し合える、とか。ただ、そういうものの分かった人は必ずしも映画製作に十分にお金を持っていないということも往々にしてあります。そういうときは、その予算があればできることから考える、ということではないかと思います。兎に角、具体的な「できること」から始めるしかないのかな、という気がします。
木村
ありがとうございます。次の質問なんですけど、娯楽映画と芸術映画という比較がされますが、娯楽と芸術って別物でなくて1つの軸上に繋がっていると思います。濱口さんはその軸上のどの辺を狙って作っていらっしゃいますか?
濱口
修了作品の『PASSION』を作っている時に、黒沢清さんに相談したんですよね。観客に対するわかりやすさみたいなものと、自分の作家的なこだわりみたいなもの、どっちを優先したらいいんですかと。メールで聞いたのかな。そしたら「圧倒的に正しい映画というのは作家映画と商業映画の中間にある」と返信に書かれていて、黒沢さんの言葉というのは不思議で、何か普通のことを言われたような気もするけど、すごく腑に落ちたりするんですよね(笑)。僕も自分の経験に照らして、面白い映画とは、まったくもってそういうものなんだろうなと思います。だから僕もその中間に狙いを定めて、常にバランスを考えています。

木村
中間を狙っているということですね。ありがとうございます。濱口監督はよく国内で制作してそれを国外で披露されていますけれど、作る過程で何か注意して、外の世界を意識しながら作っていますか?
濱口
これは信じてもらえるかわからないんですけど、作っている時は海外の映画祭に行けるかどうか、対外的にこの映画が価値のあるものなのかどうかは全然わからないんです。たとえば『ハッピーアワー』は5時間ぐらいある映画で、本当に「これ誰が観るんだ?」って思いながら作っていたけれど、自分たちは作ること自体、意義あるものとして作っていた。今ここじゃなくても、誰かがどこかで、いずれ見てくれるだろう、ぐらいの期待で作るわけです。その際に、何を基準にして作っているかというと、自分自身が映画を観たり作ったりしてきた中でできた基準に沿うものを作っているわけです。その基準の中には、観客としての自分の楽しみもあるんですよね。それは見る立場になって考えるわけです。そこを信じて、自分の楽しむものをある程度、観客も楽しむとは期待してます。ただ、やっていることが本当に観客が求めているものなのかどうかは、けっこうわからないで作っている。それを幸いにして映画祭が拾ってくれた。『寝ても覚めても』なんかは、あくまで日本の商業映画として、ある程度自分なりにマーケットの要請に従いながら、持っている基準に沿うものをつくる。すると、カンヌのコンペに選ばれたりしてすごく驚くわけですね。作ってみるとこのように日本以外の場所からもリアクションがあったりするので、そこで世の中にはある程度、自分と基準を共有している人がいるんだな、ということがそこでわかるわけです。そこで、自分の基準をある程度信頼して作って構わないんだ、とも思える。なので、理想論かもしれませんけど、結局は自分自身の基準を磨いていくしかないと思います。他人の基準も聞きながら、ですね。特に時間や距離を超えて現在まで届いているものを見聞きするのはすごくよいことだと思います。いずれ自分自身の基準に即して作っていったら結果的に国際的な標準を超えていた、となるように。
木村
自分自身の基準の軌道修正を重ねながら作っているということですか? どういったフィードバックから修正しているのですか?
濱口
作っている最中は、ラッシュ上映がありますよね。ラッシュを観てこれはイケてないって思ったら、可能であれば撮り直すのが理想だと思います。いいか悪いかは、ある程度自分でわかると思うんですよね。自分の思っていた以上のものが撮れたのか、あるいは自分が思っていたのと違う、芯を外れたものになっているのか。上映して観客に見せたときに気づくこともある。最近は観客の反応がかなりビビットわかりますよね。こういう風に見えるんだという学びを得ることはある。まったく自分が想定してない反応ならば、明らかな誤解が起こらないように次はどうやればいいかを考えるしかない。
木村
僕は毎回自分の作った作品を見て、何が良くて何が悪いのかがいまいちよくわからないので、どういうふうに軌道修正をかけていらっしゃるのか気になっていたんです。難しいです…。
濱口
やっぱり、人の意見は大事じゃないですか。批判を受ければ「何だこのやろう」と思うことはあるし(笑)、自分が失敗したと認めるまで時間がかかることはあるんですけど、人が批判していることには何らかの理由がある。そこには目を向けなきゃいけないのだなあと。その際に、自分が受け止めるべきものとそうでないものを腑分けする上でも、先程言った「自分の基準」というものが大事になってくるんだと思います。でも、それが凝り固まらないように、自分には必ず盲点があって、わかっていないことがあるんだということを頭に入れておくことも大事かな、と思います。あと、失敗から得られることの方が多いので、失敗できるようにしておくことはすごく大事だと思います。
木村
濱口さんは、藝大を出た後でも失敗したことがありますか?
濱口
それは当然ありますね。ただ、1本の中でチャレンジしていく部分とある意味手堅くまとめていく部分の両方を持っていないと、今の日本で映画を撮り続けるのは難しいんだろうとも思います。トータルでは成功したというふうに作らなきゃいけないけれど、失敗するかもしれないというチャレンジ要素を常に抱えておかないといけない。その割合は調整しないといけないんですけれど。
木村
ありがとうございます。
澤
次に、美術領域の劉通さんお願いします。
劉

私は去年、『ドライブ・マイ・カー』の美術応援として撮影に参加しました。大変勉強になりました。
濱口
ありがとうございました。それはどの場面ですか?
劉
千葉と広島の舞台の撮影で、小道具を作りました。広島の撮影は授業があったので参加できませんでした。僕からは簡単な質問が1点あります。今後はどんな物語を撮影したいですか?
濱口
これがわかれば苦労はしないんですけどね(笑)。僕は物語がないと撮れないタイプの監督なので何か物語は撮ると思うんですけど。自分にすごくダイレクトに響くものと、全然よくわかんないものがあるとしたら、ここ最近、特に『ドライブ・マイ・カー』は自分とすごくテーマ的に響き合うというか、自分のそれまでやってきたこととも繋がるものだったので、できれば次は自分がどうやって手を付けたら良いかよくわからないようなものにチャレンジしたいなと思います。
澤
ありがとうございます。学生の皆さんもありがとうございます。
去年、コロナの感染症が広まって美術館やギャラリーがクローズされ、演奏会などのイベントも次々中止・延期になり、多くの芸術家が活躍の場を失っていました。そこで私たちは東京藝術大学若手芸術家支援基金を立ち上げてクラウドファンディングを呼びかけたんです。それをもとに去年の秋ごろから今年にかけて、いろいろな形で芸術家を支援する活動をしています。濱口さんも昨年、ミニシアター・エイド基金を立ち上げられました。コロナ禍の影響で映画産業、特に大きな資本に支えられていないところは大変なことになっている。そういう意味では共通した考えをお持ちなのかなと思いますが、どういうお気持ちで基金を立ち上げられたのでしょうか?
濱口
本当に個人的な気持ちといいますか、僕はそもそも映画ファンで、映画館で映画を観ることが好きな人間であり、特に大学時代にミニシアターでかかっているような映画に啓蒙されたというか、そういう映画を見たから今自分で作っているというところもあります。でもそういう映画館の閉館が目に見えている状況だったので、同じく映画監督の深田晃司さんと映画プロデューサーの大高健志さん、岡本英之さん、高田聡さんたちと一緒にミニシアターを支援する基金をクラウドファンディングで立ち上げました。これは結果的に自分たちもすごく力づけられるというか、ミニシアターという文化が多くの人にとって大事なものであること、多くの人を精神的に支えていることが可視化される機会になりました。それは映画館の人たちにとってもすごく力強いメッセージになったと思うし、僕たちも制作者として改めて映画館の中で生まれる体験の強さを再確認しました。でもそれはもう去年のことです。去年のように全く営業できない状況ではないけれど、今年も閉館してしまった映画館はある。今まさにどうしたらいいのかと思っている最中です。

澤
若手芸術家支援基金もミニシアター・エイド基金も、一時的にしか救うことはできないですよね。
今はインターネットやいろいろなツールで芸術を鑑賞できるし、音楽でもそれなりの音質の演奏を聴くことができる。でもそれで済ますのではなく、ちゃんとライブに行かなきゃダメなんだよと。無料の動画サイトで視聴できるからいいやと思われてはいけないわけです。それはミニシアターの場合も同じだと思うんですよね。
今はコロナ対策で国も大変ですけれど、やっぱり文化芸術に対する国の支援が必要です。民間のクラウドファンディングとかでなんとかやっているけれども、だからといって国が何もしなくていいわけではありません。やっぱり文化芸術を支援する人たちがいるのだから、もっと国が力を入れるように訴えていかねばならないと思います。
濱口
そういう動きが起こってほしいですね。不要不急と言われますけど、芸術が不要ではないことはまず明らかだと思います。このコロナ禍の中でどれだけ精神的な支えになっているか、数値化はできないかもしれないけれど、明らかに1人ひとり覚えがあるはずです。不急ということでは、これはむしろ時間にとらわれない文化芸術の本質なのだと思います。だから「不急」と言われて反発する必要も、恥じる必要もないとは思っています。僕は結構楽観的でまさに不急だからこそ、これからも文化芸術は人々の志とともに続いていくと思っています。ただ、緊急性が高いのは、文化芸術に関わる人の「暮らし」の問題ですよね。勿論、破綻してしまえば生活保護とかもあるわけですけれど、その人たちの暮らしが破壊されてしまうと志だけでは立ち直れないことも増えてくるとも思います。そういう事態が起こらないように、十分な支援をすることは国のスケールじゃないとできないので、文化庁とか政府に今あるものの価値を理解して、一考して欲しいところです。
澤
日本の映画界も大変な状況ではありますが濱口さんのような素晴らしい方が生み出されているので、国としてももっと力を入れてもらうことが、日本の文化芸術を盛り上げる大きな要素になるでしょう。
濱口
カンヌ国際映画祭のアーティスティック・ディレクターのティエリー・フレモーという人がいるんですけど、彼は、日本の映画作家たちにとても期待をしている、とても素晴らしい才能が揃っていると評価しています。しかし一方で、日本では公的な支援がないことがすごく問題であり、才能が出る機会が奪われているという状況があるとも指摘しています。
澤
先日、オリンピック・パラリンピックが終りました。開催国ということもあって、招致が決まった段階から、国はアスリートを育てるために注力してきた。それはやっぱり結果として目に見える形で出てきています。同じような機会が文化芸術にも与えられたら、そうでなくてもこれだけの成果が出ているのだから、すごく大きな支援になりますよね。韓国は2000年ぐらいから文化産業に対して桁外れの支援を行ってきました。韓流映画・ドラマもK-POPも、今すごいですよね。国が力を入れてくれればそれに応えられるものが日本にもあると思います。
濱口
そうですね。海外に行くと、本当に日本の文化芸術の力というものを改めて感じることがあります。西洋の美術の歴史はものすごく分厚いし圧倒されますけど、日本に戻ってきて例えば、上野の美術館を幾つかめぐるだけでも、本当に何でこんな小さな国にこんなに豊かな文化が存在し得たんだろうと思うようなものに出会いますよね。この国の文化芸術のポテンシャルというのはものすごく高いし、世界に誇れるものです。公的支援を注入すれば、
澤
最後に、藝大生や藝大を目指している方にメッセージをいただけますか?
濱口
大学の一番いいところは、映画や芸術に限らず、志の重なる同世代の人たちに会えることだと思います。特に藝大というのは、本当にトップレベルの才能が集まってくるわけですよね。そういう切磋琢磨できる環境ほど自分を育ててくれるものはないと思います。仲間やライバルたちから受ける刺激は本当に計り知れないし、そこから実際、長い付き合いになったりもする(笑)。ここでの出会いを大事にしていくと、将来いいことが起こるんじゃないかと思います。
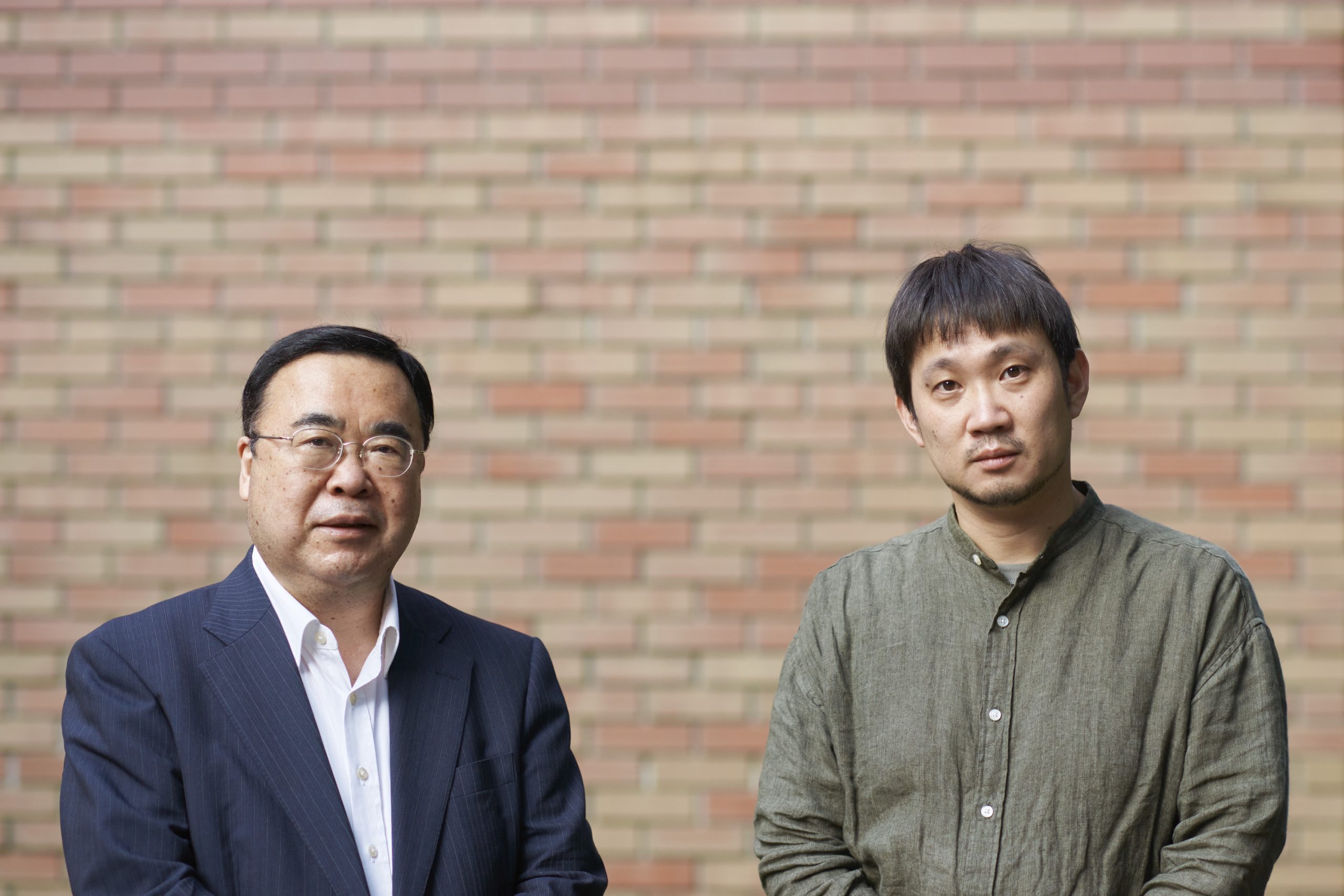
>> 過去のゲ!偉大
【プロフィール】
濱口竜介
1978年、神奈川県生まれ。
東京大学在学中に映画研究会に所属。卒業後、助監督や経済番組のADを経て、東京藝術大学大学院映像研究科に入学。08年、修了制作『PASSION』が国内外の映画祭に出品され高評価を得る。日韓共同制作『THE DEPTHS』(10)、東日本大震災の被害者へのインタヴューから成る『なみのおと』、『なみのこえ』、東北地方の民話の記録『うたうひと』(11~13/共同監督:酒井耕)、4時間を超える長編『親密さ』(12)、染谷将太主演の『不気味なものの肌に触れる』(13)を監督。15年、5時間17分の長編『ハッピーアワー』が、ロカルノ、ナント、シンガポールほか国際映画祭で主要賞を受賞し、その後も商業映画デビュー作『寝ても覚めても』(18)がカンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出、短編集『偶然と想像』(21)がベルリン国際映画祭で銀熊賞(審査員大賞)を受賞、脚本を手掛けた黒沢清監督作『スパイの妻〈劇場版〉』(20)がベネチア国際映画祭銀獅子賞に輝く。商業長編映画2作目となる『ドライブ・マイ・カー』(21)は脚本も手掛け、カンヌ国際映画祭で日本映画としては史上初となる脚本賞を受賞。国際映画批評家連盟賞、AFCAE賞、エキュメニカル審査員賞の独立賞も受賞し、4冠獲得の偉業を果たした。
20年に「ミニシアター・エイド基金」を深田晃司監督らと共同で立ち上げ、クラウド・ファンディングで目標額の三倍以上を集めた。
【参加学生】 大学院映像研究科映画専攻 菊地真里那(脚本領域) 木村愼(監督領域) 劉通(美術領域) 【撮影】 新津保建秀
- 1
- 2












