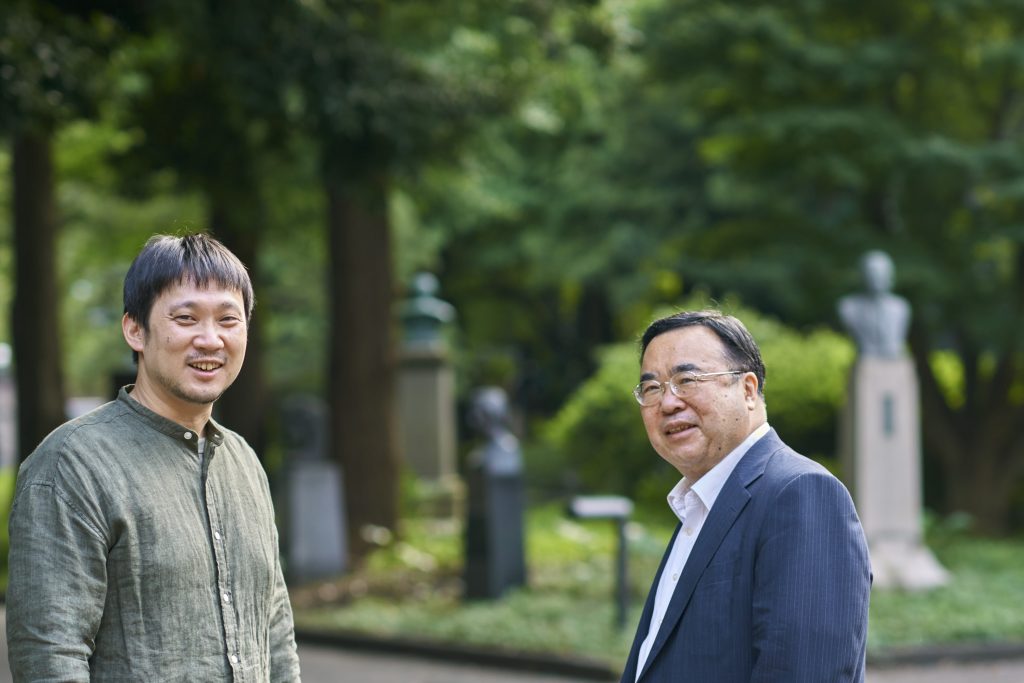
第五回 濱口竜介
第74回カンヌ国際映画祭にて監督作『ドライブ・マイ・カー』が日本映画として初の脚本賞を受賞するなど計4冠を達成した、大学院映像研究科修了生の濱口竜介さん。映画との出会いや本学での経験について、現役学生も交えて澤学長と対談を行った。
澤
まずは『ドライブ・マイ・カー』のカンヌ国際映画祭での受賞おめでとうございます。
濱口
ありがとうございます。
澤
2018年に『寝ても覚めても』がカンヌでノミネートされて、その後、黒沢清監督の『スパイの妻』でも脚本を書かれベネチア映画祭で銀獅子賞、『偶然と想像』がベルリン映画祭で銀熊賞を獲られました。ここ2、3年で世界的な映画賞を総ナメにされているという感じです。『ドライブ・マイ・カー』は映画館で観ました。
濱口
長時間、ありがとうございます(笑)。
澤
私も高齢者の部類なのでトイレ大丈夫かなと思いましたが、とにかく映画にすごく引き込まれて、そういうことも忘れて観ていました。考えさせられることが多くて、とても興味深かったです。またいろいろこの作品についてもお聞きしたいと思いますが、まず幼少期はどんな子どもでしたか?
濱口
幼少期ですか(笑)。僕は父親が公務員だったので2年に1回ぐらい移転するような生活を送っていました。神奈川県川崎市で生まれて、すぐ大阪に行きまして、2歳くらいのときにイランに行き、3年ぐらいいてまた大阪へ戻って、茨城、新潟、岐阜。中学の時に千葉に行って、そこから父親が単身赴任をしたので、中学・高校は千葉でした。なので、気がついたら時間が過ぎていたという感じで、大学に入るぐらいまでは自分というものがあんまりよくわからないような生活をしていましたね。
澤
イランでの生活というのは、我々には想像しにくいですけれど。
濱口
そうですよね。テヘラン日本人幼稚園というところに通って、基本的に家と幼稚園を行き来する生活でした。テヘランはそれなりに都市なので、そんなに不自由はなかったと思います。
澤
幼少期からいろいろなところを転々とされたことと映画少年になったことと、何か関連を感じますか?
濱口
やっぱりひとりで何かするという趣味の方が軸になるというか、多かったですね。それは漫画とかゲームも含めてですけれど。映画館へは最初は友達と行ったり父親に連れられて行ったりしていましたが、高校生ぐらいからひとりで行くことが多くなりました。

澤
高校生のときは月に何本ぐらいのペースで観ていたんですか?
濱口
そんなにお小遣いもないしバイトもしていなかったので、月に1、2本、映画館で観らればいいかなという感じでした。あとはレンタルビデオが多かったですね。うちのすぐ近所にレンタルビデオ屋があったので。それでだんだん、いわゆるアート系の映画、ハリウッド映画以外の映画が世の中にあることを理解していきました。
澤
その時期、お気に入りの監督はいましたか?
濱口
高校時代は岩井俊二監督でしたね。岩井俊二監督の作品をテレビで観て、「これは自分が知っているドラマとかと違うな」と思って。千葉から東京に行って岩井俊二監督の作品をミニシアターで観たり、そういうことを高校生の時から始めました。
澤
それから東京大学に入り、映画研究会で実際に映画を作るようになった。
濱口
はい。1年間予備校生活を送ったのですが、それがなかなか「これからどうなるんだろう」という不安のある生活でストレスが溜まっていたということもあって、大学ではやりたいことをやろうと映画研究会というサークルに入りました。それまでも一応、自分は映画が好きなんじゃないかと思っていたんですが、「なんで18、19歳でそんなの観てるんだ?」っていうようなすごく映画を見ている先輩方がいて、そういう環境の中で自分も新たに映画を発見して観る、それで作るというサイクルに入りました。
澤
卒業後は実際に現場で助監督の仕事をされたそうですね。
濱口
就職活動でいわゆる映像業界を受けたんですが、軒並み落ちてしまったんです。それで所属していた研究室の先生が心配してくださって、この研究室を出た人で監督になった人がいるから紹介状を書いてあげようと。それで助監督になるんですけれど、まあ助監督としては端的に言うと無能だったので、長続きはしませんでした。商業映画で1本、2時間ドラマで1本助監督をやったあと、その監督からは暇を出されました。ちょっと別のところで修行しろと、経済のテレビ番組を作るところを紹介していただいて、そこで1年ぐらいAD(アシスタント・ディレクター)をやりました。
澤
濱口さんは藝大の映像研究科の2期生ですよね。藝大に映像研究科ができたのはいつごろ知りましたか?
濱口
2005年からですが、2004年の後半にその創設のニュースがありました。経済番組に携わるのもそれなりに楽しかったんですが、明らかにもともと自分が作りたいものではなかったので、どうしようかなと思っていた時にその、映像研究科ができるというニュースがあって。教授は北野武さんや黒沢清さん。おお、それはすごいなと。国立の映画教育機関はそれまでなかったので、結構大きなニュースでした。もうこれが最後、蜘蛛の糸かもしれないということで、ADを辞めて受験をしました。でも1期では落ちてしまったので1年ぐらい塾講師とかをやって、次の年に受かって入学しました。
澤
藝大の映像研究科ではどんなことを学んだと思いますか?
濱口
やっぱり黒沢清さんとの出会いはとても大きかったですね。黒沢さんは当時すでに世界的な監督で、その人にほぼ毎週会えるというだけでも興奮するものがありましたし、ちょうどその頃に黒沢さんの新作が公開されたり、レトロスペクティブも開催されていたので、黒沢さんのお話を聞きながら黒沢さんの映画を観るという、素晴らしいサイクルでした。黒沢さんが他の映画について語ることも、「そういう理由で黒沢さんはこういうことをしているのか」という作家の目線で観ることができました。率直に言えばそれまではファンというほどではなかったんですが、その2年間で本当に魅了されました。映画の作り方を根本的に変えられるというか、それまでも自主映画を作っていましたけれど、今までの作り方ではうまくいくはずがなかったなと思いました。
澤
具体的に、今までと一番違うなと思ったのはどういうところですか?
濱口
言葉にすると当たり前のことですが、カメラは現実を記録する機械なんだということです。なので、現実に映っているものを受け入れるところから始めないといけない。もちろんいろいろな人力・人海戦術で現実の形を変えることはできるけれど、目の前の現実を映すということ自体は変えられない。それがこのカメラ、映画の根本的な力であって、やっぱりドキュメンタリー的なものなんですよね。それを使ってドラマを作ると、基本的にはそんなにうまくいかないということを黒沢さんはおっしゃっていました。
例としては、これは黒沢さんが本に書かれていることですが、韓国の映画学校の学生がこんな質問を黒沢さんにしました。俳優に台詞を言わせても白々しくて、台詞を覚えて言っているようにしか聞こえないんだけど、これはどうやったら自然になるのかと。黒沢さんは、「まさにそれが自然だ。なぜなら彼が覚えたとおりに台詞を話しているんだから、それはそういうふうに映るんだ。カメラっていうのはそういうふうな記録の機械なんだ」と答える。だからそういうものを使ってドラマを作ることがそもそも矛盾した行為なんだとおっしゃっていて。じゃあどうすればいいかという禅問答みたいな話なんですが、そこを出発点にして、ドラマを語るのであれば撮った現実を一体どうやってフィクションにしていくのかを、自分なりに考えないといけないんだと。そういうことを教えていただいた感じです。
澤
ホームページの対談企画「クローズアップ藝大」で黒沢さんに国谷裕子さんがインタビューされたんですが、藝大の映像研究科は濱口さんをはじめ素晴らしい映画人を育てていると言われたときに、「みんな僕が教えたことにはなっているけど、実は教えたんじゃなくて選んだだけだ」とおっしゃっていました。もちろん謙遜もあるでしょうけれど。同じ藝大でもいろんな分野があるし、先生と学生の関係はさまざまです。例えば器楽の場合だと先生の演奏を真似て学習したり、先生が学生に対して教え込むというか、比較的そういう要素が音楽は強い。逆に美術はあんまり教えちゃだめで、ほったらかしにしておいた方がいいとおっしゃる先生もいます。映像の場合もどっちかというと美術に近いのかもしれませんね。やっぱり黒沢さんのような巨匠のそばにいて、その考え方を盗むというか。

濱口
そうだと思います。大きな道を示されるというか。その道はいくつも枝分かれをしているようなもので、根本的な進むべき方向は示されるけれども、あとは自由にやりなさいと。野垂れ死んでもお前の責任、みたいなところもありつつ。黒沢さんにそういう意識がどの程度あったかわかりませんが、何かを教え込もうというよりは、大きな方向性を示してくださったというのが僕の実感です。
澤
黒沢先生は、「日本の映画界は危うい状況にある」とおっしゃっていますけど、そういう視点ではどのように思いますか?
濱口
僕は日本の映画産業で映画を作ってまだ2本目なので、お客さんのような気持ちというか、日本の映画産業がどういうものかまだわかっていないんじゃないかなと。ただ自分が仕事をするときに、ずいぶん余裕がないなとは思います。作品のクオリティだけのことを考えたら、もう少し時間をかけてしかるべきところに、なかなか時間を割く余裕がない。でもそれは日本の映画産業においてはすごく当たり前のことになっている。もうちょっと企画の方向性を考えるだけで、もっと活気づくのではないだろうかと思います。もう少し時間をかけやすいような企画や、制作体制を考えるだけで随分と作品のクオリティは変わってくると思います。そういう企画の作り方をしないと、結果的に観客を裏切り続けることになるんじゃないかと思っています。そういう業界の中でいったいどうやって生きていけるのか、僕自身すごく危惧しているところです。
澤
今回の『ドライブ・マイ・カー』もそれ以前のいくつかの作品でも、藝大での同期生や先輩・後輩たちとのチームで作り上げている作品もすごく多いですよね。黒沢さんの『スパイの妻』もそうです。やっぱり学生時代から一緒にやっていたということで、共感が生まれやすいのでしょうか?
濱口
それもあると思います。同じ空間にいて同じ授業を受けて、同じような大きな方向性を示されている中で各自やってきた。我々がいた頃は6人監督がいて、短篇長篇合わせて2年の間に1人あたり4本、計24本作ります。これは相当な数ですよね。時には僕も他の監督の助監督をやったり、シャッフルしながらやっていると、それぞれの人となりがわかってきます。撮影現場はそういうものがすごくビビッドに感じられるし、成長とか変わっていくさまとかも見ていて、この人と何か一緒にやろうと思うまでもなく一緒にいる感じで。根本的な信頼関係というか、仕事ももちろんですが人間を知っているということがすごく大きいので、ここのところ作っている長篇の多くは藝大で会った人と仕事をしていますね。
澤
濱口さんの作品は、『PASSION』や『THE DEPTHS』で横浜の町並みがロケーションとして使われていますね。
濱口
そうですね。横浜は本当にロケーションが豊富なんです。海に近いけれど、ちょっと行けば山っぽい場所もあるし、住宅街もあれば繁華街もある。僕らの在学時はさらにスタジオもあって、横浜で多様なロケーション撮影ができたので、ここですべて揃うような感じでした。
澤
中華街をはじめ異国情緒豊かなところがずいぶんありますからね。そこは横浜にいることのすごく大きなメリットですよね。
修了制作の『PASSION』もDVDで見せていただきましたけれど、もうあの段階で、国際的な評価を得ている今の濱口さんが想像できてしまうぐらい、すごく完成度の高い作品だなと思いました。音楽でも学生が国際コンクールの上位に入賞するようなことはありますが、音楽家として見た場合はそれから先の30年40年を想像することは難しい。もちろん濱口さんの修了制作も伸び代を十分に感じる作品でしたけれど、もう一人前というか。僕は門外漢だからそう感じてしまうのかもしれないですけれど。
 (東京藝術大学大学院映像研究科 第二期生修了作品集 2008 【PASSION】)
(東京藝術大学大学院映像研究科 第二期生修了作品集 2008 【PASSION】)
濱口
これは映像研究科の底力というか、映像研究科があったからできたことだと思います。入ったときにすごく感動したんですよね。これだけ機材があって、いろいろな分野のスタッフがいて、その人たちと2年過ごして、制作のための予算も出る。商業映画に比べれば予算は小さいものですけれど、それまで自分がやったことのないような規模のものが制作できる。修了作品で何ができるかということを考えながら、2年間かけて短編とかも撮る。修了制作では、限られた10日間の撮影期間と予算をどう使うか考えながらやりました。
澤
『PASSION』や『THE DEPTHS』、今回の『ドライブ・マイ・カー』でも、LGBTとか障害を持った人とか、多様な人たちにスポットを当てていらっしゃると感じました。『PASSION』と『THE DEPTHS』はもう今から十数年前ですよね。ここ1、2年は日本でも多様性ということが当たり前に言われていますが、十数年前だとそういうことに問題意識を持っている人はそんなにいなかったかもしれません。その辺りはどうですか?
濱口
『THE DEPTHS』の企画は韓国のプロデューサーが出したもので、それをどれだけ自分がちゃんと形にできるかを考えながらやっていました。僕自身は当事者の人たちの気持ちとか環境をわかっているわけではありませんが、そのキャラクターが一体どういう生を生きているのか、その個人に焦点を当てるようにはしています。そして状況や来歴はまったく違っても究極的には自分と全く違う人間だとは思わないようにすると言うか。それはどんなキャラクターを描くときでもそうなんですけれど、所詮はひとりの人間ですから、そうしかできないんですよね。「多様性」という言葉で考えるということは今も昔もありません。とにかく、1人ひとりをできる限り想像する、ということ。わからないことがあれば状況や来歴が近いと思われる人に取材をする、ということ。マイノリティと呼ばれる人たちも、我々の社会に当たり前にいる人たちなので、そういう人たちが物語の中に入ってくることがあれば、ちゃんとリスペクトを持って扱うということです。でもそれは他のキャラクターも全員一緒なんですけれど。

澤
『ドライブ・マイ・カー』でいくつかすごく心に残ったことがあります。劇中劇で『ワーニャおじさん』が使われていて、それが多言語演劇で手話も入る。原作は村上春樹さんの短篇小説ということですが、多言語演劇は濱口さんのアイデアですか?
濱口
そうですかね。多言語演劇だとやっぱり言葉でやりとりをするのではなくて、音でやりとりをする、ある種音楽的なアプローチになります。もちろん意味がわからないと演じることができないので、劇中にあったように読み合わせをして、この音声の時にはおそらくこういうことを言っているというようなことを頭に入れた上で演じるんですけれど、体から出る音に反応し合ったほうが、よりなまなましく演技ができるんじゃないかなと考えました。それが「音楽的」ということなのかもしれません。
澤
本読みのシーンで、感情を入れないで棒読みすることを演出家である主人公が指示をしていましたけれど、あれは濱口さんの演出の際の手法でもあるんですか?
濱口
そうですね。元々、ジャン・ルノワールというフランスの映画監督がやっていた「イタリア式本読み」というものがあって、演劇の方にルーツがある手法で、本家本元は早口で棒読みするそうです。ジャン・ルノワールが言うには、台詞にあらかじめ想定した感情を込めてしまうと演技はそこで発展しない、その場で反応できなくなってしまう。なので、その台詞をまず完全にフラットな状態にしておくことによって、演技とか、その場で起きる即興的なものが入り込みやすくなると。これは実際にやってみて、まったくその通りだと思いました。ただ、日本語でやる場合には、おそらくフランス語やイタリア語でやるようにはいかない。早口でもやりづらいんですね。なので、自分なりにアレンジをしてやっています。『ドライブ・マイ・カー』でやっているのも、やはりお話なので全部その通りというわけではないですが、エッセンスを入れているという感じですね。
澤
私の専門のヴァイオリンですと、指を震わせるビブラートというのが感情表現に重要な役割を持っているんですけど、これが往々にしてオーバーになりすぎて実際の音楽をむしろ壊してしまうことがある。そういうときに、まったくビブラートをかけないで、それでいて感情豊かに弾くようにと言うと、思わずかかってしまう。それが意外と良かったりするんですよね。そういう教え方をすることがあるので、すごく似ているなと思ったんです。

濱口
その「思わず」が重要なんですよね、きっと。意図せず出てくるものというか、本当にその場で出てくるものというのは、やっぱりなんか正しいというか。現場で驚きがあるのはそういう瞬間だし、そういう偶然が起こりやすいようにやっているような気がします。僕は音楽は門外漢ですが、本読みはオーケストラとかで楽器を調律している感じに近いのかなと思います。本当にニュアンスを抜いてやっていくと、だんだん言葉に口が慣れていって、体自体がリラックスしてその言葉を言えるようになってくる。そうするとその体自体から出てくる声を聞いているような感じになる。楽器の調律を聴いているというか、役者さんが自分のトーンをチューニングしてるのに立ち会っているような、そういう感覚になることがあるんです。
澤
『ドライブ・マイ・カー』の音楽の扱いもすごく興味深かったです。モーツァルトのピアノ曲やベートーヴェンの弦楽四重奏の普通はあまり演奏されない初期のものなど、印象に残りました。いわゆるBGM的な、その場の雰囲気を出すための音楽はほとんどなかった気がします。しばらく無音の状態もありましたよね?
濱口
はい。やはり映画自体が音楽的である、ということが一番大事なことだと思っているので、映画音楽は必要最小限にしようとは考えています。ただ、やはり音楽があることで観客は見方を示唆されるようなところがあるので、観客との関係づくりという点で音楽自体もとても大事なものだと思います。今回は石橋英子さんの音楽が素晴らしかったので、思った以上にふんだんに使ってしまいました(笑)。ご指摘いただいた無音の状態に至るまでは、すごくノイズが多いんです。車やフェリーのエンジン音とか、耳を疲れさせるような音がずっと続く。撮影で北海道ロケに行ったときに、音のない世界にいるような感覚に陥ったんです。雪って音を吸収するので。それがすごく印象に残っていて、自然と無音の演出になりました。ここから大事なことが起きるので、耳を一旦リフレッシュするというか、耳の感度をもう1回上げ直すというか。
澤
無音になる前がかなりハードな音だったので、突発性難聴かと一瞬焦りました(笑)。
濱口
今回は音の作業をする時間も結構いただけたのと、サウンドミキサーの野村みきさんのおかげで、すごく満足のいく音ができました。
澤
外国の映画祭で上映されるときは字幕が出るのですか?
濱口
はい、字幕です。英語と、例えばベルリンだったらドイツ語、カンヌだったらフランス語の字幕が出ます。
澤
日本語の台詞を訳す、そこでも相当評価が変わってくる可能性がありますよね?
濱口
それはすごくあると思います。特に自分の映画は言葉も多いので、翻訳のクオリティによって評価が左右されるだろうなと思います。だから外国で評価していただいている背景には、翻訳をするスタッフの層の厚さと、彼らの技術というのがすごく重要だと思います。
澤
翻訳したものも後で厳しくチェックされるんですか?
濱口
英語に関してはある程度わかるので、ニュアンスが合っているかチェックしたりします。他の言語はお手上げですけど。解釈が難しいところもあるので、できる部分は共同作業をするようにしています。
- 1
- 2












