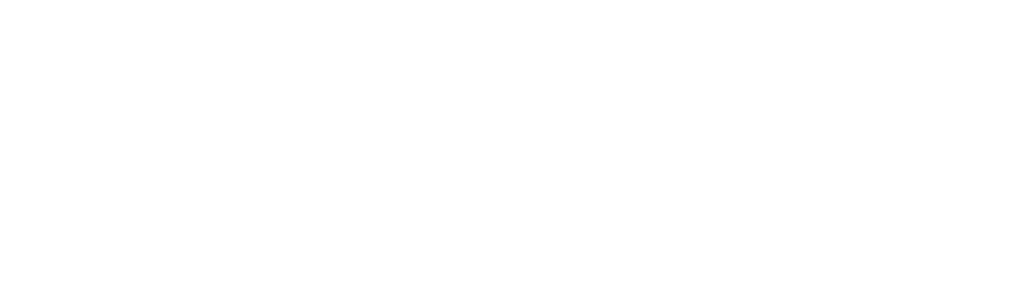- 大学概要
- 学部・研究科・附属機関・センター等
- 展覧会・演奏会情報
- 広報・大学情報
- 学生生活
- 卒業生の方へ
- 一般・企業の方へ
- 教職員の方へ
- 入試情報
- 藝大に寄附をする

第五回 迫昭嘉「藝大生 今昔」
6月の終わりから7月にかけての藝大ウィンド・オーケストラ・フランス公演を終えたところでこの原稿を書いている。南仏での音楽祭、その後、パリで室内楽のコンサート、これらすべてが大成功であった。演奏には我々教員も7名参加していたが、藝大の学生たちは堂々と、生き生きとパフォーマンスを繰り広げ、その質の高さで現地の聴衆から惜しみないスタンディングオーベーションを浴びたのである。彼らのその姿は私には大変誇らしいものだった。
まさに昔日の感である。自分が藝大生だったころ、はたしてこのようにのびのびと海外で演奏できただろうか? 学生の生活は今も昔も変わらない。かなり突っ張った志を持ち、日々の努力の積み重ね、そしてアップダウンの激しい感情の中でよく遊んだ。ただ、ヨーロッパの伝統音楽を演奏しなければならない我々の前に西洋文化の壁は敢然と立ちはだかっていた。まだ距離が遠かったのである。
大学院1年の時にコンクールを受けに初めて海外に出た時の緊張は今でも忘れられない。軍用機にしか思えなかったソヴィエトの飛行機に乗った時のカルチャーショック、今のハッピーなフライトとは比べ物にならない何やら命がけの感がしたものである。見るもの聞くもの食べるもの、すべてが自分の持っていた情報と想像をはるかに超えていた。余談だが‘80年代の初頭は東京でもスパゲッティ・カルボナーラすら未知の食べ物だったのだ。私たちの世代は、西洋に「臨む」、「挑戦する」という言葉を使われ、コンクールに優勝でもしようものなら「凱旋」といった感じであった。これでは出征兵士だ。今は何か違う。この「構えた感」が今の藝大生には全くない。まるで藝祭のノリそのままに海外でも演奏してしまう。自然体なのだ。
以前は西洋人からも東洋は遠かったはずである。90年代になってもなお、ヨーロッパでは、「お前は日本人なのに何故我々の音楽を演奏するのだ?」という質問に何度も出くわした。それに対して私の用意できた回答は、音楽の力や人間の感情の普遍性というキーワードくらいだった。今日では西洋人にも東洋の音楽家に対する偏見はほとんどなくなっている。それはグローバル化とネット情報社会のなせる業?
相容れないものでもリスペクトを持って共存していくのか、それとも薄めてしまってグローバルと称して間口の広いものに変容していくのか、きっとどちらも大切なのだろう。でも、そんなことを超えて、藝大生はこれからも「自然体」と逞しいヴァイタリティで創造の力を発揮していくに違いない。

1980年(大学院1年) ジュネーヴ国際コンクール授賞式(右から2番目)
【プロフィール】
迫 昭嘉
東京藝術大学音楽学部長
1957年、東京都生まれ。
東京藝術大学及び東京藝術大学大学院、ミュンヘン音楽大学マイスタークラス修了。中山靖子、クラウス・シルデ各氏に師事。東京藝術大学大学院にてクロイツァー賞を受賞、ジュネーヴ国際音楽コンクール最高位、東京国際音楽コンクール室内楽部門優勝(1980年)、ハエン国際ピアノコンクール優勝およびスペイン音楽賞(1983年)、ABC国際音楽賞受賞(1998年)。
1998年、東京藝術大学音楽学部助教授(2007年より准教授)
2008年、音楽学部教授
2013年、音楽学部副学部長を経て、2016年より現職